歯磨きをしていて、鏡で何気なく唇の内側を見ていると、なにやら白いできものがある。
痛みはない、もしくは、少し刺激物がしみるように感じる程度。
こすっても取れないし、長期間同じ場所にあって原因がわからない、といったことはありませんか?
このように、唇に白いできものを見つけた時、経験したことがないために、これがどういうもので、どうしたらいいのかよくわからない、と悩む方が多いようです。
ここでは、この白いできものとして考えられるもののうち、パピローマウイルス、口唇がん、粉瘤を取り上げ、それぞれの原因と予防法を見ていきます。
白いできものは感染症の疑い

唇によく見られるできものの1つに、乳頭腫というものがあります。
いわゆる「いぼ」というものです。
これは良性の腫瘍で、ヒトパピローマウイルス(HPV)というウイルスによる感染症です。
ヒトパピローマウイルスにはいくつかの種類(型)があり、その中には子宮頸癌や中咽頭癌との関係が深いとされるものもありますが、ここでとりあげる乳頭腫のたいていの場合は良性のものです。
その他に考えられる疾患としては、口唇がん、粉瘤(アテローム)などいくつかあります。
パピローマウイルスが原因の場合の治療
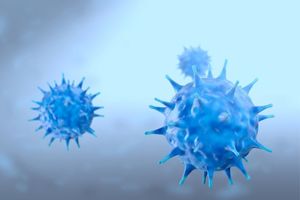
乳頭腫は良性腫瘍ですが、気になってこすったり、爪でひっかいたりすることで、体中に広がったり、他人に伝染することがあります。
また、治療しない限りはなかなか消滅することもありません。
この乳頭腫の治療には、レーザーなどによる切除や、液体窒素による凍結療法などがあります。
生薬として、ヨクニンというハトムギの皮を除いた種も、昔から、内服薬として乳頭腫の治療に使われています。
気になったら、広がる前に歯科医院や皮膚科で相談してみましょう。
口唇がんが原因の場合の治療

口にもがんはできます。
唇だけでなく、舌や歯肉、頰の粘膜など様々です。
これらを総称して口腔がんと言います。
日本国内で年間4万人が口腔がんと診断されています。
この数字は、胃がんや食道がんなど他のよく聞かれるがんに比べると、患者数の少ないがん(希少がん)の1つです。
著名人が舌がんを治療したというニュースを聞いたことがあるかもしれませんが、皆さんの親戚や知人・友人の中で、この口腔がんを治療をしたことがある、という方は比較的少ないのではないでしょうか?
患者数が少ないために、口腔がんの認知度は低い状況にあります。
また、初期の口腔がんは口内炎に似ているため、発症から診断まで時間がかかり、結果として治療開始が遅れてしまう、ということもあります。
口唇がんと口内炎はとてもよく似ていることがあります。
まず発症の原因ですが、どちらも歯が口唇によく当たって噛んでしまったり、やけどすることなどがきっかけです。
タバコは紙巻きタバコ・加熱タバコいずれであっても原因になります。
初期段階では、見た目での区別がつけにくいこともよくあります。
口腔がんが口内炎と違う点は、口内炎の治療(ステロイド軟膏や、レーザー治療)をしても、口腔がんは消えないどころか、悪化する(広がる)という点です。
発生する頻度で見れば口内炎が圧倒的に多いので、もし口内炎のようなアフタを見つけた時は、まず口内炎としての治療を開始します。
ステロイド軟膏の塗布や、うがい薬で清潔に保つことなどです。
ただし、2週間たっても改善の傾向が無ければ、口内炎ではない可能性を疑う必要がありますので、歯科医院で相談しましょう。
口唇がんの治療は、手術での切除をまず検討します。
その場合はまず、切除後の唇の形を十分に考慮しなければなりません。
また、年齢や体力によっては、手術ではなく抗がん剤や放射線治療を検討します。
粉瘤が原因の場合の治療
唇の皮膚側、ひげなどがある側において、粉瘤ができることがあります。
粉瘤(アテローム、表皮のう腫)とは、皮膚の内側に袋ができ、皮膚からの角質(垢)や皮脂などが、袋の中にたまったものです。
毛穴が広がってできるとも言われていますが、この袋ができる原因はまだ明らかになっていません。
毛穴があれば体のどこにでも出来る可能性があるとされ、その多くは背中、うなじ、頬、耳たぶなどにできやすいとされています。
強く圧迫すると、袋の中に溜まった角質、皮脂などが混ざった泥のようなものが出てくることもあります。
また、細菌感染すると、急激に痛みを伴って大きくなることもあります。
とてもまれな話ではありますが、粉瘤を長期間放置すると、悪性化することがあります。
一番多いのは有棘細胞がん、基底細胞がんといったものです。
薬だけで治療できることはまずないと思われ、手術で取り除くことになります。
小さいうちに取り除けば、術後の傷も小さくできるでしょう。
唇のできものを予防するには
今回は乳頭腫(パピローマウイルス感染症)、口唇がん、粉瘤の3つを見てみました。
それぞれの予防については、乳頭腫は口を清潔に保つ、口唇がんは噛まないような歯並びの治療や禁煙(加熱タバコを含む)、粉瘤は日々洗顔フォームを使うなどで清潔に保つ、といったことになります。
しかし、予防することはなかなか難しいところでもあります。
洗顔や歯磨きなどで、日々こまめに口の周囲を観察して早期発見につとめ、もし気になることがあれば、歯科医師などに相談して、必要に応じて治療してもらいましょう。
