「歯磨きのたびに出血する…」
「歯ぐきがムズムズする…」
「口が臭いと子供に言われた…」
それはもしかしたら歯肉炎のサインかもしれません。
歯肉炎は、非常に多くの方が経験するおそれのあるお口の病気です。
厚生労働省の調査では、30代以上の成人の約7~8割が歯肉炎またはより進行した歯周炎にかかっているというデータもあります。
特に、歯肉炎の段階であれば自覚症状が少ないため、気づいていない人も含めると、非常に多くの人が該当すると考えられます。
しかし、この歯肉炎こそが、より深刻な歯周病へとつながる重要なサインなのです。
この記事では、歯肉炎の正しい知識を深め、その原因、症状、そして効果的な予防法と対処法について、分かりやすく解説します。
あなたの健康な歯ぐきと口腔環境を守るために、ぜひ最後までお読みください。
歯肉炎とは何か?

歯肉炎とは、歯周病の初期段階にあたる病気で、歯ぐき(歯肉)に炎症が起きている状態です。
この段階では、炎症は歯肉に限定されており、歯を支える歯槽骨(しそうこつ)などの歯周組織の破壊はまだ起こっていません。
主な原因は、歯の表面に付着した細菌の塊である歯垢(プラーク)です。
歯肉炎は適切なケアを行えば、健康な状態に回復可能ですが、放置すると歯周炎へと進行するおそれがあり、注意が必要です。
歯肉炎の主な症状
歯肉炎の主な症状は以下の通りです。
歯ぐきの赤みや腫れ
健康な歯ぐきは薄いピンク色で引き締まっていますが、歯肉炎になると赤みを帯びたり、少し腫れぼったくなったりします。
歯磨き時の出血
歯ブラシやデンタルフロスを使用した際に、歯ぐきから出血しやすくなります。これは炎症によって歯肉の組織が弱くなっているサインです。
歯ぐきの違和感
ムズムズするようなかゆみや、軽い痛みを感じることがあります。
口臭の変化
細菌の増殖により、以前よりも口臭が気になるようになることもあります。
これらの症状は、軽度であるために日常生活で見逃されがちですが、口腔からの重要なサインと捉え、早めに歯科医院を受診しましょう。
歯肉炎と歯周病の違い
歯周病は、歯ぐき(歯肉)や歯を支える骨(歯槽骨)など、歯の周りの組織(歯周組織)に起こる病気の総称です。
歯周病は、進行段階によって歯肉炎・歯周炎・歯槽膿漏に分類できます。
簡単に説明すると、
・炎症が歯ぐきだけにある軽度の状態を「歯肉炎」
・炎症が歯を支える骨(歯槽骨)まで進行した中度の状態を「歯周炎」
・さらに歯槽(骨を支える骨のくぼみ)から膿が漏れる重度な状態を「歯槽膿漏(しそうのうろう)」
という違いがあります。
つまり、歯肉炎は歯周病という大きな枠組みの中の初期の病態であり、この段階でしっかりと対処することが、歯周病への進行を防ぐ上で極めて重要になります。
歯肉炎の原因とリスク要因

歯周炎の原因とリスク要因は以下の通りです。
歯垢(プラーク)の蓄積
歯肉炎の主な原因は、歯の表面に付着する細菌の塊である歯垢(プラーク)です。
この歯垢が歯と歯ぐきの境目や歯周ポケットに長時間付着していると、細菌が毒素を出し、歯肉に炎症を引き起こします。
歯垢は粘着性が強く、うがいだけでは除去できません。
日々の丁寧な歯磨きによる物理的な除去が必要です。
歯磨きで取り残された歯垢は、唾液の中の成分(カルシウムなど)とくっついて硬くなり、「歯石」に変わります。
この歯石の表面はザラザラしているため、歯垢が付きやすくなってしまいます。
その結果、歯ぐきの炎症がますます悪化する原因になるのです。
この状態を放置すると、炎症が歯周組織の深部へと進行し、軽度の歯周病から、さらに深刻な歯周炎へと悪化していく可能性が高まります。
ホルモンバランスの変化
私たちの体は、ホルモンによって様々な影響を受けています。
特に女性の場合、一生の中でホルモンバランスが大きく変動する時期があり、これが歯肉炎のリスクを高めることがあります。
- 思春期
性ホルモンの分泌が活発になる思春期には、特定の歯周病菌が増殖しやすくなったり、歯ぐきがプラークに対して過敏に反応しやすくなったりするため、「思春期性歯肉炎」と呼ばれる歯肉炎が起こりやすくなります。歯ぐきが赤く腫れ、歯磨きで出血しやすくなるのが特徴です。 - 妊娠期
妊娠中は、エストロゲンやプロゲステロンといった女性ホルモンの分泌量が著しく増加します。これにより、歯肉の血管が拡張して炎症が起きやすくなったり、特定の歯周病菌が繁殖しやすくなったりします。つわりで歯磨きが十分にできなかったり、食生活が不規則になったりすることも重なり、「妊娠性歯肉炎」を発症しやすくなります。 - 月経周期
月経前になると、一時的にホルモンバランスが変化し、歯ぐきが敏感になったり、軽い炎症や出血が見られたりする方もいます。 - 更年期
更年期に入り女性ホルモンが減少すると、唾液の分泌量が減ってお口が乾燥しやすくなったり、骨粗しょう症の影響で歯を支える骨が弱くなったりすることも、間接的に歯肉炎や歯周病のリスクを高める可能性があります。
これらの時期は、特に丁寧な口腔ケアが重要となります。
ストレス
現代社会において、ストレスは多くの方が抱える問題ですが、実はお口の健康にも大きな影響を及ぼします。
- 免疫力の低下
強いストレスや慢性的なストレスは、体の免疫力を低下させます。免疫力が弱まると、プラーク中の細菌に対する抵抗力が落ち、歯肉炎が発症・悪化しやすくなります。 - 唾液の減少
ストレスは唾液の分泌量を減少させることがあります。唾液には、お口の中の細菌を洗い流したり、細菌の活動を抑えたりする自浄作用がありますが、唾液が減るとこれらの機能が低下し、細菌が繁殖しやすくなります。 - 生活習慣の乱れ
ストレスを感じると、歯磨きがおろそかになったり、甘いものやアルコールの摂取が増えたり、睡眠不足になったりと、生活習慣が乱れがちです。これらも歯肉炎のリスクを高めます。 - 歯ぎしり・食いしばり
ストレスは、無意識のうちに歯ぎしりや食いしばりを引き起こすことがあります。これにより歯や歯ぐきに過度な力がかかり、歯肉炎を悪化させる要因となることがあります。
心身の健康を保つことが、お口の健康にも繋がります。
喫煙
喫煙は、歯肉炎や歯周病にとって最大のリスク要因の一つと言われています。
タバコに含まれる多くの有害物質が、お口の健康に深刻なダメージを与えます。
- 血流障害
タバコに含まれるニコチンは、歯ぐきの血管を収縮させ、血流を悪化させます。これにより、歯ぐきに必要な酸素や栄養が届きにくくなり、細菌に対する抵抗力が低下します。また、傷の治りも遅くなります。 - 免疫機能の低下
喫煙は、白血球など免疫細胞の働きを弱め、細菌と戦う力を低下させます。 - 唾液の性状変化と自浄作用の低下
唾液の質が変わり、お口の中の自浄作用が低下しやすくなります。 - 炎症のサインが隠される
喫煙者の歯ぐきは、ニコチンの影響で血流が悪いため、炎症が起きていても出血や腫れといった典型的な症状が現れにくいことがあります。そのため、気づかないうちに歯周病が進行してしまう危険性があります。 - 治療効果の低下
喫煙していると、歯周病治療を行っても効果が出にくく、再発しやすいことも知られています。
禁煙は、歯肉炎予防だけでなく、全身の健康のためにも非常に重要です。
栄養不足
バランスの取れた食事は、健康な歯ぐきを維持するために不可欠です。
特定の栄養素が不足すると、歯肉炎のリスクが高まることがあります。
- ビタミンC不足
ビタミンCは、歯ぐきのコラーゲン線維を作るのに必要な栄養素です。不足すると、歯ぐきの組織が弱くなり、出血しやすくなったり、細菌に対する抵抗力が低下したりします。 - ビタミンA不足
ビタミンAは、歯ぐきなどの粘膜を保護し、健康に保つ働きがあります。不足すると、細菌に感染しやすくなる可能性があります。 - ビタミンB群不足
ビタミンB群は、粘膜の健康維持や炎症を抑える働きに関わっています。不足すると口内炎や口角炎などが起こりやすくなるほか、歯肉炎の悪化にも影響する可能性があります。 - タンパク質不足
タンパク質は、歯ぐきを含む体の組織を作る基本的な材料です。不足すると、組織の修復力が低下し、歯肉炎が治りにくくなることがあります。 - カルシウム・ビタミンD不足
これらは直接的に歯肉炎の原因とはなりにくいですが、歯を支える骨の健康に重要です。骨が弱くなると、将来的に歯周病が進行しやすくなる可能性があります。
偏った食生活を避け、様々な食品からバランス良く栄養を摂取することが大切です。
薬の副作用
服用しているお薬の種類によっては、その副作用として歯肉炎のリスクが高まったり、歯ぐきに変化が現れたりすることがあります。
歯肉増殖を引き起こす薬剤
・降圧剤の一部(カルシウム拮抗薬など)
高血圧の治療に使われる薬の一部に、副作用として歯ぐきが腫れぼったく増える(歯肉増殖)ことがあります。
・抗てんかん薬の一部(フェニトインなど)
てんかんの治療薬の一部にも、同様の歯肉増殖が見られることがあります。
・免疫・免疫抑制剤(シクロスポリンなど)
臓器移植後などに使われる免疫抑制剤の一部にも、歯肉増殖の副作用が報告されています。 増殖した歯ぐきはプラークが溜まりやすく、除去も困難になるため、歯肉炎が起こりやすくなります。
唾液の分泌を減少させる薬剤
・抗ヒスタミン薬(アレルギーや風邪薬)、鎮痛剤、抗うつ薬、利尿薬など
多くの薬剤で唾液の分泌量が減る副作用が見られます。唾液が減ると、お口の中の自浄作用が低下し、細菌が繁殖しやすくなり、歯肉炎やむし歯のリスクが高まります。
免疫力を抑制する薬剤
・ステロイド剤や免疫抑制剤など
体の免疫反応を抑えるため、感染に対する抵抗力が低下し、歯肉炎が悪化しやすくなることがあります。
持病の治療でお薬を服用している場合は、歯科医師に必ずその旨を伝え、お薬の種類や副作用について情報を共有することが重要です。
歯科医師は、お薬の影響を考慮した上で、適切な口腔ケア指導や予防策を提案してくれます。
糖尿病・心臓病
歯周病は全身疾患と密接な関係があるため、糖尿病や心臓病の人は歯肉炎が悪化しやすいです。
糖尿病になると免疫力が低下し、歯肉炎を悪化させる歯周病菌への抵抗力も弱まります。
また、糖尿病によって高血糖状態が続くと、歯ぐきの血管がもろくなり、炎症を引き起こしやすくなります。
同様に、心臓病になると免疫力が低下するため、歯肉炎が進行が進みやすく、注意が必要です。
さらに、糖尿病や心臓病の薬の一部には、唾液の分泌量を減らす副作用があります。
唾液には歯周病菌の増殖を抑制する役割があるため、口の中が乾きやすくなると歯肉炎などの歯周病が悪化しやすくなります。
糖尿病や心臓病といった全身疾患をお持ちの方は、健康な人よりも歯周病のリスクが高いので、歯肉炎を放置せずに歯科医院での治療を受けましょう。
HIV感染症
HIV(ヒト免疫不全ウイルス)感染症も、歯肉炎や歯周病になりやすくなります。
これは、HIVによって全身の免疫力が弱くなってしまい、口腔内でも細菌感染が起こりやすくなるためです。
その結果、
・普通の歯周炎よりもひどい状態になったり
・歯ぐきが腫れたり、血が出たり、痛みが出やすくなります。
そのため、HIVに感染している方は、歯医者さんでの専門的な治療と、毎日の丁寧な歯磨きが特に大切になります。
歯肉炎の予防と対策

歯肉炎は、日々の歯磨きや生活習慣の見直し、定期的な歯科医院の受診により予防が可能です。
毎日の正しい歯磨き
歯肉炎の主な原因は「歯垢(プラーク)」という細菌の塊です。これをしっかり取り除くことが一番大切です。以下のポイントを意識しましょう。
・適切な歯ブラシの選択
ヘッドが小さく、毛先が細かく、適度な硬さの歯ブラシを選びましょう。
・正しいブラッシング方法
歯ブラシを歯の表面に対して45度の角度で当て、歯と歯ぐきの境目に毛先が届くように意識しながら、軽い力で小刻みに動かします。
力を入れすぎると歯ぐきを傷つける原因になるので注意が必要です。
・プロに習うのが一番
歯医者さんで、自分に合った正しい歯磨きの方法を教えてもらうのが効果的です。
デンタルフロスや歯間ブラシの使用
歯ブラシだけでは、歯と歯の間に隠れた歯垢を完全に取り除くのは難しいものです。
歯と歯の間や、ブリッジの下、矯正装置の周囲など、歯ブラシが届きにくい部分の清掃には、デンタルフロスや歯間ブラシの併用が不可欠です。
デンタルフロスは、歯と歯が接している面のプラーク除去に効果的です。
歯間ブラシは、歯と歯の間の隙間の大きさに合わせて適切なサイズを選び、無理なく挿入できるものを使用しましょう。
これらを毎日使うと、歯垢がしっかり落ちるので、歯肉炎予防にとても役立ちます。
歯医者さんで定期的なチェック&クリーニング
自分では気づかないうちに歯垢が硬い「歯石」になってしまったり、磨き残しがあったりします。
・プロの技でスッキリ
歯医者さんでは、専用の機械で歯石を取り除いたり、歯の表面をツルツルに磨いたりしてくれます(クリーニング)。
・早期発見・早期治療
歯肉炎の初期症状を見つけてもらえたり、歯周病へ進むのを防いだりできます。
・歯磨き指導も
自分のお口の状態に合わせたアドバイスがもらえます。
・より精密な検査・治療も
場合によっては、「マイクロスコープ(歯科用顕微鏡)」という機械を使うこともあります。
これは、肉眼では見えない小さな歯石や汚れを拡大して確認し、より正確に、そして丁寧に取り除くためのものです。
歯肉炎が悪化するのを防ぎ、健康な歯ぐきを守るのに役立ちます。
生活習慣の見直し
体の健康が、お口の健康にもつながります。
・バランスの良い食事、十分な睡眠、適度な運動
これらは体の免疫力を高め、歯肉炎になりにくい状態を作ります。
・禁煙
タバコは歯肉炎や歯周病の最大の敵の一つです。禁煙は歯ぐきの健康改善にとても効果があります。
・ストレスを溜めない
上手にストレスを発散することも大切です。
これらのことを毎日の生活で意識して、歯肉炎知らずの健康な歯ぐきを目指しましょう。
歯肉炎に関するよくある質問

歯肉炎について、患者さんからよくいただくご質問と、そのお答えをまとめました。
Q1. 歯肉炎はどのくらいで治りますか?
A1. 治るまでの期間は、歯肉炎のひどさや、お手入れの仕方によって変わってきます。
■軽い歯肉炎の場合
正しい歯磨きを始め、歯医者さんで専門的なクリーニング(お掃除)を受けると、数日から2週間くらいで歯ぐきの出血や腫れといった症状が良くなることが多いです。
■ただし、これはあくまで目安です。
完全に健康な歯ぐきに戻るには、その後もきちんとお手入れを続けることが大切です。歯医者さんの指示に従って、根気強くケアを続けましょう。
Q2. お家でできる治療法はありますか?
A2. はい、軽い歯肉炎であれば、お家でのセルフケアが治療の中心になります。
■一番大切なこと
原因である「歯垢(プラーク)」という細菌の塊をしっかり取り除くことです。
- 毎食後の丁寧な歯磨き
- デンタルフロスや歯間ブラシの使用 この2つが基本です。
■うがい薬(洗口液)について
殺菌成分が入っているものは、補助的な効果が期待できます。しかし、歯垢をブラシなどで物理的にこすり落とすことが最も重要だということを忘れないでください。
■こんな時は歯医者さんへ
- 症状がなかなか良くならない
- 痛みが強い
- 出血が続く このような場合は、自分で判断せず、必ず歯医者さんを受診してください。
■覚えておいてほしいこと
お家でのケアは、あくまで予防や軽い症状の改善が中心です。進んでしまった歯肉炎や、さらに悪化した歯周病の治療は、歯医者さんでの専門的な処置が必要です。
Q3. 歯肉炎がまたならないようにするには、どうすればいいですか?
A3. 歯肉炎は一度治っても、お口の清掃状態が悪くなると再発しやすい病気です。再発を防ぐためには、以下の点がとても大切です。
■毎日の丁寧な歯磨きを続けること
正しい歯磨きの習慣を維持し、デンタルフロスや歯間ブラシも忘れずに使いましょう。
■歯医者さんで定期的にプロのケアを受けること
自分では取りきれない歯石や、細菌が作ったネバネバした膜(バイオフィルム)を、定期的に歯医者さんで取ってもらいましょう。歯医者さんや歯科衛生士さんから、お口の状態に合わせたアドバイスをもらうことも重要です。
■生活習慣を見直すこと
・禁煙する(タバコは歯周病の大きな原因です)
・バランスの取れた食事を心がける
・十分な睡眠をとる
・ストレスを上手に発散する
これらは体全体の健康を守り、歯肉炎の再発予防にもつながります。
■持病があれば、しっかり管理すること
糖尿病などの全身の病気がある場合は、その病気のコントロールをしっかり行うことが、お口の健康にも良い影響を与えます。
これらのことを守り、歯医者さんと協力しながらケアを続けることが、歯肉炎の再発を防ぎ、長い間健康なお口の状態を保つためのカギとなります。
【まとめ】歯肉炎は油断大敵!早めのケアで歯を守ろう
歯肉炎は、歯ぐきの赤みや出血といったサインで始まる身近な病気ですが、放置すると歯周炎へと悪化し、最悪の場合、歯を失うこともあります。
主な原因は、歯の表面に付く細菌の塊「歯垢(プラーク)」です。
歯肉炎を防ぎ、悪化させないためには、毎日の丁寧な歯磨きやデンタルフロス、歯間ブラシを使ったセルフケアで歯垢をしっかり落とすことが基本です。
さらに、歯科医院での専門的なケアも重要です。
歯科医院では、自分では取りきれない歯垢や歯石を除去し、必要に応じて「マイクロスコープ」という歯科用顕微鏡を使って、見えにくい部分の汚れまで精密に取り除くことで、歯肉炎の根本原因にアプローチし、進行を食い止めます。
「痛くないから大丈夫」と自己判断せず、定期的な歯科検診を受け、正しいお手入れを続けることが大切です。
歯ぐきの変化に気づいたら、早めに歯科医師に相談しましょう。
早期発見・早期治療、そして予防の継続が、お口と体の健康を守る鍵となります。
歯周病の関連コラム
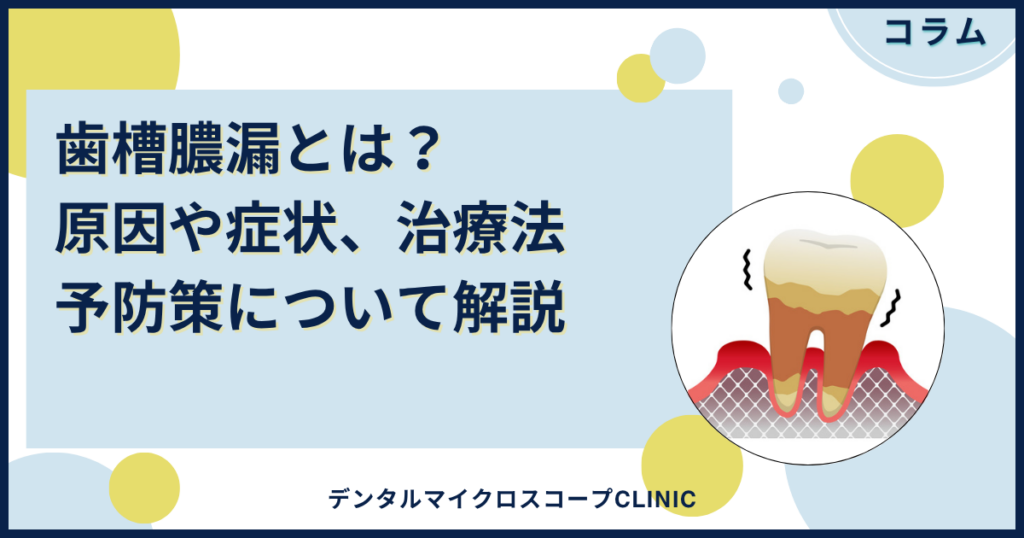
歯槽膿漏とは?原因や症状、治療法、予防策について解説
「もしかして、これって歯槽膿漏?」歯ぐきから出血や口臭、歯のグラつき...。そんな症状に心当たりはありませんか?この病気は、自覚症状が少ないまま静かに進行し、大...
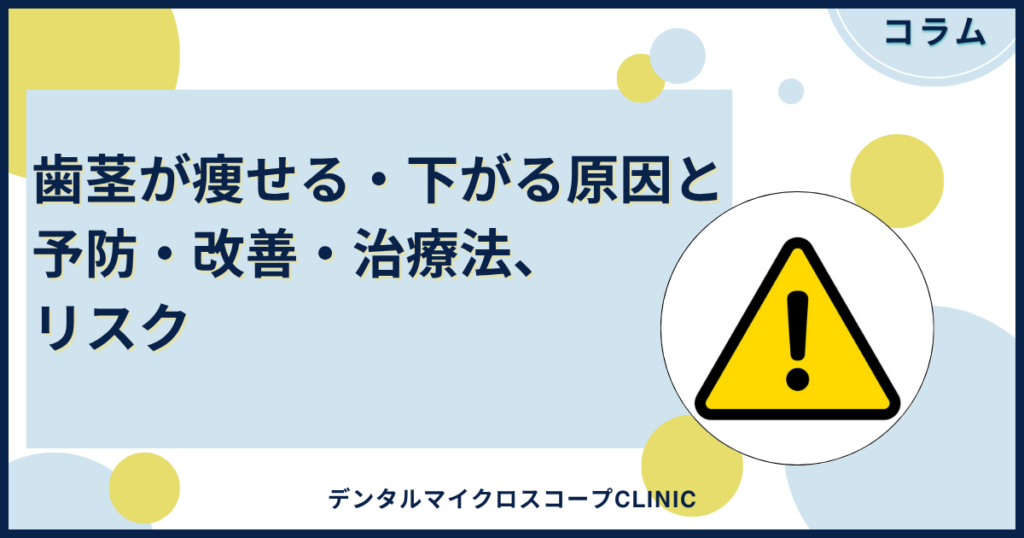
歯茎が痩せる・下がる原因と予防・改善・治療法、リスク
歯茎の痩せは、多くの方が経験するにもかかわらず、その重大さに気づかれにくい口腔トラブルです。年齢を重ねるにつれて自然に進行することもありますが、様々な原因によっ...
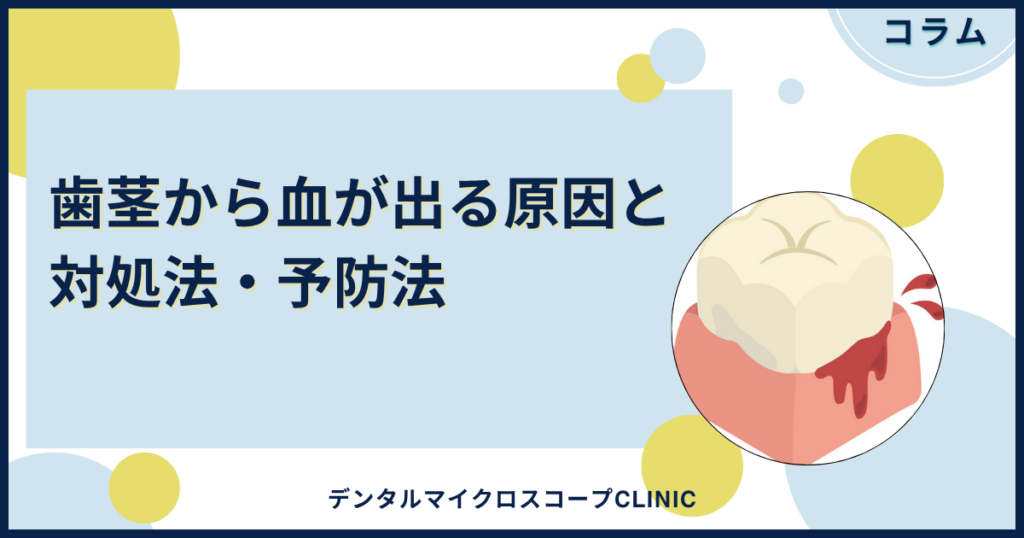
歯茎から血が出る原因と対処法・予防法
歯茎から血が出ることは、多くの方が経験される身近な症状ですが、その背景には様々な原因が隠れています。軽度な歯肉炎から重篤な全身疾患まで、出血の原因は実に多岐にわ...
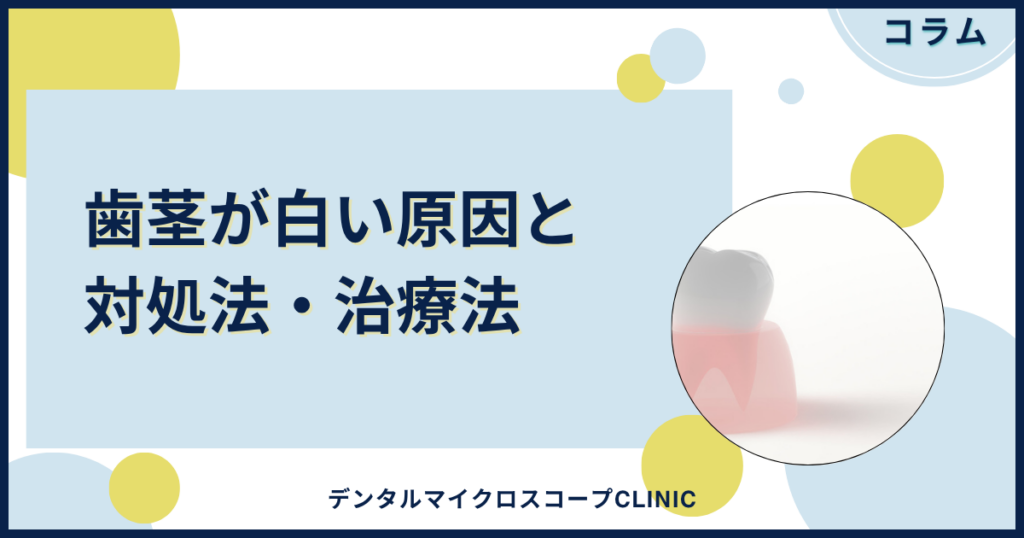
歯茎が白い原因と対処法・治療法
歯茎の健康は全身の健康状態を映し出す鏡とも言われています。普段はピンク色をしている歯茎が白く変化すると、何かしらの異常が起きているサインかもしれません。歯茎が白...


