冷たい水を飲んで「キーンとしみる」、「歯が黒いかも」という場合は、虫歯の可能性があり、放置するのは危険です。虫歯は風邪と違い、自然に治ることはなく、気づかないうちに静かに進行していきます。
この記事では、ご自宅でできる虫歯の見分け方を5つのポイントで詳しく解説します。さらに、虫歯を放置した場合のリスクや、進行度C0〜C4までの治療法の違いも紹介しています。
初期なら数千円で済む治療が、神経に達すると数万円に増えるだけでなく、全身の病気につながる危険性もあります。手遅れになる前に、この記事で歯の状態を正しく把握し、大切な歯を守る知識を身につけましょう。
この記事の監修歯科医師

清水歯科 歯科医師
明石 陽介
愛知学院大学歯学部卒業。口腔外科、一般歯科診療に携わり
現在は、愛知県内の歯科医院にて訪問歯科診療を中心に活動。通院が難しい方にも安心して歯科治療を受けていただけるようサポート。
義歯治療や摂食嚥下の支援にも力を入れ、患者様一人ひとりの生活に寄り添った診療を大切にしている。
自分でわかる虫歯の見分け方5つのポイント

以下では、ご自宅でできる虫歯の見分け方を5つ解説します。
①歯の色や見た目で進行度を確認する
②痛み・しみ方から危険度を見極める
③前歯・奥歯・歯間を部位別にチェックする
④着色や知覚過敏との違いを見分ける
⑤詰め物・被せ物の下の虫歯を見つける
虫歯の早期発見・早期治療につなげるために、ぜひお役立てください。
①歯の色や見た目で進行度を確認する
虫歯は進行度(C0〜C4)によって、歯の色や見た目が少しずつ変化していきます。鏡を使い、明るい場所で歯の表面をじっくりと観察してみましょう。
特に、歯の溝や歯と歯ぐきの境目は、汚れがたまりやすく虫歯になりやすい場所です。進行度別の色の変化や見た目の特徴を、以下の表にまとめています。
| 進行度 | 色の変化 | 見た目の特徴 |
| C0 | 白く濁る(白斑) | 穴はなく、表面のツヤが失われザラザラする |
| C1 | 茶色や黒い点・線 | 歯の溝などにごく小さな穴があく |
| C2 | 明らかな黒ずみ | 見てわかる大きさの穴があき、食べ物が詰まる |
| C3 | 大きな黒い穴 | 歯の形が崩れるほど大きく欠ける |
| C4 | 歯の色はほぼない | 歯冠部が崩壊し、歯の根だけが残る |
②痛み・しみ方から危険度を見極める
虫歯は痛みやしみ方から、内部でどのような状態が起きているかを推測できます。以下の症状がある場合は、進行している可能性が高いため注意しましょう。
- 冷たいもの・甘いものがしみる:象牙質が露出して刺激が神経に伝わりやすい状態
- 熱いものがしみる:神経が炎症を起こしている状態(歯髄炎)
- 何もしなくてもズキズキ痛む(自発痛):急性歯髄炎が悪化して強い痛みがある状態
- 噛むと痛い・響く:根の先が炎症を起こしている状態(根尖性歯周炎)
- 痛みが急になくなった:神経が死んで痛みを感じない状態(歯髄壊死)
上記の内容に当てはまれば、自己判断せず早急に歯科受診しましょう。
③前歯・奥歯・歯間を部位別にチェックする
虫歯は部位によって見つけやすさや進行の仕方が異なります。鏡やデンタルフロスを活用し、以下のポイントを確認しましょう。
| 部位 | 特徴 | チェックポイント |
| 前歯 | 鏡で直接見やすく比較的発見しやすい | 拡歯と歯の間や裏側に黒ずみや白濁がないか |
| 奥歯 | 溝が深く複雑で虫歯になりやすいが暗く見えにくい | デンタルミラーで溝が黒くなっていないかを明るい場所で確認 |
| 歯と歯の間(歯間) | 歯ブラシが届きにくく虫歯を見つけにくい | ・フロスが引っかかる、切れる ・使用後に腐ったような臭いがする ・歯ぐきが赤く腫れるまたは出血する |
④着色や知覚過敏との違いを見分ける
しみる症状や歯の変色は、虫歯以外の原因でも起こります。正確な診断は歯医者さんにしかできませんが、見分けるためのポイントは以下のとおりです。
| 項目 | 虫歯 | 着色(ステイン) | 知覚過敏 |
| 見た目 | 点や線状の黒ずみ、穴があく | ・歯の表面全体が黄ばむ ・茶色くなる | 見た目に変化は少ない(歯の根元が露出している場合も) |
| 表面の状態 | ザラザラして、器具で触ると引っかかる | 滑らか | 基本的に滑らか |
| 痛み・症状 | ・甘いものでも痛む ・持続的な痛みになる場合あり | 痛みはない | ・冷たいものや風で一瞬しみる ・痛みはすぐに消える |
上記の違いはあくまで目安です。気になる症状があれば、自己判断せずに受診しましょう。
⑤詰め物・被せ物の下の虫歯を見つける
治療した歯でも、詰め物や被せ物と歯の間にできた隙間から虫歯が再発することがあります。これを「二次カリエス(二次虫歯)」と呼びます。
詰め物の下で静かに進行するため発見が遅れやすく、気づいた時には大きく悪化していることもあります。以下のようなサインに注意しましょう。
境目の変色:詰め物・被せ物と歯の境目が黒っぽく変色している
段差や隙間:舌で触ると段差がある、食べ物が詰まりやすい
フロスの引っかかり:毎回同じ場所でフロスが引っかかる、糸がほつれる
しみる・痛む:冷たいものや甘いものでしみる、噛んだ時に違和感がある
歯ぐきの腫れや口臭:原因不明の口臭や、治療歯周辺の歯ぐきの腫れ
二次虫歯はレントゲンでしか確認できないことも多く、症状がなくても定期的な歯科検診でのチェックが重要です。
歯科医院で行う専門的な診断方法

歯科医院では、より専門的な診療器具や技術を用いて、正確に虫歯を診断することが可能です。どのような診断が行われるのか、詳しく見ていきましょう。
①視診
②触診
③レントゲン検査(X線撮影)
④ダイアグノデント(光学式う蝕検出装置)
⑤歯髄電気診
①視診
視診は、歯科診断の中で最初に行われる基本的な方法です。歯の形や大きさ、表面の凹凸、欠けやすり減りなどを肉眼で確認し、健康な部分と比較しながら異常を見極めます。色やツヤ、透明感の変化も虫歯や病変のサインになるため重要です。
また、歯ぐきの腫れや出血、膿の有無なども観察し、歯周病の可能性を判断します。デンタルミラーを使うことで奥歯や裏側まで見えるため、見逃しやすい部分の異常も発見できます。
②触診
歯の表面に以上が見られて、虫歯かどうかはっきりしない場合には、探針などの器具を用いて触診を行うことがあります。先端で軽く表面をなぞると、健康な歯質は滑らかですが、虫歯がある部分ではザラつきや引っかかり、小さな穴が感じられることがあります。
こうした触診により、見た目だけでは判別しづらい初期の虫歯を確認できるのが特徴です。
③レントゲン検査(X線撮影)
レントゲン検査は、肉眼では確認できない歯や歯根の内部を調べるために行われます。特に歯と歯の間や神経の近くなど、外から見えにくい部分の虫歯を発見するのに有効です。撮影すると虫歯の部分は黒く映り、進行の程度や炎症の有無を正確に把握できます。
必要に応じて、全体像を確認するパノラマや一部分を詳しく写すデンタルなどを使い分けます。
④ダイアグノデント(光学式う蝕検出装置)
歯科医院では、視診やレントゲンに加えて、専用の機器を用いた精密な検査を行うことがあります。その一つが「ダイアグノデント」と呼ばれる光学式う蝕検出装置です。
歯にレーザー光を当て、その反射を数値化することで虫歯の有無や進行度を調べます。特に初期の虫歯や歯の溝、歯と歯の間など、肉眼やレントゲンでは分かりにくい部分の診断に有効です。
短時間で痛みもなく測定できるため、経過観察や早期発見、治療方針の決定のために活用されています。
⑤歯髄電気診
歯髄電気診とは、歯に微弱な電流を流して神経(歯髄)が生きているかどうかを調べる検査です。刺激に対してしみるような感覚があれば神経が反応していると判断でき、まったく反応がなければ神経が死んでいる可能性があります。
この検査によって、神経を保存できるか、それとも根管治療が必要かを見極めることができます。視診やレントゲンでは分からない歯髄の状態を直接確認できるのが特徴です。
ここまで紹介したように、歯医者さんでは虫歯に関する専門的な検査を受けることができます。自己判断には限界があり、正確な診断には専門家の診察が不可欠です。専門的な検査を受けることで、自己判断では見落としがちな異常を早期に発見でき、それが適切な治療につながります。
虫歯を放置する3つのリスク

虫歯は放置すればするほど、確実に進行していきます。お口の中の問題にとどまらず、体全体の健康や経済面にも大きな影響を及ぼす可能性があります。虫歯を放置する3つのリスクは以下のとおりです。
①激しい痛み・口臭・全身疾患の可能性
②二次虫歯や抜歯リスクの増加
③治療の遅れによる費用・期間の負担
①激しい痛み・口臭・全身疾患の可能性
虫歯を放置すると、痛みや口臭などの不快な症状だけでなく、全身への影響も及ぶ危険があります。主なリスクは以下のとおりです。
- 激しい痛み:神経まで達したC3虫歯で強い脈打つ痛みが続く
- 痛みの急な消失:神経が死んだ歯髄壊死の可能性がある
- 口臭:虫歯穴の細菌と食べカスが発酵して強い悪臭を発生
- 全身疾患(歯性病巣感染):細菌が血流に入り、心内膜炎や脳梗塞のリスクを高める
特に激しい痛みが急に消えた場合は、治癒ではなく危険な進行のサインです。口臭は自覚しにくく、周囲に不快感を与えるだけでなく、対人関係にも影響します。
また、糖尿病や心臓疾患などの持病がある方は、全身疾患へのリスクがさらに高まるため、早期受診が重要です。
②二次虫歯や抜歯リスクの増加
虫歯を1本放置すると、その歯だけでなく口全体の環境が悪化します。虫歯菌が増えて唾液が酸性に傾き、隣の歯まで虫歯になるリスクが上昇します。
治療済みの歯でも詰め物や被せ物の下で再発する「二次虫歯」が起こりやすくなります。虫歯は進行が進むほど保存は難しくなり、抜歯の可能性が高まります。
進行度別の歯の状態や、抜歯の可能性を以下の表にまとめています。
| 進行度 | 歯の状態 | 抜歯の可能性 |
| C0〜C1 | エナメル質(表層)のみの虫歯 | 抜歯の可能性 |
| C2 | 象牙質まで進行した虫歯 | ほとんどない |
| C3 | 神経まで進行した虫歯 | 根管治療で残せる可能性が高い |
| C4 | 歯の大部分が崩壊した状態 | 高い |
C4では土台が残らず、抜歯せざるを得ないケースが多いです。歯を失うと噛み合わせが崩れ、隣の歯が傾いたり向かいの歯が伸びたりするなど、口全体のバランスも悪くなります。
③治療の遅れによる費用・期間の負担
虫歯治療は、早期発見・早期治療が負担の少ない方法です。進行度によって、治療にかかる費用と期間は下記のように大きく変わります。
| 進行度 | 主な治療法 | 通院回数の目安 | 費用目安(3割負担) |
| C1 | レジン充填(白い詰め物) | 1回 | 約2,000~3,000円 |
| C2 | インレー(詰め物) | 2~3回 | 約3,000~10,000円 |
| C3 | 患根管治療+クラウン(被せ物) | 4~8回以上 | 約10,000~20,000円 |
| C4 | 抜歯+ブリッジ/入れ歯 | さらに長期化 | 約20,000円~ |
上記の通院回数や費用はあくまで目安であり、治療内容や使用材料により変動します。
抜歯後にインプラントなどの自費診療を選ぶ場合は、数十万円の費用がかかることもあります。お口の小さな違和感に気づいた時に歯科医院へ相談することが、結果的に時間・健康・お金を守る最善の選択となるでしょう。
C0〜C4の5段階別に見る虫歯の治療法
虫歯の治療法は、進行度「C0〜C4」でそれぞれ異なります。早期の段階ほど治療はシンプルで、歯へのダメージも最小限に抑えられます。
虫歯の段階ごとの治療法は、大まかに以下の通りです。
①C0:再石灰化による経過観察
②C1:フッ素塗布で再石灰化の促進、虫歯の進行を抑制、レジンで部分修復
③C2:レジン、インレーで修復
④C3:根管治療を行いクラウンで歯を修復
⑤C4:抜歯と人工歯による機能回復
まとめ
歯の色やしみる感覚など、セルフチェックは虫歯のサインに気づくための大切な第一歩です。「これくらい大丈夫かな?」という自己判断が、気づかないうちに虫歯を悪化させてしまうこともあります。
虫歯は放置しても自然には治りません。受診を先延ばしにするほど、治療の痛みや期間、費用の負担は大きくなってしまいます。「虫歯かも?」と感じたら、迷わず歯科医院へ相談しましょう。
むし歯の関連コラム
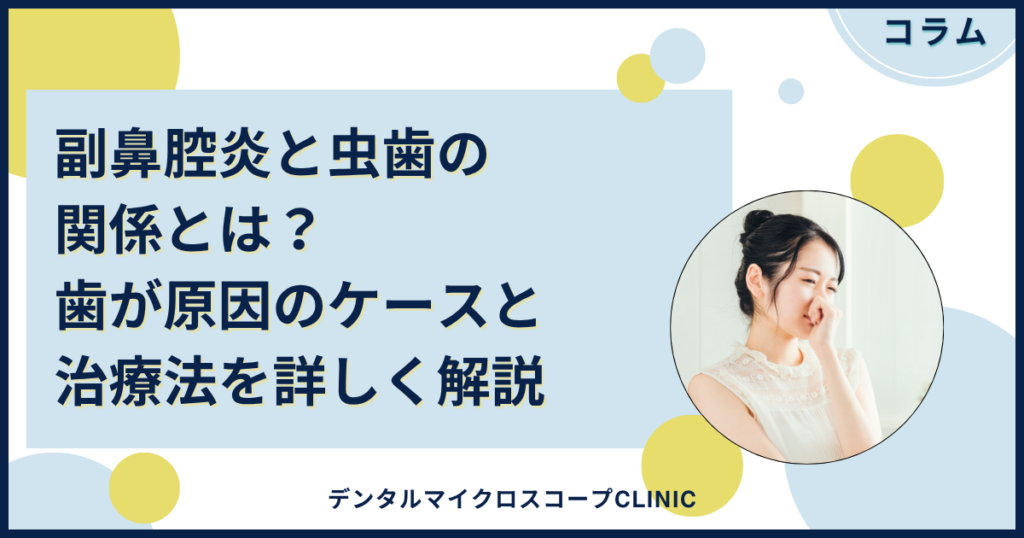
【医師監修】副鼻腔炎と虫歯の関係とは?歯が原因のケースと治療法を詳しく解説
耳鼻咽喉科で治療を続けているのに、片側の鼻づまりや頬の痛みが一向に良くならないと悩んでいませんか。しつこい鼻づまりや頬の痛みは、歯に原因があるかもしれません。上...
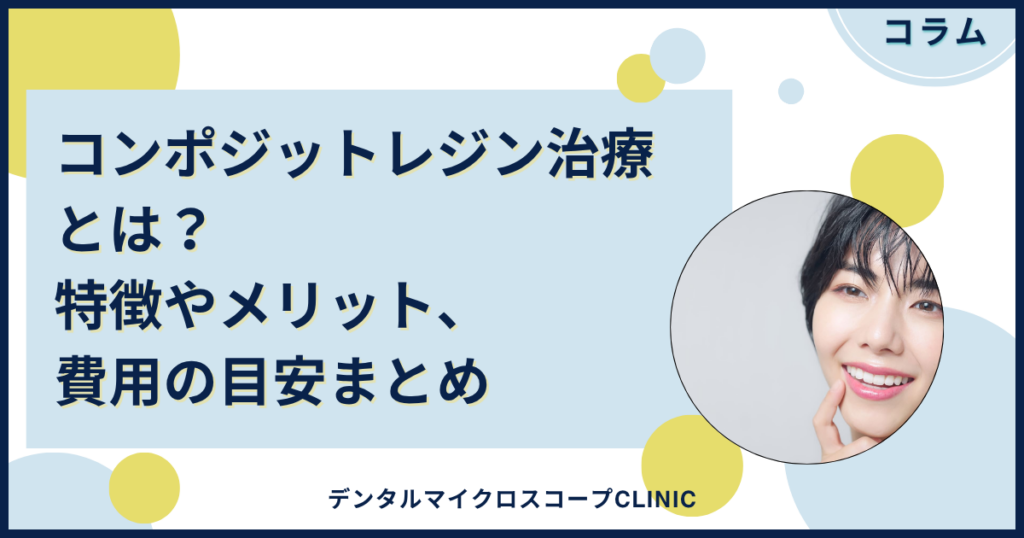
【医師監修】コンポジットレジン治療とは?特徴やメリット、費用の目安まとめ
コンポジットレジン治療は、歯の色に近い白い樹脂を使って、虫歯や欠けた部分を修復する方法です。多くの場合は1回の来院で治療が完了し、保険が適用されれば費用は比較的...
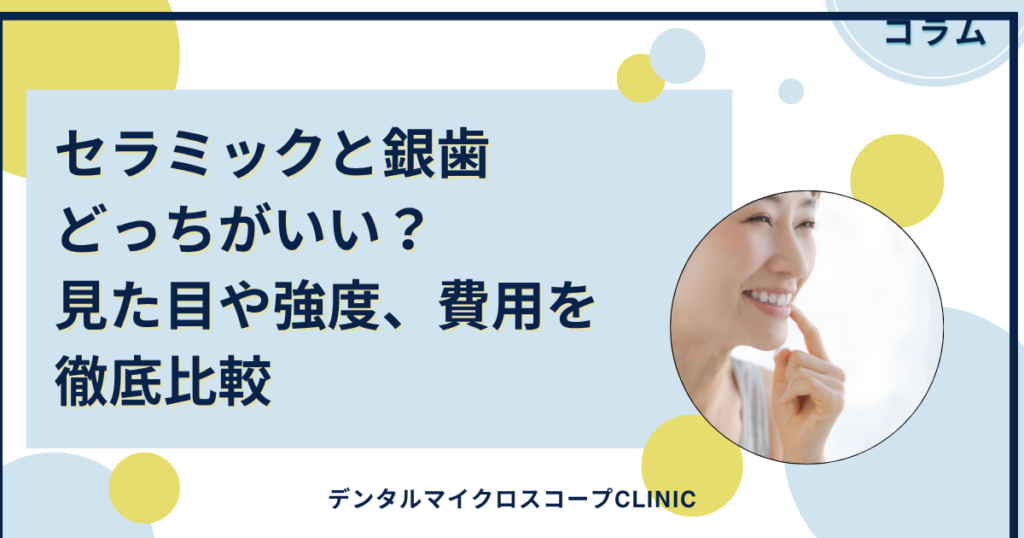
【医師監修】セラミックと銀歯どっちがいい?見た目や強度、費用を徹底比較
「保険の銀歯と自費のセラミック、どちらにしますか?」と尋ねられると、つい費用だけで選びがちです。しかし、その選択は10年後の口元の印象や、口全体の健康に大きな違...
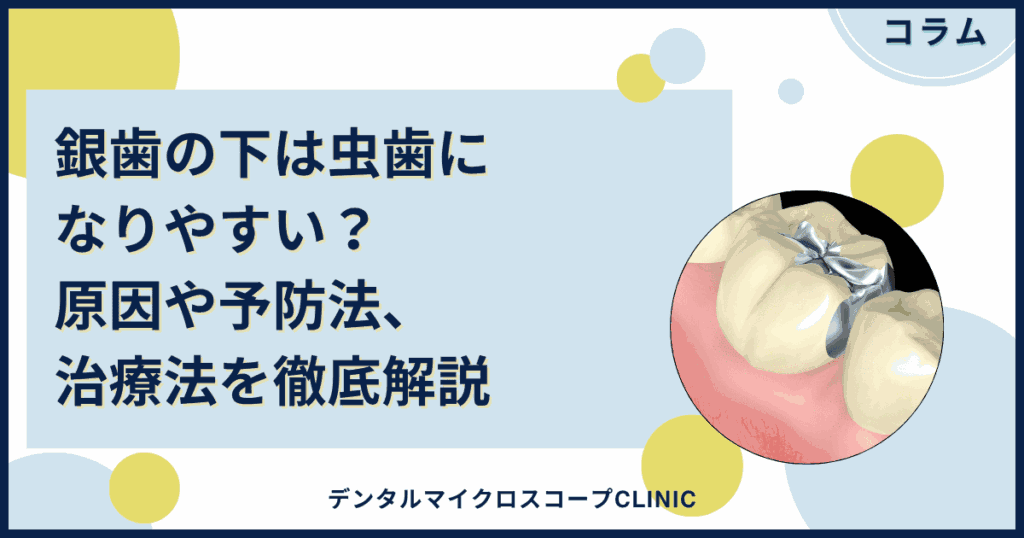
【医師監修】銀歯の下は虫歯になりやすい?原因や予防法、治療法を徹底解説
虫歯の治療を終えたはずなのに、再び痛みや違和感を感じて不安になった経験はありませんか。一度治療した銀歯の下に再び虫歯ができ、気づかないうちに症状が進行してしまう...
むし歯でおすすめの歯科医院

福岡・福岡市|ひどい虫歯や歯医者が怖い方は「痛みに配慮した治療」の池尻歯科医院へ
「ひどい虫歯を、ずっと見て見ぬふりしている…」「歯医者に行きたいけど、痛いのも、歯を削られるのも怖い」「もう虫歯を繰り返したくない」福岡市で虫歯治療でお悩みの方...

横浜市港北区・綱島でおすすめするマイクロスコープ精密歯科治療は高田歯科クリニック
横浜市港北区・綱島エリアでマイクロスコープを用いた精密な歯科治療をご希望の方へ。東急東横線「綱島駅」から徒歩3分の高田歯科クリニックは、医学的根拠(エビデンス)...
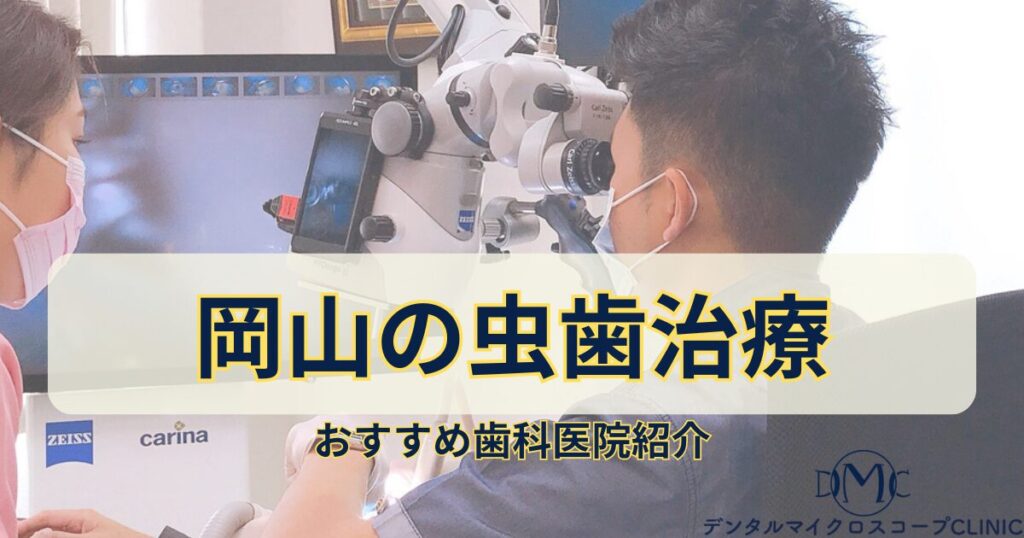
【岡山の虫歯治療】痛みが少ない・できる限り歯を削らない|おすすめの野亀歯科医院
冷たいものや甘いものがしみる、歯の表面に白い濁りや黒い筋がある…。虫歯を治療しなければと思いつつ、歯を削られる感覚や痛みが苦手で、歯科医院から足が遠のいていませ...
