虫歯は風邪とは違い、自然に治ることはありません。放置すれば静かに、しかし着実に進行し、やがては激しい痛みや抜歯など、最悪の結果を招くこともあります。
虫歯にはC0〜C4までの5つの進行段階があり、早い段階で発見し適切に対処できれば、治療の負担を大きく減らすことが可能です。この記事では、虫歯の進行度別に具体的な治療法を詳しく解説します。ご自身の歯の状態と照らし合わせ、手遅れになる前に、正しい知識を身につけましょう。
この記事の監修歯科医師

清水歯科 歯科医師
明石 陽介
愛知学院大学歯学部卒業。口腔外科、一般歯科診療に携わり
現在は、愛知県内の歯科医院にて訪問歯科診療を中心に活動。通院が難しい方にも安心して歯科治療を受けていただけるようサポート。
義歯治療や摂食嚥下の支援にも力を入れ、患者様一人ひとりの生活に寄り添った診療を大切にしている。
虫歯の進行度5段階

虫歯の進行度は、国際的に使われる基準で「C」と数字で分類されます。Cは虫歯を意味する「Caries」の頭文字です。
C0〜C4までの5段階があり、数字が大きくなるほど重症です。
C0:初期虫歯
C0(シーゼロ)は、虫歯菌が作り出した酸によって、歯の表面からミネラルが溶け出した「脱灰(だっかい)」という状態です。「初期う蝕」や「要観察歯」とも呼ばれ、まだ歯に穴は開いていません。
歯の表面がチョークのように白く濁ることがあり(ホワイトスポット)、奥歯の溝がうっすらと茶色っぽく見えることもあります。痛みやしみるなどの自覚症状はほとんどないので、ご自身で気づくことが難しい段階です。
この段階では歯を削る必要はなく、唾液には溶け出したミネラルを歯に戻す「再石灰化」という働きがあります。適切な歯磨きで汚れを落とし、フッ素を活用することで歯の質を強化し、再石灰化を促進できます。これにより歯が健康な状態に戻る可能性がありますが、あくまで進行が止まっているだけで治ったわけではありません。
経過観察またはフッ素塗布を行うことがあり、費用は保険適用で1,500〜3,000円程度です。
油断してケアを怠ると、簡単に次の段階(C1)へ進行してしまうので、歯科医院で定期的な検診を受けて進行していないかを経過観察することが重要です。
C1:エナメル質の虫歯
C1は、歯の一番外側を覆う、人体で最も硬い組織「エナメル質」の内部にまで虫歯が進行した状態です。この段階になると、残念ながら再石灰化による修復は期待できず、治療が必要になります。
歯の表面に黒い点や線が見られるようになり、見た目には小さな点でも内部で少し広がっていることがあります。痛みを感じることはほとんどなく、エナメル質には神経が通っていないため、この段階では痛みは感じません。冷たいものを飲んだ時に違和感を覚えることがあります。
痛みがないため放置されがちですが、この段階での治療が最も理想的です。治療は、虫歯に侵された部分だけを最小限に削り、歯科用の白いプラスチック(コンポジットレジン)を詰めるだけで済みます。費用は保険適用で1,000〜2,000円程度です。
多くの場合、1回の通院で治療が完了し、時間的・費用的な負担も少なくて済みます。この段階を逃すと、虫歯はより内部へと進行していきます。
C2:象牙質の虫歯
C2は、エナメル質の内側にある「象牙質(ぞうげしつ)」まで虫歯が達した状態です。この段階から、はっきりとした自覚症状が現れ始めます。
歯に黒い穴が見えるようになり、硬いエナメル質の入り口は小さくても、内側にある柔らかい象牙質で虫歯が急激に広がるため、内部では予想以上に大きな虫歯が進行していることがあります。
冷たいものや甘いものがしみるようになります。これは象牙質の中にある無数の細い管(象牙細管)を通じて、刺激が歯の神経に伝わるためです。
象牙質はエナメル質よりも柔らかく、虫歯の進行スピードが急速に速まります。しみる症状を我慢していると、あっという間に虫歯が神経まで進行してしまうため、一刻も早い治療が必要です。
虫歯の範囲が比較的小さければ、C1と同様にレジンを詰める治療で済むこともあります。しかし、虫歯が広範囲に及んでいる場合は、削った部分の型を取ってインレー(部分的な詰め物)を作成し、装着する必要があります。この場合、型取りと装着で最低でも2回の通院が必要です。
C3:神経まで進行した虫歯
C3は、虫歯が象牙質を突き破り、歯の中心部にある神経や血管の集まりである「歯髄(しずい)」まで到達した深刻な状態です。歯髄が細菌に感染し、強い炎症(歯髄炎)を起こします。
ここまで虫歯が進行すると、何もしていなくてもズキズキと脈打つような激しい痛み(自発痛)が生じます。温かいものを口にすると、炎症による内圧の高まりで痛みが悪化します。痛みがひどくなると、夜も眠れなくなったり、痛み止めが効きにくくなったりします。
この段階では、歯の神経を残すことは困難です。多くの場合、「根管治療」という、歯の根の中をきれいにする治療が必要になります。根管治療では、感染した神経や血管をすべて取り除き、歯の根の中を細い器具で清掃・消毒します。根管内が完全に無菌状態になった後、薬剤を詰めます。
その後、もろくなった歯を守るために土台を立て、クラウン(被せ物)で歯全体を覆います。この治療は複数回の通院を要するため、治療期間も長くなるのがデメリットです。治療費用に加えて、土台やクラウン(被せ物)の素材費もかかり、保険適用で1〜2万円程度かかります。
ただし、自由診療では費用は5万円〜20万円程度と高くなりますが治療回数を短くできるので、早めに治療を終えたい人は検討してみましょう。
C4:歯根だけ残った末期虫歯
C4は、虫歯の最終段階です。歯の見える部分(歯冠)が虫歯によってほとんど溶けて崩壊し、歯の根(歯根)だけが歯ぐきの中に残っている状態を指します。
C3であれほど激しい痛みを伴った歯の神経は死んでいるのでそのためズキズキとした痛みは一旦消えます。しかし、これは治ったわけではありません。根の先に膿の袋(根尖病巣)ができると、歯ぐきが大きく腫れたり、食べ物を噛めないほどの激痛が起こったりします。また、膿が原因で強い口臭が発生することもあります。
この状態では、歯を残せる可能性は低く、多くの場合、抜歯(歯を抜くこと)が選択されるのが一般的です。放置すると歯の根から顎の骨に細菌が広がり骨が溶けたり、細菌が血液に乗って全身に回り、心臓病や糖尿病などの深刻な全身疾患を引き起こす危険性もあります。
抜歯後は、失った歯の機能を補うために、ブリッジ、入れ歯、インプラントなど、さらに大がかりな治療が必要になります。
抜歯そのものは保険診療で1,000〜5,000円程度です。その後にブリッジや入れ歯を入れる場合は、保険適用で10,000〜30,000円程度かかります。インプラントを選ぶと自由診療となり、200,000円以上かかるケースもあります。
虫歯は自力で治せるのか

歯に穴が開く一歩手前の初期虫歯(C0)であれば、進行を食い止め、健康な状態に近づけられる可能性はあります。
私たちの唾液には、歯から溶け出したミネラルを修復する再石灰化(さいせっかいか)という力が備わっています。C0の段階なら、フッ素配合の歯磨き粉を使ったり、丁寧な歯磨きを意識したりすることで、進行を止められるのです。
しかし、これは治ったのではなく、あくまで進行が停止した状態です。油断すれば、すぐに穴が開くC1段階へと進んでしまいます。
一度でも歯に穴が開いてしまった虫歯(C1以降)は、市販の痛み止めで、一時的に痛みを和らげることはできますが、自然に元へ戻ることはありません。皮膚がすりむけても新しい皮膚ができるのとは違い、歯の組織には失われた部分を再生する能力がないためです。
症状がなくなったからと放置すると、虫歯は確実に進行します。気づいた時には神経を抜くか、抜歯しか選択肢がなくなるのです。
少しでも異変を感じたら、迷わず歯科医院を受診してください。
歯科医院で行う虫歯治療の主な選択肢3つ
虫歯の治療と聞くと、歯を削るイメージが強いかもしれません。しかし、歯科医院で行う治療は、虫歯の進行度に応じて大きく異なります。
歯は一度削ると、二度と元の健康な状態には戻りません。そのため、治療の基本方針は常に「いかに削る量を最小限に抑えるか」です。そして「失われた部分の機能と見た目を、いかに補うか」が重要になります。
ここでは治療法を大きく3つに分け、それぞれの特徴を解説します。ご自身の歯の状態と照らし合わせ、治療への理解を深めていきましょう。
詰め物治療(レジン・インレー)
比較的初期の虫歯(C1〜C2)に対して行われる、最も基本的な治療法です。虫歯に侵された部分だけを慎重に削り取り、その穴を材料で埋めて修復します。主に「レジン充填」と「インレー」の2つの方法があります。
| 項目 | レジン | インレー |
| 治療方法 | 直接詰めて固める | 型取りして詰め物を装着 |
| 適応 | 小さな虫歯、前歯 | 奥歯、大きな虫歯 |
| 素材 | 歯科用プラスチック | 金属(銀歯)、セラミック、ゴールド |
| 見た目 | 歯の色に近い | セラミックは天然の歯に近い、金属は目立つ |
| 耐久性 | 低め | 高い(セラミック、ゴールド) |
| 保険適用 | 保険適用 | 金属(銀歯)は保険、セラミックは自費 |
| 治療回数 | 1回 | 2回以上 |
| メリット | 低価格、自然な見た目、短時間治療 | 長持ち、強度が高い、審美性に優れる |
| デメリット | 変色しやすい、強度が低い | 自費診療の場合高額、治療回数が増える |
被せ物治療(クラウン・セラミック)
虫歯が広範囲に及ぶ場合や、神経の治療後に行われるのが被せ物(クラウン)治療です。歯の全体を冠のように覆うことで、弱くなった歯を補強します。歯の機能と見た目を大きく回復させることができる治療法です。
歯の神経を失うと、歯に栄養を送る血管も失われます。すると歯は、いわば枯れ木のような状態になり、もろく割れやすくなります。そのため、神経の治療後は、歯が破折するのを防ぐ目的で、被せ物による保護が不可欠です。
<治療の流れ>
【テキスト】
1. 虫歯を取り除き、歯を整える
2. 精密な型を取り、色や形を確認
3. 仮歯を装着し、1〜2週間待機
4. 完成した被せ物を装着し、治療完了
根管治療
虫歯が神経まで達したC3や、歯の頭の部分が崩壊したC4の状態では、根管治療が必要です。
根管治療では、歯の内部にある、細菌に汚染された神経や血管をきれいに取り除きます。そして、歯の根の中を徹底的に洗浄・消毒し、再感染を防ぐ処置を行うという流れです。
歯の根の中は、複雑に枝分かれしています。この見えない部分から細菌を完全に取り除くには、高度な技術と多くの時間を要します。そのため、治療回数は3〜5回、あるいはそれ以上かかることも珍しくありません。
治療の途中で痛みが和らぐと、通院をやめてしまう方がいらっしゃいます。しかし、根管内に細菌が残ったまま放置すると、中で再び感染が広がり、症状が悪化します。その結果、最終的に抜歯に至る可能性が高くなります。根管治療は、必ず最後まで完了させることが何よりも重要です。
虫歯を未然に防ぐ方法

歯科治療は完了した時点がゴールではなく、むしろ新たなスタートとして捉えても良いかもしれません。
一度人の手が加わった歯は、どうしても健康な天然の歯より弱くなります。治療を繰り返すたびに、ご自身の歯は少しずつ失われ、寿命も短くなります。つらい治療を繰り返さないためには、虫歯になった根本原因を見直すことが不可欠です。
虫歯は、高血圧や糖尿病と同じ生活習慣病の一種です。日々の小さな習慣の積み重ねが、お口の健康を大きく左右します。ここでは、歯を生涯守るための、具体的な予防法を3つ見ていきましょう。
- 毎日正しく歯を磨きフロスを使う
- 間食や糖分の摂取を控える
- 定期的に歯科検診とクリーニングを受ける
毎日正しく歯を磨きフロスを使う
虫歯予防の基本は、原因である歯垢(プラーク)を毎日確実に取り除くことです。歯垢は単なる食べカスではなく、細菌が塊になったものです。わずか1mgの歯垢に、約1〜10億個もの細菌がいるといわれています。
この細菌の塊を、いかに効率よく除去できるかが重要です。そのためには回数よりも質を重視した歯磨きが求められます。
実は、歯ブラシだけで丁寧に磨いても、歯の表面積の約60%しか清掃できません。残りの40%は、歯と歯の間や、歯と歯ぐきの境目です。これらの歯ブラシが届きにくい場所こそ、虫歯が最も発生しやすい場所なのです。
以下のセルフケア・チェックリストを参考に歯のケアを見直してみてください。
【虫歯予防のためのセルフケア・チェックリスト】
- 歯ブラシの当て方:歯と歯ぐきの境目に45度で毛先を当て、小刻みに優しく振動させて磨く。
- デンタルフロス・歯間ブラシ:歯と歯の間の汚れを取るため、最低1日1回フロスを使用する。
- 歯ブラシの交換:毛先が開いた歯ブラシでは効果が半減。遅くとも1か月に1回交換する。
間食や糖分の摂取を控える
お口の中では、食事のたびに脱灰と再石灰化が繰り返されています。
- 脱灰:食事で摂取した糖分が虫歯菌のエサとなり、酸を作り出し歯の表面からミネラルが溶け出す現象。
- 再石灰化:唾液が酸を中和し、溶け出したミネラルを歯に戻す働き。歯を修復する力。
健康な口内では、この2つのバランスが保たれています。しかし、間食の回数が多かったり、糖分を含む飲み物を飲み続けたりすると、お口の中が酸性になっている時間が長くなります。すると、再石灰化による修復が追いつかず、脱灰ばかりが進み、やがて歯に穴が開いて虫歯になってしまうのです。
特に、以下の習慣は虫歯のリスクを著しく高めるため注意が必要です。
- アメやガムを長時間口に入れている
- スポーツドリンクやジュースを水代わりに飲む
- デスクワーク中に甘いコーヒーや紅茶を頻繁に飲む
- お菓子を常に手の届く場所に置いている
就寝中は唾液の分泌量が大幅に減少し、お口の防御機能が最も低下します。この時間帯に飲食をすると、酸が中和されず、歯が長時間酸にさらされ続けることになります。寝る前の飲食は、虫歯予防の観点から最も避けるべき習慣です。
定期的に歯科検診とクリーニングを受ける
毎日丁寧にセルフケアを行っていても、残念ながら歯垢を100%除去することは不可能です。磨き残した歯垢は、約48時間で唾液中のミネラルと結びつき、石のように硬い「歯石」へと変化します。こうなると、歯ブラシでは取り除くことはできません。
さらに、歯の表面には「バイオフィルム」という、細菌が作り出した強力なバリアが形成されます。これは、キッチンの排水溝のヌメリのようなもので、内部の細菌を包み込んでしまいます。
この歯石とバイオフィルムを破壊・除去できる方法が、歯科医院で行う専門的なクリーニング(PMTC)です。
お口に問題を感じていなくても、3か月〜半年に1回は定期検診を受けましょう。
まとめ
虫歯は風邪と違い、極初期の段階を除いて放置しても自然に治ることはありません。「少ししみるだけ」「痛くないから大丈夫」と考え小さなサインを見過ごすと、気づいた時には神経の治療や抜歯しか選択肢がなくなってしまうこともあります。
この記事を読んで、ご自身の歯に少しでも気になる変化を感じた方は、どうか自己判断で放置せず、まずは一度歯科医院へ相談してみてください。早めに受診することで、治療の負担が減り、大切な歯を長く守るためには最も大事です。
むし歯の関連コラム
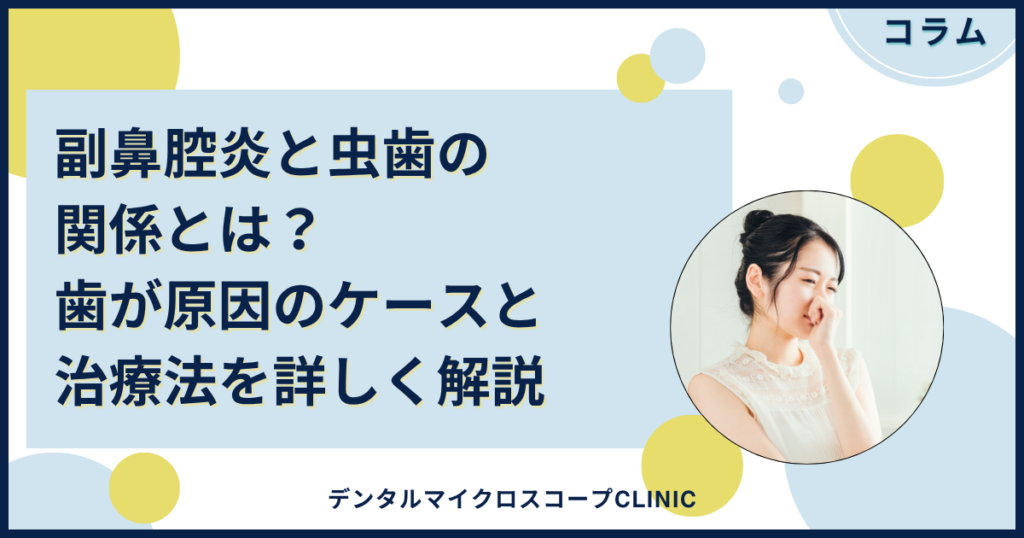
【医師監修】副鼻腔炎と虫歯の関係とは?歯が原因のケースと治療法を詳しく解説
耳鼻咽喉科で治療を続けているのに、片側の鼻づまりや頬の痛みが一向に良くならないと悩んでいませんか。しつこい鼻づまりや頬の痛みは、歯に原因があるかもしれません。上...
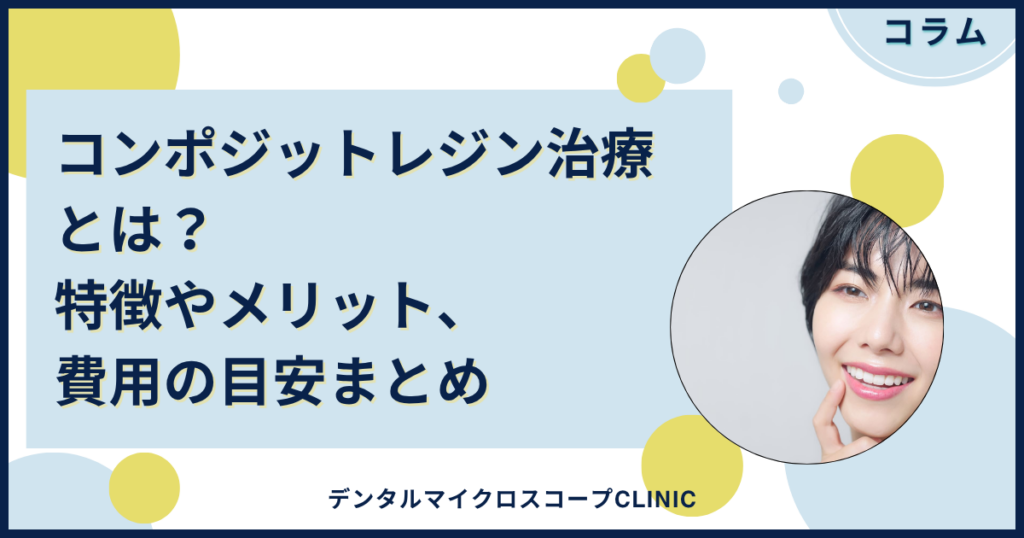
【医師監修】コンポジットレジン治療とは?特徴やメリット、費用の目安まとめ
コンポジットレジン治療は、歯の色に近い白い樹脂を使って、虫歯や欠けた部分を修復する方法です。多くの場合は1回の来院で治療が完了し、保険が適用されれば費用は比較的...
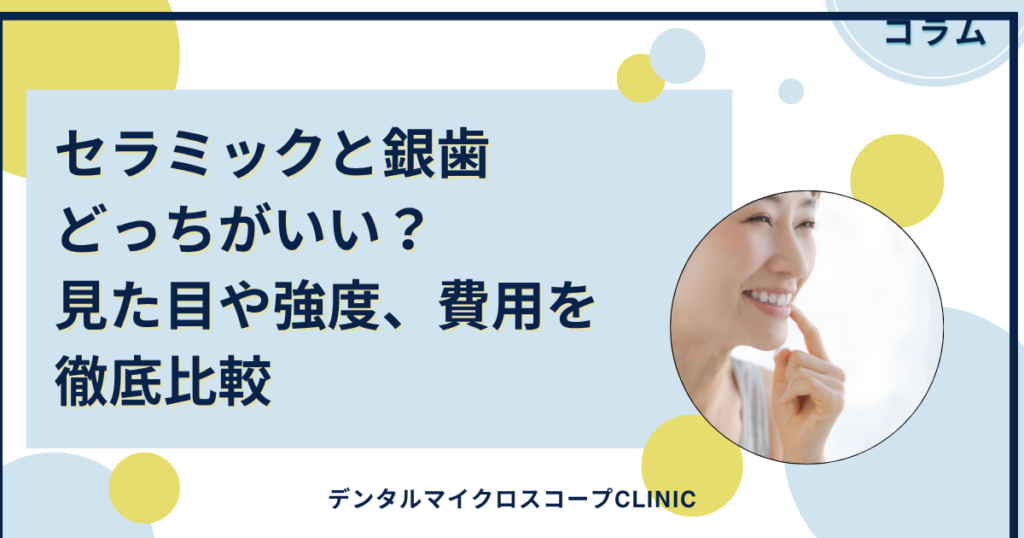
【医師監修】セラミックと銀歯どっちがいい?見た目や強度、費用を徹底比較
「保険の銀歯と自費のセラミック、どちらにしますか?」と尋ねられると、つい費用だけで選びがちです。しかし、その選択は10年後の口元の印象や、口全体の健康に大きな違...
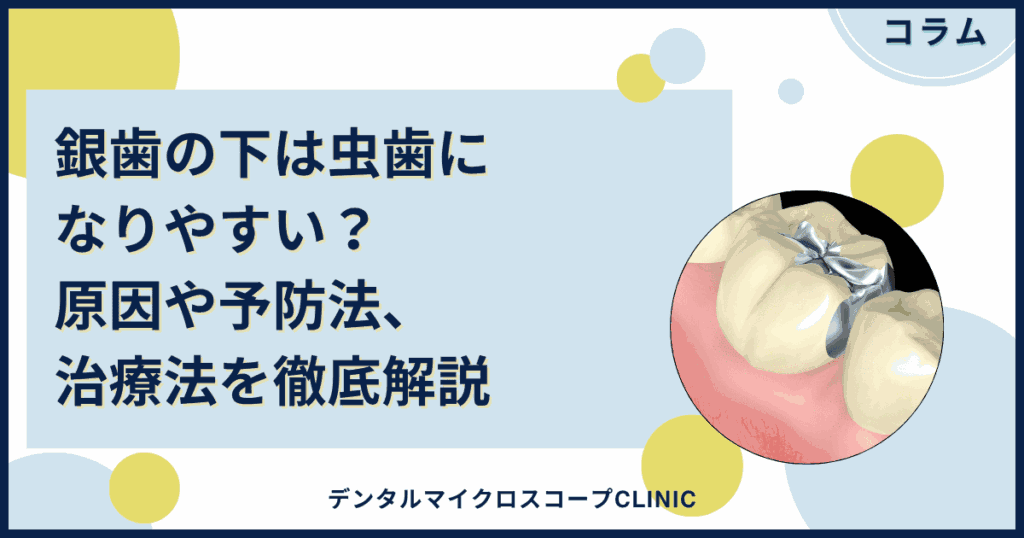
【医師監修】銀歯の下は虫歯になりやすい?原因や予防法、治療法を徹底解説
虫歯の治療を終えたはずなのに、再び痛みや違和感を感じて不安になった経験はありませんか。一度治療した銀歯の下に再び虫歯ができ、気づかないうちに症状が進行してしまう...
むし歯でおすすめの歯科医院

福岡・福岡市|ひどい虫歯や歯医者が怖い方は「痛みに配慮した治療」の池尻歯科医院へ
「ひどい虫歯を、ずっと見て見ぬふりしている…」「歯医者に行きたいけど、痛いのも、歯を削られるのも怖い」「もう虫歯を繰り返したくない」福岡市で虫歯治療でお悩みの方...

横浜市港北区・綱島でおすすめするマイクロスコープ精密歯科治療は高田歯科クリニック
横浜市港北区・綱島エリアでマイクロスコープを用いた精密な歯科治療をご希望の方へ。東急東横線「綱島駅」から徒歩3分の高田歯科クリニックは、医学的根拠(エビデンス)...
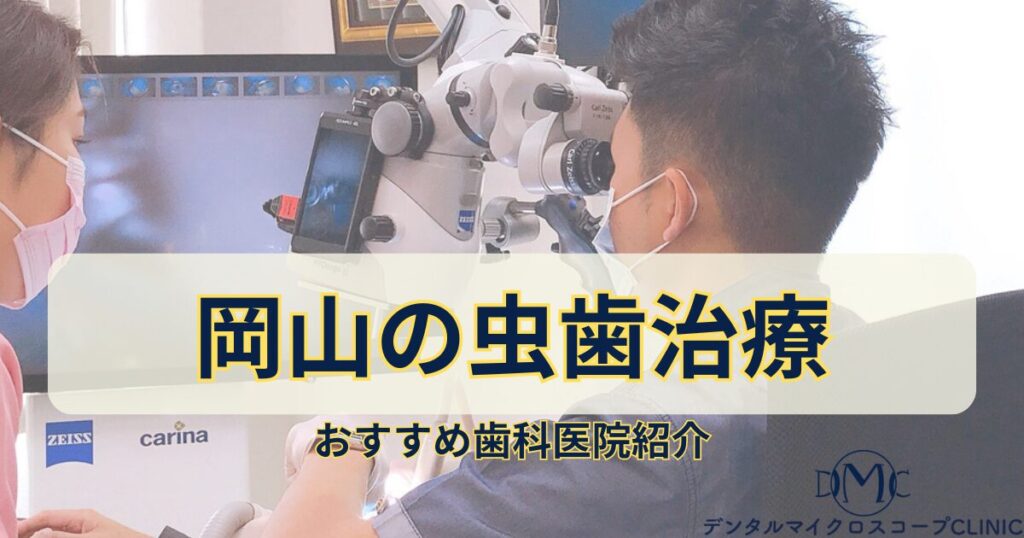
【岡山の虫歯治療】痛みが少ない・できる限り歯を削らない|おすすめの野亀歯科医院
冷たいものや甘いものがしみる、歯の表面に白い濁りや黒い筋がある…。虫歯を治療しなければと思いつつ、歯を削られる感覚や痛みが苦手で、歯科医院から足が遠のいていませ...
