「治療が終わったはずなのにズキズキ痛む」「この痛み、一体いつになったら治まるの?」歯の神経を抜いた後、多くの方が同じ不安を抱えます。体は治療後も回復のために働き続けており、その過程で痛みが生じることは珍しくありません。
この記事では、歯の神経を抜いた後は何日くらい痛むのか、そして痛みが治らない場合の対処法を解説します。
この記事の監修歯科医師

医療法人あかり会歯科
脇田奈々子
大阪大学歯学部卒業後、同大学予防歯科学教室にて医員として勤務。
現在は大阪市内の歯科医院で、予防歯科からインプラント、矯正治療まで幅広く対応している。治療の先の心のケアにもつながる“医療としての美容歯科”として、ボツリヌス治療、ヒアルロン酸注入、リップアートメイクにも注力している。
「口元の健康と美を通じて、最後まで美味しく食べ、自信を持って笑える人生」をサポートすることを理念としている。
歯の神経を抜いた後の痛みはいつまで続くのか

ここでは、歯の神経を抜いた後の痛みはいつまで続くのか、痛みが起こる理由について、詳しく解説します。ご自身の症状と照らし合わせ、回復までの見通しを立てるための参考にしてください。
痛みのピークは治療後2〜3日
歯の神経を抜いた後の痛みは、治療でかけた麻酔が切れてから徐々に始まり、治療当日〜3日後あたりにピークを迎えることが一般的です。その後、体自身の治癒力によって痛みは少しずつ和らぎ、多くの場合、1週間以内には日常生活に支障がない程度に落ち着きます。
ただし、痛みの強さや期間には個人差があります。虫歯の炎症が根の先まで及んでいたか、歯の根の形が複雑で治療に時間を要したかなど、治療前の状態によっても経過が異なるでしょう。
痛みの一般的な経過の目安を以下に示します。
| 時期 | 痛みの特徴と強さ | 日常生活でのポイント |
| 治療後〜3日目 | ズキズキとした拍動を伴う痛み | ・処方された鎮痛剤を指示通りに服用する・安静にする |
| 治療後4日〜1週間 | 鈍い痛みや、歯を押した時・噛んだ時に違和感がある | ・痛むときは鎮痛剤を服用する |
| 治療後1週間以降 | 患部のほとんど痛みを感じなくなるが軽い違和感が残ることもある | ・痛むときは鎮痛剤を服用する |
1週間を過ぎても強い痛みが続いたり、一度和らいだ痛みが再び強くなったりする場合は、別の原因が考えられます。我慢せずに治療を受けた歯科医院に相談しましょう。
神経を取っても痛むのは治療後の炎症が原因
治療後に痛みを感じる理由は、歯そのものではなく、治療の刺激によって歯を支える周りの組織が一時的に炎症を起こしているためです。
歯の根と骨の間には「歯根膜(しこんまく)」という、薄い膜があり神経や血管が豊富に通っています。噛んだときの硬さや感触を脳に伝える重要なセンサーです。
歯の神経を抜く治療で慎重に進めても、器具が歯根膜に物理的な刺激を与え小さな炎症が起る可能性があります。その他、消毒液や薬剤による刺激、噛み合わせによる刺激も原因となることもあります。
これらの痛みは、体の治癒とともに炎症が治まれば、自然に軽快していきます。
歯茎の腫れや軽い出血は一般的な術後症状
痛みと同時に、歯茎の腫れや軽い出血がみられることもありますが、これらも治療後の炎症反応に伴う症状の一つです。
歯茎の腫れ歯の根の先で起きている炎症が、周りの歯茎にまで影響を及ぼし、少し腫れることがあります。腫れも痛みと同様に、治療後2〜3日をピークに徐々に引いていくことがほとんどです。
腫れや熱っぽさを感じるときは、腫れている部分の頬の外側から、濡れタオルや保冷剤をタオルで包んだもので冷やしましょう。
10分冷やして10分休む、というように当てたり休ませたりを繰り返してください。冷やしすぎは血行不良の原因になるため注意しましょう。
歯の神経を抜いた後の痛みを和らげる5つの自宅ケア

ここでは、歯の神経を抜いた後の痛みを和らげる5つのケアをご紹介します。いずれも自宅で取り組めるものなので、ぜひ試してみてください。
- 鎮静剤の服用タイミングを知る
- 痛むときは頬を濡れタオルで冷やす
- 治療後に避けたほうが良い食品を知る
- 傷口を刺激しない歯磨きをする
- 痛みを悪化させる原因を知る
鎮痛剤の正しい服用タイミングを知る
歯科治療後に処方される鎮痛剤について、正しい飲み方と安全に使うための注意点を解説します。服用のポイントは以下の3つです。
- 痛み出す前に飲む
- 用法・用量は必ず守る
- 空腹時を避ける
鎮痛剤は、麻酔が切れる前や軽い痛みを感じ始めた時点で服用しましょう。その際、服用間隔や量は処方箋や薬剤師の指示を必ず守ってください。
自己判断で量を増やしたり間隔を詰めたりすると副作用のリスクが高まります。また、多くの鎮痛剤は胃に負担をかけるため、食事の後か、何か少しお腹に入れてから飲むようにしましょう。
処方された薬がなくなった場合、自己判断で市販の鎮痛剤を追加で服用することは避けてください。市販薬と処方薬では成分が重複していたり、飲み合わせが悪影響を及ぼしたりする可能性があります。必ず治療を受けた歯科医院に相談しましょう。
痛むときは頬を濡れタオルで冷やす
治療後のズキズキや腫れは炎症によるもので、濡れタオルやタオルで包んだ保冷剤を5〜10分当てて冷やすと和らぎます。長時間続けず、休みを挟みながら断続的に行いましょう。
冷やしすぎは血行を悪くし治りを遅らせるため注意が必要です。痛みや腫れが悪化する場合は、冷却だけで対応せず歯科医院に連絡してください。
治療後に避けたほうが良い食品を知る
治療後の歯やその周りの組織は、デリケートな状態です。食事の際に余計な負担をかけると、痛みを悪化したり、治りを遅らせたりする原因になります。
治療した歯に刺激を与えず、反対側の歯でゆっくり噛むようにしましょう。
避けたほうが良い食品と理由については以下の表を参考にしてください。
| 避けたほうが良い食品 | 理由 |
| 硬いもの(せんべい、ナッツ、硬い肉など) | 噛むときに強い力がかかるため |
| 熱すぎる・冷たすぎるもの(熱々のスープ、アイスなど) | 急激な温度変化が痛みを悪化させるため |
| 刺激の強いもの(香辛料、酸っぱいものなど) | 化学的刺激が痛みの原因となる。 |
| 粘着性の高いもの(キャラメル、餅、ガムなど) | 治療中につめている仮蓋や被せ物が取れてしまうリスクがある |
一方で、体力を回復させ、傷の治りを早めるためには、栄養をしっかり摂ることも大切です。
傷口を刺激しない歯磨きをする
治療後の痛みで歯磨きをためらいがちですが、口内を不潔にすると細菌が繁殖し、傷の治りを遅らせる原因になります。感染を防ぎ、順調な回復を促すために、以下の3つのことを守りましょう。
- 歯ブラシの選択:ヘッドが小さく、毛の硬さが「やわらかめ」のものを選ぶ
- 磨き方:治療した歯やその周りを避け、他の健康な歯から一本一本丁寧に磨く
- 歯磨き粉:低刺激性のものを選ぶ
うがいは静かに行いましょう。勢いよくすると傷口が開いて強い痛みにつながります。ぬるま湯や洗口液は、含んだらそっと吐き出してください。
痛みを悪化させる原因を知る
治療後、痛みのピークである2〜3日の間は、血行が良くなる行動は避けましょう。特に「飲酒」「激しい運動」「喫煙」は治癒そのものを妨げる大きな要因となります。
飲酒・激しい運動は、全身の血流を促進させる作用があります。血行が良くなると、炎症を起こしている部分の血管が拡張し、神経がより強く圧迫されて「ズキズキ」とした拍動性の痛みが増します。
また、血圧が上がることで、一度止まったはずの傷口から再び出血するリスクもあります。治療当日はシャワーで済ませ、しばらくは安静に過ごすよう心がけましょう。
タバコに含まれるニコチンは、血管を強く縮める働きがあるので要注意です。そのせいで歯ぐきなどの傷のまわりに血液が流れにくくなり、傷の治りが遅くなってしまいます。
血流が悪くなると、傷の修復に必要な酸素や栄養素が行き渡らなくなり免疫機能が落ちて、感染に対する抵抗力が落ちます。
歯科医師に相談すべき3つのケース

ここでは、どのような場合に歯科医院へすぐに連絡すべきか、具体的な3つのケースを詳しく解説します。
1週間以上も痛みが改善しない
治療後の痛みは、通常2〜3日後がピークであり、1週間もすれば日常生活に支障がないレベルまで落ち着くのが一般的です。もし、1週間を過ぎても強い痛みが続き、また痛みが再びぶり返して悪化する場合は注意しましょう。
考えられる主な原因には、以下のようなものがあります。
- 神経の取り残し
- 歯根のひびや破折
- 薬剤による化学的刺激
- 根管内の細菌の取り残し
これらの状態を放置すると、炎症があごの骨にまで広がるなど、治療がより難しく大がかりになる可能性があります。「もう少し様子を見よう」と自己判断せず、痛みが長引く場合は治療を受けた歯科医院へ相談しましょう。
急性炎症を起こしている
痛みだけでなく、体に明らかな異常のサインが現れた場合は、緊急性が高いと考えられます。通常の回復で見られる軽い腫れとは違い、もし次のような症状が出ている場合は要注意です。根の中で細菌が増えて、強い炎症(急性根尖性歯周炎)を起こしている可能性があります。
- 発熱
- 強い腫れ
- 開口障害
- 排膿(はいのう)
これらの状態を放置すると炎症があごの骨にまで広がり、骨が溶けたり骨髄炎になったりします
ごく稀ですが、細菌が血液に乗って全身に回り、重篤な状態を引き起こす危険性もゼロではありません。ためらわずに、すぐに歯科医師の診察を受けてください。
鎮痛剤が効かない
歯科医院で処方される鎮痛剤は、術後の正常な範囲の痛みをコントロールするために処方されます。そのため、「指示通りに飲んでも全く痛みが和らがない」「薬が切れると、仕事や睡眠もままならないほどの激痛に襲われる」という状況は異常が起こっているサインです。
こうしたケースでは、以下のような状態が考えられます。
- 歯の根の先に膿が大量に溜まり、内側からの圧力が高まっている
- 炎症の範囲が広範囲に及び、鎮痛剤で抑えきれないほど強い炎症が起きている
- 取り残された神経が過敏に反応し、激しい痛みを引き起こしている
処方された鎮痛剤で痛みをコントロールできない場合は、。遠慮なく歯科医院に連絡し、現状を正確に伝えてください。
まとめ
治療後の痛みは、2〜3日後をピークに1週間ほどで落ち着くことがほとんどです。これは体が回復しようとしている正常な反応なので、過度に心配しすぎず、処方された鎮痛剤や患部の冷却、食事の工夫などで上手に乗り切りましょう。
ただし、痛みが長引いたり日ごとに悪化したり、強い腫れや膿が出たりする場合は、別の原因が隠れているサインかもしれません。不安な症状があれば、すぐに治療を受けた歯科医院に相談しましょう。
むし歯の関連コラム
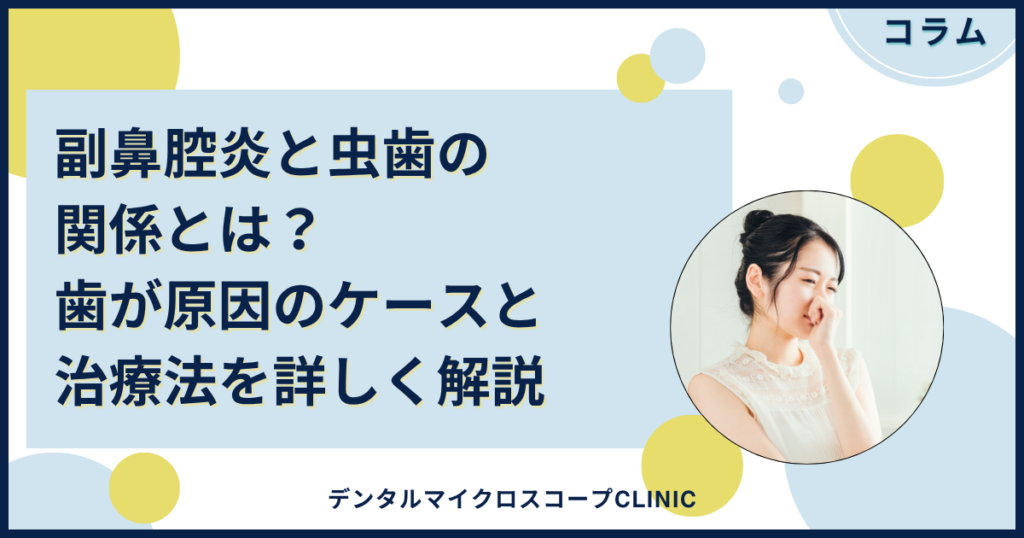
【医師監修】副鼻腔炎と虫歯の関係とは?歯が原因のケースと治療法を詳しく解説
耳鼻咽喉科で治療を続けているのに、片側の鼻づまりや頬の痛みが一向に良くならないと悩んでいませんか。しつこい鼻づまりや頬の痛みは、歯に原因があるかもしれません。上...
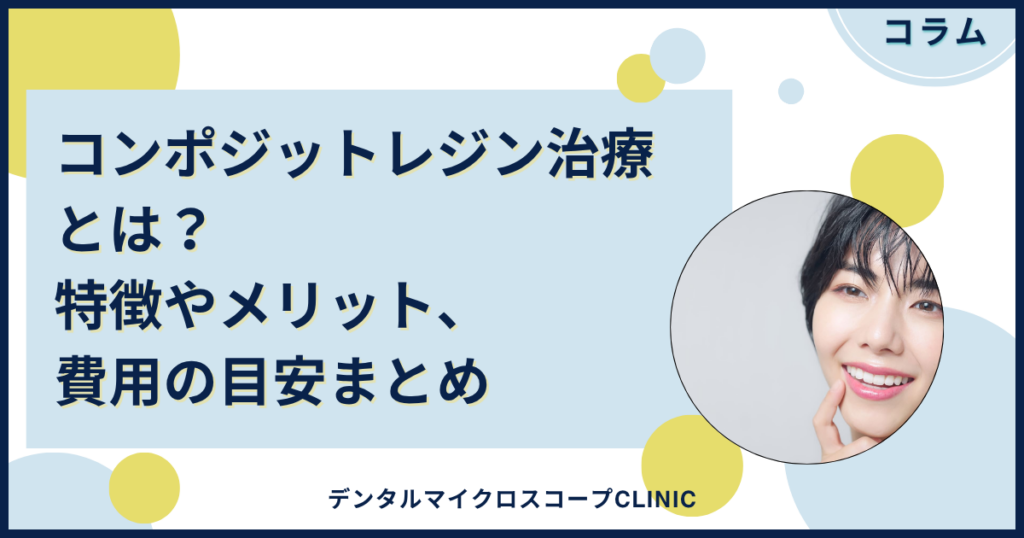
【医師監修】コンポジットレジン治療とは?特徴やメリット、費用の目安まとめ
コンポジットレジン治療は、歯の色に近い白い樹脂を使って、虫歯や欠けた部分を修復する方法です。多くの場合は1回の来院で治療が完了し、保険が適用されれば費用は比較的...
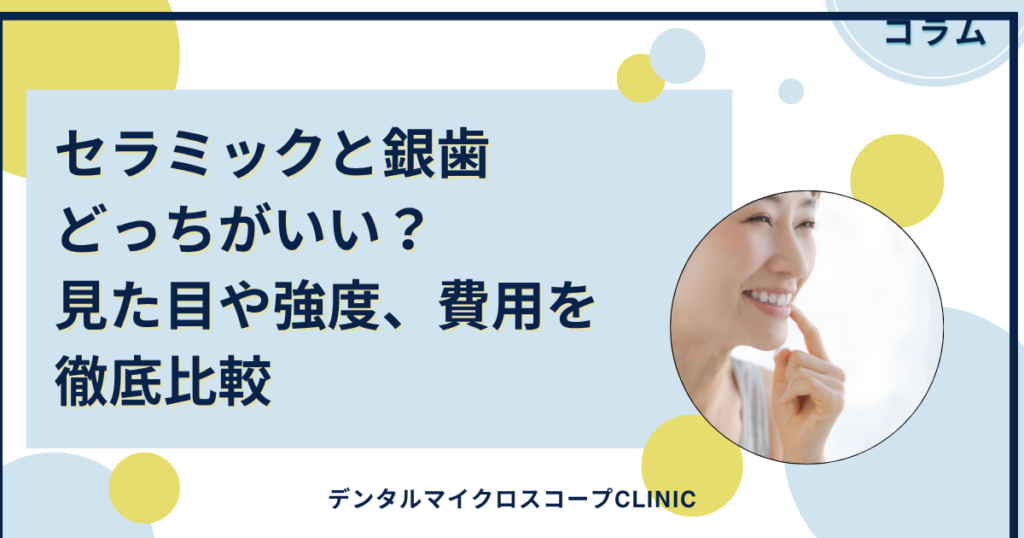
【医師監修】セラミックと銀歯どっちがいい?見た目や強度、費用を徹底比較
「保険の銀歯と自費のセラミック、どちらにしますか?」と尋ねられると、つい費用だけで選びがちです。しかし、その選択は10年後の口元の印象や、口全体の健康に大きな違...
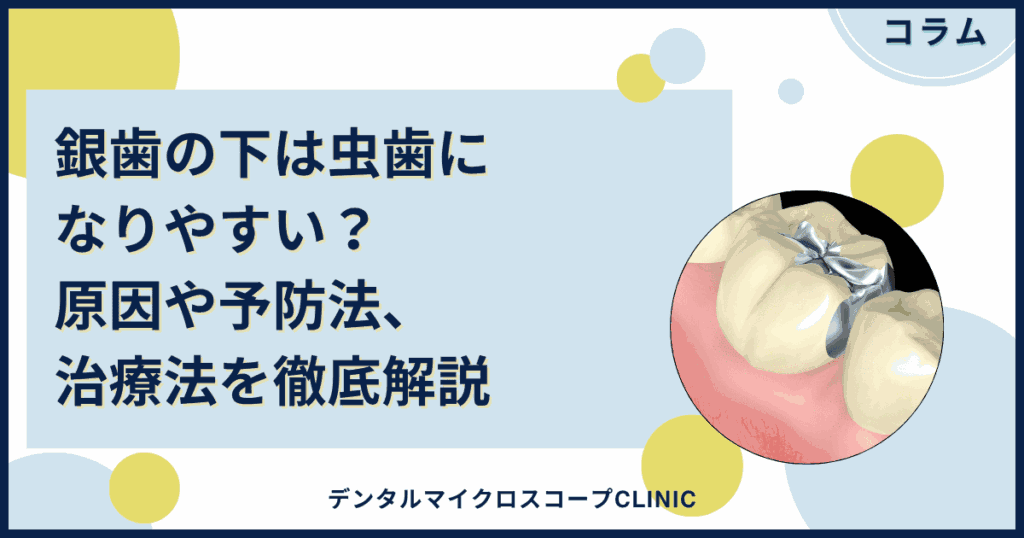
【医師監修】銀歯の下は虫歯になりやすい?原因や予防法、治療法を徹底解説
虫歯の治療を終えたはずなのに、再び痛みや違和感を感じて不安になった経験はありませんか。一度治療した銀歯の下に再び虫歯ができ、気づかないうちに症状が進行してしまう...
むし歯でおすすめの歯科医院

福岡・福岡市|ひどい虫歯や歯医者が怖い方は「痛みに配慮した治療」の池尻歯科医院へ
「ひどい虫歯を、ずっと見て見ぬふりしている…」「歯医者に行きたいけど、痛いのも、歯を削られるのも怖い」「もう虫歯を繰り返したくない」福岡市で虫歯治療でお悩みの方...

横浜市港北区・綱島でおすすめするマイクロスコープ精密歯科治療は高田歯科クリニック
横浜市港北区・綱島エリアでマイクロスコープを用いた精密な歯科治療をご希望の方へ。東急東横線「綱島駅」から徒歩3分の高田歯科クリニックは、医学的根拠(エビデンス)...
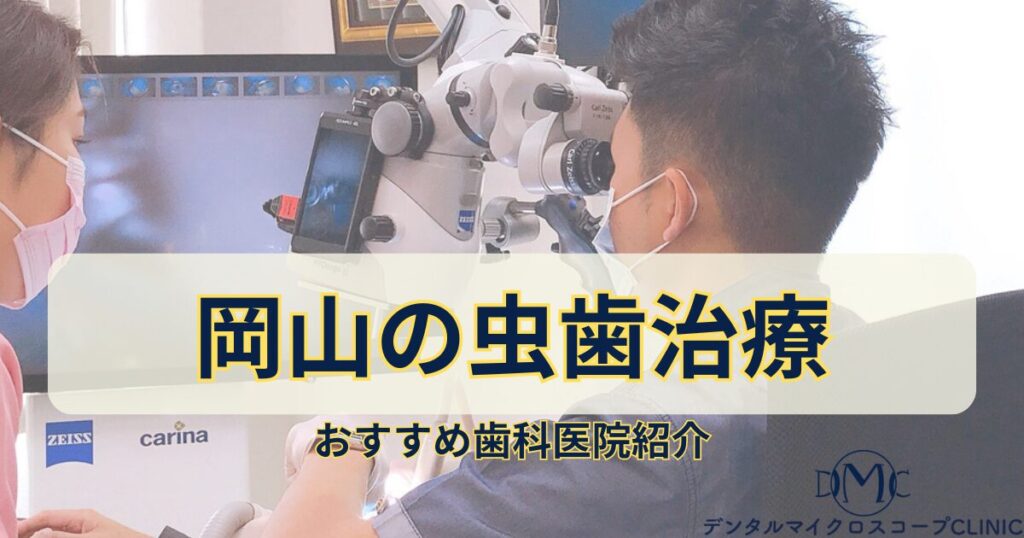
【岡山の虫歯治療】痛みが少ない・できる限り歯を削らない|おすすめの野亀歯科医院
冷たいものや甘いものがしみる、歯の表面に白い濁りや黒い筋がある…。虫歯を治療しなければと思いつつ、歯を削られる感覚や痛みが苦手で、歯科医院から足が遠のいていませ...
