耳鼻咽喉科で治療を続けているのに、片側の鼻づまりや頬の痛みが一向に良くならないと悩んでいませんか。しつこい鼻づまりや頬の痛みは、歯に原因があるかもしれません。
上の奥歯と鼻の奥にある副鼻腔は解剖学的に近く、人によっては1mmにも満たない薄い骨で隔てられているだけです。位置が近いため、重度の虫歯や歯周病を放置すると、細菌が副鼻腔にまで達し、薬だけでは治りにくい歯性上顎洞炎を引き起こします。(※1)
この記事では、歯が原因となる副鼻腔炎の特有の症状や見分け方、適切な病院選びを詳しく解説します。長引く不調の根本原因を知り、正しい治療への一歩を踏み出しましょう。
この記事の監修歯科医師

谷川歯科医院
谷川 淳一 副院長
歯科医師。日本口腔インプラント学会専修医。小児歯科治療や小児矯正、インプラント治療を得意とし、他の歯科医師への指導も行う。
患者様一人ひとりと真摯に向き合って治療方針を決めていくことを信条としている。
目次
副鼻腔炎とは

副鼻腔炎(蓄膿症)は、頬・目の奥・おでこにある空洞(副鼻腔)の粘膜が炎症を起こし、膿がたまる病気です。風邪などをきっかけに粘膜が腫れて出口(排泄路)がふさがることで、鼻づまりや頬・頭の重い痛みが生じます。
ここでは、副鼻腔炎に関する以下の内容を解説します。
- 主な症状(鼻づまり・頬の痛み・発熱など)
- 種類
主な症状(鼻づまり・頬の痛み・発熱など)
副鼻腔炎を発症すると、鼻だけでなく顔全体にさまざまな不快な症状が現れます。主な症状は以下のとおりです。
| 症状の場所 | 症状 |
| 鼻の症状 | ・しつこい鼻づまり ・粘性の黄〜緑色の鼻汁 |
| 顔の痛みや圧迫感 | ・頬の圧痛 ・目の奥の痛み ・おでこの圧迫感 ・頭重 ・咬合痛 |
| 全身の症状 | ・頬の圧痛 ・目の奥の痛み ・おでこの圧迫感 ・頭重 ・咬合痛 |
これらの症状は一つだけ現れることもあれば、複数が同時に現れることもあります。特に顔の痛みや頭痛が強い場合は、我慢せずに医療機関を受診しましょう。
種類
副鼻腔炎は、症状が続く期間によって急性副鼻腔炎と慢性副鼻腔炎に分類されます。急性副鼻腔炎は、発熱や顔面痛、頭痛などが強く、4週間以内に改善することが一般的です。(※2)一方、慢性副鼻腔炎は軽めの痛みに加え、鼻づまりや後鼻漏(鼻水が喉の奥に流れ落ちる症状)が12週以上続きます。(※2)
どちらの種類も主な原因は以下のとおりです。
| 原因 | 仕組み |
| ウイルス性・細菌性 | 風邪ウイルスで粘膜が弱り、二次的に細菌感染が加わって炎症が拡大 |
| アレルギー性 | アレルギー性鼻炎で粘膜腫脹し、副鼻腔の換気・排泄が悪化 |
| 歯性(歯性上顎洞炎) | 虫歯・歯周病・根尖病巣などから上顎洞へ感染が波及 |
慢性副鼻腔炎は、急性副鼻腔炎が長引くことで発症するケースもある点には注意してください。
歯が原因の鼻づまり?歯性上顎洞炎の症状と原因
ここでは、歯が原因で起こる歯性上顎洞炎(しせいじょうがくどうえん)の基本的な知識として、以下の内容を解説します。
- 歯性上顎洞炎とは?虫歯から副鼻腔炎になる
- 片側の頬の痛み・悪臭・鼻づまりなど主な症状
- 原因になる歯の病気
- 通常の副鼻腔炎との違いと見分け方
歯性上顎洞炎とは?虫歯から副鼻腔炎になる
歯が原因で起こる副鼻腔炎を歯性上顎洞炎と呼びます。歯性上顎洞炎は、上の奥歯の細菌が、顔にある上顎洞という副鼻腔に侵入し、炎症を起こして膿が溜まってしまう病気です。
歯性上顎洞炎が起こる仕組みは、以下のとおりです。
1.重度の虫歯や歯周病ができる
2.放置することで歯の根の先端に細菌の巣ができる
3.細菌が歯の根と上顎洞を隔てている薄い骨を少しずつ溶かしていく
4.骨を突き破り、細菌が本来は無菌であるはずの上顎洞に侵入する
5.上顎洞内で細菌が繁殖し、強い炎症反応が起こって膿が溜まる
上顎洞とつながっているのは上の奥歯だけなので、下の歯の虫歯が原因で歯性上顎洞炎になることはありません。
片側の頬の痛み・悪臭・鼻づまりなど主な症状
歯性上顎洞炎になると、原因のある歯側の頬の痛みや腫れ、鼻づまり、悪臭を伴う膿性鼻汁などの症状が見られます。歯の痛みや上顎洞の内圧上昇による顔面痛・頭痛が現れることもあるでしょう。風邪が原因で起こる一般的な副鼻腔炎とは症状が異なります。
これらの症状は、通常の副鼻腔炎で使われる抗菌薬だけでは改善しにくい傾向です。耳鼻咽喉科の治療を続けても症状が良くならない場合は、歯が原因ではないかと疑ってみることが重要です。
原因になる歯の病気
歯性上顎洞炎を引き起こすのは、重度の虫歯だけではありません。口腔内の細菌感染が関わる以下のような病気が、原因となります。
- 重度の虫歯
- 根尖病巣(歯の根の先で細菌感染が起こる病気)
- 重度の歯周病
- インプラント周囲炎
- 歯の破折
- 抜歯後の感染
通常の副鼻腔炎との違いと見分け方
歯性上顎洞炎と、風邪やアレルギーが原因の通常の副鼻腔炎との違いを以下の表にまとめました。
| 比較項目 | 歯性上顎洞炎 | 通常の副鼻腔炎 |
| 通常の副鼻腔炎 | 片側のみに起こることが多い(原因歯がある側) | 両側に起こることが多い |
| 鼻水の臭い | 強い悪臭(腐敗臭など)を伴うことが多い | 臭いがないか、あっても弱い |
| 歯の症状 | 特定の歯に噛んだり、叩いたしたときに痛みがある | 歯の症状はほとんどない |
| 発症のきっかけ | 虫歯・抜歯などの歯科治療後の感染で発症しやすい | 風邪やアレルギーの悪化などに伴って発症する |
| 治療への反応 | 耳鼻咽喉科の薬だけでは治りにくく、歯科治療で改善しやすい | 耳鼻咽喉科の治療で反応しやすい |
気になる症状があれば、まずは医療機関を受診し、適切な診断を受けることが解決への第一歩となります。
歯性上顎洞炎かも?受診の流れと病院の選び方

歯性上顎洞炎の疑いがある方に向けて、医療機関の受診に関する以下の内容を解説します。
- 歯科・口腔外科・耳鼻咽喉科のどこを受診すべきか
- 診断に必要な検査(レントゲン・CT)の流れ
- マイクロスコープを用いた精密診断の役割
- 歯科と耳鼻咽喉科が連携する医療機関の探し方
歯科・口腔外科・耳鼻咽喉科のどこを受診するべきか
歯性上顎洞炎が疑われるとき、最初の受診先はつらい症状に応じて選びましょう。症状別のおすすめ受診科は以下のとおりです。
| 主な症状 | 推奨される最初の受診先 | 理由 |
| 鼻の症状が強い | 耳鼻咽喉科 | まずは副鼻腔炎の診断を確定させ、アレルギーなど他の原因がないかを確認するため |
| 歯の症状が強い | 歯科・口腔外科 | 歯のレントゲン撮影などで直接的な原因を特定するため |
| 鼻と歯の両方の症状がある | 歯科・口腔外科または耳鼻咽喉科 | 歯性上顎洞炎の可能性が高く、どちらの診療科を先に受診しても構わない |
ご自身の症状で判断に迷う場合は、まずかかりつけの歯科医院か耳鼻咽喉科に相談してみましょう。ただし、鼻と歯の症状が両方ある方は、歯科と耳鼻咽喉科が連携している病院を選ぶと、治療がスムーズになります。
診断に必要な検査(レントゲン・CT)の流れ
歯性上顎洞炎の診断を正確に行うためには、レントゲンやCTで目に見えない部分の状態を画像で確認することが不可欠です。
診断の際は、まずレントゲンで歯全体を撮影し、根尖病巣や上顎洞の濁りがないかを確認します。レントゲン撮影後、CTで検査し、歯性上顎洞炎の確定診断を行います。
CTは三次元で以下の内容を確認できるため、レントゲンで見えない部分の検査も可能です。
1.原因の特定:歯根と上顎洞の位置関係や骨の厚さがわかる
2.炎症範囲:上顎洞内の広がりと程度を立体的に確認できる
3.微細病変:歯の亀裂や隠れた病巣も検出できる
耳鼻咽喉科でCTを撮影した場合でも、歯の状態をより詳しく調べるために、解像度の高い歯科用CTでの再撮影が必要になることがあります。
マイクロスコープを用いた精密診断の役割
歯性上顎洞炎の原因となる歯の治療を行う際は、患部を数倍〜数十倍に拡大して治療できるマイクロスコープ(歯科用顕微鏡)の使用が重要です。マイクロスコープは、肉眼では確認できないレベルでの精密な診断と治療を実現します。
マイクロスコープは感染源の特定と除去をより正確に行い、根管内の取り残しや穿孔のリスクを低減します。結果として治療精度が向上し、再発率の低下・治療期間の短縮・抜歯回避につながるでしょう。(※3)
マイクロスコープ画像を共有することで、患者さん自身が状態を視覚的に理解しやすくなり、説明の透明性と信頼性の向上にも貢献します。
歯科と耳鼻咽喉科が連携する医療機関の探し方
歯性上顎洞炎の治療を成功させるために、以下のような方法で歯科と耳鼻咽喉科が連携する医療機関を探しましょう。
- 「歯性上顎洞炎」「歯科口腔外科 耳鼻咽喉科 連携」でウェブ検索
- 総合病院・大学病院の調査
- かかりつけ医への連携先の紹介依頼
ウェブ検索する際は、症例実績や設備の情報(マイクロスコープの有無など)をチェックすることが大切です。実績が豊富で精密診断・治療が可能な医療機関を選ぶことをおすすめします。
総合病院や大学病院で治療を受けたい場合は、紹介状が必要なことがあるため注意してください。事前に紹介状の要否を確認することが重要です。
歯性上顎洞炎の治療法
歯性上顎洞炎と診断されたときの治療法に関する以下の内容を解説します。
- 歯科で行う治療:根管治療か抜歯かの判断
- 耳鼻咽喉科での治療:薬と内視鏡手術(ESS)
- 治療期間と保険適用される費用の目安
歯科で行う治療:根管治療か抜歯かの判断
歯科での治療の目的は、感染源の完全除去であり、以下のような方法で行われます。
| 治療法 | 判断基準 | 内容 | メリット | 注意点 |
| 根管治療 | 歯の保存が可能で感染が根管内に限局 | 根管を洗浄・消毒し、薬剤を充填する | 自分の歯を残せる | 術者の技量・設備の影響が大きい |
| 抜歯 | ・重度う蝕崩壊 ・歯根破折 ・重度歯周病 ・再根管治療でも制御不能 | 原因歯を除去し感染源を断つ | 症状がすみやかに改善することが多い | 歯が失われるので、ブリッジや入れ歯などで補綴が必要 |
どちらの治療法が最適かは、CTなどの精密な検査結果にもとづき、歯の状態や患者さんの希望を考慮して総合的に判断されます。
耳鼻咽喉科での治療:薬と内視鏡手術(ESS)
耳鼻咽喉科では、副鼻腔に溜まってしまった膿を取り除き、炎症で腫れた粘膜の状態を改善します。耳鼻咽喉科での治療は、歯科での原因治療と並行して進められ、主な方法は以下のとおりです。
- 薬物療法
- 内視鏡下鼻内副鼻腔手術(ESS)
多くの場合、薬物療法から始めます。抗菌薬で副鼻腔内の炎症を鎮めたり、消炎酵素薬や去痰薬で膿を排出しやすくしたりします。ただし、薬物療法はあくまで対症療法です。原因である歯の治療を行わない限り、一時的に症状が和らいでも、薬をやめると再び悪化してしまいます。
薬物療法で改善が見られず、炎症が慢性化している場合には、ESSが検討されます。ESSは内視鏡で副鼻腔と鼻腔を隔てる骨の壁を一部広げ、溜まった膿やポリープなどを取り除き、副鼻腔の換気を改善する方法です。
ESSのメリットは、表面に傷が残らず身体への負担が少ないことです。一方、鼻の中の状態が安定するまで、定期的な通院や処置が必要な点には注意してください。
治療期間と保険適用される費用の目安
歯性上顎洞炎の治療にかかる期間と保険適用される費用の一般的な目安は、以下のとおりです。
| 治療内容 | 治療期間の目安 | 費用の目安(3割負担) |
| 歯科:根管治療 | 数週間〜数か月 | 1歯あたり約5,000〜20,000円 |
| 歯科:抜歯 | 1日 | 約2,000〜10,000円 |
| 耳鼻咽喉科:薬物療法 | 数週間〜数か月 | 1回あたり約1,500〜3,000円 |
| 耳鼻咽喉科:ESS | 3日〜1週間程度(入院) | 約10〜15万円 |
ただし、治療にかかる期間や費用は、症状の重さや治療内容によって大きく異なる点に注意してください。マイクロスコープなどで根管治療を行う場合は、自費診療となり、費用が高額となることがあります。自費診療での根管治療の費用は5〜15万円程度です。
手術などで医療費が高額になった場合は、所得に応じて自己負担額に上限が設けられる高額療養費制度が利用できます。事前に申請が必要なので、自身の健康保険組合などにご確認ください。なお、マイナ保険証をお持ちの方は申請は不要です。
歯性上顎洞炎の予防とセルフケア
歯性上顎洞炎の予防とセルフケアの方法は、以下のとおりです。
①虫歯や歯周病を放置しない
②鼻や副鼻腔の健康を保つ
③定期検診を受ける
虫歯や歯周病を放置しないことが最大の予防
虫歯や歯周病などの歯の病気が続くと、上顎洞へ感染が波及しやすくなります。虫歯や歯周病を見つけたら、放置せずに早めに歯科医院を受診しましょう。早めに治療することで、歯性上顎洞炎の予防につながります。
自宅でのセルフケアは、就寝前に歯ブラシ・歯間ブラシ・デンタルフロスで丁寧に行うことがポイントです。就寝中は唾液の分泌が減り、細菌が繁殖しやすい環境になるためです。CPC(塩化セチルピリジニウム)やIPMP(イソプロピルメチルフェノール)といった殺菌成分を含むマウスウォッシュを併用しても良いでしょう。
鼻や副鼻腔の健康を保つ生活習慣
お口のケアと合わせて、鼻や副鼻腔を健康に保つことも予防には欠かせません。鼻の粘膜が持つバリア機能を高め、体全体の免疫力を維持することが、細菌の侵入や炎症の発生を防ぎます。
鼻と副鼻腔を守る生活習慣リストは、以下のとおりです。
- 室内の湿度を50〜60%に保つ
- こまめに水分補給する
- バランスの良い食事を心がける
- 質の良い睡眠を確保する
- 禁煙する
- 過度なストレスがかからないように管理する
- 鼻うがいを行い、鼻と副鼻腔を清潔に保つ
上記の生活習慣は、歯性上顎洞炎の治療後の再発を防ぐことにも役立ちます。治療の有無に関わらず、できる限り守るようにしましょう。
定期検診で早期発見・再発防止を
毎日のセルフケアをどんなに丁寧に行っていても、残念ながら100%の予防はできません。自分では気づかないうちに虫歯や歯周病が進行していることがあるため、専門家による定期的なチェックが予防・再発防止に重要です。
歯科医院での定期検診は、病気にならないために不可欠な手段です。特に、一度でも歯性上顎洞炎を経験した方は、3か月〜半年に一度は歯科医院を受診し、お口の健康状態を確認してもらいましょう。
詰め物や被せ物(レジンなど)、インプラントで治療した場合も、定期検診を受けてください。自身の歯との間に微小な隙間が存在すると、細菌が侵入して感染源となります。感染して炎症を起こす前に、歯科医院で早めに発見し、治療することが大切です。
副鼻腔炎と虫歯に関してよくある質問

ここでは、患者さんから特によく寄せられる以下の質問に一つひとつ丁寧にお答えしていきます。
①虫歯を治せば副鼻腔炎も治る?
②歯性上顎洞炎は自然治癒する?
③どれくらいで治る?再発しやすい?
虫歯を治せば副鼻腔炎も治る?
原因が虫歯や歯根の病気にある歯性上顎洞炎の場合、歯を適切に治療することで、副鼻腔炎も改善に向かう可能性が高いです。歯の内部から副鼻腔への細菌の供給を止められるからです。
ただし、歯の治療をすれば、すべて解決するとは限りません。炎症の症状が強かったり、慢性化したりする場合、耳鼻咽喉科での治療も必要になります。歯性上顎洞炎を治療する際は、歯科と耳鼻咽喉科の両方で治療を進めることが確実な改善への道筋です。
歯性上顎洞炎は自然治癒する?
歯性上顎洞炎は、感染源である細菌が免疫細胞が直接届きにくい歯根の内部に潜んでいるため、自然に治ることはありません。感染源を根本的に除去しない限り、症状はくすぶり続けます。
歯性上顎洞炎を放置してしまうと、以下のようなリスクが高まります。
| 放置した場合のリスク | 具体的な症状・状態 |
| 症状の悪化(急性増悪) | 頬や目の奥に激しい痛みが出たり、顔がパンパンに腫れたり、高熱が出たりする |
| 慢性化による生活の質の低下 | 常に色のついたネバネバした鼻水が出たり、自分でも鼻から嫌な臭いを感じたりする状態が続く |
| 周囲への感染拡大 | 感染が目の周りや脳にまで広がり、視力障害や髄膜炎などの重篤な合併症を引き起こす危険性もある |
「片方の鼻だけ調子が悪い」「歯の痛みと鼻づまりが同時にある」などの症状に気づいたら、自己判断で様子を見ずに、できるだけ早く専門の医療機関を受診してください。
どれくらいで治る?再発しやすい?
歯科の根管治療や耳鼻咽喉科での薬物療法を行う場合は、数週間〜数か月で症状が治ります。抜歯での治療であれば、1日で終わるでしょう。耳鼻咽喉科での内視鏡手術を受けた方は、3日〜1週間程度が治療期間の目安です。
ただし、治療期間は、症状の程度や原因となっている歯の状態によって大きく異なる点には注意してください。
歯性上顎洞炎は、再発のリスクがある病気です。特に、一度治療した歯が再び感染源となるケースは少なくありません。再発を防ぐためには、マイクロスコープなどの精密治療で修復物と歯の隙間を小さくし、治療後も定期検診を受けることが大切です。
マイクロスコープを使う治療のメリットは?
マイクロスコープは患部を数倍〜数十倍に拡大して歯性上顎洞炎を治療できるため、以下のようなメリットがあります。
1.肉眼で見えない亀裂や細い根管を拡大視野で正確に確認できる
2.健康な歯をできる限り残せる
3.汚染組織の精密な清掃・消毒により治療の成功率が上がる(※4)
4.隙間なく薬物を充填し、再発を予防する
マイクロスコープを用いた治療は、再発を繰り返しがちな難治性のケースでも効果が期待できます。(※5)
まとめ
歯性上顎洞炎の原因は、鼻ではなく歯にある可能性があります。耳鼻咽喉科の治療だけでは根本的な解決は難しく、感染源となっている歯の治療が不可欠です。
耳鼻咽喉科に通院しても症状がなかなか改善しない場合は、一度歯科や口腔外科を受診することをおすすめします。つらい症状からの回復には、歯科と耳鼻咽喉科の連携が何より大切です。気になる症状があれば、放置せずに専門医へ相談しましょう。
参考文献
- Psillas G, Papaioannou D, Petsali S, Dimas GG, Constantinidis J.Odontogenic maxillary sinusitis: A comprehensive review.J Dent Sci,2021,16(1),p.474-481.
- Kwon E, Hathaway C, Sutton AE.:「Acute Sinusitis」.
- Sirinirund B, Chan HL, Velasquez D.Microscope-Assisted Maxillary Sinus Augmentation: A Case Series.Int J Periodontics Restorative Dent,2021,41(4),p.531-537.
- Wang H, Xu X, Bian Z, Liang J, Chen Z, Hou B, Qiu L, Chen W, Wei X, Hu K, Wang Q, Wang Z, Li J, Huang D, Wang X, Huang Z, Meng L, Zhang C, Xie F, Yang D, Yu J, Zhao J, Pan Y, Pan S, Yang D, Niu W, Zhang Q, Deng S, Ma J, Meng X, Yang J, Wu J, Du Y, Ling J, Yue L, Zhou X, Yu Q.Expert consensus on apical microsurgery.Int J Oral Sci,2025,17(1),p.2.
- Kang ES, Kim MK, Yu MK, Min KS.Surgical management of maxillary sinusitis of endodontic origin after reestablishing maxillary sinus floor healing through a nonsurgical approach: a case report.Restor Dent Endod,2025,50(2),p.e12.
むし歯の関連コラム
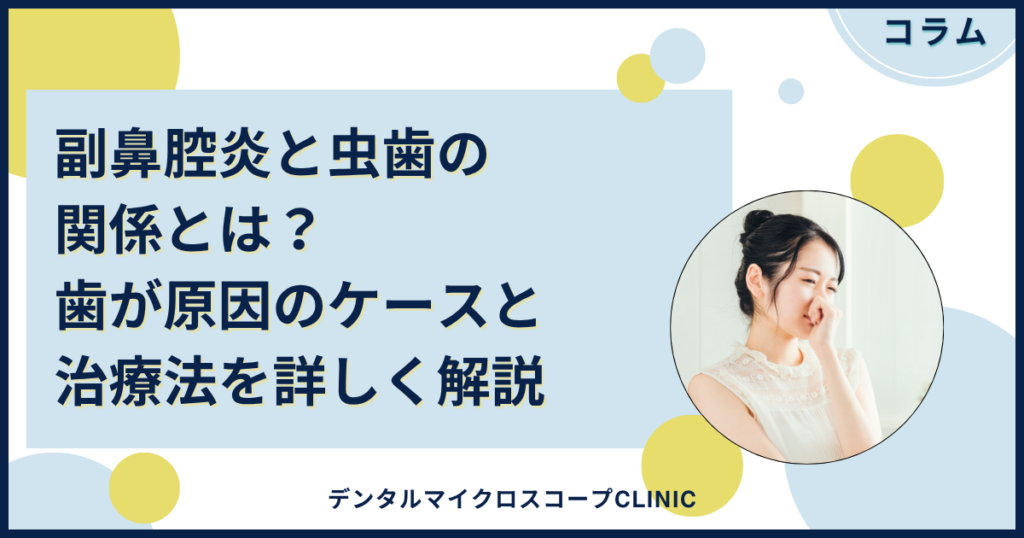
【医師監修】副鼻腔炎と虫歯の関係とは?歯が原因のケースと治療法を詳しく解説
耳鼻咽喉科で治療を続けているのに、片側の鼻づまりや頬の痛みが一向に良くならないと悩んでいませんか。しつこい鼻づまりや頬の痛みは、歯に原因があるかもしれません。上...
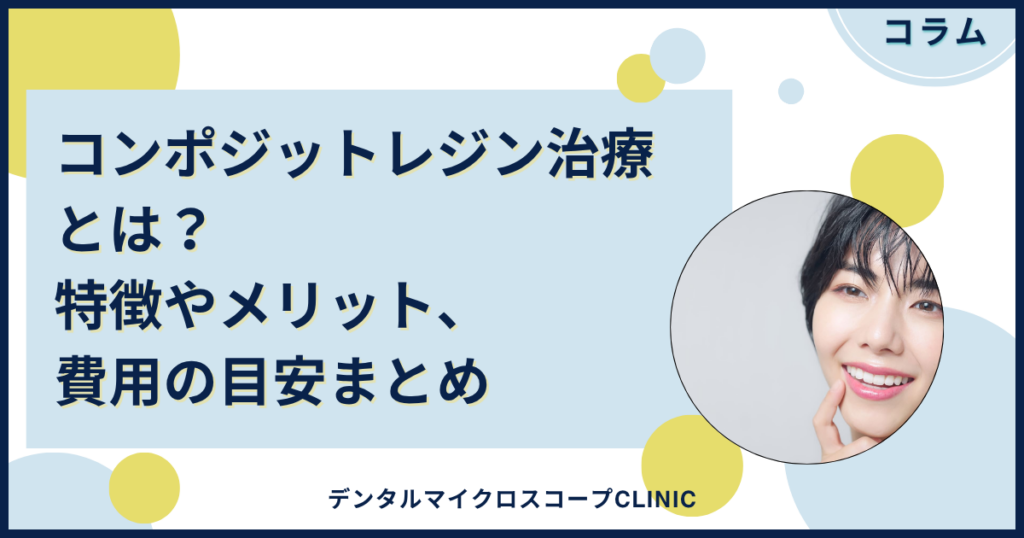
【医師監修】コンポジットレジン治療とは?特徴やメリット、費用の目安まとめ
コンポジットレジン治療は、歯の色に近い白い樹脂を使って、虫歯や欠けた部分を修復する方法です。多くの場合は1回の来院で治療が完了し、保険が適用されれば費用は比較的...
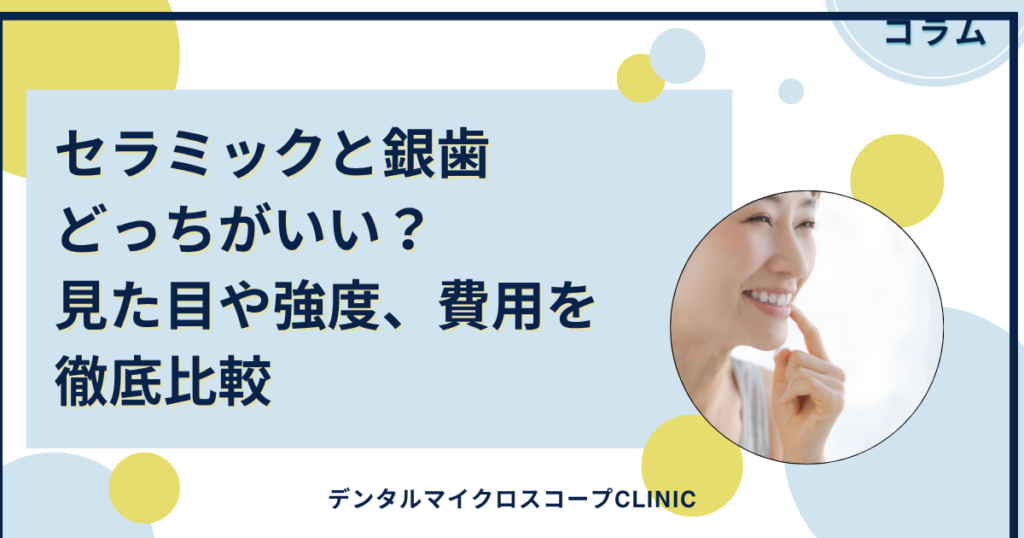
【医師監修】セラミックと銀歯どっちがいい?見た目や強度、費用を徹底比較
「保険の銀歯と自費のセラミック、どちらにしますか?」と尋ねられると、つい費用だけで選びがちです。しかし、その選択は10年後の口元の印象や、口全体の健康に大きな違...
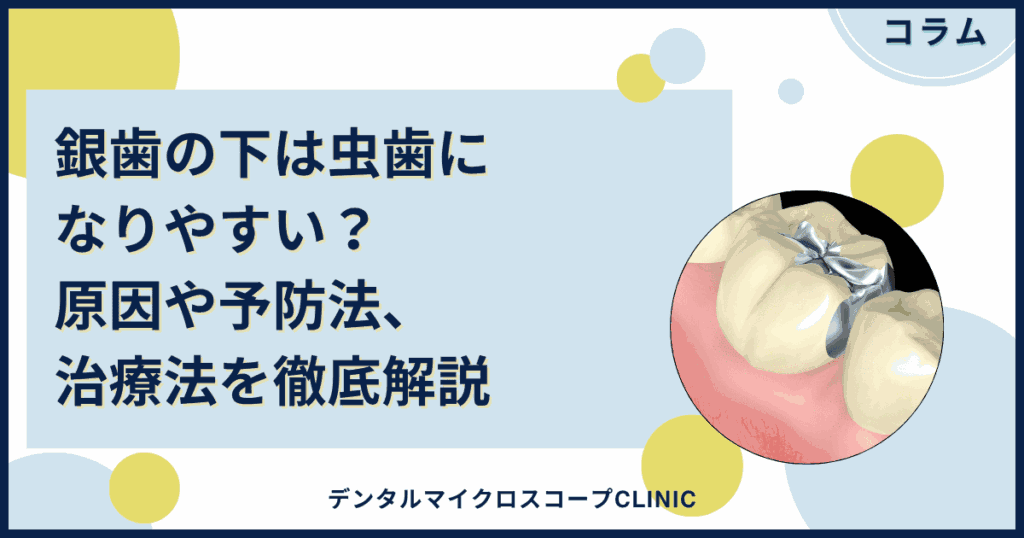
【医師監修】銀歯の下は虫歯になりやすい?原因や予防法、治療法を徹底解説
虫歯の治療を終えたはずなのに、再び痛みや違和感を感じて不安になった経験はありませんか。一度治療した銀歯の下に再び虫歯ができ、気づかないうちに症状が進行してしまう...
むし歯でおすすめの歯科医院

福岡・福岡市|ひどい虫歯や歯医者が怖い方は「痛みに配慮した治療」の池尻歯科医院へ
「ひどい虫歯を、ずっと見て見ぬふりしている…」「歯医者に行きたいけど、痛いのも、歯を削られるのも怖い」「もう虫歯を繰り返したくない」福岡市で虫歯治療でお悩みの方...

横浜市港北区・綱島でおすすめするマイクロスコープ精密歯科治療は高田歯科クリニック
横浜市港北区・綱島エリアでマイクロスコープを用いた精密な歯科治療をご希望の方へ。東急東横線「綱島駅」から徒歩3分の高田歯科クリニックは、医学的根拠(エビデンス)...
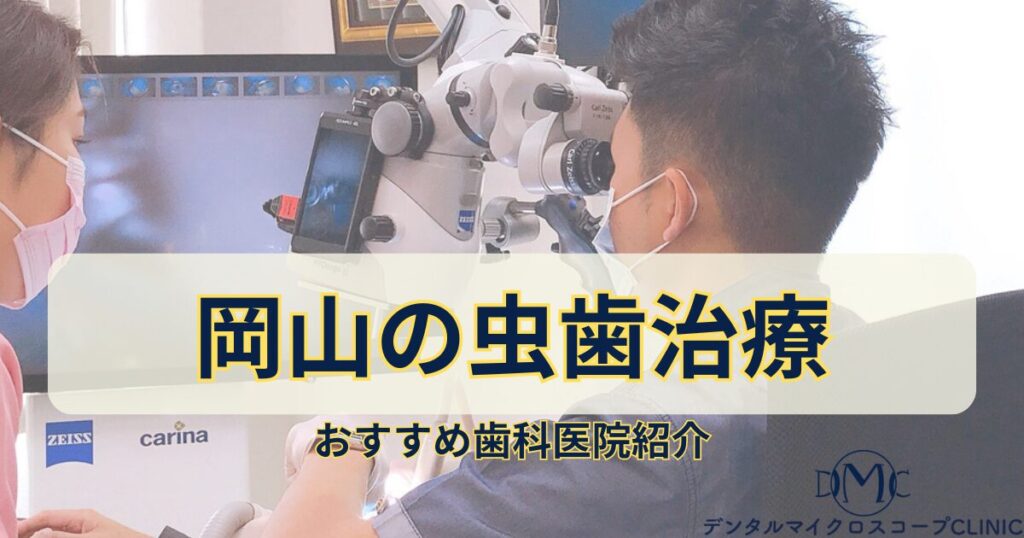
【岡山の虫歯治療】痛みが少ない・できる限り歯を削らない|おすすめの野亀歯科医院
冷たいものや甘いものがしみる、歯の表面に白い濁りや黒い筋がある…。虫歯を治療しなければと思いつつ、歯を削られる感覚や痛みが苦手で、歯科医院から足が遠のいていませ...
