虫歯の治療を終えたはずなのに、再び痛みや違和感を感じて不安になった経験はありませんか。
一度治療した銀歯の下に再び虫歯ができ、気づかないうちに症状が進行してしまうケースもあります。しかし適切な処置により、症状の悪化を防ぐことが可能です。
本記事では、銀歯の下に虫歯ができる原因や予防法、治療の選択肢までを解説します。早めの対応が将来の歯の健康を守る第一歩となるので、ぜひ最後までご覧ください。
この記事の監修歯科医師

谷川歯科医院
谷川 淳一 副院長
歯科医師。日本口腔インプラント学会専修医。小児歯科治療や小児矯正、インプラント治療を得意とし、他の歯科医師への指導も行う。
患者様一人ひとりと真摯に向き合って治療方針を決めていくことを信条としている。
目次
銀歯とは虫歯治療に使う金属製の詰め物・被せ物のこと

銀歯とは、虫歯を削ったあとに歯の形を補うために使われる金属製の詰め物や被せ物のことです。治療で削った部分を型取りし、その形に合わせて銀歯を作製して歯に装着します。
素材は銀だけではなく、金・銀・パラジウムを中心とした合金が用いられるのが一般的です。合金は耐久性があり加工もしやすいため、長年にわたり虫歯治療で広く使われてきました。
日本では保険診療で認められているため、費用を抑えられることから多くの患者さんに選ばれています。
銀歯の下に虫歯ができる原因
虫歯治療を終えた後に、時間が経つと銀歯の下に虫歯が再発する場合もあります。二次虫歯(二次カリエス)と呼ばれ、気づきにくく発見が遅れることも少なくありません。
銀歯の下に虫歯ができる主な原因は、以下のとおりです。
- プラークの付着
- 接着剤の溶解
- 銀歯の劣化
- 温度変化による銀歯の変形
それぞれの理由を詳しく見ていきましょう。
プラークの付着
銀歯の表面は天然の歯よりも粗く、プラーク(歯垢)が付着しやすいのが特徴です。
食後に口内が酸性に傾くと、プラーク内の細菌が活発に活動しやすくなり、虫歯菌が繁殖し、酸を排出します。酸によって歯が溶け、気づかないうちに銀歯の下の虫歯が進行してしまうのです。
口内環境の変化が重なるほど、銀歯の下で虫歯が再発するリスクにもつながります。プラークの付着部位と主な特徴は、以下のとおりです。
| 付着部位 | 特徴・影響 |
| 歯茎より上の歯の表面 | 虫歯や歯肉炎の原因となる細菌が多い |
| 歯茎より下の歯周ポケット内 | 歯周病の原因菌が繁殖し、進行しやすい |
プラークの放置は、虫歯だけでなく歯周病の悪化につながるため注意が必要です。
接着剤の溶解
銀歯を歯に固定しているのは、歯科用セメントと呼ばれる接着剤です。保険診療で使われる接着剤は唾液に弱く、以下のような原因で時間の経過とともに少しずつ溶け出します。
| 原因 | 特徴 |
| 接着剤の劣化 | 保険診療で使われる接着剤は唾液に弱く、接着力が低下して詰め物が外れやすくなる |
| 二次虫歯の発生 | 劣化部分や隙間から虫歯菌が侵入し、歯と詰め物の間に隙間が広がる |
| 歯ぎしり・食いしばり | 歯に過度な力が加わることで、接着部分に負担がかかる |
銀歯の下に隙間ができると、虫歯菌が増殖しやすい環境となります。内部に入り込んだ細菌はバイオフィルムを形成し、強固なバリアで守られながら象牙質を溶かしていきます。
象牙質はエナメル質よりも柔らかいため、侵食が進むと虫歯が急速に広がる危険性があります。
銀歯の劣化
銀歯は耐久性に優れていますが、寿命は一般的に5〜7年程度といわれています。銀歯の劣化を引き起こす主な原因は、噛む力による負担や、金属の腐食によるものです。
食事や日常生活の噛み合わせによって強い力が加わると、銀歯と歯の間にわずかな歪みが生じます。さらに、唾液の成分で金属が錆びやすくなり、変形や劣化につながります。
噛む力や食事の衝撃が繰り返し加わることで、銀歯と歯の間には目に見えない微細な隙間も形成されます。肉眼では確認できませんが、虫歯菌が侵入するには十分な大きさであり、結果として経年劣化は二次虫歯のリスクを高める要因となります。
温度変化による銀歯の変形
銀歯は金属で作られているため、天然の歯とは熱の膨張や収縮の度合いが異なります。温度変化により銀歯が変形する主な要因は、「金属と天然歯の膨張の違い」と「高い熱伝導率」の2つです。
金属は天然歯に比べて膨張率が大きく、熱い飲み物や冷たい食べ物を口にするたびに膨張と収縮を繰り返します。銀歯は、天然歯のおよそ50倍以上の熱伝導率を持つとされ、温度の変化を歯の神経に伝えやすいのが特徴です。
熱いものや冷たいものを口にすると、銀歯と歯がわずかに伸び縮みして、その境目にすき間ができやすくなります。
銀歯の下が虫歯かも?すぐに確認したい7つの症状セルフチェック

銀歯は一見しっかり治療されたように見えても、実はその下で虫歯が再発していることがあります。
詰め物や被せ物の隙間から細菌が侵入し、知らないうちに歯の内部で進行してしまう「二次カリエス」は、痛みが出にくく、気づいたときには神経まで達していることも少なくありません。
ここでは、銀歯の下で虫歯が進んでいるかもしれない7つのサインをまとめました。
- 冷たいものや熱いものがしみる
- 噛むと痛い、または違和感がある
- 銀歯と歯の境目が黒ずんでいる
- 歯茎が腫れたり、押すと膿が出たりする
- 銀歯の周辺から口臭がする
- 銀歯が取れた、または浮いている感じがする
- フロスが特定の場所で引っかかる、または糸が切れる
当てはまる項目があれば、早めに歯科医院でのチェックをおすすめします。
冷たいものや熱いものがしみる
銀歯の下で虫歯が進行すると、歯の内部にある神経が刺激を受けやすくなり、冷たい飲み物や温かい食べ物がしみるようになります。特に、以前はしみなかったのに最近になって違和感を覚える場合は注意が必要です。
詰め物と歯の間にわずかな隙間ができ、そこから細菌が入り込んでいる可能性があります。しみる感覚が一時的ではなく続くときは、銀歯の下で虫歯が進行しているサインかもしれません。
噛むと痛い、または違和感がある
噛んだときに痛みや違和感を感じる場合、銀歯の下で炎症が起きていることがあります。歯の内部に圧がかかると神経が敏感に反応し、鈍い痛みや浮いたような感覚として現れるのが特徴です。
一時的におさまっても、同じ場所で繰り返し違和感を覚えるなら注意しましょう。噛むたびに感じるわずかな違和感は、歯の中で圧力がかかっているサインです。
「なんとなくおかしい」と感じる段階で気づけるかどうかが、悪化を防ぐポイントになります。
銀歯と歯の境目が黒ずんでいる
銀歯と歯のあいだが黒く見える場合、詰め物の隙間から細菌が入り込み、虫歯が進行している可能性があります。銀歯そのものが変色しているように見えても、実際には内部の歯質が溶けて黒く透けて見えていることもあります。
また、境目の黒ずみが徐々に広がっている場合は、汚れではなく虫歯による変化であることが多いです。
見た目の小さな変化でも、歯の中ではすでに進行していることがあります。
歯茎が腫れたり、押すと膿が出たりする
銀歯のまわりの歯茎が赤く腫れたり、押すと白っぽい膿がにじむ場合、歯の根の奥で炎症が起きていることがあります。虫歯が深く進むと細菌が根の先にたまり、内部で膿が発生することがあります。
痛みがなくても腫れを繰り返すときは、炎症が慢性化している可能性があり、注意が必要です。体調を崩したときや疲れがたまったときに再び腫れることも多く、時間をかけて悪化していくケースもあります。
銀歯の周辺から口臭がする
銀歯のまわりから口臭を感じる場合、詰め物の下や境目で汚れや細菌がたまり、虫歯が進行していることがあります。銀歯と歯のあいだにできたわずかな隙間に食べかすが入り込むと、そこで細菌が繁殖し、嫌なにおいを発生させます。
歯みがきをしても口臭が取れないときは、表面ではなく内部に原因があるかもしれません。
特に、特定の歯のまわりだけににおいを感じる場合は、銀歯の下で変化が起きていることが考えられます。
銀歯が取れた、または浮いている感じがする
銀歯が外れたり、噛んだときにわずかに浮くような感覚がある場合、詰め物の下で虫歯が進行していることがあります。
歯と銀歯のあいだに細菌が入り込むと、接着面が弱まり、徐々に浮き上がっていくことがあります。
見た目はしっかりしていても、内部の歯が溶けて隙間ができていることも少なくありません。食事のときに違和感を覚えたり、銀歯が動くような感触があるときは注意が必要です。
フロスが特定の場所で引っかかる、または糸が切れる
フロスを通したときに同じ箇所で引っかかったり、糸がほつれて切れたりする場合、銀歯と歯のあいだにわずかな段差ができていることがあります。詰め物の縁がすり減ると、表面がざらつき、糸が傷つきやすくなります。
他の歯はスムーズに通るのに特定の場所だけ違和感があるときは、そこに汚れや細菌が溜まりやすくなっている可能性が高いです。毎日のケアで引っかかりを感じるなら、小さな変化として意識しておくとよいでしょう。
銀歯の下の虫歯を放置するとどうなる?考えられる3つのリスク

銀歯の下で進行する虫歯は、気づかないうちに深く広がっていくことがあります。表面上は問題がないように見えても、内部では神経や歯の根にまで影響が及ぶことがあります。
放置すると、強い痛みを伴う炎症や、神経を失う治療、さらには歯そのものを失う結果につながることもあるでしょう。
ここでは、銀歯の下の虫歯を放置したときに起こりうる3つのリスクについて解説します。
神経まで虫歯が進行し、激しい痛みが出る
銀歯の下で進んだ虫歯は、やがて歯の内部にある神経(歯髄)にまで達します。この段階になると、冷たいものや温かいものだけでなく、何もしていなくてもズキズキと痛むようになります。
炎症が強いと夜眠れないほどの痛みを感じることもあり、痛み止めが効かなくなるケースもあります。初期の違和感を放置すると、痛みが急激に悪化することがあるので決して放置してはいけません。
神経を失い、歯の寿命が短くなる
虫歯が神経を侵すと、歯を残すために神経を取り除く処置が必要です。神経を失った歯は血流や栄養の供給が絶たれ、もろく割れやすい状態になります。
見た目には残っていても、内部では寿命が縮んでいくような状態です。時間の経過とともに変色したり、再び内部で炎症や痛みが起きやすくなることもあります。
歯が割れたり溶けたりして、最終的に失うことがある
虫歯が根の奥深くまで進行すると、歯の構造そのものが弱くなります。銀歯を支える部分が溶け、わずかな力で歯が欠けたり割れたりすることもあるでしょう。
一度割れた歯は元の形に戻らず、最終的に抜歯が避けられなくなる場合もあります。痛みが落ち着いたように見えても、内部では虫歯が進行していることもあるので、そのままにしないようにしましょう。
銀歯の下の虫歯の予防法
銀歯の下の虫歯を防止するためには、日常のセルフケアや定期的な管理が欠かせません。虫歯の再発を防ぐためには、以下のケアを心がけましょう。
- 歯磨きを丁寧に行う
- 定期的に歯科検診を受ける
- 二次虫歯になりにくい素材を選択する
歯磨きを丁寧に行う
虫歯の原因の一つに、銀歯と歯の間に食べかすや細菌が入り込み、汚れがたまりやすくなることがあります。これを防ぐ基本は毎日の歯磨きです。特に夜は唾液の分泌が減って細菌が繁殖しやすいため、就寝前の歯磨きを徹底しましょう。
歯ブラシは小さめのヘッドで柔らかめを選び、鉛筆を持つように軽く握ります。毛先を歯と歯ぐきの境目に45度で当て、1本ずつ小刻みに動かすのがポイントです。
ただし歯ブラシだけでは境目の汚れを取り切れません。詰め物や被せ物の周囲には段差ができやすいため、フロスや歯間ブラシを最低でも1日1回、特に就寝前に取り入れることが大切です。さらに、フッ素入り歯磨き粉を使ってうがいは一回にとどめること(イエテボリ法)で歯を強くし、虫歯菌の働きを抑える効果も期待できます。
こうしたセルフケアを習慣づけることで、銀歯の下で虫歯が進行するリスクを大きく減らせます。
定期的に歯科検診を受ける
虫歯予防にはセルフケアだけでなく、歯科医院での定期検診と専門的なケアが大切です。歯科医院の定期検診でできることは、以下のとおりです。
- 詰め物・被せ物の精密チェック:劣化や欠け、隙間の有無を確認する
- 虫歯の早期発見:レントゲンで初期虫歯や銀歯下の虫歯を発見する
- 専門的なクリーニング(PMTC):歯石やバイオフィルムを専用器具で除去する
- オーダーメイドのセルフケア指導:歯並びや口腔環境に合う磨き方を提案する
定期検診を受けることで、虫歯や歯周病の早期治療につながります。定期検診は、3〜6か月に1回を目安に受診し、治療した歯をできるだけ長く守りましょう。
二次虫歯になりにくい素材を選択する
虫歯の再発リスクを抑えるには、治療後に用いる素材選びが重要になります。保険診療の銀歯は安価で広く普及していますが、二次虫歯が起こりやすい点が課題です。
近年注目されているのが、自費診療で用いられるセラミックです。セラミックは表面が滑らかでプラークが付着しにくく、歯との接着性にも優れています。長期間使用しても変質や変形が少なく、レントゲンでも観察しやすいため、虫歯を早期発見できるというメリットもあります。
こうした特性から、再発リスクを抑えやすい素材として評価されています。さらに、抗菌性を持つ新しいレジン素材の研究も進んでおり、虫歯菌の繁殖を抑える効果が報告されています。(※1)ただし、現段階では臨床での有効性はまだ検証段階です。
長期的に自分の歯を守るためには、素材ごとの特性を理解したうえで、自分に合った選択をすることが大切です。素材選びは治療の仕上がりだけでなく、その後の歯の健康を大きく左右するポイントになります。
銀歯の下に虫歯ができてしまった際は、銀歯を外した後に、虫歯の進行度や歯の状態に応じて、最適な治療法を選ぶことが重要です。
保険診療と自費診療の選択によって、仕上がりや耐久性は大きく変わります。再発を防ぐためにも、それぞれの特徴を理解したうえで判断することが重要です。
銀歯を外した後の主な治療法として、以下の4つを紹介します。
- コンポジットレジンでの詰め直し
- セラミックインレーによる修復
- ジルコニアインレーでの補強
- マイクロスコープ根管治療
コンポジットレジンでの詰め直し
コンポジットレジンとは、歯科用の白いプラスチックを用いた詰め物です。虫歯を削った部分にペースト状の材料を直接詰め、特殊な光を当てて硬化させます。
コンポジットレジンで詰め直すことで、虫歯などで欠損した歯の修復や補修ができます。歯を削る量を最小限に抑えられるため、患者の負担を軽減できる治療法です。
コンポジットレジン治療のメリット・デメリットは、以下のとおりです。
| メリット | デメリット |
| ・保険適用で経済的負担が少ない ・治療期間が短く、1回の通院で完了する ・白色で銀歯より目立たない | ・水分や食品の色素を吸収し、黄ばみやすく、汚れが付きやすい ・強度がやや低く、奥歯や大きな虫歯には不向き ・材料が劣化すると隙間が生じやすい |
コンポジットレジンは耐久性には限りがあり、使用環境や日々のケアで寿命は大きく変わります。長持ちさせるためには、毎日のセルフケアに加え、硬い食べ物を避けるなど生活習慣にも注意が必要です。
保険適用の場合、1本あたり1,000〜2,000円程度の治療費がかかります。通常は1回で治療は終了です。
CAD/CAMインレーによる修復
CAD/CAM(キャドカム)インレーは、虫歯で削った歯の部分をセラミックとコンポジットレジンが混ざった、天然歯の見た目に近い材料で修復する方法です。
CAD/CAMインレーの主なメリット・デメリットは以下のとおりです。
| メリット | マイクロスコープ治療 |
| ・保険適用で経済的負担が少ない ・白色で銀歯より目立たない ・コンポジットレジンより強度が高い | ・水分や食品の色素を吸収し、黄ばみやすく、汚れが付きやすい ・強い衝撃や歯ぎしりで欠けることがある |
CAD/CAMインレーは、強度に不安はあるものの、コンポジットレジンより強度は優れており、銀歯による見た目も解消できることから、あまり強い力がかからないようなケースに向いています。
保険適用時の費用は、1本あたり3,000円〜5,000円程度、自由診療の場合は1本あたり30,000〜70,000円程度です。治療は原則2回にわたって行われ、1回目は虫歯を削って型を取り、2回目に詰め物をはめ込んで仕上げます。
セラミックインレーによる修復
セラミックインレーは、虫歯で削った歯の部分を天然歯に近い見た目や質感を持つセラミックで修復する方法です。金属アレルギーや歯茎の黒ずみのリスクがないため、見た目や健康面に配慮して選ばれる方もいます。
セラミックインレーの主なメリット・デメリットは以下のとおりです。
| メリット | デメリット |
| ・天然歯のような見た目を再現できる ・表面が滑らかで虫歯になりにくい・変色や変形がほとんどない | ・自費診療のため、費用が高額 ・強い衝撃や歯ぎしりで欠けることがある |
セラミックインレーは、年数が経過しても着色しにくく、白さを長く保てます。銀歯による見た目や金属アレルギーの悩みも解消でき、自然な美しさと健康面の両方でメリットの多い治療法です。
セラミックインレーは、保険適用外で行う自然な見た目の詰め物治療で、費用は1本あたり約3〜7万円が目安です。通常は2回の通院で完了し、1〜2週間ほどで仕上がります。
ジルコニアインレーでの補強
ジルコニアインレーは、歯ぎしりや嚙み合わせの強い奥歯に適した治療法です。ジルコニアは、人工ダイヤモンドとも呼ばれるほど硬く、耐久性に優れたセラミックの一種です。
従来は加工が難しい素材でしたが、技術発展により天然歯に近い見た目を再現できるようになりました。
ジルコニアインレーには以下のようなメリット・デメリットがあります。
| メリット | デメリット |
| ・金属に匹敵する強度があり、割れにくい ・自然な白さを再現でき、目立ちにくい ・表面が滑らかで汚れがつきにくい ・金属を使わないためアレルギーの心配がない | ・自費診療のため経済的負担が大きい ・噛み合う天然歯をすり減らす可能性がある ・透明感ではセラミックにやや劣る |
ジルコニアインレーは、変色や摩耗が少なく、長期的な安定性も期待できます。ただし、硬さゆえに噛み合わせの調整が重要となるため、歯科医師による精密な診断と管理が欠かせません。
ジルコニアインレーによる修復は、保険適用外の自由診療で、費用は1本あたりおよそ3〜10万円が目安です。治療は2回の通院で行われ、1回目に銀歯を外して歯の形を整え、型取りと仮詰めを行い、2回目で完成したジルコニアインレーを専用の接着剤で装着します。
虫歯の再発防止の鍵は「マイクロスコープ」による精密治療
再発リスクを抑えて歯を長持ちさせやすい方法が、マイクロスコープ(歯科用顕微鏡)を用いた根管治療です。
虫歯が銀歯の下で進行し神経(歯髄)に達すると、放置すれば抜歯が必要になることがあります。その際、歯を残すために行うのが根管治療です。
マイクロスコープ根管治療には以下のようなメリットがあります。
- 初期の虫歯や詰め物との微細な隙間まで発見でき、早期対応が可能
- 治療部位を高倍率で拡大でき、肉眼では見えない細部まで確認できる
- 感染源を確実に取り除けるため、再発リスクを軽減できる
- 虫歯に感染した部分だけを精密に削り、健康な歯を最大限残せる
- 詰め物・被せ物と歯の適合精度が高まり、二次虫歯のリスクを抑えられる
- 従来の方法で見逃されやすい部分まで処置できる
マイクロスコープ治療には高度な技術と専用設備が必要で、対応できる歯科医院は限られています。受診を検討する際は、治療の可否や費用を事前に確認しておくと安心です。
まとめ
銀歯の下の虫歯は、歯の状態や生活習慣など、複数の要因が重なって起こります。予防には、毎日の丁寧なセルフケアに加え、定期的な歯科検診で専門的なチェックを受けることが大切です。
再治療が必要になった場合でも、見た目や耐久性など複数の治療法から、自分に合った方法を選択できます。将来の歯を守るために治療法を理解し、今日から意識できるケアを実践していきましょう。
参考文献
- Reinaldo Adelino de Sales-Junior, Mariana Silva de Bessa, Francisca Jennifer Duarte de Oliveira, Bárbara Faria de Sá Barbosa, Kaiza de Sousa Santos, Michael Owen, Victor Pinheiro Feitosa, Boniek Castillo Dutra Borges. Multifaceted characterization of antibacterial resin composites: A scoping review on efficacy, properties, and in vivo performance. Jpn Dent Sci Rev, 2025, 61, p.112-137.
むし歯の関連コラム
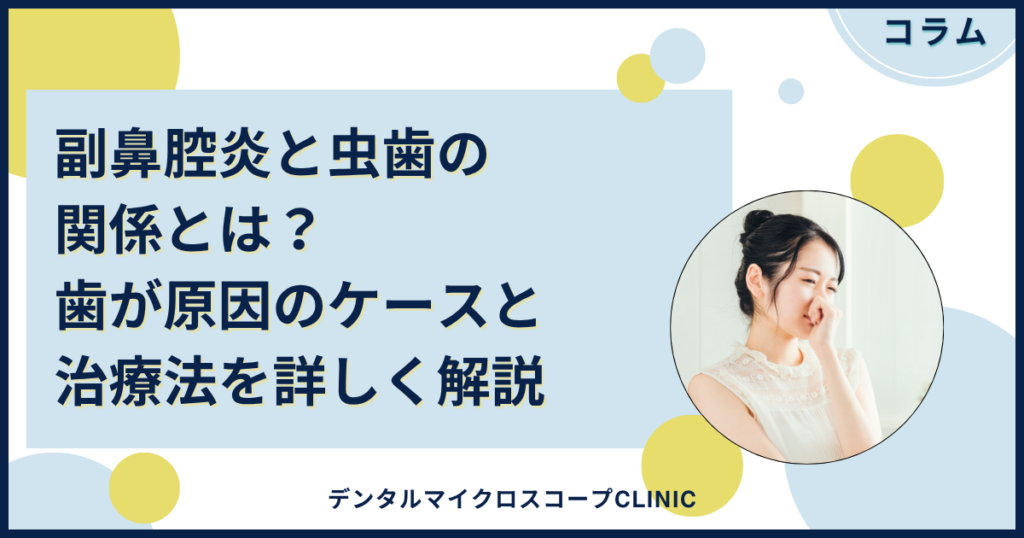
【医師監修】副鼻腔炎と虫歯の関係とは?歯が原因のケースと治療法を詳しく解説
耳鼻咽喉科で治療を続けているのに、片側の鼻づまりや頬の痛みが一向に良くならないと悩んでいませんか。しつこい鼻づまりや頬の痛みは、歯に原因があるかもしれません。上...
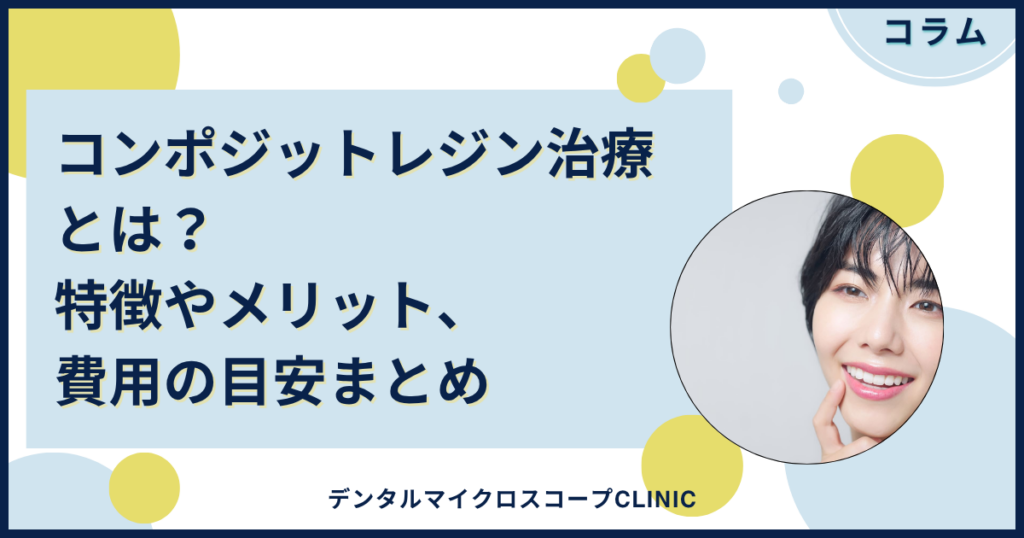
【医師監修】コンポジットレジン治療とは?特徴やメリット、費用の目安まとめ
コンポジットレジン治療は、歯の色に近い白い樹脂を使って、虫歯や欠けた部分を修復する方法です。多くの場合は1回の来院で治療が完了し、保険が適用されれば費用は比較的...
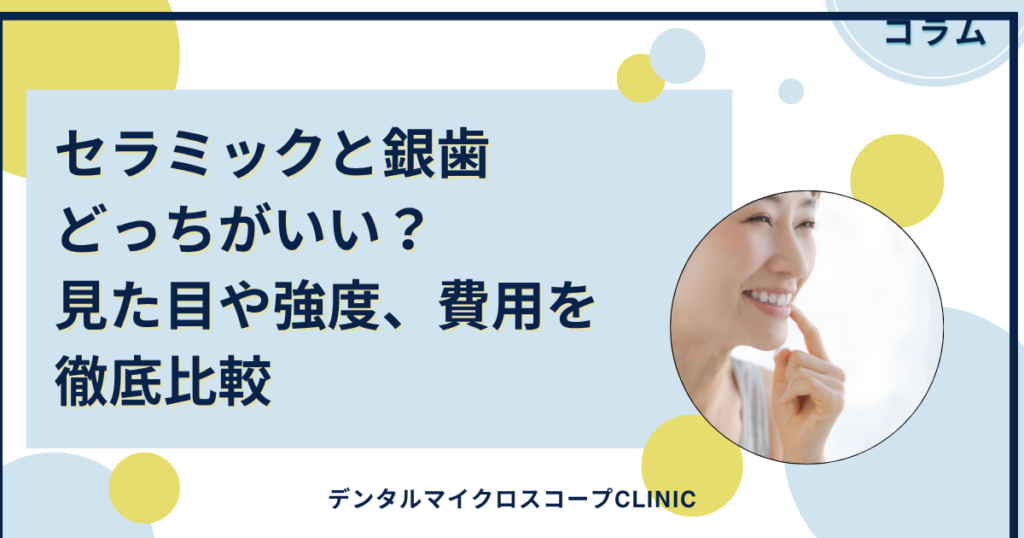
【医師監修】セラミックと銀歯どっちがいい?見た目や強度、費用を徹底比較
「保険の銀歯と自費のセラミック、どちらにしますか?」と尋ねられると、つい費用だけで選びがちです。しかし、その選択は10年後の口元の印象や、口全体の健康に大きな違...
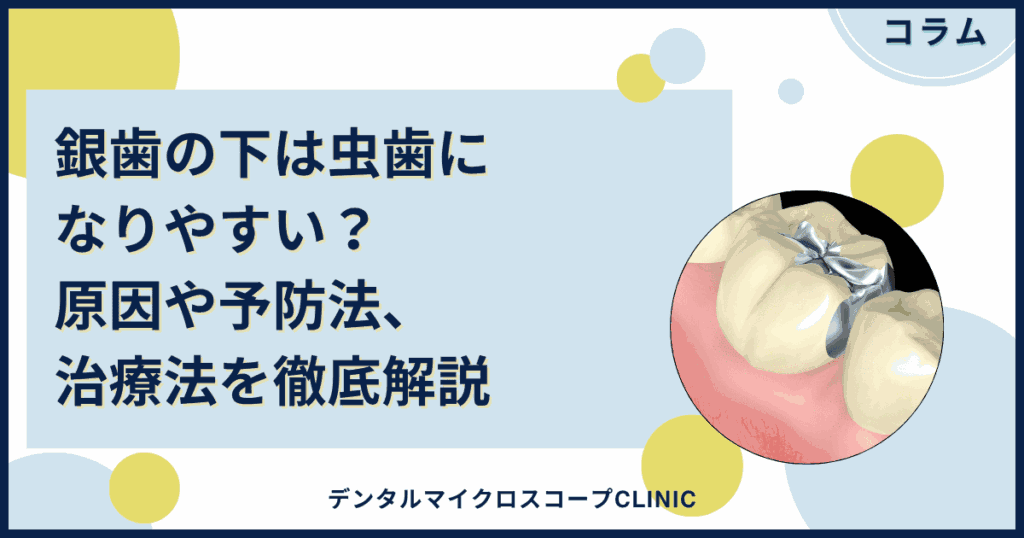
【医師監修】銀歯の下は虫歯になりやすい?原因や予防法、治療法を徹底解説
虫歯の治療を終えたはずなのに、再び痛みや違和感を感じて不安になった経験はありませんか。一度治療した銀歯の下に再び虫歯ができ、気づかないうちに症状が進行してしまう...
むし歯でおすすめの歯科医院

福岡・福岡市|ひどい虫歯や歯医者が怖い方は「痛みに配慮した治療」の池尻歯科医院へ
「ひどい虫歯を、ずっと見て見ぬふりしている…」「歯医者に行きたいけど、痛いのも、歯を削られるのも怖い」「もう虫歯を繰り返したくない」福岡市で虫歯治療でお悩みの方...

横浜市港北区・綱島でおすすめするマイクロスコープ精密歯科治療は高田歯科クリニック
横浜市港北区・綱島エリアでマイクロスコープを用いた精密な歯科治療をご希望の方へ。東急東横線「綱島駅」から徒歩3分の高田歯科クリニックは、医学的根拠(エビデンス)...
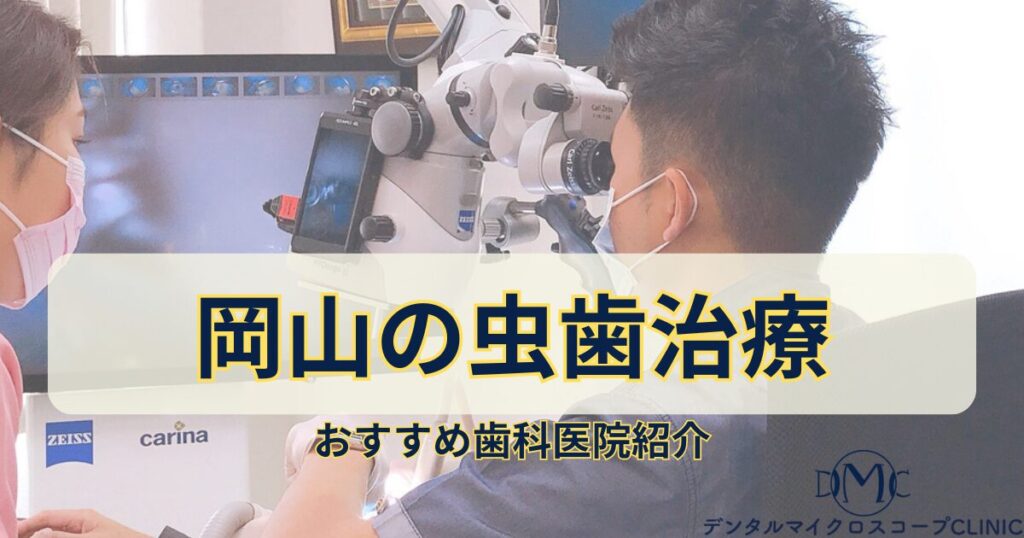
【岡山の虫歯治療】痛みが少ない・できる限り歯を削らない|おすすめの野亀歯科医院
冷たいものや甘いものがしみる、歯の表面に白い濁りや黒い筋がある…。虫歯を治療しなければと思いつつ、歯を削られる感覚や痛みが苦手で、歯科医院から足が遠のいていませ...
