歯茎にできたニキビのようなできもの、噛んだ時の痛み、歯が浮いたような違和感などの症状を放置していませんか。実はそれ、歯の根っこに膿がたまり、顎の骨が静かに溶けている危険なサインかもしれません。
放置すれば歯を失うだけでなく、細菌が全身に広がり重篤な病気につながることもあります。原因の多くは、痛みが消えて治ったと勘違いしがちな重度の虫歯です。過去に治療した歯や歯周病が原因で、数年後に突然症状が現れることも少なくありません。
この記事では、歯の根に膿がたまる本当の原因と、抜歯を避けるための治療法を詳しく解説します。手遅れになる前に、ご自身の症状と照らし合わせ、正しい知識を身につけましょう。
この記事の監修歯科医師

医療法人あかり会歯科
脇田奈々子
大阪大学歯学部卒業後、同大学予防歯科学教室にて医員として勤務。
現在は大阪市内の歯科医院で、予防歯科からインプラント、矯正治療まで幅広く対応している。治療の先の心のケアにもつながる“医療としての美容歯科”として、ボツリヌス治療、ヒアルロン酸注入、リップアートメイクにも注力している。
「口元の健康と美を通じて、最後まで美味しく食べ、自信を持って笑える人生」をサポートすることを理念としている。
目次
歯の根っこに膿がたまる3つの原因

歯茎が腫れて痛む、歯が浮いた感じがする症状は、歯の根の先に膿がたまっているサインかもしれません。この状態は「根尖性歯周炎(こんせんせいししゅうえん)」と呼ばれます。膿がたまる主な3つの原因は以下のとおりです。
- ①神経まで達した重度の虫歯
- ②歯周病の進行による歯の根っこへの感染
- ③過去の治療の不備や歯のひび割れ(歯根破折)
①神経まで達した重度の虫歯
歯の根っこに膿がたまる原因の多くは、放置された重度の虫歯です。虫歯は、口の中の細菌が作る酸で歯が溶かされる病気です。感染が歯の根の先にまで及ぶ経緯は、以下のとおりです。
| 時期 | 症状 |
| 初期〜進行期 | ・歯の表面(エナメル質)から、内側(象牙質)へと虫歯が進行する ・冷たい物や甘い物がしみる程度の症状が出始める |
| 重度期(歯髄炎) | ・虫歯が歯の中心部にある神経や血管(歯髄)まで到達する ・細菌が歯髄に感染し、「歯髄炎」という激しい痛みを引き起こす |
| 末期(歯髄壊死) | 感染が進むと歯髄は壊死し、腐敗していく強かった痛みは一旦治まる(病状が悪化しているサイン) |
| 根尖性歯周炎の発症 | ・死んだ歯髄を温床に、細菌は歯の根の管(根管)を通って先端へ進む ・根の先から顎の骨へと感染を広げ、炎症を起こして膿をため始める |
虫歯の原因菌として、Streptococcus mutans(ストレプトコッカス・ミュータンス)が有名です。近年の研究では、歯根の虫歯にLactobacillus属(ラクトバチルス属)など多様な細菌の関与もわかっています。(※1)
②歯周病の進行による歯の根っこへの感染
虫歯だけでなく、歯周病の進行も歯の根に膿がたまる原因です。歯周病は、歯と歯茎の境目にたまる歯垢(プラーク)の中の細菌が引き起こす感染症です。虫歯がなくても、歯周病だけで膿がたまることがあります。
感染の経過は以下のとおりです。
| 経過 | 症状 |
| 歯周ポケットの深化 | ・歯周病の進行で歯と歯茎の溝が深くなる ・健康時は1〜2mmだが、炎症で4〜5mm以上に |
| 細菌の侵入と骨の破壊 | ・深いポケットが歯周病菌の温床になる ・細菌が歯茎内部から顎骨へ侵入し溶かす ・感染が歯根に沿って下方へ広がる |
| 根尖部への感染 | 菌が歯の内部に侵入し、周囲の組織に炎症を起こして膿をためる |
歯周病は自覚症状が少ないまま進行するため「静かなる病気」とも呼ばれます。歯周病関連の細菌としては、Prevotella denticola(プレボテラ・デンティコーラ)などが知られており、感染の引き金となります。
③過去の治療の不備や歯のひび割れ(歯根破折)
過去に受けた歯科治療が原因で、数年後に膿がたまることもあります。また、外傷や歯ぎしりなどで歯にひびが入る「歯根破折(しこんはせつ)」も感染の原因です。それぞれの症状の詳細は、以下のとおりです。
| 原因 | 症状 |
| 過去の治療の不備 | ・以前の治療で、残っていた細菌が再び活動を始めて膿がたまる ・被せ物や詰め物と歯の隙間に、細菌が侵入して内部で感染を起こす |
| 歯のひび割れ(歯根破折) | ・噛む衝撃や外傷、強い歯ぎしりなどで歯根に微細なひびが入る ・ひびから細菌が侵入し、内部や周囲に感染し膿がたまる ・神経を抜いた歯はもろくなり、歯根破折しやすい |
上記の原因は、通常のレントゲン検査だけでは発見が難しいこともあります。CT撮影など、より精密な検査で初めて原因がわかる場合もあります。
歯の根っこに膿がたまったときの主な症状3つ

歯の根っこに膿がたまったときの主な症状は以下の3つです。
- ①局所症状
- ②進行時の全身症状
- ③慢性化による無症状
①局所症状
歯の根っこに膿がたまると、まず現れるのが局所的な症状です。多いのは、ズキズキと脈打つような強い痛みで、安静にしていても続きます。噛むと響くような痛みも特徴的で、食事や会話のたびに不快感が増します。
歯茎が赤く腫れ、触れると痛みを伴うことも多く、膿が溜まっている場合は口の中に苦みや嫌な臭いを感じることがあります。これらは感染が進んでいるサインで、自然に治ることはほとんどありません。
放置すると症状が悪化するため、早めの歯科受診が必要です。
②進行時の全身症状
膿がたまった状態を放置すると、炎症が広がり全身にも影響が出ます。代表的な症状には次のようなものがあります。
- 発熱:体が細菌と戦っているサイン
- 顔やあごの腫れ:炎症が周囲組織に波及
- 倦怠感:全身のエネルギーが奪われ、日常生活に支障
上記の症状が現れる頃には、炎症はかなり進行しており、入院や外科的処置が必要な場合もあります。特に顔の腫れや高熱は緊急性が高く、命に関わる感染症に発展する場合もあります。
これらの症状があれば、ためらわずに歯科を受診しましょう。
③慢性化による無症状
歯の根っこに膿がたまっていても、必ずしも痛みが出るとは限りません。慢性化すると、体が炎症に慣れてしまい、強い痛みがなくなることがあります。
しかし、治ったわけではなく、内部では細菌が活動を続け、骨や歯の周囲組織をじわじわ破壊しています。放置すると、ある日突然激しい痛みや腫れが再発したり、歯を残せなくなったりします。
無症状でもレントゲンやCTで発見できるため、定期的な歯科検診が早期発見の鍵になります。
歯の根っこに膿がたまった時の応急処置と注意点

ここでは、歯の根っこに膿がたまった場合の応急処置と注意点を詳しく見ていきましょう。
- ①自分で膿を出すのはNG
- ②市販の痛み止めは一時的な対処にすぎない
- ③患部を冷やし、安静にして早めに受診する
①自分で膿を潰すのはNG
歯ぐきに膿がたまると、白い膨らみができることがあります。強く押したり、針などで突いて中身を出そうとする方もいますが、これは絶対に避けるべき行為です。
膿の袋は細菌のかたまりであり、無理に潰すと細菌が周囲の組織や血流に広がり、炎症が悪化したり全身に感染が及ぶ危険性もあります。症状を自己判断で処置するのではなく、必ず歯科医院で適切な治療を受けることが大切です。
②市販の痛み止めは一時的な対処にすぎない
感染が炎症が起き、強い痛みが生じることがあります。ロキソニンやアセトアミノフェンといった市販の痛み止めを飲めば、一時的に症状を和らげることは可能です。
しかし、これはあくまで「痛みを感じにくくしているだけ」であり、膿の原因となっている細菌感染そのものを治しているわけではありません。薬で痛みが軽くなっても病変は進行しているため、自己判断で放置するのは危険です。必ず早めに歯科医院を受診して、根本的な治療を受けることが大切です。
③患部を冷やし、安静にして早めに受診する
強い腫れや痛みがある場合は、患部を冷やすことで炎症が一時的にやわらぐことがあります。冷たいタオルや保冷剤をハンカチで包んで頬の外側から当てるといいでしょう。
一方で、熱いお風呂に長く入ったり、飲酒・激しい運動をすると血流が増えて腫れや痛みが悪化することがあります。安静にして、刺激を避けることが大切です。
症状が良くならない場合はできるだけ早めに歯科医院を受診し、根本的な治療を受けるようにしましょう。
歯の根っこにたまった膿の代表的な治療法3つ

治療法は大きく分けて、歯を残すための治療と、やむを得ず歯を抜く治療があります。代表的な治療法として、以下の3つを解説します。
- ①歯を残すための基本治療「精密根管治療」
- ②外科的アプローチで歯を救う「歯根端切除術」
- ③最終手段としての「抜歯」・その後の選択肢
①歯を残すための基本治療「精密根管治療」
精密根管治療は、歯の中の神経や血管が感染した際に行う、歯を残すための基本かつ重要な治療です。歯の根の内部(根管)を清掃・消毒し、無菌状態にしたうえで薬剤で密閉します。
精密根管治療の主な流れは、以下のとおりです。
- 1.感染部分を除去し根管の入り口を確保
- 2.専用器具で汚染物質を掻き出す
- 3.CTやマイクロスコープで根管の状態を確認
- 4.薬剤で根管内を消毒しシーラーで密閉
- 5.土台(コア)を立てて被せ物(クラウン)を装着
根管は複雑な形状をしており、肉眼では確認が難しいため、マイクロスコープやCTを活用します。消毒剤によって充填材の浸透が妨げられることもあり、成功には高度な技術が求められます。
神経を取った歯はもろくなるため、被せ物で補強して噛む力に耐えられるようにします。治療期間は1か月前後で、通院回数は4〜6回程度が目安です。
丁寧な処置を積み重ねることが、歯を長く守る鍵になります。
②外科的アプローチで歯を救う「歯根端切除術」
歯根端切除術は、精密根管治療を複数回行っても症状が改善しない場合などに選択される外科的な治療法です。歯の内部からではなく、歯茎の外側から直接アプローチして原因を取り除きます。
歯根端切除術が検討される主なケースは、以下のとおりです。
- 根管治療を繰り返しても、歯茎の腫れや痛みが治まらない
- 歯の根の先に、通常の根管治療では除去できない大きな膿の袋(歯根嚢胞)がある
- 歯の根の形が大きく曲がっているなど、器具が先端まで届かない
- 根管内に折れた器具が残っており、除去が困難
- 高価な被せ物が入っており、外して再治療が難しい
歯根端切除術では、まず歯茎を小さく切開して、顎の骨を少しだけ削ります。そして、膿の原因となっている歯の根の先端部分と、膿の袋を直接摘出します。根の断面から細菌が再び侵入しないよう特殊なセメントで封鎖し、歯茎を縫い合わせます。
根管治療とは異なるアプローチで、抜歯を回避できる可能性がある有効な治療法です。ただし、外科手術のため術後に腫れや痛みを伴うことや、お口の状態によっては適応できない場合もあります。
③最終手段としての「抜歯」・その後の選択肢
抜歯は、感染が周囲の骨に広がり、他の歯に悪影響を及ぼすのを防ぐための最終手段です。抜歯になる主なケースは以下のとおりです。
- 歯の根が縦に割れている「歯根破折」を起こしている
- 虫歯が歯茎の下深くまで進行し、被せ物を作れない
- 膿によって歯を支える骨が広範囲に溶けて、歯がひどくぐらついている
歯を抜いた後は、失われた機能を補う治療が必要です。抜いたまま放置すると、お口全体の噛み合わせが崩れ、新たな問題を引き起こす原因になります。
抜歯後の主な治療の選択肢を以下の表にまとめています。
| 治療法 | 特徴 | メリット | デメリット |
| ブリッジ | 両隣の健康な歯を土台にして、橋を架けるように一体型の人工歯を装着する | ・固定式で違和感が少ない ・保険適用できる場合がある | ・健康な歯を削る必要がある ・土台の歯に負担がかかる |
| 入れ歯 | 隣の歯にバネをかけるなどして固定する、取り外し式の人工歯 | ・周囲の歯をほとんど削らない ・比較的短期間で製作できる ・保険適用ができる | ・違和感や異物感が出やすい ・毎日の着脱や手入れが必要 ・バネをかけた歯に負担がかかる |
| インプラント | 顎の骨に人工の歯根を埋め込み、その上に人工歯を装着する | ・自分の歯のように自然に噛める ・周囲の歯に負担をかけない ・見た目が美しい | ・外科手術が必要 ・治療期間が長い ・自費診療で費用が高額 |
どの治療法にも一長一短があります。ご自身の希望やライフスタイル、お口の状態に合わせて、歯科医師と十分に相談して決めることが重要です。
根管治療の成功率を高める3つのポイント

根管治療は、歯を残すための重要な治療です。しかし、歯の根の中は暗く、複雑な構造をしています。そのため、治療の難易度が高く、成功率は100%ではありません。
根管治療の成功率を高めるポイントとして、以下の3つを解説します。
- ①CTやマイクロスコープを用いた精密な検査
- ②治療期間・回数の目安と費用
- ③再発を防ぐセルフケアと定期検診の重要性
①CTやマイクロスコープを用いた精密な診査
根管治療の成功には、肉眼では見えない根の構造や、感染部位の正確な把握が不可欠です。そのために活躍するのが、歯科用CTとマイクロスコープです。
歯科用CTの特徴は以下のとおりです。
- 三次元で歯や顎骨を立体的に確認できる
- 根の本数・形・膿の広がりを正確に把握できる
- 治療前に「詳細な設計図」を作れる
マイクロスコープとそれを使った治療の特徴は以下のとおりです。
- 約20倍の拡大視野で明るく、直接確認できる
- 感染部のみを的確に除去し、健康な歯質を温存できる
- 薬剤の残留も確実に除去し、シーラー密着性を確保できる
近年の研究では、薬剤が根管内に残りすぎると、最終的に詰める薬(シーラー)の密着を妨げる可能性が指摘されています。(※2)
特に歯の根の中央部分で影響が強く出ることがわかっており、マイクロスコープにより薬剤残留も確実に除去できます。これにより、再感染リスクを大きく減らせます。
②治療期間・回数の目安と費用
根管治療は1回で完了せず、平均1か月・4〜6回通院が必要です。根管内の消毒薬の効果を待つ期間があるためで、重度感染や再治療ではさらに延びることもあります。
保険診療と自費診療では、治療内容や使用機器、費用に大きな違いがあります。主な違いは以下のとおりです。
| 項目 | 保険診療 | 自費診療 |
| 目的 | 必要最低限の機能回復 | 高精度・審美性・長期安定性 |
| 使用機器 | 制限ありで、CTなどは一般的でない | CT・マイクロスコープ活用 |
| 材料 | 国指定の材料 | 高品質で耐久性の高い材料 |
| 治療時間 | 制約あり | 十分な時間を確保 |
| 費用 | 数千円〜(3割負担) | 数万円〜十数万円(全額負担) |
自費診療は高額ですが、精密機器や高品質材料を使用でき、時間をかけた丁寧な治療で再発リスクを抑え、歯の寿命を延ばせる可能性があります。
③再発を防ぐセルフケアと定期検診の重要性
根管治療後の歯は神経を失い脆くなっているため、再発防止には毎日のケアと定期検診が不可欠です。
再発を防ぐ主なセルフケアは以下のとおりです。
- 歯間清掃:フロスや歯間ブラシで細菌侵入を防ぐ
- 根面う蝕予防:歯茎下がりで露出した根元を丁寧に清掃する
神経を抜いた歯は痛みが出にくく異変を見逃しやすいため、3〜6か月に一度は歯科で定期検診を受けましょう。専門的なクリーニングで、セルフケアでは落とせない汚れ(バイオフィルム)を除去し、再発リスクを大きく下げられます。
まとめ
歯茎の腫れや痛み、ニキビのようなできものは、歯が発している危険なサインです。原因は虫歯や歯周病などによる細菌感染であり、自然に治ることはありません。
放置すれば、大切な歯を失うだけでなく、全身の健康に悪影響が及ぶこともあります。治療の基本は、精密根管治療などで感染源を徹底的に取り除くことです。
市販薬で一時的に痛みが和らいでも、原因は残ったままです。気になる症状があれば、自己判断で様子を見ずに、できるだけ早く歯科医院で相談しましょう。
参考文献
根管治療の関連コラム
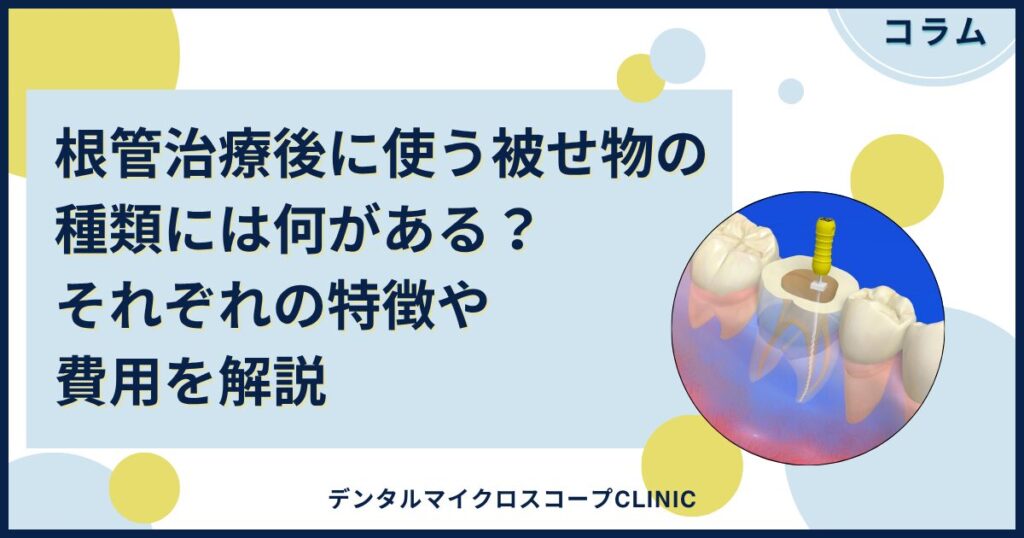
【医師監修】根管治療後に使う被せ物の種類には何がある?それぞれの特徴や費用を解説
根管治療をした後は、歯や神経を守るために被せ物をします。被せ物にはいくつか種類があり、特徴や保険適用となるのか、費用などが異なります。この記事では、保険・自費合...
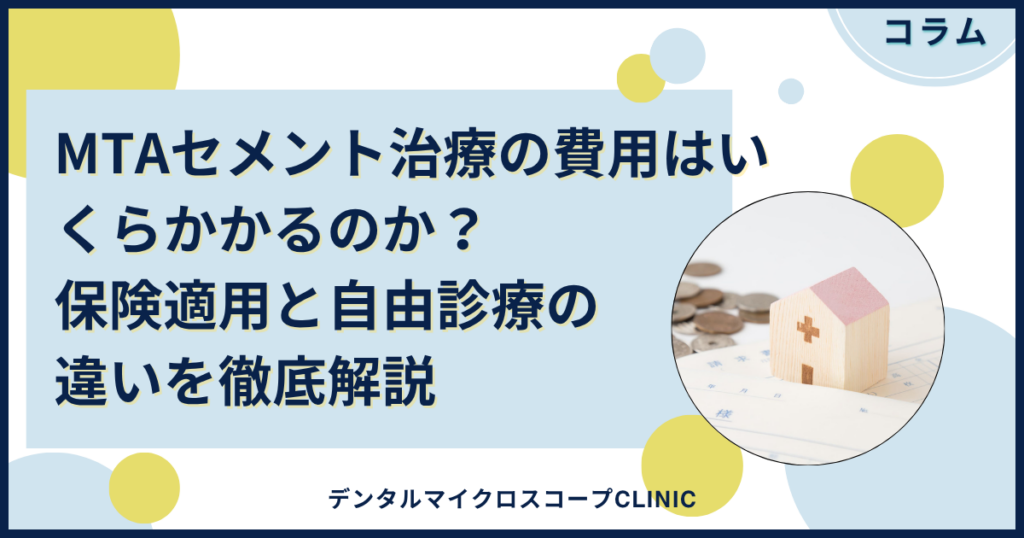
【医師監修】MTAセメント治療の費用はいくらかかるのか?保険適用と自由診療の違いを徹底解説
歯科医療の進歩により、従来なら抜歯しか選択肢がなかった歯も「MTAセメント治療」という方法で救える可能性が大きく広がっています。しかし、「MTAセメント治療はど...
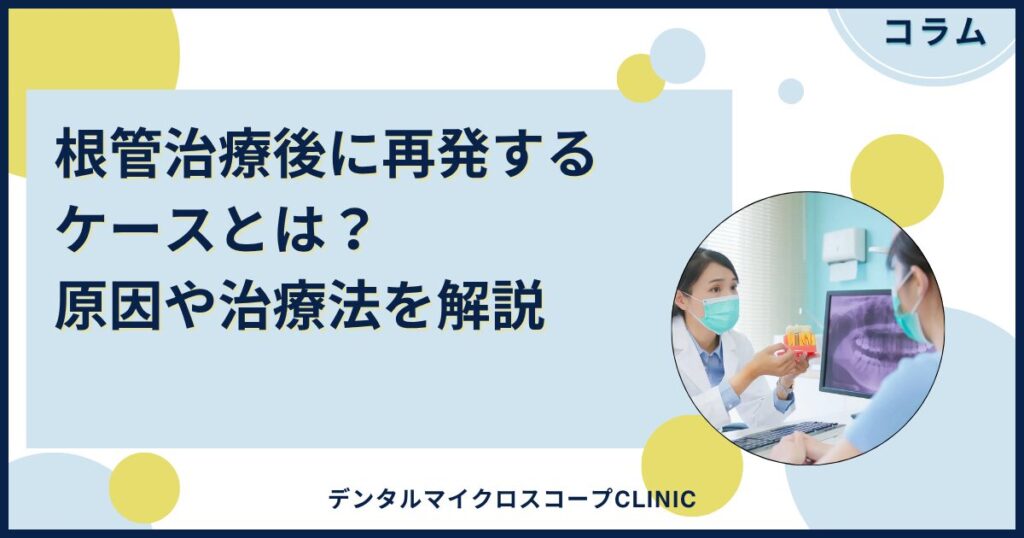
【医師監修】根管治療後に再発するケースとは?原因や治療法を解説
一度治療を終えたはずの歯が、また痛みだして、「治療がうまくいかなかったの?」と、不安な気持ちになっていませんか。歯の根の神経を取り除く根管治療は、歯を残すための...
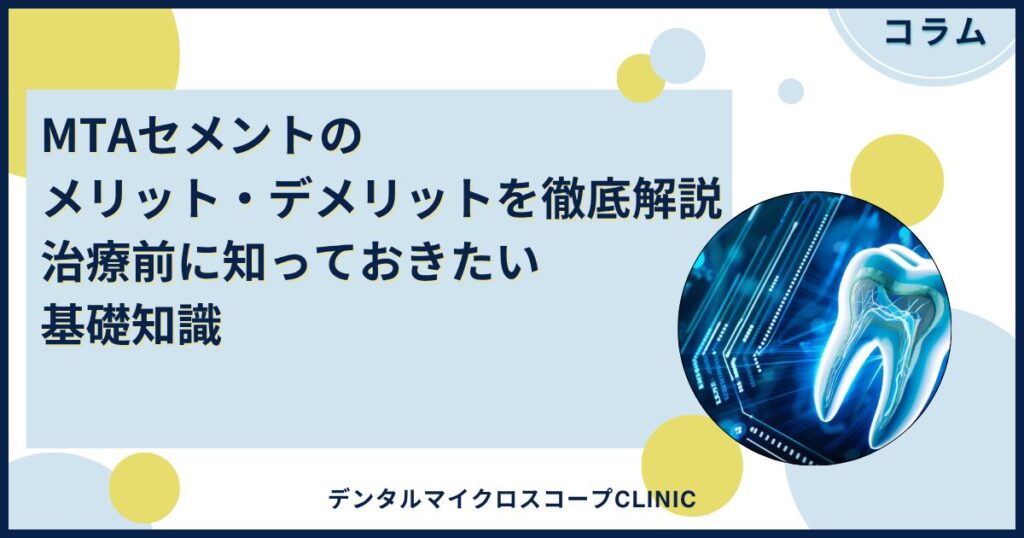
【医師監修】MTAセメントのメリット・デメリットを徹底解説|治療前に知っておきたい基礎知識
「この歯はもう抜くしかないかもしれません」歯科医師からそう告げられ、大切な歯を諦めかけていませんか。しかし、深い虫歯でも神経を残し、歯の寿命を延ばせる可能性を秘...
根管治療でおすすめの歯科医院
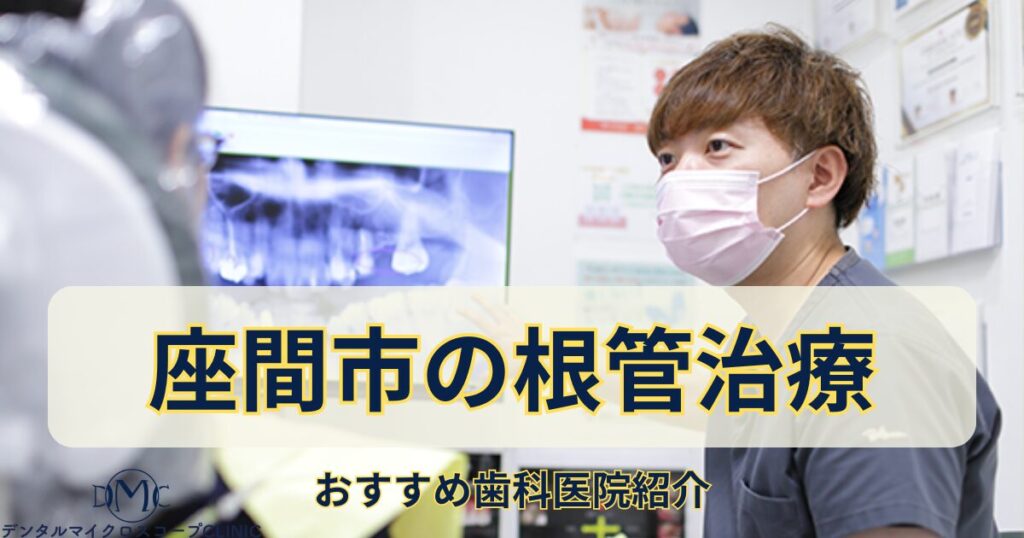
【座間市・精密根管治療】再発を防ぎ歯を残すマイクロスコープ|相武台ゆうデンタルクリニック
「治療したのに歯の痛みが引かない」「歯の神経を抜く治療が必要と言われた」神奈川県座間市で根管治療を受けるなら、無駄に歯を削らない・神経をなるべく抜かない精密治療...

【再発を防ぐ】盛岡市の根管治療|歯を残すなら日本顕微鏡歯科学会・認定指導医在籍のたかデンタルクリニックへ
「他の歯科医院で抜歯しかないと言われた」「痛みが治らない……もしかして治療に失敗した?」岩手県盛岡市で、ご自身の歯をできる限り残したい方、根管治療を繰り返してい...

横浜市港北区・綱島でおすすめするマイクロスコープ精密歯科治療は高田歯科クリニック
横浜市港北区・綱島エリアでマイクロスコープを用いた精密な歯科治療をご希望の方へ。東急東横線「綱島駅」から徒歩3分の高田歯科クリニックは、医学的根拠(エビデンス)...
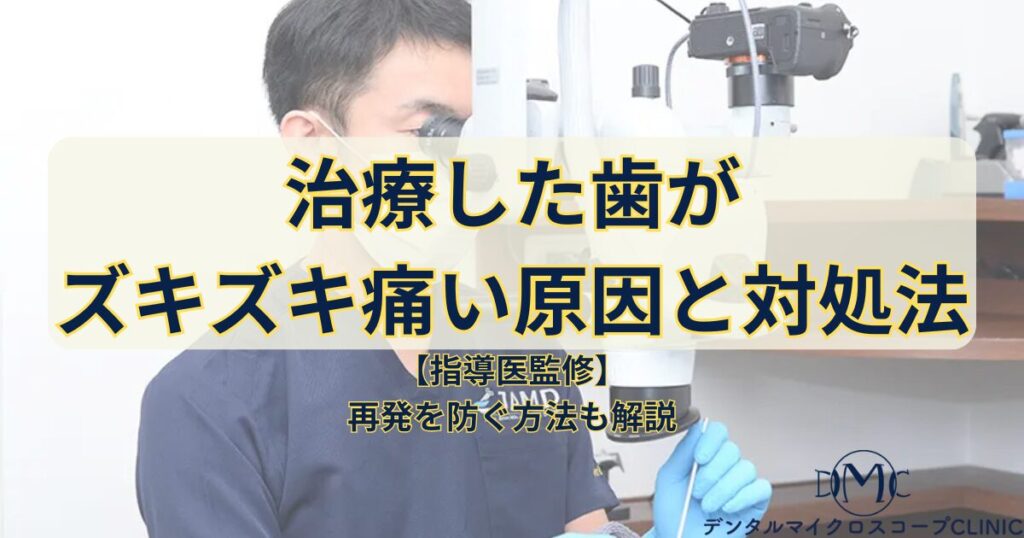
【指導医監修】治療した歯がズキズキ痛い原因と対処法|再発を防ぐマイクロスコープ
「ズキズキと脈打つような歯の痛みをなんとかしたい」「以前治療した歯が痛い……もしかして失敗した?」当記事では、治療した歯が痛くなる原因、【治療後すぐ】【しばらく...
