歯茎の健康は全身の健康状態を映し出す鏡とも言われています。
普段はピンク色をしている歯茎が白く変化すると、何かしらの異常が起きているサインかもしれません。
歯茎が白くなる原因はさまざまで、単なる外傷や刺激から始まり、アフタ性口内炎、カンジダ症、さらには全身疾患による影響まで多岐にわたります。
当記事では歯茎が白くなったときの対処法や治療法について解説します。
歯茎が白くなる原因・病気

歯茎が白くなる原因・病気についてご説明します。
フィステル(瘻孔・ろうこう)
フィステルは、歯の根の先に膿がたまり、その膿が出ていくための通り道(瘻孔)が歯茎にできた状態です。
この状態では歯茎の表面に白い膨らみや出っ張りができ、それが破れて膿が出てくることもあります。
また、瘻孔の周りの歯茎も白っぽくなったり、周囲の粘膜が硬く変わったりすることがあります。
アフタ性口内炎
アフタ性口内炎は、口の中に小さな白い潰瘍ができる症状です。
この潰瘍は周りが赤く炎症を起こしていて、中心部分が白く見えるのが特徴です。
これは口の中の粘膜のあらゆる場所に発生し、歯茎にも現れることがあります。
この症状は体の疲れやストレス、免疫力が下がっているときに起こりやすく、寝不足が続いているときや風邪の後などに発症しやすい傾向があります。
通常は1〜2週間ほどで自然に治りますが、その間は痛みを伴うため、歯磨きがつらくなったり、話しづらくなったりすることがあります。
ウイルス感染症
口の中がウイルスに感染すると、歯茎が白くただれたような状態になることがあります。
この症状は特に子どもや若い方に多く見られます。
代表的なものとしてヘルペス性口内炎があり、これにかかると歯茎全体が赤白く腫れたり、小さな水ぶくれができて破れ、白い潰瘍になったりします。
口腔カンジダ症
口腔カンジダ症は、カビの一種であるカンジダ菌(主にカンジダ・アルビカンス)が口の中で異常に増殖することで起こる感染症です。
この症状では、歯茎や頬の内側、舌などに白い苔のような膜(偽膜)が付着し、歯茎全体が白っぽく見えるようになることがあります。
この症状は特定の条件で発症しやすくなります。
例えば、抗生物質やステロイド薬を長期間使用している方、口が乾きやすい状態(ドライマウス)の方、糖尿病を患っている方などは発症リスクが高まります。
また、高齢の方や入れ歯を使用している方にも多く見られ、入れ歯の下の歯茎が白くただれる「義歯性口内炎」の原因にもなります。
扁平苔癬(へんぺいたいせん)
扁平苔癬は、自己免疫の異常によって口の中の粘膜にレース模様や網目状の白い模様が現れる慢性的な炎症性疾患です。
歯茎にも発症することがあり、その場合は白い網の目のような線が見られます。
進行して「びらん型」になると、赤く腫れて痛みを伴うようになります。
この病気は50代以上の中高年の女性に多く見られます。
特徴として、口の中の左右対称の場所に現れやすく、また長期間にわたって症状が続きます。
辛い食べ物や熱い飲み物などの刺激物で症状が悪化することが多く、特にびらん型では痛みが強くなり、歯磨きも困難になることがあります。
歯周病
歯周病は歯の周りの組織(歯肉や歯を支える骨など)に起こる慢性的な炎症性疾患です。
一般的には歯茎の腫れや出血が特徴ですが、炎症によって血液の流れが妨げられると、歯茎が白っぽく見えることもあります。
また、病気が進行すると歯茎がやせて下がったり(退縮)、全体的な色が変わったりします。
歯の表面に付着した歯垢(プラーク)や歯石が蓄積することで炎症が起こり、慢性的に血液循環が悪くなって歯茎が白く見えることがあります。
歯周病の特徴として、初期段階では自覚症状がほとんどないことが多く、気づいたときには歯がグラグラするほど進行していたというケースも少なくありません。
骨隆起(こつりゅうき)
骨隆起とは、歯茎の下にある骨が過剰に成長して突き出した状態のことです。
この骨の出っ張りを覆う歯茎の粘膜が薄く伸ばされるため、その部分が白っぽく見えることがあります。
上あごの真ん中(口蓋側)や下あごの内側(舌側)に、左右対称にできることが多いのが特徴です。
この症状は特に歯ぎしりや食いしばりの習慣がある方に多く見られ、40歳以降で気づかれることが多いです。
白板症(はくばんしょう)
白板症は、口の中の粘膜に現れる、拭いても取れない白い斑点や斑紋のことです。
歯茎を含む口腔内のどの部位にも発生する可能性があります。
見た目は白く硬くなった(角化した)ような変化で、がんに変化する可能性がある「前がん病変」として注意が必要です。
この症状はタバコを吸う方やお酒をよく飲む方に多く見られ、歯茎や舌、頬の内側などに白く硬い病変として現れます。
歯茎が全体的に白くなる原因・病気

歯茎が全体的に白くなる原因・病気についてご説明します。
貧血
歯茎が白く変色する原因のひとつに貧血があります。
貧血は赤血球の数が減少することにより、体内を巡る血液の酸素運搬能力が落ちてしまう状態です。
これによって体全体の組織へ十分な酸素が供給されなくなります。
普段の生活で顔色が青白かったり、体がだるい、息切れがするといった症状を感じていた方が、実は歯科医院での定期検診で歯茎の色の異常を指摘され、それをきっかけに内科を受診して貧血が発見されるというケースも珍しくありません。
歯茎の血行不良
歯茎の血液の流れが悪くなると、必要な栄養や酸素が十分に行き渡らなくなります。
このため歯茎の色つやが悪くなり、白っぽくくすんだように見えることがあります。
タバコを習慣的に吸っている方は、タバコの成分によって血管が縮まってしまうため、常に歯茎の血流が低下している状態になります。
また体が冷えやすい方や血圧が低めの方は、手先や唇が冷たくなるのと同じように、歯茎も血行不良の影響を受けやすいといえます。
低栄養状態
体に必要な栄養が不足している状態も、歯茎が白くなる要因となります。
特にビタミン類やたんぱく質が足りないと、口の中の粘膜全体の健康が保てなくなり、自然な修復能力も低下します。
偏った食事を長く続けていたり、極端なダイエットや食事の問題を抱えていたりすると、低栄養状態に陥り、歯茎だけでなく舌や口の端にも異常が現れることがあります。
特に高齢者や、一人暮らしで食事がどうしても偏りがちな方などは、歯科での口腔内の状態チェックが、体全体の栄養状態を知る大切な目安になることもあるでしょう。
歯茎が白いときの対処法・治療法

歯茎が白いときの対処法・治療法をご紹介します。
セルフケア・対処法:口腔内を清潔に保つ
歯茎が白く見える状態の背景には、炎症や感染、免疫力の低下などが関係していることが多くあります。
細菌や真菌(カビの一種)の増殖を防ぐために、口の中を清潔に保つことは非常に大切です。
毎日の基本ケアとして、1日2~3回の歯磨きを習慣にしましょう。
特に就寝前の歯磨きは最も重要です。
歯ブラシは柔らかめのものを選び、白くなっている部分を傷つけないよう、優しく磨くことがポイントです。
歯と歯茎の境目(歯周ポケット)は汚れがたまりやすいので、特に意識して丁寧に磨きましょう。
セルフケア・対処法:市販薬・セルフケア用品の利用(軽症の場合)
軽度の炎症や粘膜の異常であれば、薬局やドラッグストアで手に入るケア用品や薬を上手に使うことで、症状を和らげることができます。
ただし、自己判断で長期間使用することは避け、症状が改善しない場合は早めに歯科医院や医療機関を受診することが大切です。
アフタ性口内炎の場合は、ステロイド成分を含む市販の軟膏(例:ケナログ、アフタッチなど)を患部に塗ると効果的です。
特に貼り付けるタイプのパッチ製品は、会話や食事の際に薬が取れにくく便利です。
口の中の炎症予防には、抗菌成分が入ったうがい薬(アルコールが入っていないタイプ)で口をすすぐことが有効です(例:コンクールF、イソジンうがい薬など)。
歯科医院での治療:歯周病治療
慢性的な歯周病によって歯茎の血流が悪化すると、色がくすんだり白っぽく見えることがあります。
このような症状に対する歯科医院での治療は、まずスケーリングと呼ばれる歯石除去から始まります。
歯の表面や歯と歯茎の間の溝(歯周ポケット)内にある歯石やプラーク(歯垢)を専用の器具で丁寧に取り除きます。
さらに必要に応じてルートプレーニングという処置も行います。
これは、歯の根の表面をなめらかにして、細菌が再び付着しにくくする治療です。
治療の過程では、歯周ポケットの深さを測ったり、触った時の出血の有無を確認したりして、炎症の程度を数値化し、治療効果を継続的に評価していきます。
歯周病が重度の場合には、歯肉を切開して処置を行う歯周外科手術(歯肉切除、フラップ手術、再生療法など)が必要になることもあります。
歯科医院での治療:口内炎・扁平苔癬など粘膜疾患の治療
アフタ性口内炎や扁平苔癬(へんぺいたいせん)などの粘膜疾患では、口の中の粘膜に白いびらん(ただれ)や潰瘍、レース状の模様が現れることがあります。
これらの疾患に対する歯科医院での治療では、主にステロイド軟膏の塗布が行われます。
例えばトリアムシノロンという成分が含まれた軟膏を患部に塗ることで、炎症を抑える効果があります。
痛みが強い場合には、局所麻酔薬が入ったゲル(例:キシロカイン軟膏)を短時間使用して、一時的に痛みを和らげることもあります。
また、これらの症状がアレルギー反応によって引き起こされている可能性もあります。
特に歯の詰め物や被せ物に使われている金属に対するアレルギー(金属アレルギー)が原因となっていることもあるため、検査を行い、必要に応じて金属を除去することもあります。
歯科医院での治療:抗真菌薬の処方(カンジダ症など)
口腔カンジダ症は、カンジダという真菌(カビの一種)が口の中で異常に増殖することで起こる感染症です。
歯科医院でのカンジダ症の治療では、抗真菌薬と呼ばれるカビに効く薬を使用します。
ミコナゾールというゲル状の薬を患部に塗ったり、アムホテリシンBという成分が含まれたうがい薬で口をすすいだりします。
入れ歯が原因でカンジダ症になっている場合は、入れ歯の使用を一時的に中止し、専用の洗浄剤でしっかり消毒することが大切です。
歯科医院での治療:根管治療(感染が原因のフィステルなど)
歯の根の先に細菌感染が起こり膿がたまると、その膿が逃げ道を作って歯茎の表面に出てくることがあります。
この膿の出口を「フィステル(瘻孔)」と呼び、これが歯茎に現れると、その部分が白く膨らんだように見えることがあります。
このような症状を治療するためには、まず感染源となっている歯の根の内部(根管)の治療が必要です。
歯科医院では、細菌が繁殖した根管内を特殊な器具を使って丁寧に清掃・消毒します。
その後、きれいになった根管内に薬剤を詰めて封鎖し、細菌が再び侵入するのを防ぎます。
根管内の感染が適切に処置されると、フィステルは通常自然に閉じていきます。
しかし、感染が強い場合や再発を繰り返す場合には、歯根端切除術という外科的な処置が必要になることもあります。
歯科医院での治療:外科的処置(骨隆起・病変切除)
歯茎の下にある骨に「骨隆起(こつりゅうき)」という硬い出っ張りができることがあります。
また、白板症(はくばんしょう)と呼ばれる前がん病変や、慢性の潰瘍、腫瘤(しゅりゅう)などによっても、歯茎に白い変化が現れることがあります。
骨隆起は、多くの場合は無害ですが、強い違和感があったり、入れ歯が合わなくなったりする場合には、切除手術が必要になることがあります。
これは通常、局所麻酔をして歯茎を切開し、出っ張った骨を削り取る処置です。
また、白板症などの病変は、がん化するリスクがある場合には、その部分を切除して病理検査に回すことがあります。
粘膜に異常が長期間続く場合には、組織の一部を採取して調べる「生検(バイオプシー)」を行うこともあります。
まとめ
歯茎が白くなる状態は、私たちの口の健康に関わる重要なサインです。
その原因は多岐にわたり、歯の根の感染によるフィステル(瘻孔)の形成、アフタ性口内炎やウイルス感染症、口腔カンジダ症などが挙げられます。
全身的な要因としては、貧血や血行不良、低栄養状態なども歯茎の白色化を引き起こすことがあります。
対処法としては、まず日常的なセルフケアが基本となります。
柔らかい歯ブラシでの優しい歯磨きや、抗菌成分入りのうがい薬の使用が有効です。
軽症の場合は市販薬を活用しながら、症状が改善しない場合は早めに歯科受診が大切です。
歯科医院では症状に応じて、歯周病治療(スケーリングやルートプレーニング)、粘膜疾患へのステロイド軟膏の塗布、カンジダ症に対する抗真菌薬の処方、感染歯の根管治療、必要に応じた外科的処置などが行われます。
口腔内の健康は全身の健康と密接に関わっています。
歯茎の白い変化に気づいたら、自己判断せず専門家に相談することで、早期発見・早期治療が可能となり、より効果的な改善が期待できます。
定期的な歯科検診も、口腔内の異常を早期に発見する重要な機会となります
歯周病の関連コラム
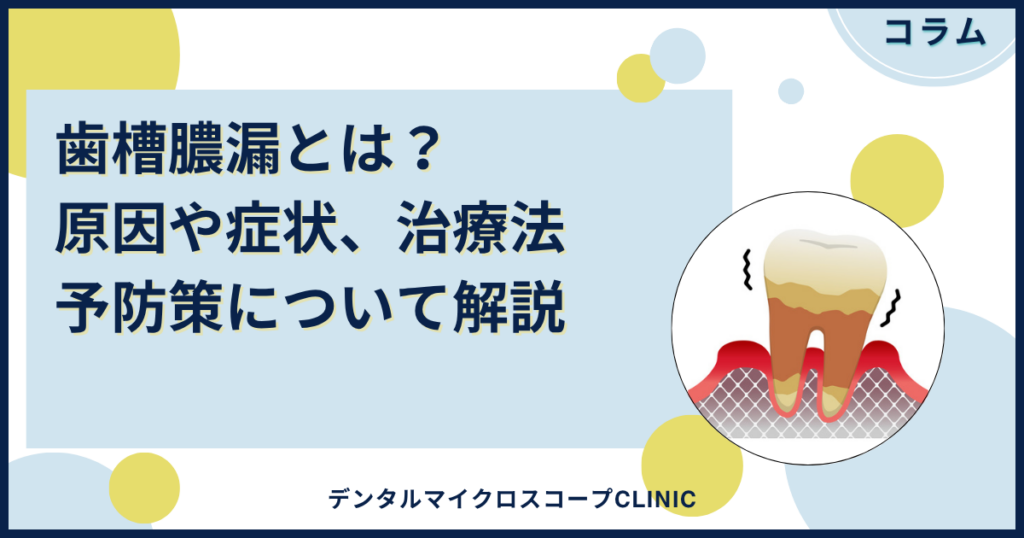
歯槽膿漏とは?原因や症状、治療法、予防策について解説
「もしかして、これって歯槽膿漏?」歯ぐきから出血や口臭、歯のグラつき...。そんな症状に心当たりはありませんか?この病気は、自覚症状が少ないまま静かに進行し、大...
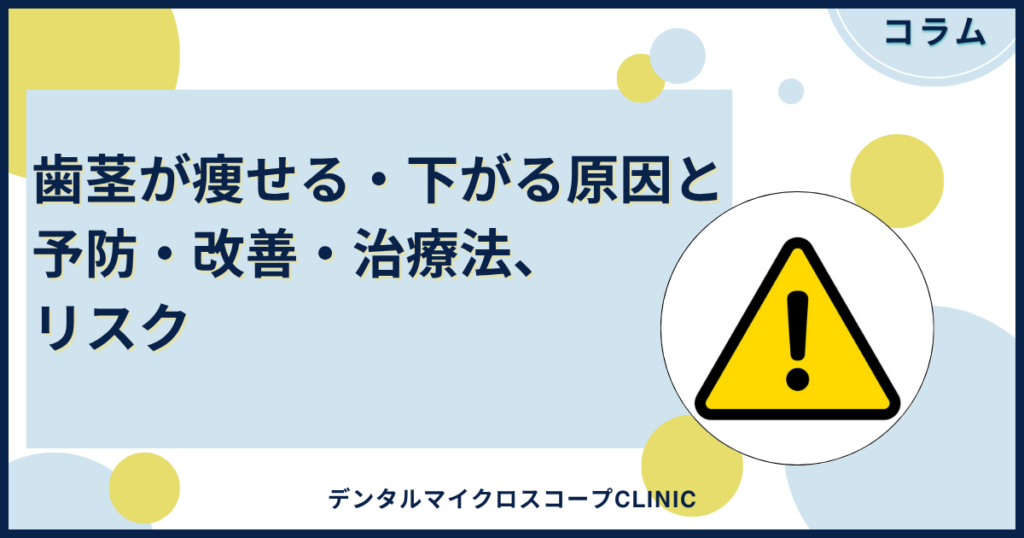
歯茎が痩せる・下がる原因と予防・改善・治療法、リスク
歯茎の痩せは、多くの方が経験するにもかかわらず、その重大さに気づかれにくい口腔トラブルです。年齢を重ねるにつれて自然に進行することもありますが、様々な原因によっ...
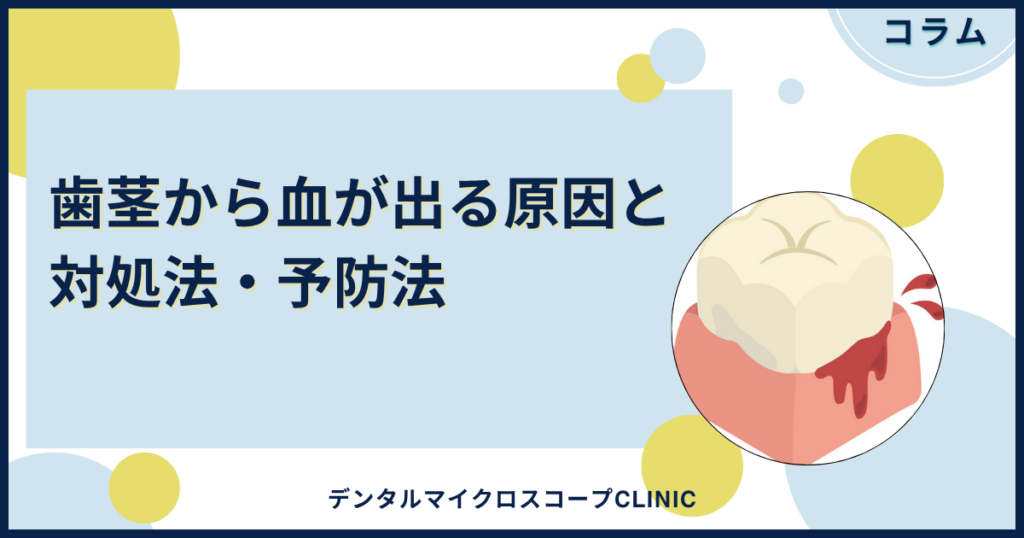
歯茎から血が出る原因と対処法・予防法
歯茎から血が出ることは、多くの方が経験される身近な症状ですが、その背景には様々な原因が隠れています。軽度な歯肉炎から重篤な全身疾患まで、出血の原因は実に多岐にわ...
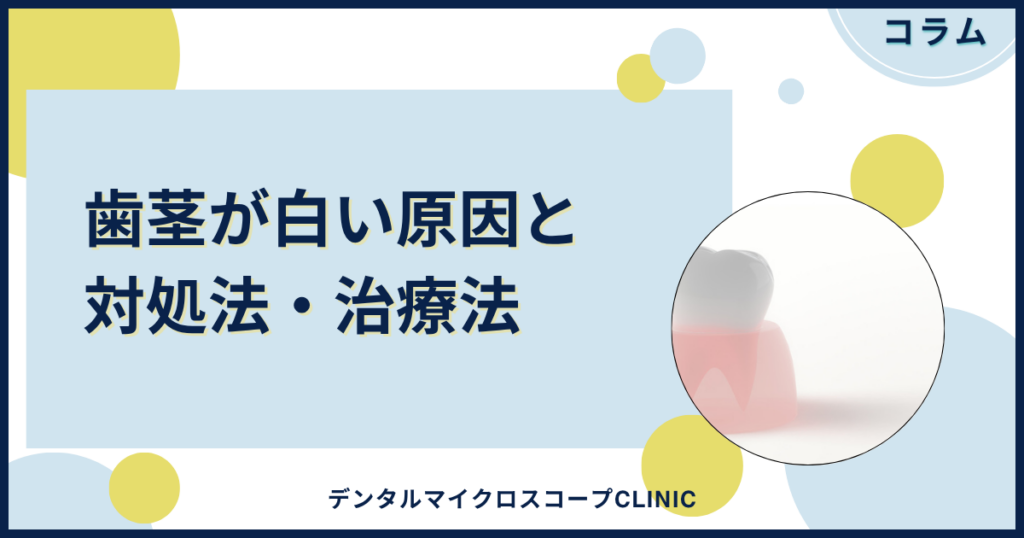
歯茎が白い原因と対処法・治療法
歯茎の健康は全身の健康状態を映し出す鏡とも言われています。普段はピンク色をしている歯茎が白く変化すると、何かしらの異常が起きているサインかもしれません。歯茎が白...


