歯茎が腫れて痛んだり、膿が出てきたりする場合、歯の内部が細菌に感染し炎症が進んでいるサインです。放置すれば激しい痛みや腫れはもちろん、顎の骨を溶かし、最悪の場合は大切な歯を失うだけでなく、全身の健康に影響を及ぼすことさえあります。
この危機から歯を守るのが根管治療ですが、「何度も通院が必要」「治療したのにまた痛む」といった経験から、不信感を抱く方も少なくありません。
この記事では、膿を出す方法や治療が長引く理由、そしてどうしても治らない場合の選択肢までを専門的に解説します。あなたの不安を解消し、納得して治療に臨むための一歩となるはずです。
この記事の監修歯科医師

谷川歯科医院
谷川 淳一 副院長
歯科医師。日本口腔インプラント学会専修医。小児歯科治療や小児矯正、インプラント治療を得意とし、他の歯科医師への指導も行う。
患者様一人ひとりと真摯に向き合って治療方針を決めていくことを信条としている。
目次
根管治療で膿が出る理由

根管治療で膿が出る理由は、歯の根の中やその周囲に感染が起きているからです。ときには全身の健康にまで影響を及ぼすこともあるため、原因菌を徹底的に取り除き、膿をしっかり出し切る「根管治療」が不可欠です。
ここでは、根管治療で膿が出る・たまる理由や治療の重要性について詳しく見ていきましょう。
歯の根に膿がたまる原因とは?
歯の根に膿がたまる最も一般的な原因は、歯の内部にある神経(歯髄)が細菌感染を起こす「根尖性歯周炎(こんせんせいししゅうえん)」です。この病気は、主に以下の流れで進行します。
- 細菌の侵入
- 歯の神経が死ぬ(壊死)
- 細菌の繁殖
- 膿の袋ができる
膿は、細菌を閉じ込めようとする体の防御反応です。しかし、大元である細菌を取り除かない限り、自然に治ることはありません。
膿を放置するとどうなる?
歯の根にたまった膿を治療せずにいると、さまざまなトラブルにつながる可能性があります。普段は症状がなくても、体の抵抗力が落ちたときに急に以下のような症状が悪化することがあります。
- 激しい痛みや顔の腫れ
- 顎の骨が溶ける
- 歯を失うリスク
- 全身の病気への影響(歯性病巣感染)
一時的に痛みが引いても、原因が解決したわけではありません。早めに適切な治療を受けることが、歯と体の健康を守るために重要です。
膿を出し切らないと再発リスクが高まる
根管治療の最大の目的は、歯の根の中から原因となる細菌を完全に取り除き、膿を出し切ることです。しかし、歯の根の中は非常に細く、木の根のように複雑に枝分かれしています。
この複雑な構造に潜む細菌を、一度の治療で完全に取り除くのは極めて困難です。もし治療を途中でやめたり、清掃が不十分で細菌が残ったりすると、その細菌が再び活動を始めます。
その結果、数ヶ月から数年後に再び膿がたまり、痛みや腫れが再発します。症状が落ち着いたからといって自己判断で通院をやめると、再発のリスクを高めてしまいます。大切な歯を長く守るためにも、歯科医師の指示に従い、根気強く治療を最後までやり遂げましょう。
根管治療で膿を出す際の治療の流れ

歯の根に膿がたまっていると聞くと、「痛そう」「どんなことをされるのだろう」と、不安でいっぱいになるかもしれません。
根管治療は、歯の内部にある非常に細かく複雑な管をきれいにする、とても繊細な処置です。治療は以下のステップに分かれており、一つひとつ丁寧に進めていきます。
- 1.診察・レントゲンで膿の状態を確認
- 2.歯を開けて根管内の清掃・洗浄
- 3.根の先の膿を出す処置
より詳細な治療の流れは、こちらの記事で詳しく解説しているので、あわせて参考にしてください。
根管治療で膿を出す方法
膿を効率よく排出するためには、以下のような処置が行われます。
- 根管内のドレナージ
- あえて開放したまま様子見
- 瘻孔(フィステル)からの排膿
- 歯肉切開による排膿
- 抗菌薬の併用
根管内のドレナージ
根管内のドレナージは、神経が壊死して膿が溜まった際に、歯の内部に通路を作って膿を排出する応急的な処置です。腫れや痛みを和らげる効果がありますが、感染源の除去や根管充填といった根本的な治療が別途必要となります。
あえて開放したまま様子見
膿が多くたまっている場合には、根管に仮封をせず、しばらく開放状態にしておくことがあります。これにより、内部の膿が徐々に排出され、痛みや腫れの軽減につながることがあります。
ただし、外部から細菌が入り込むリスクもあるため、歯科医の慎重な判断と経過観察が欠かせません。
瘻孔(フィステル)からの排膿
膿が内部にたまり圧が高まると、歯ぐきに小さな出口(瘻孔)ができて自然に排膿されることがあります。瘻孔があれば、膿が自然に出ていきます。
歯肉切開による排膿
膿のたまりが大きく自然に出にくい場合は、歯ぐきを小さく切開して直接排膿する処置が行われます。局所麻酔のもとで行われるので、処置自体はそこまで痛みません。
抗菌薬の併用
感染の広がりを抑えるために抗菌薬を併用することもあります。しかし根管内には血流はないため、抗菌薬を内服しても根本的な治療にはなりません。あくまでも補助的な役割であり、排膿することが重要です。
根管治療で膿を出すのに必要な回数と期間

「この治療、あと何回くらい通えば終わりますか?」根管治療を受けている多くの患者さんから、このような質問を受けます。終わりが見えない治療は、誰にとっても不安なものです。
根管治療の回数や期間は、患者さん一人ひとりのお口の状態で大きく変わります。歯の根の形は、指紋のように一つとして同じものはありません。そのため、治療計画もオーダーメイドとなり、回数や期間も異なってくるのです。
治療の回数と期間は以下の要素に左右されます。
- 膿の量
- 炎症の程度
- 感染の広がり
- 症状の強さ
- 再治療かどうか
基本的に1回で終わることは少なく、確実な治療で再発を防ぐためには複数回の治療が必要です。
根管治療で膿を出す際に注意すべきポイント

根管治療は、歯科医師の処置だけで成功するものではありません。治療の成功率を高めるには、患者さんご自身の協力が不可欠です。
治療期間中の過ごし方が、再発を防いで大切な歯を守るための鍵となります。これからお伝えする注意点を守ることが、治療効果を最大限に高めることにつながります。
- 自己判断で薬をやめたり中断したりしない
- 抗生物質や痛み止めの正しい使い方を把握する
- 食生活・生活習慣にも気をつける
自己判断で薬をやめたり中断したりしない
根管治療では、歯の根の奥に潜む細菌と戦うため、抗生物質が処方されます。この薬を飲み始めると、多くの場合、数日で痛みや腫れが和らいできます。
しかし、症状が楽になったからといって、自己判断で服用をやめるのは危険です。症状が消えたのは「治った」のではなく、薬で細菌の活動が抑えられているだけです。ここで服用を中断すると、生き残った細菌が再び勢いを盛り返し、症状がぶり返します。
さらに、中途半端に薬をやめることは、薬が効きにくい「薬剤耐性菌」を生む原因になります。次に同じ薬を使っても効果がなくなることも。処方された薬は、必ず歯科医師の指示通りに最後まで飲み切ってください。
抗生物質や痛み止めの正しい使い方
処方される薬には、それぞれに大切な役割があります。薬の特性を正しく理解し、効果的に治療を進めていきましょう。
| 薬の種類 | 目的と役割 |
| 抗生物質(化膿止め) | 歯の根の中にいる細菌の増殖を抑え、感染の広がりを防ぐ |
| 痛み止め(鎮痛剤) | 治療後のズキズキとした痛みや、歯茎の腫れに伴う痛みを一時的に和らげる |
食事や生活上の注意点
根管治療中の歯は、仮の蓋がしてあるだけで、デリケートな状態です。歯への負担を減らし、体が本来持つ治癒力を最大限に引き出すために、日常生活でも以下の点にご注意ください。
【食事で気をつけたいこと】
- 硬いものは避ける
- 粘着性の高いものは避ける
- 治療中の歯で噛まない
【生活習慣で気をつけたいこと】
- 血行が良くなる行動は控える
- 喫煙はできるだけ控える
- 十分な睡眠と休息をとる
根管治療で膿が出ない・治らないときの選択肢

根管治療を続けているのに、なかなか膿や痛みが引かない。このような状況では、「このまま治らないのでは…」と強い不安を感じてしまいますよね。
しかし、すぐに諦める必要はありません。標準的な根管治療で改善が難しい場合でも、歯を残すための次の選択肢があります。
根管の形が非常に複雑だったり、感染が大きく広がっていたりする難症例では、別の角度からのアプローチが必要です。ここでは、そのような場合に検討される治療法や、納得して治療を進めるための方法を解説します。
外科的処置(歯根端切除術・抜歯)が必要なケース
通常の根管治療を続けても症状が改善しない場合、外科的な処置が検討されます。これは、歯の根の中からではアプローチできない場所に、感染の原因が潜んでいる可能性があるためです。
歯根端切除術(しこんたんせつじょじゅつ)
歯の根の中を清掃するのではなく、歯茎側から直接アプローチする方法です。
麻酔を行った後に歯茎を小さく切開し、感染の温床となっている歯の根の先端部分と、膿の袋(根尖病巣)を丸ごと摘出します。根管の先が複雑に枝分かれしている場合など、器具が届かない部分の細菌を物理的に除去できるのが特徴です。
抜歯
抜歯歯根端切除術でも改善が難しい場合や、歯の状態が著しく悪い場合は、やむを得ず抜歯が選択されることもあります。
【抜歯が選択されるケース】
- 歯の根にヒビが入っている
- 割れている(歯根破折)
- 歯を支える顎の骨が、膿によって広範囲に溶かされている
- 虫歯が歯茎の下深くまで進行し、被せ物ができない
抜歯はあくまで最終手段であり、歯科医師は常に歯を残すことを第一に考えます。
根管治療専門医に相談するメリット
根管治療は、歯の内部にある非常に細かく複雑な管を扱う、専門性の高い治療です。もし治療が難航している場合、根管治療を専門に行う歯内療法専門医へ相談してみましょう。
専門医は、再治療や根管の穿孔(穴が開いた状態)の修復など、難易度の高い症例を数多く経験しています。こちらのホームページで確認できるので、ぜひチェックしてみてください。
まとめ
今回は、根管治療で膿を出す理由や、治療の流れ・注意点について詳しく解説しました。
歯の根にたまった膿の治療は、目に見えない部分を扱うため、時間がかかり不安に感じるかもしれません。しかし、これは再発を防ぎ、大切な歯を将来にわたって守るための非常に重要な処置です。自己判断で治療を中断せず、処方されたお薬や生活での注意点を守ることが、治療を受けるうえで重要です。
もし治療が長引いて心配な時や、説明に疑問を感じた時は、一人で抱え込まずに、遠慮なく歯科医師に相談してください。納得して治療を進めることが何より大切です。根気強く治療を続けて、健康な歯を取り戻しましょう。
根管治療の関連コラム
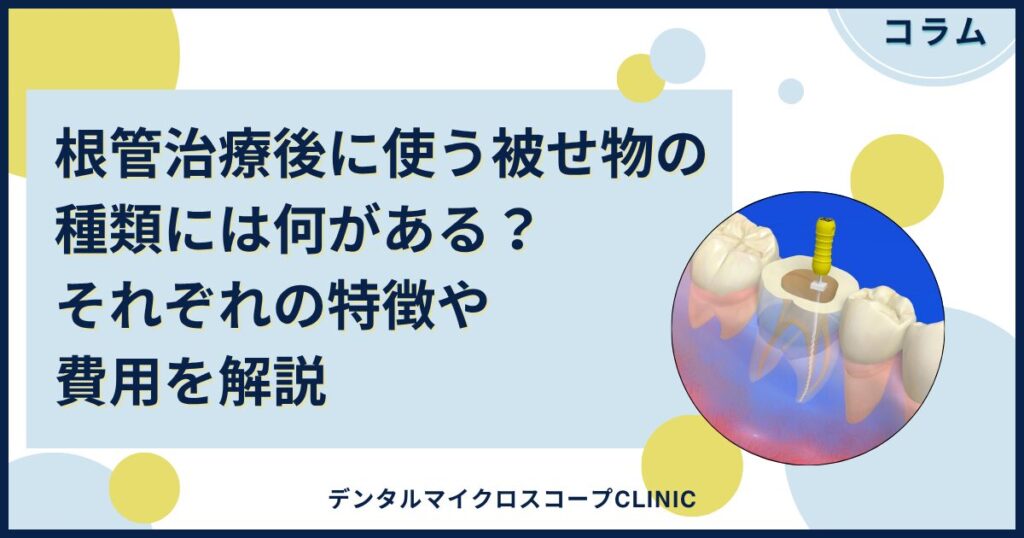
【医師監修】根管治療後に使う被せ物の種類には何がある?それぞれの特徴や費用を解説
根管治療をした後は、歯や神経を守るために被せ物をします。被せ物にはいくつか種類があり、特徴や保険適用となるのか、費用などが異なります。この記事では、保険・自費合...
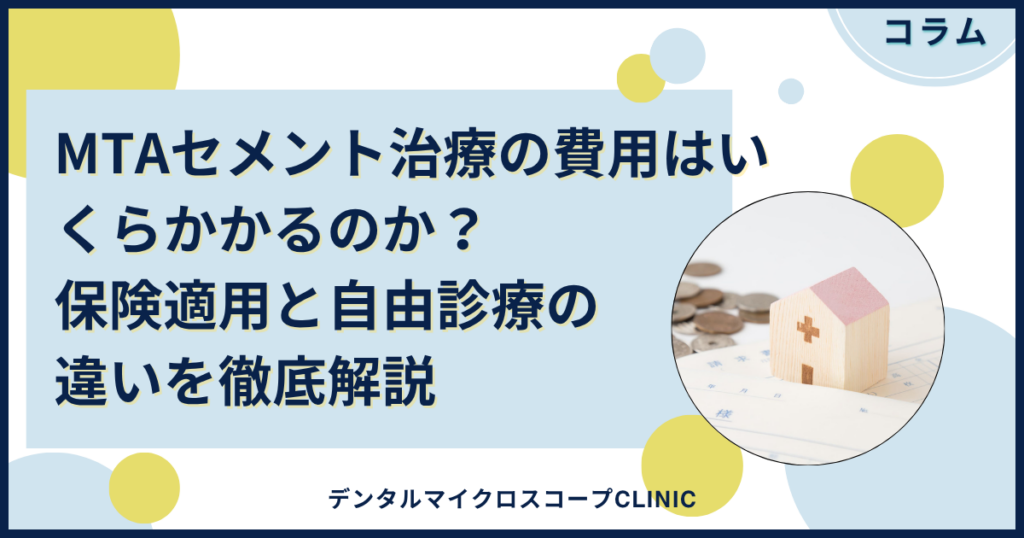
【医師監修】MTAセメント治療の費用はいくらかかるのか?保険適用と自由診療の違いを徹底解説
歯科医療の進歩により、従来なら抜歯しか選択肢がなかった歯も「MTAセメント治療」という方法で救える可能性が大きく広がっています。しかし、「MTAセメント治療はど...
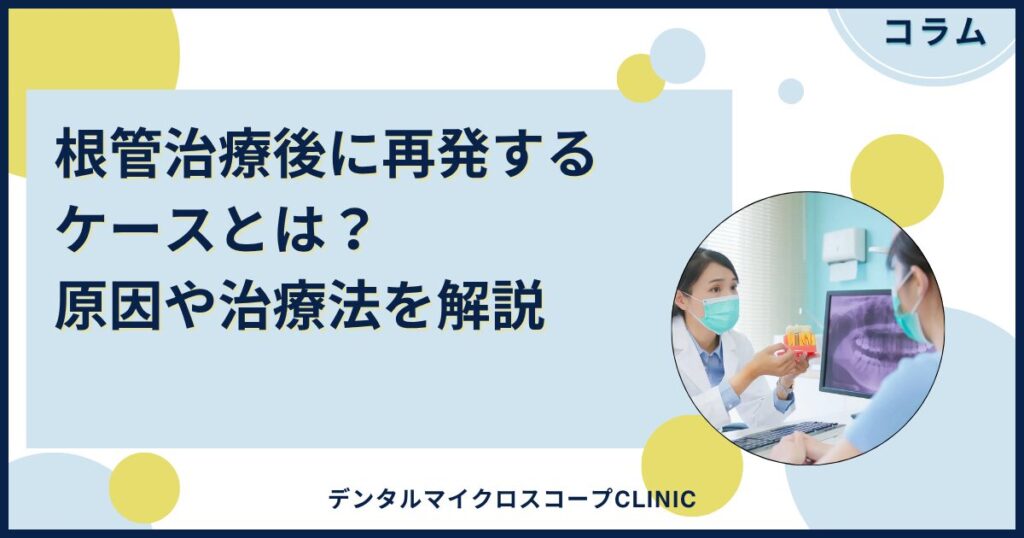
【医師監修】根管治療後に再発するケースとは?原因や治療法を解説
一度治療を終えたはずの歯が、また痛みだして、「治療がうまくいかなかったの?」と、不安な気持ちになっていませんか。歯の根の神経を取り除く根管治療は、歯を残すための...
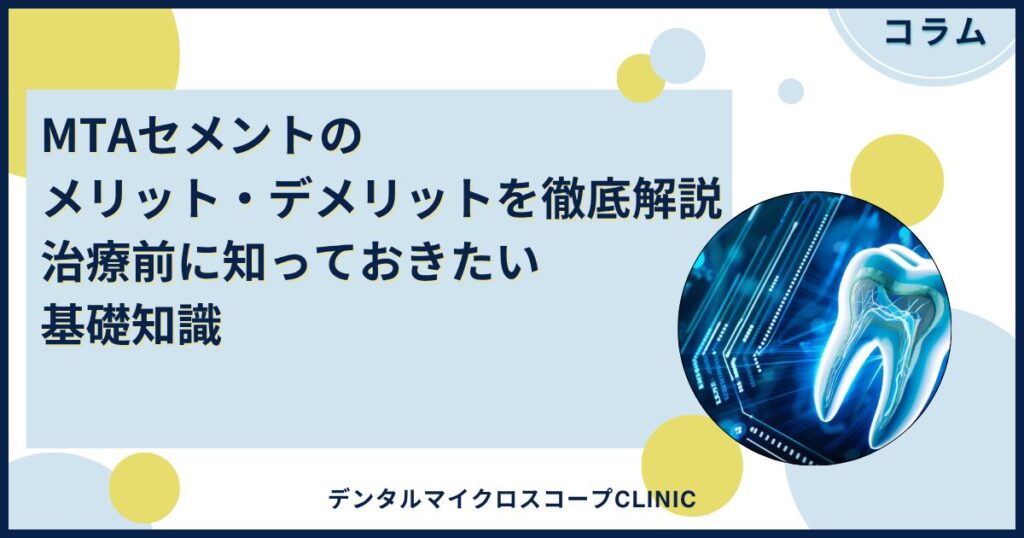
【医師監修】MTAセメントのメリット・デメリットを徹底解説|治療前に知っておきたい基礎知識
「この歯はもう抜くしかないかもしれません」歯科医師からそう告げられ、大切な歯を諦めかけていませんか。しかし、深い虫歯でも神経を残し、歯の寿命を延ばせる可能性を秘...
根管治療でおすすめの歯科医院
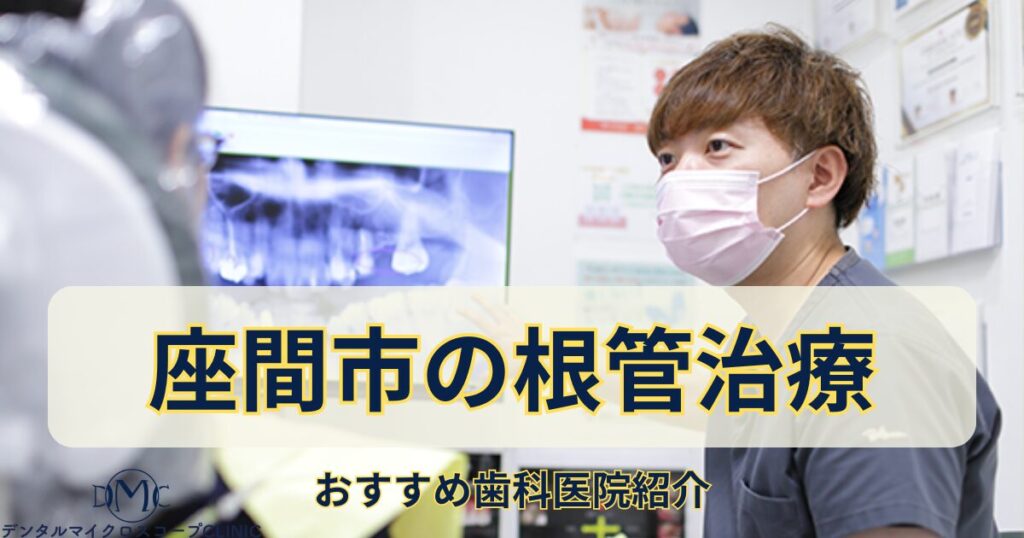
【座間市・精密根管治療】再発を防ぎ歯を残すマイクロスコープ|相武台ゆうデンタルクリニック
「治療したのに歯の痛みが引かない」「歯の神経を抜く治療が必要と言われた」神奈川県座間市で根管治療を受けるなら、無駄に歯を削らない・神経をなるべく抜かない精密治療...

【再発を防ぐ】盛岡市の根管治療|歯を残すなら日本顕微鏡歯科学会・認定指導医在籍のたかデンタルクリニックへ
「他の歯科医院で抜歯しかないと言われた」「痛みが治らない……もしかして治療に失敗した?」岩手県盛岡市で、ご自身の歯をできる限り残したい方、根管治療を繰り返してい...

横浜市港北区・綱島でおすすめするマイクロスコープ精密歯科治療は高田歯科クリニック
横浜市港北区・綱島エリアでマイクロスコープを用いた精密な歯科治療をご希望の方へ。東急東横線「綱島駅」から徒歩3分の高田歯科クリニックは、医学的根拠(エビデンス)...
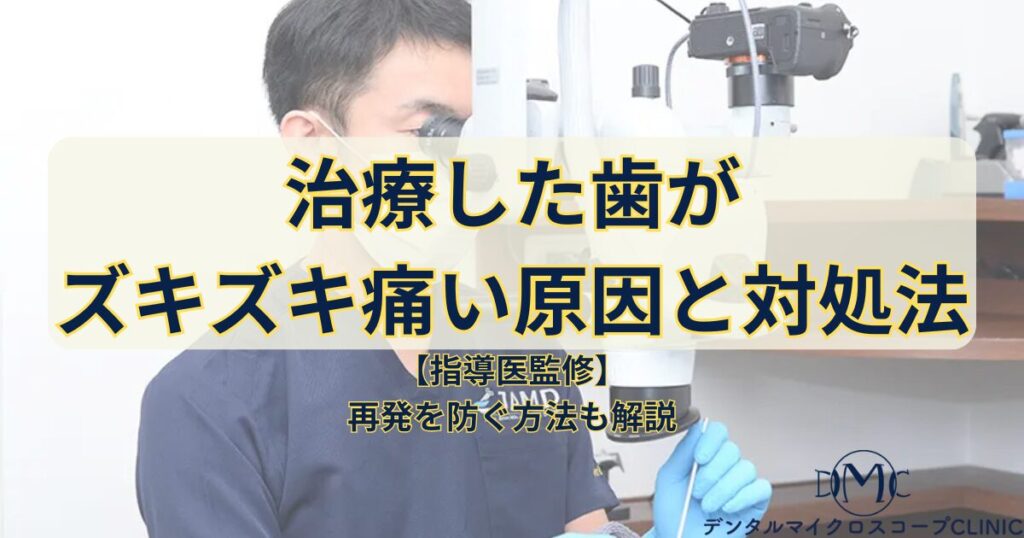
【指導医監修】治療した歯がズキズキ痛い原因と対処法|再発を防ぐマイクロスコープ
「ズキズキと脈打つような歯の痛みをなんとかしたい」「以前治療した歯が痛い……もしかして失敗した?」当記事では、治療した歯が痛くなる原因、【治療後すぐ】【しばらく...
