「口の中がネバネバする」「朝起きたとき口がベタつく」
そんな不快感を感じることはありませんか?
口腔内のねばつきは誰もが経験する症状ですが、その原因や対処法については意外と知られていません。
唾液の減少、細菌の増殖、生活習慣など、様々な要因が複雑に絡み合っています。
本記事では、口のねばつきの主な原因と効果的な対策について、わかりやすく解説します。
口の中がねばつく原因
口の中がねばつく原因について解説します。

ドライマウス(唾液の減少)
口の中がねばつく原因の一つは、唾液の分泌量の減少です。
唾液は口腔内を潤し、細菌の繁殖を抑える「自然の洗浄液」として機能しています。
この唾液が減少すると、口内の乾燥が進み、ねばつきや不快感を感じるようになります。
唾液減少の要因としては、まず加齢が挙げられます。
高齢になるにつれて唾液腺の機能が低下し、自然と唾液の分泌量が減っていきます。
70歳以上の方では「口が乾く」「舌にヒリヒリ感がある」といった訴えが多く見られ、これはドライマウスによる典型的な症状となります。
また、睡眠中は唾液の分泌が抑制されるため、朝起きたときに口のねばつきを強く感じることがあります。
これは自然な生理現象ですが、不快感の原因となります。
細菌・雑菌の増殖
口腔ケアが不十分な場合、細菌や雑菌が増殖しやすい環境が生まれます。
就寝前の歯磨きを怠ったり、義歯やブリッジの清掃が不十分だったりすると、これらが細菌の温床となります。
また、食事後に水分摂取やうがいを行わないと、口腔内に残った食べかすが細菌の栄養源となり、急速に細菌が増殖することもあります。
この細菌の増殖がねばつきの原因となります。
糖分の多い食べ物・飲み物の摂取
糖分を多く含む食べ物や飲み物の摂取は、口腔内のねばつきを引き起こす要因になります。
糖分は口腔内の細菌にとって格好の栄養源となり、これによって細菌が急速に増殖するのです。
特にチョコレートや飴などの粘着性の高いお菓子は、歯の表面や歯と歯の間に長時間残りやすい特性があります。
この残った糖分をエサとして虫歯菌(ミュータンス菌など)が増殖し、酸とねばつく物質(バイオフィルム)を生成するのです。
飲酒
アルコールには体内の水分を奪う脱水作用があり、全身の水分が減少するとともに唾液の分泌量も減少します。
唾液の分泌量の減少は、ねばつきや乾燥感を引き起こす原因となります。
特に甘いカクテルやチューハイなどは、アルコールと糖分の両方を含むため、口腔内の環境をさらに悪化させ、細菌が増殖しやすい状態を作り出します。
また、飲酒後は舌の筋力が低下し、無意識のうちに口呼吸になりやすくなります。
口呼吸は口腔内の乾燥を促進するため、結果としてさらなる乾燥感やねばつきを招くことになります。
喫煙
喫煙は唾液の分泌を抑制するだけでなく、口腔内の免疫力を低下させ、細菌の増殖を促進する要因になります。
タバコに含まれるニコチンには血管を収縮させる作用があり、唾液腺への血流が悪くなります。
血流が減少すると唾液腺に必要な栄養が十分に届かなくなり、唾液の分泌量が減少します。
また、タバコの煙やタールは口腔内の粘膜に付着し、これが細菌の温床となります。
この付着物が直接的にねばつきの原因となることも少なくありません。
薬の副作用
ある種の薬剤は副作用として唾液分泌を抑制する作用を持っており、これがねばつきやドライマウスを引き起こすことがあります。
まず、抗うつ薬や抗不安薬、特にセロトニン系や三環系の薬剤には唾液分泌を抑制する作用があります。
そして、アレルギー症状に対して処方される抗ヒスタミン薬も同様の副作用があり、花粉症シーズンには口腔乾燥を訴える患者が増加する傾向にあります。
その他にも、頻尿や胃腸症状の治療に用いられる抗コリン薬は、唾液腺の機能を直接抑制するため、長期間の服用により慢性的なドライマウス症状を引き起こすことがあります。
ストレス
ストレスは唾液の分泌に大きな影響を与え、口腔内のねばつきを引き起こす要因となります。
ストレスを感じると自律神経のバランスが乱れ、特に交感神経が優位になることで唾液腺の機能が抑制されます。
本来、唾液はリラックスしているとき(副交感神経優位の状態)に多く分泌されるものです。
そのため、緊張や不安、プレッシャーなどのストレス状態では唾液の分泌量が大幅に減少してしまいます。
例えば、面接など緊張を強いる場面では口がカラカラになってしまうという経験をした方も多いかと思いますが、強いストレスは唾液も分泌を抑制してしまいます。
睡眠不足
睡眠不足は体全体の修復機能を低下させるだけでなく、自律神経の乱れや免疫力の低下を招きます。
これらの変化が唾液分泌の減少や口腔内の細菌増殖に直結し、ねばつきを引き起こします。
睡眠が十分でないと、睡眠中の唾液分泌調整が乱れます。
特に睡眠が浅くなると自律神経の切り替えがスムーズに行われず、唾液の分泌がうまく調整されなくなります。
また、睡眠不足は成長ホルモンの分泌も低下させるため、口腔粘膜の再生が遅れ、ねばつきを感じやすくなります。
体調不良(風邪・疲労・脱水など)
体調を崩すと全身状態の変化により唾液の量や質も変化しやすく、口のねばつきや不快感が生じやすくなります。
発熱や風邪などの症状がある場合、体内から水分が失われやすくなる一方で、唾液の分泌は抑制される傾向にあります。
また、脱水状態や強い疲労時には、体が水分を節約しようとして唾液腺の活動も抑えられます。
これらの体調不良時には、普段以上に意識的な水分補給と口腔ケアが重要になります。
歯周病
歯周病は歯を支える歯ぐきや骨に炎症が生じる疾患であり、進行すると歯の喪失を招く深刻な病気です。
この歯周病は口腔内のねばつきを引き起こす原因ともなります。
歯周病では歯と歯ぐきの間にできる歯周ポケット内で嫌気性菌が増殖します。
これらの細菌は代謝物として悪臭を放つ物質や粘性の高い物質を産生します。
また、炎症が慢性化すると膿が混じり、口の中全体がねばつく不快感を生じさせます。
歯周病については下記の記事で詳しく解説しています。
閉経
女性が閉経を迎えると女性ホルモン(エストロゲン)の分泌が急激に減少します。
このホルモンバランスの変化が唾液腺や口腔粘膜に影響を与え、ドライマウスやねばつきの原因となることがあります。
エストロゲンには粘膜の潤いを保つ重要な働きがあります。
そのため、エストロゲンの減少により口腔内も乾燥しやすくなります。
また、唾液の分泌自体も減少するため、口臭やねばつきが強く感じられるようになります。
また、更年期障害の症状の一環として、ホットフラッシュや不眠などの症状と並行して口腔乾燥を訴える患者も少なくありません。
糖尿病
糖尿病は全身の健康に影響を及ぼす疾患ですが、高血糖の影響により口腔内にもさまざまなトラブルが発生します。
その一つが唾液量の減少とそれに伴うねばつきの増加です。
糖尿病では高血糖によって体が水分を失いやすくなる脱水傾向が生じます。
この全身的な水分不足により唾液の分泌量が減少し、口腔内が乾燥してねばつきを感じるようになります。
また、血液中の糖分が高いと唾液中の糖分も増加し、これが細菌の増殖を促す温床となります。
その結果、口臭や舌苔(ぜったい)も増加します。
口の中が酸っぱい症状が気になる方は下記記事をご覧ください。
口の中がねばつくときの対処法・予防法
口の中がねばつくときの対処法・予防法をご紹介します。

歯磨きをする
口腔内のねばつきを感じる原因として、プラーク(歯垢)や舌苔、食べかすの残留による細菌の繁殖があります。
これらを改善するためには、基本的な「正しい歯磨き」を行うことで細菌を物理的に減らし、清潔な口腔環境を維持することが非常に重要です。
歯磨きは1日2~3回行うことを習慣化し、特に「就寝前のケア」が重要となります。
寝ている間は唾液の分泌が減少するため、細菌が増殖しやすい環境になるからです。
また、歯だけでなく舌も軽くブラッシングすることで舌苔を除去できます。
ただし、舌は強くこすりすぎないよう注意が必要です。
マウスウォッシュを使用する
口腔内のねばつきの原因となる細菌を効果的に除去するには、薬用のマウスウォッシュの活用も有効です。
抗菌成分を含む洗口液を使用することで、歯ブラシでは届きにくい部分まで殺菌作用が広がります。
マウスウォッシュを選ぶ際は、「薬用」表示があるものを選び、CPC(塩化セチルピリジニウム)やクロルヘキシジンなどの抗菌成分が含まれているものが効果的です。
また、口腔乾燥が気になる方にはアルコールフリータイプがおすすめです。
鼻呼吸を意識する
口呼吸をしていると口の中が常に空気にさらされ、唾液が蒸発しやすくなります。
その結果、口腔内が乾燥してねばつきが生じやすくなります。
鼻呼吸を意識することで、口内の湿度を保ち、唾液の保湿作用を維持することができます。
就寝中に無意識に口が開いてしまう方は、口テープや口閉じグッズの活用も効果的な方法です。
バランスの良い食事をとる
栄養バランスの偏った食事は、口腔内の健康だけでなく、唾液腺の機能低下や粘膜の乾燥を引き起こすことがあります。
特に「ビタミンA・B群」「鉄分」「亜鉛」などの栄養素が不足すると、唾液分泌や粘膜修復に悪影響を与えることがわかっています。
具体的には、粘膜を保護するビタミンAはにんじんやかぼちゃ、レバーなどに多く含まれています。
細胞の修復を助けるビタミンB2やB6は納豆、卵、豚肉などから摂取できます。
また、免疫機能と唾液腺の機能維持に必要な鉄分や亜鉛は赤身肉、海藻類、貝類などに豊富に含まれています。
よく噛んで食事をする
咀嚼(そしゃく)には唾液の分泌を直接的に促進する作用があります。
よく噛むことで唾液腺が刺激され、ねばつきのないサラサラとした質の良い唾液が分泌されやすくなります。
実践のポイントとしては、1口あたり30回を目安に噛む習慣をつけると効果的です。
また、やわらかい食べ物ばかりではなく、歯ごたえのある野菜や根菜類、玄米などを意識的に食事に取り入れることも大切です。
これにより、自然と咀嚼回数が増え、唾液の分泌が促進されます。
禁煙・節酒
喫煙や過度の飲酒は、唾液腺の機能低下や血流悪化、粘膜の炎症を引き起こします。
その結果として口腔内のねばつきや乾燥感が悪化することがあります。
喫煙の影響としては、タバコに含まれるニコチンが血管を収縮させることで唾液腺への血流が低下します。
また、タールが口腔粘膜に残ることで細菌の温床となりやすくなります。
さらに唾液の質も悪化し、ねばねばした不快な唾液が増加する傾向があります。
飲酒の影響については、アルコールには利尿作用があるため体内の脱水を引き起こし、結果として唾液量が減少します。
特に甘いカクテルなどの飲み物は口腔内の細菌繁殖を促進する可能性があります。
ストレスをためない
ストレスは唾液の分泌を抑制する「交感神経」を優位にし、口の渇きやねばつきの直接的な原因となります。
心身のリラックスを意識することが唾液の分泌改善につながるため、日常生活の中でストレスをためないよう工夫することが重要です。
具体的な方法としては、日常的にリラックスできる時間を作ることが効果的です。
深呼吸や軽いストレッチ、趣味に没頭する時間などを意識的に取り入れましょう。
また、十分な睡眠をとり、生活リズムを整えることも自律神経のバランスを保つうえで重要です。
唾液腺をマッサージする
顔の周りには唾液を分泌する「唾液腺」が3つあり、それぞれを手で優しく刺激することで、唾液の分泌を促進することができます。
このマッサージは特に朝や食事前、口の乾燥を感じたときに有効です。
具体的な実践方法としては、まず耳下腺のマッサージがあります。
耳たぶの少し前の部分を円を描くように優しくマッサージします。
次に顎下腺は、あごの内側のくぼみに沿って指で軽く押します。
さらに舌下腺は、あごの真下を指の腹で軽く押すようにマッサージします。
これらのマッサージは各部位を1回10~15秒程度、1日2~3回行うとよいでしょう。
舌の運動を行う
舌は唾液腺への物理的刺激に深く関与しており、舌を積極的に動かすことで唾液の分泌を促進することができます。
また、舌の運動は「飲み込む力」や「話す力」を維持するためにも非常に重要であり、口腔内のねばつき防止だけでなく、誤嚥予防にもつながる効果があります。
実践できる簡単な舌の運動としては、舌を上下・左右に大きく動かす運動があります。
また、舌を使って歯ぐきの内側をぐるりとなぞるように回す運動(各方向に5回ずつ)も効果的です。
さらに「パ・タ・カ・ラ」と発音練習をすることで、舌だけでなく唇や咀嚼筋も同時に活性化させることができます。
あめやガムなどを利用し唾液の分泌を促す
唾液腺は「味」や「噛む」という刺激によって活性化します。
特に無糖のガムや飴は、唾液の分泌を自然に促す簡単な方法として医療現場でも推奨されています。
選び方としては、無糖(シュガーレス)でキシリトール配合の製品を選ぶことで、唾液促進と同時に虫歯予防にも効果的です。
また、できれば人工甘味料ではなく天然系の風味(レモン、梅、緑茶など)が含まれているものを選ぶと、唾液腺をより効果的に刺激することができます。
特に食後や口が乾燥しやすい時間帯(午後や就寝前)に利用すると効果が高まります。
定期的に歯科健診をうける
口のねばつきの背景には、歯周病や虫歯、義歯の不具合などの問題が隠れていることもあります。
また、口腔乾燥や舌の異常に対しても、歯科医院での早期対応によって症状の改善が期待できます。
歯科医院では、プロフェッショナルによるプラークや歯石の除去が行われます。
これらは自宅でのケアだけでは完全に取り除くことが難しい汚れです。
また、歯科医師は唾液量の測定や舌の動きのチェックなども行うことができます。
必要に応じて唾液分泌促進剤の処方や保湿ジェルの提案などの専門的な対応も可能です。
歯医者での定期的な検診・メンテナンスについては下記記事で詳細に解説しています。
口の中のねばつきを放置した場合のリスク
口の中のねばつきを放置した場合のリスクについてご説明します。

口臭の悪化
口の中がねばつく状態は、唾液の減少や細菌の増殖を示しています。
このような状態を放置すると、揮発性硫黄化合物(VSC)などの悪臭成分が発生しやすくなります。
これが「自分では気づきにくいが他人には強く感じられる」口臭の原因となります。
口腔内がねばついた環境では、舌苔や歯垢に含まれる細菌が活発に増殖し、口臭の原因となる物質を産生します。
細菌の代謝活動によって生じるガス状の化合物が口臭として感じられるのです。
歯周病・虫歯
唾液には本来「抗菌作用」や「自浄作用」があり、口腔内の健康を維持する重要な役割を果たしています。
しかし、これらの機能が低下すると、歯周病菌や虫歯菌が繁殖しやすい環境が整ってしまいます。
放置すると歯ぐきの腫れや出血、歯のぐらつき、虫歯の進行など深刻な口腔トラブルへと発展する可能性があります。
ねばねばとした唾液にはプラーク(歯垢)が絡まりやすく、通常の歯磨きでは取り除きにくくなります。
また、唾液中の緩衝作用(pHを中和する力)が失われることで口腔内が酸性に傾き、歯のエナメル質が溶けやすくなります。
このような状態が続くと、歯の表面から徐々に脱灰が進み、虫歯へとつながります。
味覚障害
唾液には食べ物を溶かし、味を感じる味蕾(みらい)まで成分を届ける重要な役割があります。
唾液が減少すると、味を「感じにくい」「何を食べても同じような味がする」といった味覚障害が生じることがあります。
これにより食事の楽しみが減少し、食欲低下や栄養摂取の問題にもつながりかねません。
味覚障害が起こるメカニズムとしては、舌の表面が乾燥することで味蕾が正常に機能しなくなることが挙げられます。
また、舌苔(ぜったい)が増加することで味の成分が味蕾に到達しにくくなり、味を感じる能力が低下することもあります。
誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)
唾液が減少すると、口腔内で病原菌(特に歯周病菌や嫌気性菌)が増殖し、これらの細菌が食事や唾液を飲み込む際に誤って気管に入ることで肺炎を引き起こすリスクが高まります。
これが誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)です。
ねばついた唾液は喉や舌にまとわりつき、スムーズな嚥下(えんげ)を妨げる要因となります。
また、口腔内が不潔な状態では、飲み込む動作のたびに細菌を肺に送り込む可能性があります。
このリスクは特に高齢者や嚥下機能が低下している方に顕著です。
まとめ
口腔内のねばつきは、様々な要因が複合的に関わる症状です。
主な原因としては唾液の減少(ドライマウス)があり、これは加齢や薬の副作用、ストレス、睡眠不足などによって生じます。
また、細菌の増殖も大きな要因となり、不十分な口腔ケアや糖分の多い食べ物の摂取、喫煙・飲酒によって悪化します。
その他にも歯周病や閉経、糖尿病などの全身疾患も関与することがあります。
対策としては、正しい歯磨きと舌のケア、マウスウォッシュの利用、鼻呼吸の意識づけが基本となります。
さらに、バランスの良い食事摂取、よく噛む食習慣、ストレス管理も重要です。
唾液腺のマッサージや舌の体操、無糖ガムの活用も効果的な方法といえるでしょう。
ねばつきを放置すると口臭の悪化、歯周病・虫歯の進行、味覚障害、さらには誤嚥性肺炎のリスクまで高まります。
早期の対応と定期的な歯科検診で、快適な口腔環境を維持していきましょう。
予防歯科の関連コラム
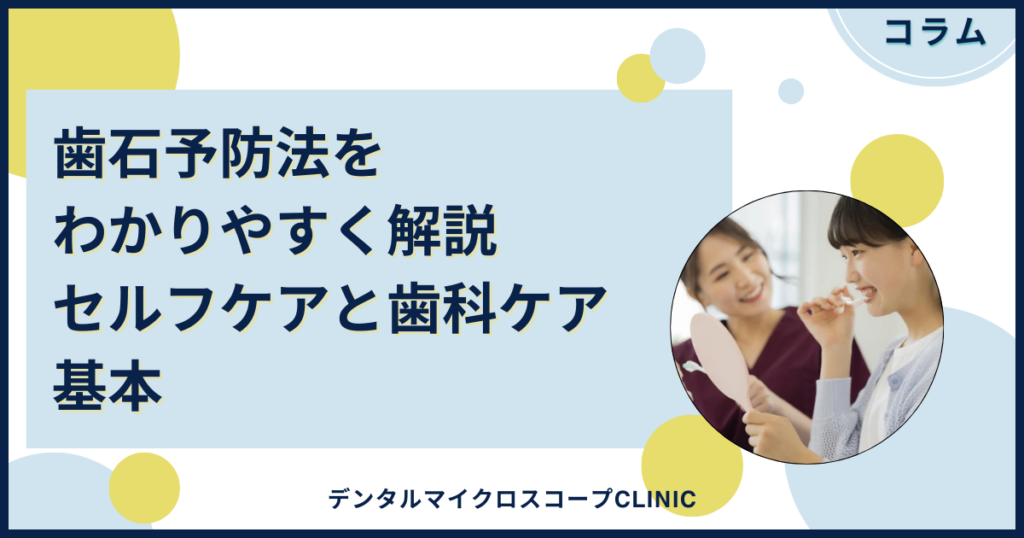
歯石予防法をわかりやすく解説|セルフケアと歯科ケアの基本
「毎日しっかり歯を磨いているつもりなのに、鏡で見ると歯の裏側に白い塊がついている……」「歯科医院で『歯石が溜まっていますね』と言われるけれど、何がそんなに悪いの...
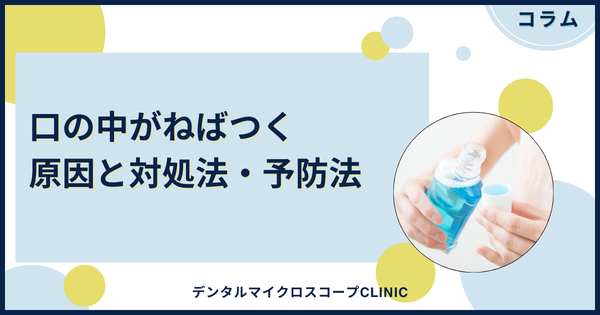
口の中がねばつく原因と対処法・予防法
「口の中がネバネバする」「朝起きたとき口がベタつく」そんな不快感を感じることはありませんか?口腔内のねばつきは誰もが経験する症状ですが、その原因や対処法について...

【医師監修】電動歯ブラシの正しい磨き方
手磨きだけではきちんと磨けているのか心配、歯周病の予防には超音波ブラシがいいと聞いた、などの理由から、最近では電動歯ブラシの人気が高まっています。高い清掃能力を...

【医師監修】 歯槽膿漏に効果あり?どんな歯磨き粉を選べばいいのか
最近、テレビ番組の医療特番などで「歯科」についての特集を目にすることが多くなってきたように感じませんか。その中で「歯周病」や「歯槽膿漏」といった言葉を耳にする機...

