「根管治療は何度も通う必要があって大変…」「この治療は、あと何回で終わるのだろう?」治療を受けている多くの方が、そんな不安や疑問を抱えています。痛みがなくなった後も通院が続くことに、もどかしさを感じることもあるかもしれません。
この記事では、そんな根管治療の回数に関する疑問に答えます。治療が長引く理由から、中断するリスクまでを理解し、大切なご自身の歯を将来にわたって守るための知識を身につけましょう。
この記事の監修歯科医師

谷川歯科医院
谷川 淳一 副院長
歯科医師。日本口腔インプラント学会専修医。小児歯科治療や小児矯正、インプラント治療を得意とし、他の歯科医師への指導も行う。
患者様一人ひとりと真摯に向き合って治療方針を決めていくことを信条としている。
目次
根管治療の回数はなぜ複数回かかるのか?

なぜ1回の治療で終わらないのか、と疑問に思うお気持ちはよく分かります。
しかし、根管治療に複数回の通院が必要なのは、決して治療を引き延ばしているわけではありません。
歯の根という、非常に複雑で目に見えない部分を確実に治療するために、どうしても必要なステップなのです。ここでは、なぜ複数回の治療が必要になるかを詳しく見ていきましょう。
感染の除去に時間がかかる理由
根管治療の最大の目的は、歯の内部に侵入・増殖した細菌を完全に取り除くことです。この細菌の除去に時間がかかることが、治療が複数回にわたる最も大きな理由です。
歯の根の中は、肉眼では見えないほど細く、複雑な構造をしています。木の根のように、一本の太い管から無数の細い枝(側枝・副根管)が分かれているのです。この複雑な空間の隅々に、細菌が潜んでいます。
そのため、感染を完全に取り除くには、段階的な処置が欠かせません。
- 1.機械的な清掃
- 2.化学的な洗浄・消毒
- 3.薬剤の貼付と経過観察
このように、物理的な清掃と化学的な消毒を組み合わせ、時間をかけて細菌を確実にゼロに近づけていくことが、歯を守るための最善策なのです。
根管の構造や本数によって変わる治療工程
治療回数は、どの歯を治療するかによっても大きく変わります。なぜなら、歯の部位によって根管の数や形が全く異なるからです。
根管治療では、すべての根管に対して、先ほど説明した清掃・消毒の工程を一つひとつ丁寧に行う必要があります。当然ながら、根管の数が多ければ多いほど、治療の手間と時間は増えていきます。
歯の部位ごとの根管数の目安は、以下の表のとおりです。
| 歯の部位 | 根管の数の目安 | 特徴 |
| 前歯 | 1本 | 根管が比較的まっすぐで、構造が単純なことが多いです。 |
| 小臼歯 | 1〜2本 | 前歯よりは複雑ですが、大臼歯ほどではありません。 |
| 大臼歯 | 3〜4本以上 | 根管の数が多く、曲がっていたり細かったりする複雑な形状が多いため、治療の難易度が高くなります。 |
例えば、根管が1本の前歯と4本ある大臼歯では、単純計算でも治療の手間は4倍になります。さらに奥歯は、根管が大きく曲がっていたり、途中で合流していたりと、構造自体が非常に複雑です。
歯科医師は、この複雑な構造をレントゲン写真やCT写真で正確に把握し、一つずつ丁寧に攻略していくため、どうしても時間と回数がかかってしまうのです。
炎症の度合いや症状による個人差
根管治療の回数は、患者さん一人ひとりの状態によっても変わります。同じ歯の治療であっても、虫歯の進行度や根の先の炎症の強さ、そしてご自身の体の治癒力に個人差があるためです。
例えば、強い痛みや歯茎の腫れといった急性の症状がある場合、まずはその炎症を鎮める処置を優先します。根の先に膿が溜まっている場合は、膿を出すための処置を行い、症状が落ち着くのを待ってから本格的な清掃に入ることが多いです。症状が強いほど、慎重に治療を進める必要があり、回数が多くなる傾向があります。
また、自覚症状はなくても、レントゲンを撮ると根の先に膿の袋(根尖病巣)ができていることがあります。この病巣をなくすには、根管内を無菌化した後、ご自身の体の治癒力によって失われた骨が再生するのを待つ必要があります。
根管治療の回数の平均はどれくらい?

「この治療は、あと何回通えば終わるのだろうか」根管治療を受けていると、多くの方がこのような不安を感じるかと思います。
治療回数は、患者さん一人ひとりの歯の状態によって大きく異なるため、一概に「何回です」と言い切ることはできません。
根管治療の回数は、根管内部の清掃から最終的な薬を詰めるまでで、平均すると2回から4回程度です。ただし、これはあくまで根管の中をきれいにするための回数です。治療が無事に終わった後、歯の機能を回復させるために土台を立て、被せ物(クラウン)を作る処置が別途2〜3回ほど必要になります。
根管治療における通院ごとの流れと回数の目安は、以下のようになります。
- 1回目
感染物質の除去 - 2回目〜3回目
根管内の清掃・消毒 - 最終回(4回目など)
根管充填(こんかんじゅうてん)
感染が軽度なケースでは、回数が少なく済むこともあります。しかし、細菌を確実に取り除き、炎症が治癒したことを慎重に確認しながら進めるため、複数回の通院が標準的な治療となっています。
根管治療の回数が増えるケースとは?

ここでは、どのような場合に治療回数が増える傾向にあるのか、具体的なケースを3つご紹介します。
- 症状が強く炎症や膿がなかなか引かない場合
- 根管の形状が複雑・細すぎる場合
- 治療途中で通院が何ヶ月も空いてしまった場合
症状が強く炎症や膿がなかなか引かない場合
歯の痛みや歯茎の腫れが非常に強い状態で根管治療を始めると、治療回数が多くなることがあります。これは、まず患者さんのつらい症状を和らげることを最優先にするためです。
特に、急性症状が強い場合や、膿の排出が多い場合などは長引くかもしれません。
症状が強いときは、焦らずに炎症や感染を確実に抑えることが、最終的に歯を守ることにつながります。
根管の形状が複雑・細すぎる場合
歯の根の中にある「根管」は、必ずしもまっすぐで単純な管ではありません。人によって、また歯の部位によって、その形は千差万別です。この根管の形が複雑な場合、治療の難易度が高くなり、回数が増える原因となります。
具体的には、次のようなケースが挙げられます。
- 根管が大きく曲がっている(湾曲根管:わんきょくこんかん)
- 根管が木の枝のように分かれている(側枝・副根管:そくし・ふくこんかん)
- 根管が細すぎる、または塞がっている(石灰化根管:せっかいかこんかん)
このような複雑な構造の隅々まで感染を取り除くためには、丁寧で慎重な作業が不可欠です。歯科用CTなどで根管の立体的な構造を把握しながら治療を進めることもあり、結果として治療回数が多くなります。
治療途中で通院が空いてしまった場合
お仕事やご家庭の都合で、予約通りに通院するのが難しいこともあるかもしれません。しかし、根管治療の途中で通院間隔が大きく空いてしまうと、かえって治療回数が増えてしまう可能性があります。
その理由は、治療中の歯に施される「仮の蓋(仮封)」にあります。根管治療では、清掃した根管に唾液や細菌が入らないよう、一時的にセメントで蓋をします。ただしこれはあくまで仮の処置であり、時間が経つとすり減ったり、劣化して隙間ができたりすることがあります。
その隙間から口の中にたくさん存在する細菌が入り込むと、きれいにしたはずの根管が再び汚染されてしまい、治療のやり直しが必要になります。再感染が起きれば、根の清掃から再スタートとなり、治療期間や通院回数も増えてしまいます。
根管治療の回数を減らすことはできるのか?

「何度も通院するのは大変だから、なるべく早く終わらせたい」治療を受けていると、このように感じるのは当然のことだと思います。
根管治療は複数回の通院が基本ですが、決して回数を減らせないわけではありません。実はいくつかの条件や工夫によって、治療回数を減らせる可能性があります。
ただし、そのためには3つの大切な要素が関わってきます。
- 歯の内部の感染の状態
- 治療を行う歯科医院の設備や治療方針
- 患者さんご自身の協力
ここでは、治療回数をできるだけ少なくするために知っておきたいポイントを解説します。
1回で終わる「抜髄処置」や短期集中治療の考え方
すべてのケースで可能なわけではありませんが、条件が合えば治療回数を大幅に減らせます。特に、虫歯が神経に達した直後に行う「抜髄処置」はその代表例です。
抜髄処置とは、細菌に感染してしまった歯の神経(歯髄)を取り除く治療のことです。このとき、細菌の感染が根の先端まで広がっておらず、炎症も軽度であれば、理想的には1回から2回の通院で治療を完了できることがあります。
【1回で治療を終えられる可能性が高い条件】
- 感染が軽度であること
- 急性症状がないこと
- 根管の形が単純であること
また、歯科医院の方針によっては「短期集中治療」に対応している場合があります。これは1回あたりの治療時間を長く確保し、複数回分の治療をまとめて行う考え方です。複数回に分けて薬を交換するよりも、再感染のリスクを抑えられるという利点があります。
ただし、保険診療の場合、根管治療には使える機器や薬剤、時間に制約があるため、どうしても何度かに分けて行う必要があります。
一方で、自費診療ではマイクロスコープなどを活用した精密な治療が可能となり、複雑な根管にも対応しやすく、治療期間の短縮が期待できる場合もあります。
「いつまで通えばいいのか不安」「なるべく早く終わらせたい」と感じている方は、自費診療に対応している歯科医院でのセカンドオピニオンを検討してみるのも一つの選択肢です。
根管治療の回数が多くてもやめてはいけない理由

「痛みも引いたし、もう通わなくてもいいのでは」と感じてしまうかもしれません。しかし、根管治療を途中で中断すると、歯の内部が再び細菌に感染し、最初からやり直しになるだけでなく、歯を失うリスクも高まります。
治療中は仮の蓋(仮封)で歯の中を保護していますが、これは一時的なもの。時間が経てば隙間ができて細菌が侵入し、根の奥で静かに炎症が広がることがあります。症状がなくても完全に治ったわけではなく、痛みを感じる神経自体がすでに除去されているため、気づかないうちに病状が進行することもあります。
治療を中断したまま放置すると、歯が割れたり、顎の骨が溶けたりして、最終的に抜歯を選ばざるを得ないケースもあります。一度失った歯は二度と戻りません。根管治療は、歯を残すための最後の機会です。忙しい中でも、どうか最後までしっかり通院を続けてください。
まとめ
今回は、根管治療の回数や、治療が長引く理由について詳しく解説しました。
治療が複数回にわたるのは、決して引き延ばしではなく、歯の根という複雑な部分を確実に清掃・消毒し、将来にわたってご自身の歯を守るために必要なステップです。治療回数は、歯の部位や炎症の度合いによって変わりますが、何よりも大切なのは自己判断で治療を中断しないことです。
痛みが消えても、根管の中が完全にきれいになったわけではありません。中断は再感染を招き、最悪の場合は大切な歯を失う「抜歯」につながる可能性もあります。
通院が大変な時期もあるかと思いますが、歯科医師と二人三脚で最後まで治療をやり遂げることが、かけがえのない歯を守る最善の方法です。疑問や不安があれば、遠慮なくかかりつけの歯科医師に相談しましょう。
根管治療の関連コラム
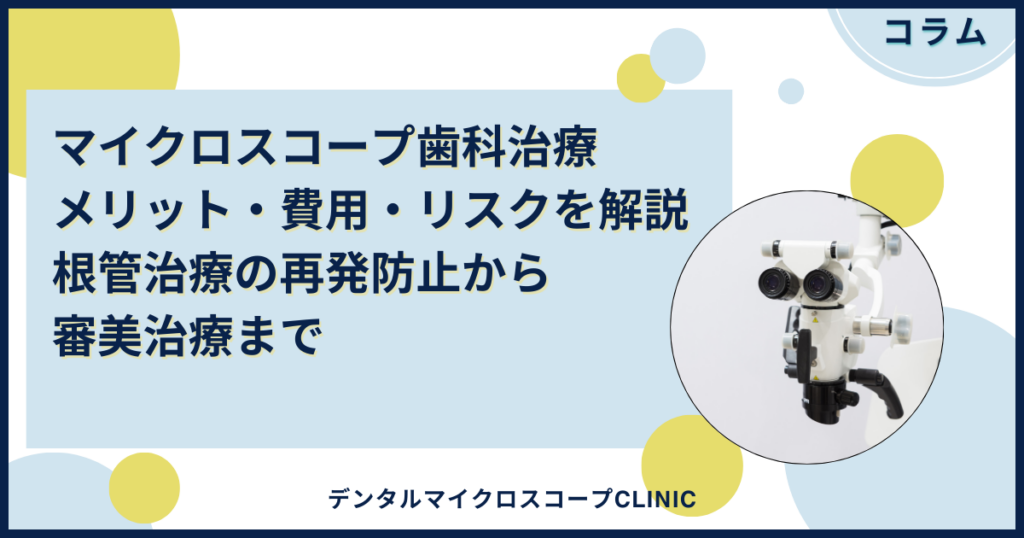
マイクロスコープ歯科治療のメリット・費用・リスクを解説|根管治療の再発防止から審美治療まで
あなたは今、「何度も治療しているのに再発してしまう」「この歯はもう諦めるしかないのか」という深い悩みや、「せっかく自費で治療するなら、一番長持ちする方法を選びた...
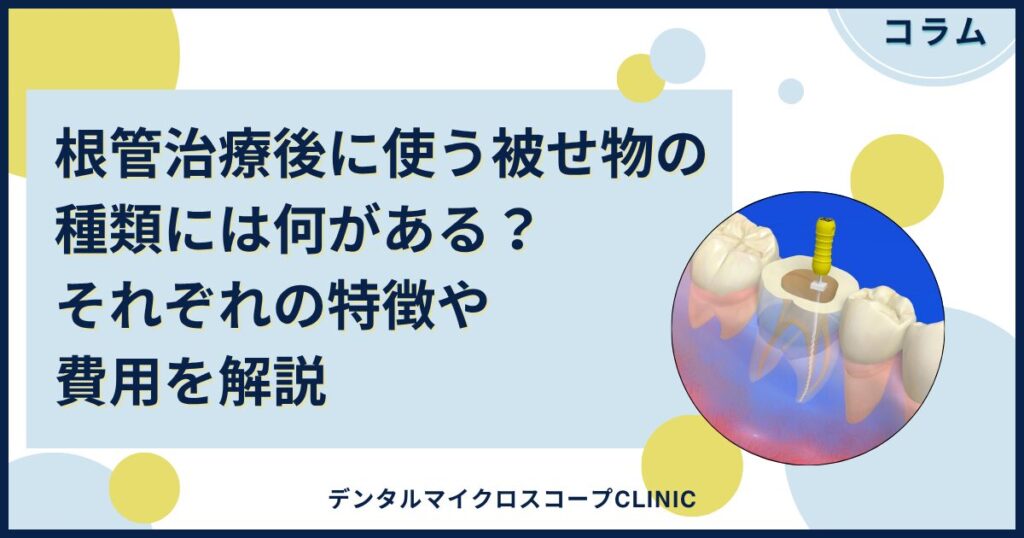
【医師監修】根管治療後に使う被せ物の種類には何がある?それぞれの特徴や費用を解説
根管治療をした後は、歯や神経を守るために被せ物をします。被せ物にはいくつか種類があり、特徴や保険適用となるのか、費用などが異なります。この記事では、保険・自費合...
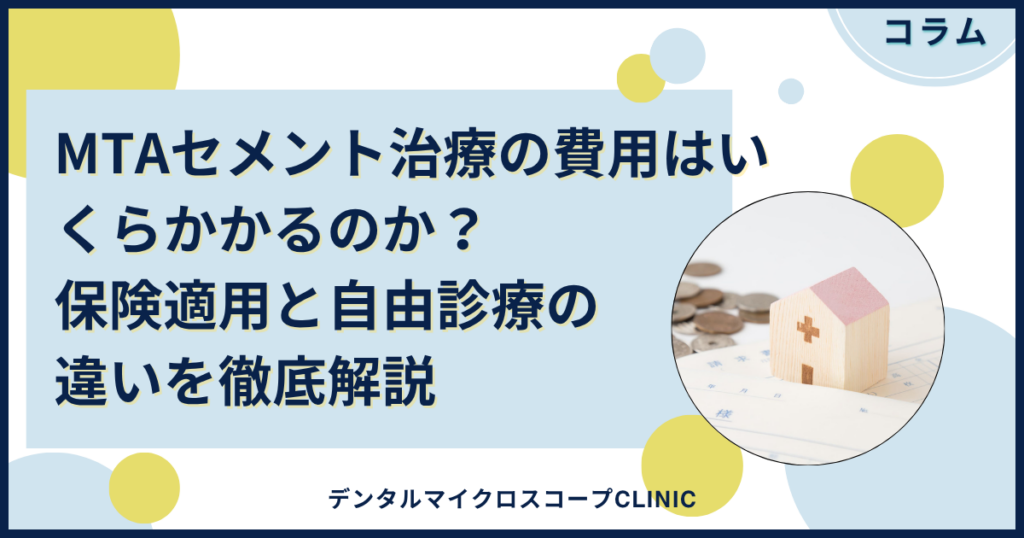
【医師監修】MTAセメント治療の費用はいくらかかるのか?保険適用と自由診療の違いを徹底解説
歯科医療の進歩により、従来なら抜歯しか選択肢がなかった歯も「MTAセメント治療」という方法で救える可能性が大きく広がっています。しかし、「MTAセメント治療はど...
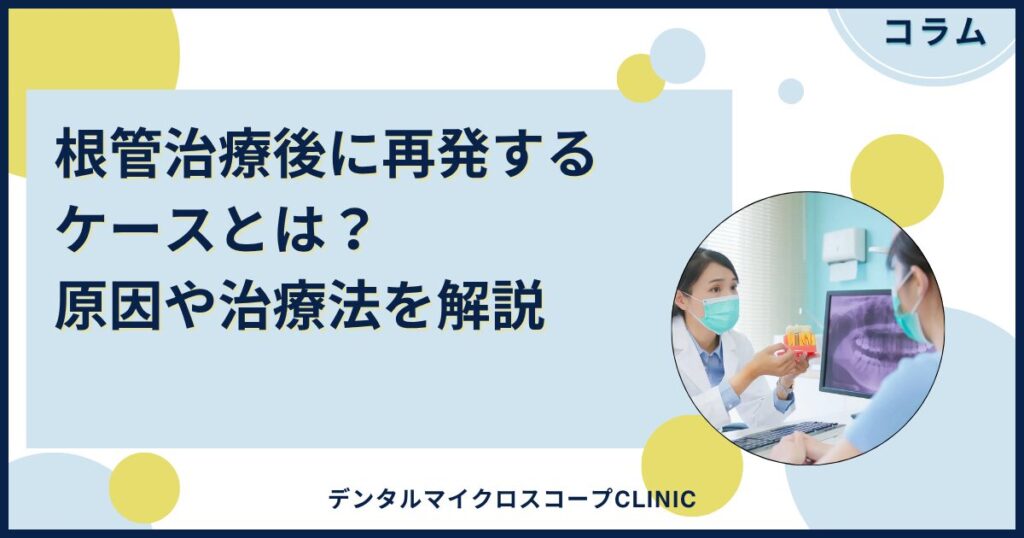
【医師監修】根管治療後に再発するケースとは?原因や治療法を解説
一度治療を終えたはずの歯が、また痛みだして、「治療がうまくいかなかったの?」と、不安な気持ちになっていませんか。歯の根の神経を取り除く根管治療は、歯を残すための...
根管治療でおすすめの歯科医院
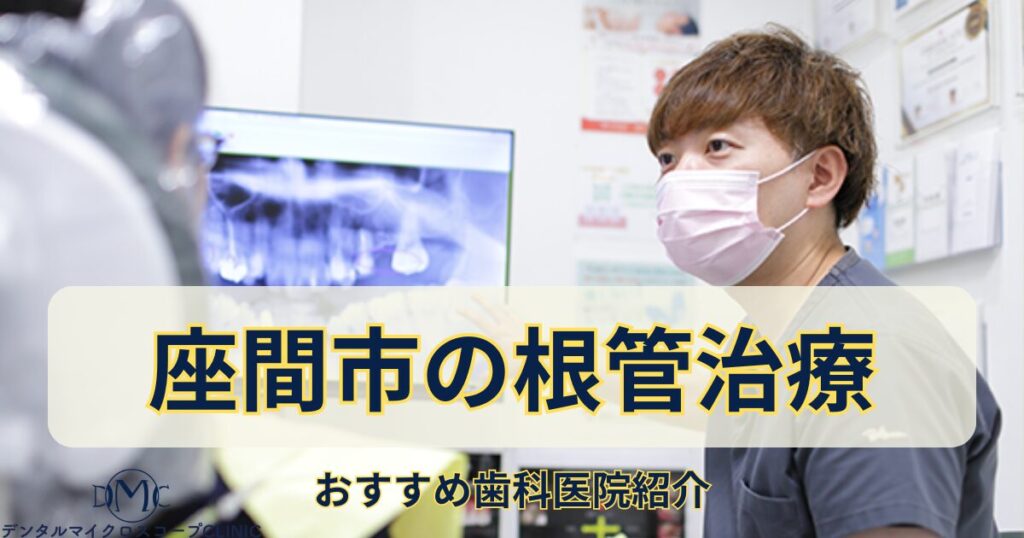
【座間市・精密根管治療】再発を防ぎ歯を残すマイクロスコープ|相武台ゆうデンタルクリニック
「治療したのに歯の痛みが引かない」「歯の神経を抜く治療が必要と言われた」神奈川県座間市で根管治療を受けるなら、無駄に歯を削らない・神経をなるべく抜かない精密治療...

【再発を防ぐ】盛岡市の根管治療|歯を残すなら日本顕微鏡歯科学会・認定指導医在籍のたかデンタルクリニックへ
「他の歯科医院で抜歯しかないと言われた」「痛みが治らない……もしかして治療に失敗した?」岩手県盛岡市で、ご自身の歯をできる限り残したい方、根管治療を繰り返してい...

横浜市港北区・綱島でおすすめするマイクロスコープ精密歯科治療は高田歯科クリニック
横浜市港北区・綱島エリアでマイクロスコープを用いた精密な歯科治療をご希望の方へ。東急東横線「綱島駅」から徒歩3分の高田歯科クリニックは、医学的根拠(エビデンス)...
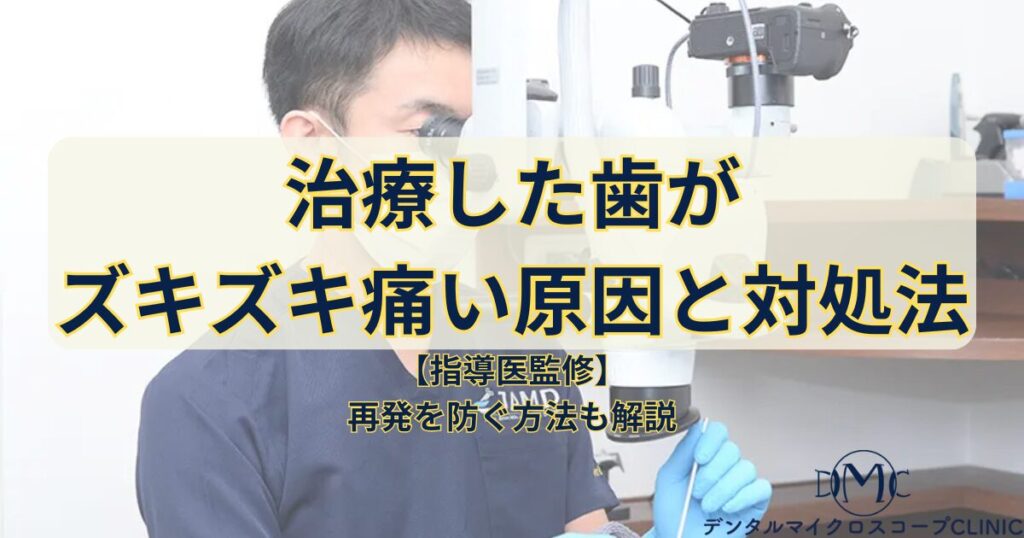
【指導医監修】治療した歯がズキズキ痛い原因と対処法|再発を防ぐマイクロスコープ
「ズキズキと脈打つような歯の痛みをなんとかしたい」「以前治療した歯が痛い……もしかして失敗した?」当記事では、治療した歯が痛くなる原因、【治療後すぐ】【しばらく...
