歯がズキズキと痛むと「また虫歯ができたのかもしれない」と心配になりますよね。しかし、歯科医院で検査をしても虫歯が見つからず、原因不明の痛みに悩まされている方も少なくありません。実は、歯の痛みを訴える方の約1割は、歯そのものではなく、筋肉や神経、鼻の炎症、時には心臓の病気など全く別の場所に原因が隠れているといわれています。
この記事では、虫歯以外で歯が痛くなる原因と、その見分け方を詳しく解説します。ご自身の症状と照らし合わせ、痛みの本当の原因を見つけるための参考にしてください。
この記事の監修歯科医師

清水歯科 歯科医師
明石 陽介
愛知学院大学歯学部卒業。口腔外科、一般歯科診療に携わり
現在は、愛知県内の歯科医院にて訪問歯科診療を中心に活動。通院が難しい方にも安心して歯科治療を受けていただけるようサポート。
義歯治療や摂食嚥下の支援にも力を入れ、患者様一人ひとりの生活に寄り添った診療を大切にしている。
目次
虫歯以外に歯が痛くなることはあるのか?

歯が痛むと、多くの方が「虫歯ができたのかもしれない」と心配になることでしょう。しかし、歯科医院でレントゲンなどの詳しい検査を受けても、虫歯が見つからないケースは決して少なくありません。
実は、歯の痛みを引き起こす原因は多岐にわたります。歯やその周りの組織に問題がある場合だけでなく、まったく別の場所の不調が、歯の痛みとして感じられることもあるのです。
歯が原因の歯痛と非歯原性歯痛の違い
歯の痛みは、原因のある場所によって「歯原性歯痛(しげんせいしつう)」と「非歯原性歯痛(ひしげんせいしつう)」の2つに大きく分類されます。
| 痛みの種類 | 主な原因の場所 | 具体的な原因の例 |
| 歯原性歯痛 | 歯・歯を支える組織 | 歯周病、歯の根の炎症(歯根膜炎)、知覚過敏、歯のひび割れ、歯ぎしり |
| 非歯原性歯痛 | 歯以外の場所 | 副鼻腔炎(上顎洞炎)、三叉神経痛、筋肉の痛み(筋・筋膜性歯痛)、心臓の病気(狭心症など) |
このように、歯の痛みといっても原因はさまざまで、歯科治療だけでは改善しないケースもあるのです。
痛みを放置するとどうなる?
「少し痛むだけだから」「そのうち治まるだろう」と痛みを我慢してしまうのは、危険な行為です。原因が何であれ、痛みを放置するとさまざまなリスクが高まります。
- 症状が悪化する
- 治療が難しくなる
- 感染が全身に広がる
- 重大な病気の見逃す
痛みは体からの重要なメッセージです。自己判断で放置せず、まずは専門家である歯科医師に相談することが大切です。
虫歯じゃないのに歯が痛くなる原因|歯が原因の歯痛

ここでは、虫歯以外で歯が直接的な原因となって起こる痛みの種類と、その特徴について、一つひとつ詳しく解説していきます。
- 歯髄炎
- 歯根膜炎
- 歯周病
- 歯肉炎
- 知覚過敏
- 親知らず
- ひび割れ
- 歯ぎしり・食いしばり
ご自身の症状と照らし合わせながら、痛みの原因を探るヒントにしてください。
歯髄炎
歯髄炎(しずいえん)は、歯の内部にある神経や血管(歯髄)が炎症を起こした状態です。
<歯髄炎でみられる痛みの特徴>
- 何もしなくてもズキズキと脈を打つように痛む(自発痛)
- 冷たいものだけでなく、温かいものが強くしみて痛む
- 夜、身体が温まると血流が良くなり、痛みが強くなることがある
- 市販の痛み止めが効きにくくなるほどの激しい痛み
歯髄の炎症には、まだ元の状態に戻れる可能性がある「可逆性歯髄炎」と、炎症が進みすぎて元には戻れない「不可逆性歯髄炎」があります。初期であれば原因を取り除くことで症状が治まることもありますが、炎症がひどくなった歯髄は自然には治りません。
この場合、痛みをなくすためには、歯の神経を取り除く「根管治療」という専門的な処置が必要になることがほとんどです。
歯根膜炎
歯根膜炎(しこんまくえん)とは、歯の根っこと顎の骨をつなぐ薄い膜(歯根膜)に炎症が起きる病気です。歯根膜は、私たちが物を噛んだときの力を吸収し、和らげるクッションのような重要な役割を担っています。
<歯根膜炎でみられる痛みの特徴>
- 食事などで噛みしめたときに、強い痛みを感じる
- 歯が少し浮き上がったような違和感がある
- 指や舌で歯を押すと、痛んだりグラグラしたりする感じがする
- 歯を軽くコンコンと叩くと、響くような痛みがある
歯根膜炎の主な原因は、歯への過剰な負担です。歯ぎしりや食いしばり、あるいは特定の歯で強く噛みすぎる癖などがあると、クッション役の歯根膜がダメージを受けて炎症を起こします。
また、過去に神経の治療をした歯の根の先に膿がたまり、その炎症が歯根膜にまで及ぶこともあります。治療は原因に応じて、噛み合わせの調整や、マウスピースの作製、根の再治療などを行います。
歯周病
歯周病は、歯垢(プラーク)に含まれる細菌によって歯ぐきが炎症を起こす疾患です。進行すると歯を支える顎の骨まで溶けることもあります。
虫歯と並んで成人が歯を失う二大原因の一つであり、「静かなる病気」とも呼ばれ、初期にはほとんど痛みがありません。痛みや腫れなどの自覚症状が出たときには、かなり進行しているケースが少なくありません。
<進行した歯周病でみられる痛みの特徴>
- 歯ぐきが赤く腫れあがり、ぶよぶよとした感触になる
- 歯が浮いたような感じや、噛んだときの鈍い痛み
- 歯ぐきから自然に出血したり、膿が出たりする
- 歯がグラグラと揺れ動き、硬いものが噛めない
- 口臭が以前よりも強くなったと感じる
歯周病が進行して骨が溶け始めると、上記のような症状と共に痛みを感じるようになります。
歯周病の治療は、原因である歯垢や、それが硬くなった歯石を、専門的な器具を用いて徹底的に除去することが基本となります。進行を食い止め、大切な歯を守るためには、早期の発見と治療介入が重要です。
歯肉炎
歯肉炎(しにくえん)は、歯周病のごく初期の段階です。炎症が歯ぐき(歯肉)だけに留まっており、歯を支える顎の骨にはまだ影響が及んでいない状態を指します。歯周病との大きな違いは、この骨の破壊があるかないかという点です。
<歯肉炎でみられる症状>
- 歯ぐきが健康的なピンク色から赤みを帯びてくる
- 歯磨きのときや硬いものを食べたときに出血しやすい
- 痛みはほとんど感じないか、あっても軽いムズムズ感程度
- 口臭がキツくなる
主な原因は、表面に付着した歯垢です。歯肉炎の段階であれば、歯科医院でのクリーニングと、日々の丁寧な歯磨きで、健康な歯ぐきの状態に戻すことが十分に可能です。痛みがないからと出血を放置せず、「歯ぐきからのSOSサイン」と捉え、早めにケアを始めることが歯周病への進行を防ぐ鍵となります。
知覚過敏
知覚過敏は、虫歯ではないにもかかわらず、一時的に鋭い痛みを感じる状態です。冷たい水や食べ物、歯ブラシの毛先が触れた瞬間などに、「キーン」としみるような痛みが走りますが、刺激がなくなるとすぐに治まるのが特徴です。
<知覚過敏が起こる仕組み>
- 1.歯周病による歯ぐきの下がりや、強すぎる歯磨き圧で歯の表面のエナメル質が削れる
- 2.刺激を伝えやすい内側の「象牙質」という組織が露出する
- 3.象牙質には神経につながる無数の小さな管があり、そこから刺激がダイレクトに伝わる
強い力での歯磨き、歯ぎしり、酸の多い飲食物(炭酸飲料、柑橘類など)の習慣が原因となりやすいです。
対処法としては、知覚過敏用の成分が含まれた歯磨き粉を使用したり、歯科医院で象牙質の表面を保護する薬剤を塗布したりする方法があります。
親知らず
一番奥に生える親知らず(智歯)は、現代人の顎が小さくなった影響で、まっすぐに生えるスペースが不足しがちです。そのため、さまざまな痛みのトラブルを引き起こす原因となります。
| 親知らずによる痛みの原因 | 症状の具体的な特徴 |
| 智歯周囲炎(ちししゅういえん) | 親知らずの周りの歯ぐきが細菌感染で腫れて痛みます。悪化すると口が開きにくくなったり、物を飲み込むときに喉まで痛んだりします。 |
| 隣の歯への圧迫 | 横向きや斜めに生えた親知らずが、手前の歯を押し続けます。これにより、歯並び全体に鈍い痛みや圧迫感を引き起こすことがあります。 |
| 虫歯・歯周病のリスク | 最も奥にあるため歯ブラシが届きにくく、親知らず自体や、その手前の大切な歯(第二大臼歯)が虫歯や歯周病になり、痛みを生じます。 |
親知らずの痛みは、洗浄や抗菌薬で一時的に治まることもありますが、疲れがたまると再発を繰り返すことも少なくありません。根本的な解決のためには、抜歯が検討されます。
ひび割れ
歯の表面に、肉眼では見えないほどの微細なひび割れ(マイクロクラック)や亀裂が入ることで、痛みを引き起こすことがあります。レントゲンにも写りにくいため、原因不明の痛みの正体であることも珍しくありません。
<歯のひび割れによる痛みの特徴>
- 普段は何ともないのに、特定の食べ物を噛んだときに「ピリッ」と電気が走るような鋭い痛みが走る
- いつもではなく、特定の角度で噛んだときだけ痛む
- 冷たいものや温かいものが、瞬間的に強くしみる
特に、神経を抜いて栄養が行き届かなくなった歯(失活歯)や、日常的に歯ぎしり・食いしばりの癖がある方は、歯がもろくなりひびが入りやすい傾向にあります。
ひびが歯の表面に留まっていれば被せ物などで保護できますが、歯の根まで達している深い場合、完治が難しいこともあります。
歯ぎしり・食いしばり
睡眠中や、日中の何かに集中しているとき、私たちは無意識に歯を強くこすり合わせたり(歯ぎしり)、食いしばったりすることがあります。このとき歯にかかる力は、食事のときとは比べ物にならないほど強力で、時にご自身の体重以上もの力がかかるといわれています。
<歯ぎしり・食いしばりが引き起こす症状>
- 1本の歯ではなく、奥歯全体がなんとなく重い、浮いたような鈍痛がある
- 朝起きたときに、顎の関節や周りの筋肉がだるい、または痛い
- 歯の先端がすり減って、平らになっている
- 原因不明の頭痛や肩こりを伴うことがある
このような過剰な力が慢性的にかかり続けると、歯そのものだけでなく、歯を支える歯根膜や顎の関節、顔周りの筋肉にまで炎症が及び、さまざまな痛みを引き起こします。
対策としては、主に就寝時にマウスピース(ナイトガード)を装着し、歯や顎にかかる力を分散させて守る治療が一般的です。
虫歯じゃないのに歯が痛くなる原因|非歯原性歯痛

歯の痛みを訴える方のうち、約1割が非歯原性歯痛だとも言われています。ここでは、歯以外に原因があるさまざまな痛みの種類について、一つひとつ詳しく見ていきましょう。
- 関連痛
- 筋・筋膜性歯痛
- 神経障害性歯痛
- 神経血管性歯痛
- 上顎洞性歯痛
- 放散痛(心臓性歯痛)
- 気圧性歯痛
- 片頭痛による歯痛
- 心理的要因による歯痛
- 突発性歯痛
関連痛
関連痛とは、痛みの原因がある場所とは全く違う離れた場所に、痛みを感じる現象です。
脳は、全身からの痛みの信号を神経を通じて受け取ります。ただし、脳が信号の発信元を誤って判断してしまうことがあります。
特に、顔や顎、耳、喉など部分の感覚を伝える神経は、歯の感覚を伝える神経と近い経路を通っています。そのため、例えば耳や顎関節に何らかの炎症が起きると、脳がその危険信号を「歯の痛み」として誤認します。
歯科医院でどんなに詳しく検査をしても歯に異常がないのに、特定の歯が痛む場合は、この関連痛を疑う必要があります。原因となっている部位の治療が進めば、歯の痛みも自然に解消されていきます。
筋・筋膜性歯痛
ストレスや就寝中の歯ぎしりは、顎や首、肩周りの筋肉(筋・筋膜)を常に緊張させます。この緊張が続くと、筋肉の中に「トリガーポイント」と呼ばれる、痛みの引き金となる硬いしこりができることがあります。このトリガーポイントが刺激されることで、離れた場所にある歯に痛みを引き起こすのが「筋・筋膜性歯痛」です。
原因は筋肉にあるため、歯を治療しても痛みは良くなりません。筋肉の緊張をほぐすマッサージやストレッチ、生活習慣の改善、薬物療法などが治療の中心となります。
神経障害性歯痛
神経障害性歯痛は、歯の感覚を脳に伝える神経そのものが傷ついたり、圧迫されたりして生じる痛みです。神経に異常が起きることで、脳に対して「痛い」と間違った信号が送られ続けてしまいます。過去の帯状疱疹のウイルスが神経に残ったり、抜歯や神経の治療、顔面の怪我などがきっかけで発症することがあります。
<痛みの特徴>
- 電気が走るような、ピリッとした瞬間的な激痛
- 焼けるようにヒリヒリ、ジンジンする持続的な痛み
- 何もしていなくても、常に痛みやしびれを感じる
- 痛む範囲がはっきりせず、ぼんやりしている
この痛みは、一般的な痛み止めが効きにくいのが特徴です。歯科治療では治すことが難しく、神経の過剰な興奮を抑える専門的な薬を用いたり、痛みを専門に扱うペインクリニックや神経内科での治療が必要になったりします。
神経血管性歯痛
頭の血管が、顔の感覚を司る「三叉神経」が刺激されることで、歯の痛みを引き起こすケースがあります。これを神経血管性歯痛と呼び、代表的なものに片頭痛や群発頭痛があります。
これらの頭痛が起こる際、頭の血管が急激に拡張し、そのすぐそばを通る三叉神経が圧迫・刺激されます。この刺激が、あたかも歯から来た痛みのように知覚されてしまうのです。ズキン、ズキンと脈打つような頭痛と連動して、上の歯が同じように痛むことが特徴です。
上顎洞性歯痛
上の奥歯の根の先は、鼻の横にある「上顎洞(じょうがくどう)」という骨の空洞と、近い位置にあります。風邪やアレルギーがきっかけで、この上顎洞の粘膜に細菌やウイルスが感染して炎症を起こすのが「副鼻腔炎(いわゆる蓄膿症)」です。上顎洞の中に膿がたまると、その圧力で近くにある上の奥歯の神経が圧迫され、歯の痛みとして知覚されます。
<上顎洞性歯痛の痛みの特徴>
- 上の奥歯が、複数本にわたって全体的に重く痛む
- 噛んだときや、階段を降りる振動で歯に響く
- 頭を下に傾けると、痛みが強くなる
- 鼻づまりや、色のついたネバネバした鼻水が出る
- 頬骨のあたりに圧迫感や痛みがある
これらの症状が歯の痛みと同時にある場合は、耳鼻咽喉科の受診が必要です。副鼻腔炎の治療によって上顎洞の炎症が収まれば、歯の痛みも改善します。
放散痛(心臓性歯痛)
放散痛(心臓性歯痛)とは、狭心症や心筋梗塞など心臓の病気の危険信号が、関連痛の一種として歯の痛みで現れる現象です。心臓の痛みを伝える神経と、顎や歯の痛みを伝える神経の通り道が近いため、脳が心臓の不調サインを、歯の痛みだと錯覚してしまうのです。
この歯の痛みは命に関わる可能性があり、最も注意しなければなりません。
<見逃してはいけない危険なサイン>
- 歩く、階段をのぼるなど、体を動かしたときに歯や顎が痛む
- 胸が締め付けられるような圧迫感や、息苦しさを伴う
- 左の肩や腕、背中にまで痛みが広がるように感じる
- 数分間安静にしていると、痛みが和らぐ
このような症状がある場合は、ためらわずにすぐに救急受診するか、循環器内科を受診してください。
気圧性歯痛
飛行機に乗っている時や、登山、ダイビング中など、周囲の気圧が急激に変化する環境で歯が痛くなることがあり、これが気圧性歯痛です。
歯の中には「歯髄腔(しずいくう)」という、神経や血管が入っている小さな空洞があります。健康な歯では問題ありませんが、治療途中の歯や、過去に治療した歯の根の中にわずかな隙間やガスが残っていると、外の気圧が急に低下した際に、歯の中の空気が膨張して神経を圧迫し、痛みを感じさせます。
自覚症状のない小さな虫歯がある場合にも起こりやすいといわれています。定期的に歯科健診を受け、虫歯や歯の詰め物の状態をチェックするのがおすすめです。
心理的要因による歯痛
強いストレスや不安、うつ状態など、心の状態が体に影響を及ぼし、歯の痛みとして現れることがあります。「精神的歯痛」や「非定型歯痛」とも呼ばれます。
脳は、精神的なストレスが長く続くと、痛みを感じる回路が過敏になってしまうことがあります。その結果、歯には何も問題がないにもかかわらず、脳が誤作動を起こし、「痛い」と信号を作り出してしまうのです。
<痛みの特徴>
- 鈍い痛みが、一日中なんとなく続いている
- 痛む場所が日によって変わったり、あちこちに移動したりする
- 仕事や趣味など、何かに集中していると痛みを忘れている
- いくつもの歯科医院で治療を繰り返しても、一向に良くならない
この場合、痛みを和らげる薬が効きにくいことも少なくありません。心療内科や精神科と連携し、ストレスの原因と向き合ったり、カウンセリングを受けたりすることが重要です。
突発性歯痛
あらゆる検査をしても、痛みを引き起こす原因が特定できない歯の痛みを「突発性歯痛(とっぱつせいしつう)」または「特発性歯痛(とくはつせいしつう)」と呼びます。
痛みの現れ方も、じんじんとした持続的な痛みから、突然の激しい痛みまで人それぞれです。原因がはっきりしないため、治療方針を立てるのが難しく、痛みを和らげるための薬物療法などが行われます。
虫歯以外の歯の痛みの治療が難しい理由
虫歯以外の歯の痛みの治療が難しいのは、いくつかの理由があります。
歯科の検査では、歯以外の原因が特定できません。筋肉や神経、鼻の奥など、レントゲンに映らない部分が原因となることがあるからです。診断は消去法で進められ、歯に関連する問題を全て確認した後でようやく歯以外の原因を考えます。
また歯以外に原因がある場合、歯科だけでは治療が完結せず、他の専門医との連携が必要です。例えば、耳鼻咽喉科や神経内科などの診療科と協力して、総合的な治療が行われることになります。
歯が痛いなら、まずは歯科医を受診するのが重要
歯の痛みの原因は多岐にわたるため、痛みを感じたらまず歯科医を受診することが重要です。
歯科医師は、痛みが歯や歯ぐきから来ているのか、他の原因があるのかを見極め、適切な治療を検討します。特に、激しい痛み、長引く痛み、顔や顎の腫れ、熱が出る場合は早急に受診してください。
また心臓の不調が疑われる症状がある場合は、早めに救急外来や循環器内科の受診も検討しましょう。早期の診断と治療が、歯と体の健康を守るうえでは欠かせません。
まとめ
歯の痛みの原因は歯や歯ぐきだけでなく、筋肉や神経、鼻の炎症、さらには心臓の病気など、思いもよらない場所に隠れている可能性も少なくありません。
痛みは、あなたの体からの大切なSOSサインです。「そのうち治まるだろう」と自己判断で我慢せず、まずは専門家である歯科医師に相談することが重要です。全身の症状に応じて、救急外来や循環器内科などを受診するのも検討しましょう。
根管治療の関連コラム
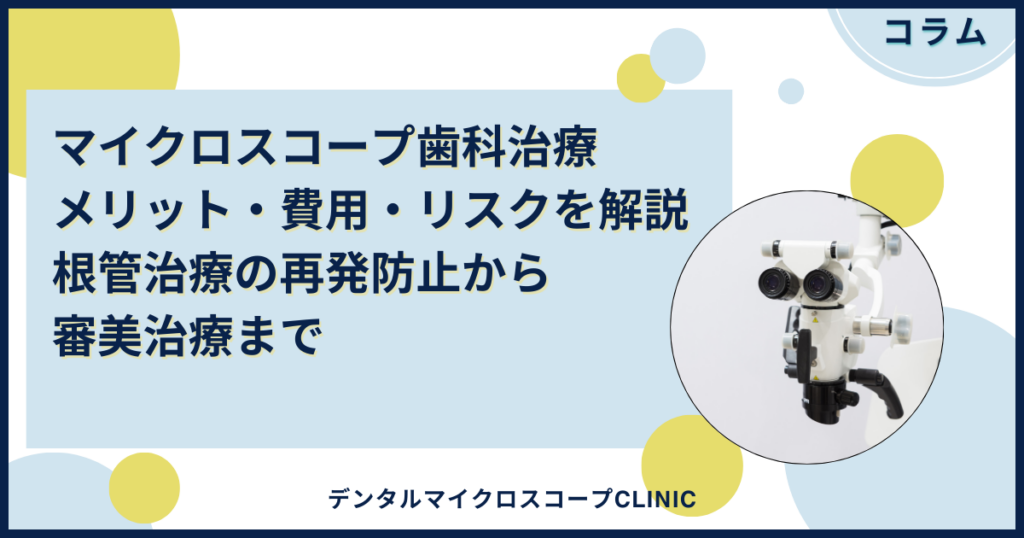
マイクロスコープ歯科治療のメリット・費用・リスクを解説|根管治療の再発防止から審美治療まで
あなたは今、「何度も治療しているのに再発してしまう」「この歯はもう諦めるしかないのか」という深い悩みや、「せっかく自費で治療するなら、一番長持ちする方法を選びた...
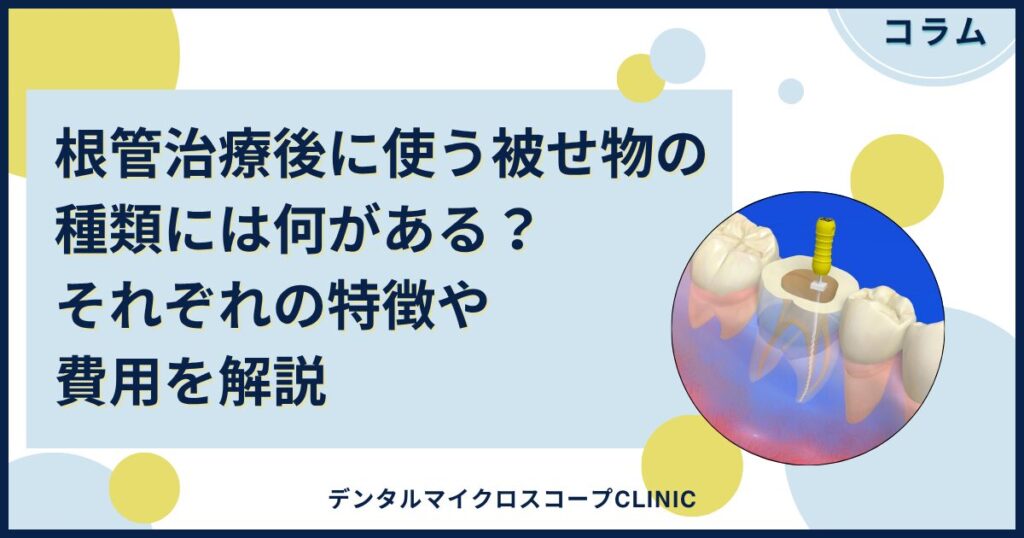
【医師監修】根管治療後に使う被せ物の種類には何がある?それぞれの特徴や費用を解説
根管治療をした後は、歯や神経を守るために被せ物をします。被せ物にはいくつか種類があり、特徴や保険適用となるのか、費用などが異なります。この記事では、保険・自費合...
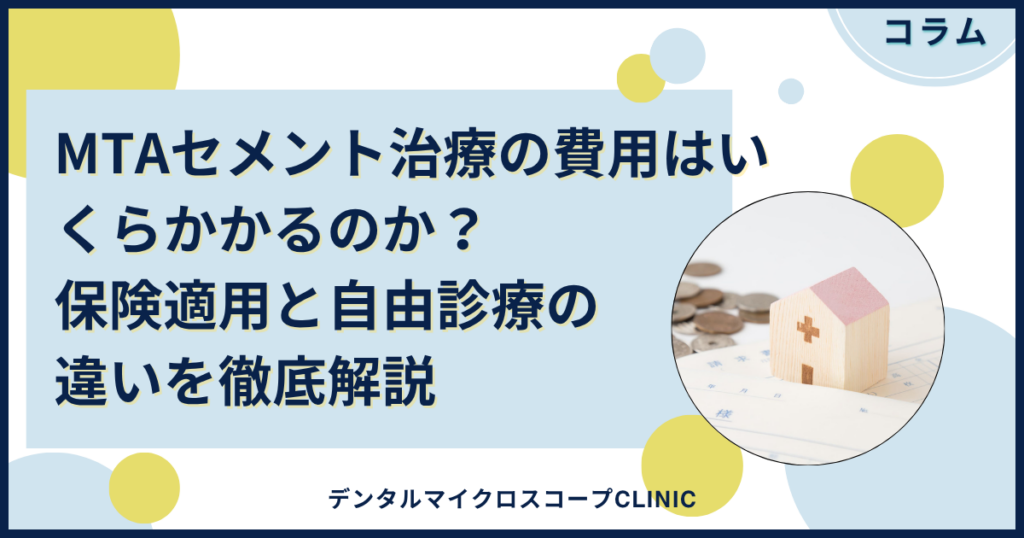
【医師監修】MTAセメント治療の費用はいくらかかるのか?保険適用と自由診療の違いを徹底解説
歯科医療の進歩により、従来なら抜歯しか選択肢がなかった歯も「MTAセメント治療」という方法で救える可能性が大きく広がっています。しかし、「MTAセメント治療はど...
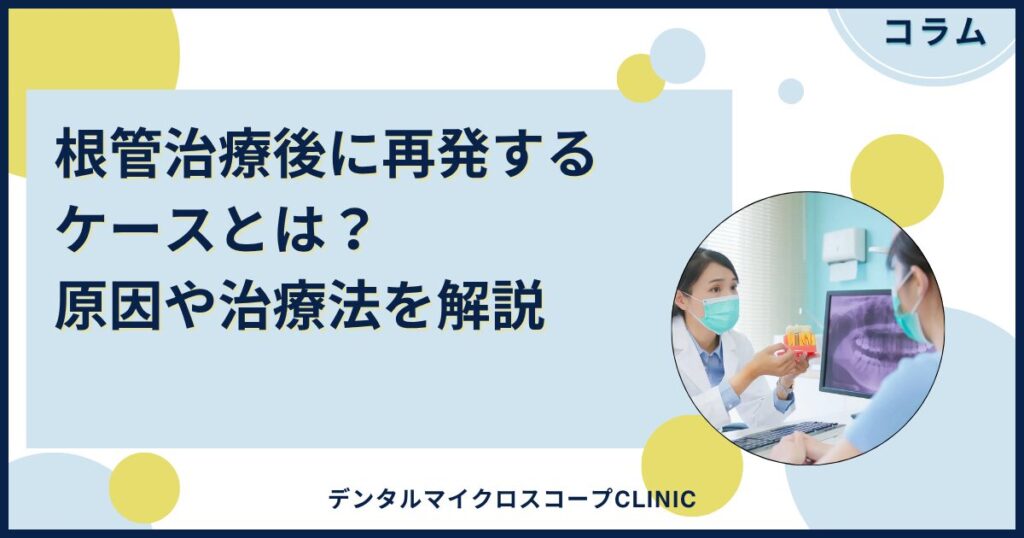
【医師監修】根管治療後に再発するケースとは?原因や治療法を解説
一度治療を終えたはずの歯が、また痛みだして、「治療がうまくいかなかったの?」と、不安な気持ちになっていませんか。歯の根の神経を取り除く根管治療は、歯を残すための...
根管治療でおすすめの歯科医院
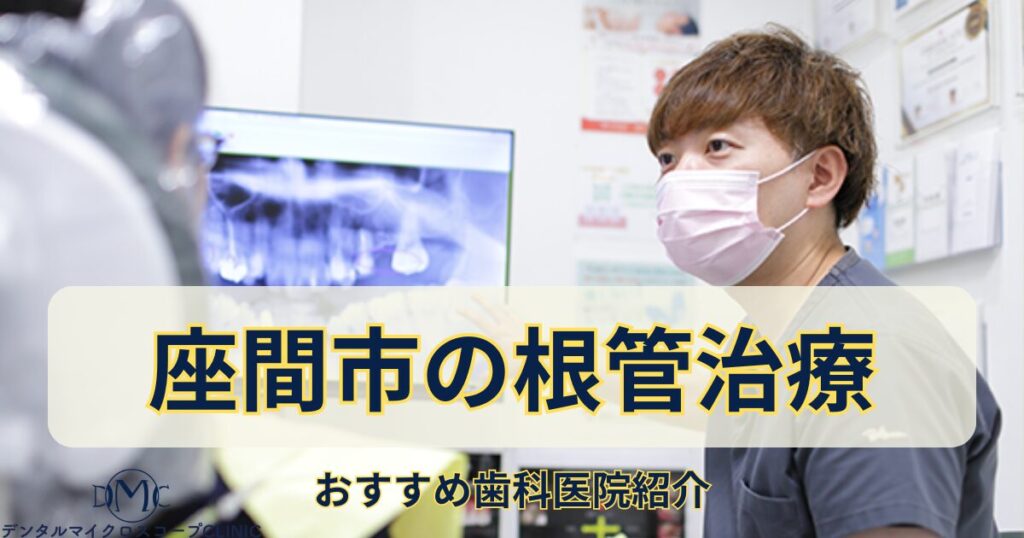
【座間市・精密根管治療】再発を防ぎ歯を残すマイクロスコープ|相武台ゆうデンタルクリニック
「治療したのに歯の痛みが引かない」「歯の神経を抜く治療が必要と言われた」神奈川県座間市で根管治療を受けるなら、無駄に歯を削らない・神経をなるべく抜かない精密治療...

【再発を防ぐ】盛岡市の根管治療|歯を残すなら日本顕微鏡歯科学会・認定指導医在籍のたかデンタルクリニックへ
「他の歯科医院で抜歯しかないと言われた」「痛みが治らない……もしかして治療に失敗した?」岩手県盛岡市で、ご自身の歯をできる限り残したい方、根管治療を繰り返してい...

横浜市港北区・綱島でおすすめするマイクロスコープ精密歯科治療は高田歯科クリニック
横浜市港北区・綱島エリアでマイクロスコープを用いた精密な歯科治療をご希望の方へ。東急東横線「綱島駅」から徒歩3分の高田歯科クリニックは、医学的根拠(エビデンス)...
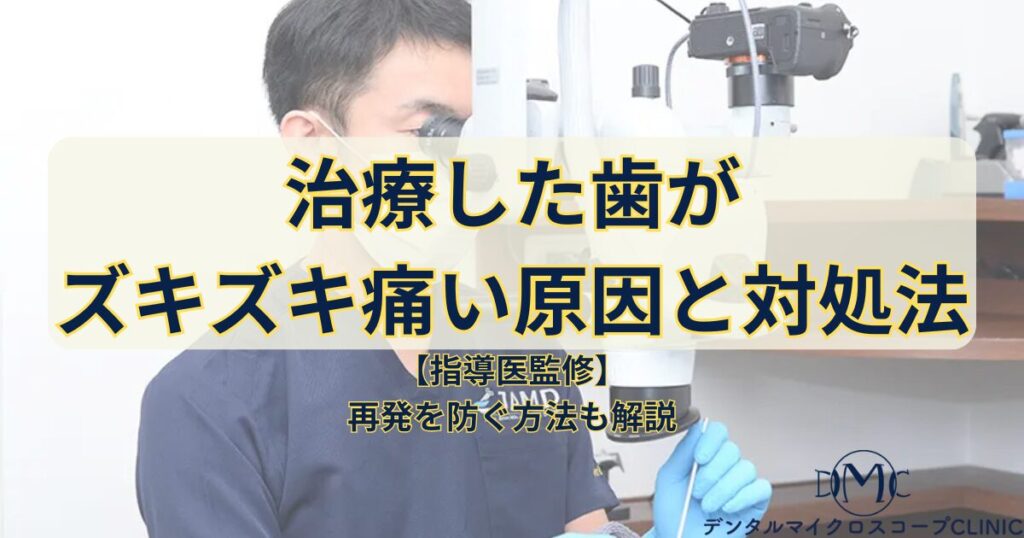
【指導医監修】治療した歯がズキズキ痛い原因と対処法|再発を防ぐマイクロスコープ
「ズキズキと脈打つような歯の痛みをなんとかしたい」「以前治療した歯が痛い……もしかして失敗した?」当記事では、治療した歯が痛くなる原因、【治療後すぐ】【しばらく...
