歯茎の痩せは、多くの方が経験するにもかかわらず、その重大さに気づかれにくい口腔トラブルです。
年齢を重ねるにつれて自然に進行することもありますが、様々な原因によって加速します。
痩せた歯茎は元に戻りにくいため、早期の対策が大切です。
当記事では、歯茎痩せが引き起こす主な原因、予防法や改善策、そしてリスクについて解説します。
歯茎痩せのリスク

歯茎痩せのリスクについてご説明します。
虫歯になりやすくなる
歯茎が痩せると、本来は歯茎に覆われていた歯の根元部分が露出してしまいます。
この露出した部分は、歯の表面を守るエナメル質ではなく、セメント質という比較的柔らかい組織で構成されています。
セメント質はエナメル質と比較すると酸への抵抗力が弱く、虫歯のリスクが高まります。
知覚過敏を起こしやすくなる
歯茎が痩せて下がると、象牙質と呼ばれる組織が露出します。
象牙質には「象牙細管」という微細な管が無数に存在しており、これらは歯の内部の神経に通じています。
そのため、冷たい水や空気が直接この部分に触れると、鋭いピリッとした痛みを感じることがあります。
これは日常生活において様々な場面で現れます。
例えば、アイスクリームを食べた際に以前より強く「キーン」という痛みを感じるようになったり、冬の寒い日に外気を吸い込んだだけで奥歯に鋭い痛みが走ったりすることがあります。
歯がゆれる・抜けやすくなる
歯茎の痩せは多くの場合、歯を支える骨である歯槽骨の減少と並行して進行します。
歯槽骨が減少すると、歯を支える土台が弱くなり、歯の安定性が損なわれます。
その結果、歯がグラつくようになったり、食事中に不快感や痛みを感じたりすることがあります。
具体的には、堅い食品(せんべいやナッツ類など)を噛んだ際に歯が揺れるような違和感を覚えたり、普段の歯磨き時にわずかな刺激でも歯が動くように感じたりすることがあります。
入れ歯が合いづらくなる
入れ歯、特に総入れ歯は、歯茎およびその下にある顎の骨によって支えられています。
歯茎が痩せていくと、入れ歯を支える土台が減少するため、様々な不具合が生じるようになります。
例えば、長年問題なく使用していた入れ歯が突然外れやすくなったり、会話中にカチカチと音を立てるようになったりすることがあります。
見た目が悪くなる
歯茎の痩せは審美的な面でも影響を及ぼします。
歯茎が後退して歯の根元部分が露出すると、歯が実際より長く見えるようになり、「老け顔」の印象を与えやすくなります。
また、口元周辺の組織が痩せることで、唇が内側に入り込み、結果としてほうれい線が目立つようになることもあります。
このような見た目の変化はコンプレックスとなり、人前で笑うことをためらったり、会話に消極的になったりする場合もあるでしょう。
歯茎が痩せる原因

歯茎が痩せる原因をお伝えします。
歯周病
歯周病は単なる歯茎の炎症ではなく、歯を支える骨を破壊する進行性の疾患です。
この病気は、歯と歯茎の間に細菌(プラーク)が侵入し、慢性的な炎症を引き起こすことから始まります。
炎症が進行すると、歯を支える「歯槽骨」が徐々に吸収され、それに伴って歯茎も痩せていきます。
加齢
年齢を重ねるにつれて、全身の骨と同様に歯槽骨の密度も自然に低下します。
骨粗しょう症と類似したメカニズムで、顎の骨も加齢とともに密度が減少し、もろくなります。
骨がもろくなることで歯を支える力が弱まり、結果として歯茎も徐々に下がっていきます。
特に60代以上の女性は、女性ホルモン(エストロゲン)の減少により骨吸収が進行しやすくなるため、歯茎の退縮がより顕著になる傾向があります。
健康診断で「骨密度が低い」と指摘された方は、口腔内においても同様の変化が起きている可能性が高いでしょう。
過度なブラッシング
「強く磨けば磨くほど歯はきれいになる」という考えは誤りです。
実際には、硬い歯ブラシを使用したり、強い力で磨いたりすることは、歯茎に物理的なダメージを与えます。
特に歯と歯茎の境目(歯肉縁)を強くこすることで、歯茎が徐々にすり減り、後退していくことがあります。
また、利き手側の歯(右利きの方なら左下や左上の奥歯など)に偏って歯茎が痩せている場合、ブラッシング圧の偏りが原因であることが多いと言えるでしょう。
噛み合わせ・歯ぎしりなどの圧力による影響
噛み合わせの不調和や無意識に行われる歯ぎしり・食いしばりは、特定の歯や歯茎に過剰な力を集中させます。
この持続的な圧力が加わることにより、歯を支える歯槽骨が徐々に吸収され、それに伴って歯茎も後退していきます。
例えば、就寝中に無意識に歯ぎしりをしていると、朝起床時に顎に疲労感を覚えたり、特に力が集中する奥歯の歯茎だけが後退している、といった状況もあり得ます。
また、被せ物や詰め物の高さが適切でない場合、片側の奥歯に過剰な力が加わり、その部位の歯茎が特に痩せてくることもあります。
生活習慣などによる影響(喫煙・栄養・ストレス)
歯茎の健康は、全身の健康状態や生活習慣と密接に関連しています。
喫煙、栄養バランスの偏った食生活、慢性的なストレスなどは、歯茎の血行を阻害し、歯周組織の再生や修復能力を低下させます。
特に喫煙は歯茎の血管を収縮させるため、歯周病の初期症状である出血や腫れといった炎症反応が現れにくくなります。
そのため、患者自身が気づかないうちに歯周病が進行し、歯茎が静かに痩せていくことがあります。
また、過度なダイエットや偏った食事制限により、ビタミンやタンパク質が不足すると、歯茎の弾力性が失われ、退縮が進行することがあります。
さらに、ストレスは歯ぎしりや食いしばりを無意識のうちに強めることで、間接的に歯茎に圧力をかける原因にもなります。
歯茎痩せの予防・改善・治療法
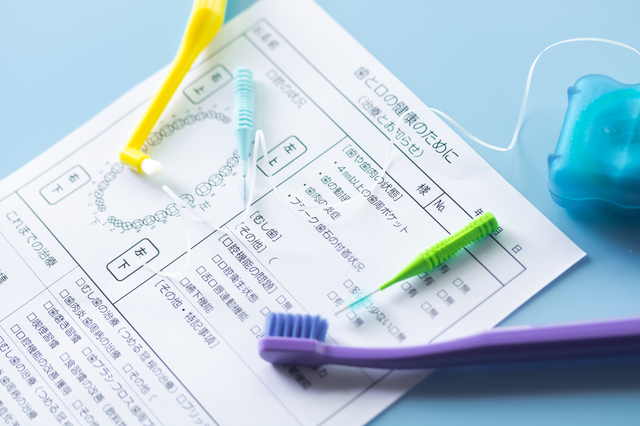
歯茎痩せの予防・改善・治療法をご紹介します。
セルフケア:歯間の汚れやプラークを除去する
歯と歯の間の領域は、通常の歯ブラシだけでは十分に清掃することが難しい部位です。
歯間部にプラーク(細菌の塊)が蓄積されたままになると、歯周病の原因となり、最終的には歯茎の退縮へとつながる恐れがあります。
歯間部の清掃には、歯間ブラシ、デンタルフロスのような専用の道具が効果的です。
歯間ブラシは、歯の間にある程度の隙間がある方に適しています。
ただし、サイズが合わないと逆に歯茎を傷つけてしまう可能性があるため、歯科医院での適切なサイズの選定が推奨されます。
一方、デンタルフロスは歯の隙間が比較的狭い方に向いています。
用方法としては、フロスを横にスライドさせるように歯間に挿入し、歯の面に沿って上下に動かすのが基本です。
セルフケア:適切な歯みがき・ブラッシングをする
ブラッシングにおいては、力加減、歯ブラシを当てる角度、そして動かし方が非常に重要です。
多くの方が行いがちな、ゴシゴシと横方向に強く磨く方法は、実は逆効果です。
このような磨き方は歯茎をすり減らすだけでなく、露出した歯根表面を傷つける危険性もあります。
理想的なブラッシング方法は、歯と歯茎の境目に歯ブラシの毛先を約45度の角度で軽く当て、小刻みに動かす「バス法」と呼ばれる技法です。
ブラッシングの際の推奨される力は、約150g~200g程度(一般的に言えば、卵を割らない程度の力)が目安となります。
セルフケア:歯茎にやさしい歯磨き粉を使う
市販の歯磨き粉の中には、強い研磨剤や発泡剤が含まれているものがあり、長期的に使用すると歯茎を刺激し、退縮を促進してしまう可能性があります。
特に歯茎が既に弱っている方や、歯の根元が露出している方は、「低研磨・低刺激」タイプの歯磨き粉を選ぶことが望ましいです。
歯茎を守るための歯磨き粉には、いくつかの有効成分が入っています。
フッ素は虫歯を防ぐのに効果的で、特に露出した歯の根元の部分を強くする働きをします。
β-グリチルレチン酸やトラネキサム酸という成分は、歯茎の腫れや出血を抑える効果があります。
また、アラントインは傷ついた組織の修復を助け、歯茎の回復を手助けする成分です。
歯科医院:マウスピース(ナイトガード)
睡眠中や仕事に集中している時など、無意識のうちに行われる歯ぎしりや食いしばりは、歯や歯茎、そして歯を支える骨(歯槽骨)に慢性的なダメージを与えます。
この問題に対処するため、歯科医院では患者さんの歯型に合わせた「マウスピース(ナイトガード)」を作製します。
マウスピースの主な効果は、歯にかかる過剰な力を分散し、特定の歯や歯茎への負担を軽減することです。
また、顎関節への負担も軽減されるため、朝の顎の疲労感や頭痛の緩和にもつながることがあります。
歯科医院:歯肉弁移動術(しにくべんいどうじゅつ)
すでに歯茎が大きく退縮し、歯の根元が露出してしまった場合、見た目の問題だけでなく、知覚過敏や根面う蝕(根元の虫歯)のリスクが高まります。
このような進行したケースでは、外科的処置である「歯肉弁移動術」が選択肢となります。
この治療法では、歯茎の一部を切開し、健康な歯茎組織を退縮した歯根部分に被せるように移動させて縫合します。
症例によっては、口蓋(上あごの内側)から組織を採取して移植する「結合組織移植術(CTG)」を併用することもあります。
歯科医院:遊離歯肉移植術(ゆうりしにくいしょくじゅつ)
すでに歯茎が大きく下がり、歯の根元が露出してしまった部位に対しては、「遊離歯肉移植術」という歯周外科処置が選択肢となります。
この手術では、患者さん自身の口蓋(上あごの内側)などから「角化歯肉」と呼ばれる丈夫な歯茎組織を採取し、退縮している部位に移植して補強します。
この治療の主な目的は、露出した歯の根面を保護して知覚過敏や根面う蝕(根元の虫歯)のリスクを軽減すること、歯茎ラインを整えて審美性を回復すること、そして噛み合わせや清掃時の物理的刺激に強い「角化歯肉」を確保することで再発を防止することにあります。
まとめ
歯茎の痩せは口腔内の健康に幅広い影響を及ぼす重要な問題です。
痩せた歯茎からは虫歯になりやすいセメント質が露出し、神経に通じる象牙細管も露出するため冷たいものがしみる知覚過敏を引き起こします。
さらに進行すると、歯の支えが弱まり歯がグラつくようになり、入れ歯の適合性低下や見た目の老化など、多岐にわたる問題につながります。
歯茎が痩せる主な原因は、歯周病による骨吸収、加齢による骨密度低下、過度なブラッシング、噛み合わせの不調和や歯ぎしり、そして喫煙などの生活習慣が挙げられます。
予防・改善策としては、歯間ブラシやフロスによる適切な清掃、正しいブラッシング方法の習得、低刺激の歯磨き粉の使用が重要です。
さらに、歯科医院での専門的なブラッシング指導や、歯ぎしり防止のためのマウスピース装着、すでに退縮した歯茎に対しては歯肉弁移動術や遊離歯肉移植術などの外科的治療も選択肢となります。
歯茎の痩せは一度進行すると自然回復が難しいため、早期発見と適切なケアが何よりも重要です。
定期的な歯科検診と正しいセルフケアで、健康な口腔環境を維持しましょう。
歯周病の関連コラム
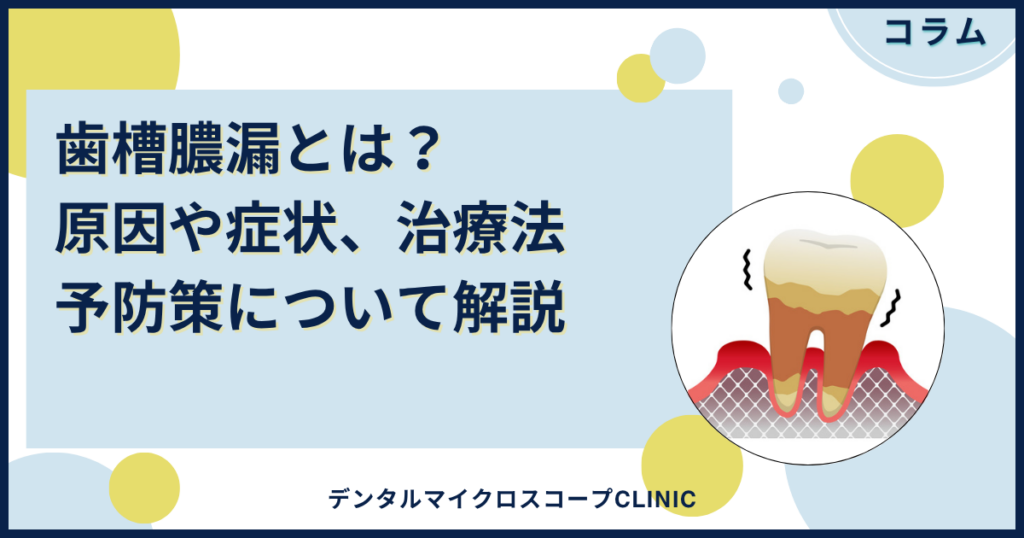
歯槽膿漏とは?原因や症状、治療法、予防策について解説
「もしかして、これって歯槽膿漏?」歯ぐきから出血や口臭、歯のグラつき...。そんな症状に心当たりはありませんか?この病気は、自覚症状が少ないまま静かに進行し、大...
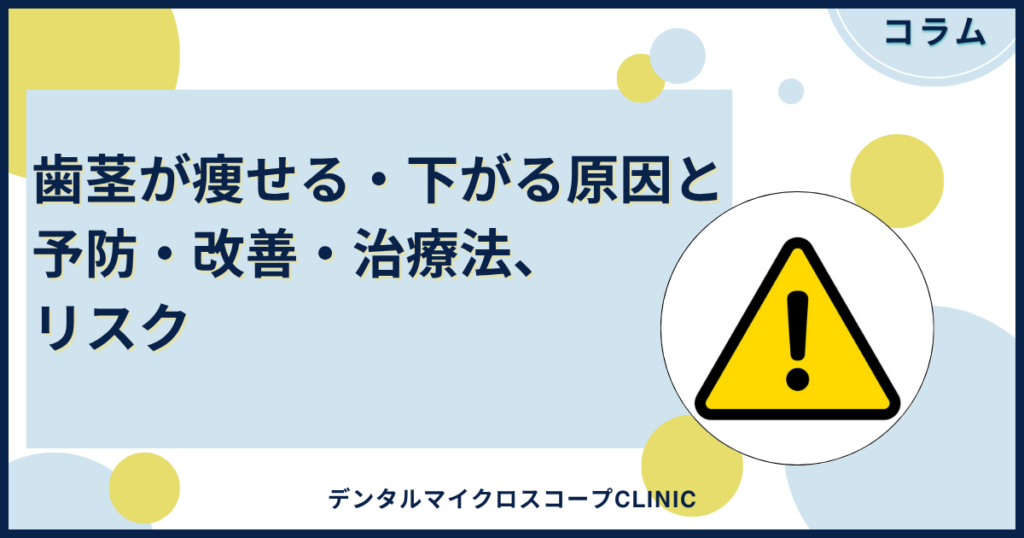
歯茎が痩せる・下がる原因と予防・改善・治療法、リスク
歯茎の痩せは、多くの方が経験するにもかかわらず、その重大さに気づかれにくい口腔トラブルです。年齢を重ねるにつれて自然に進行することもありますが、様々な原因によっ...
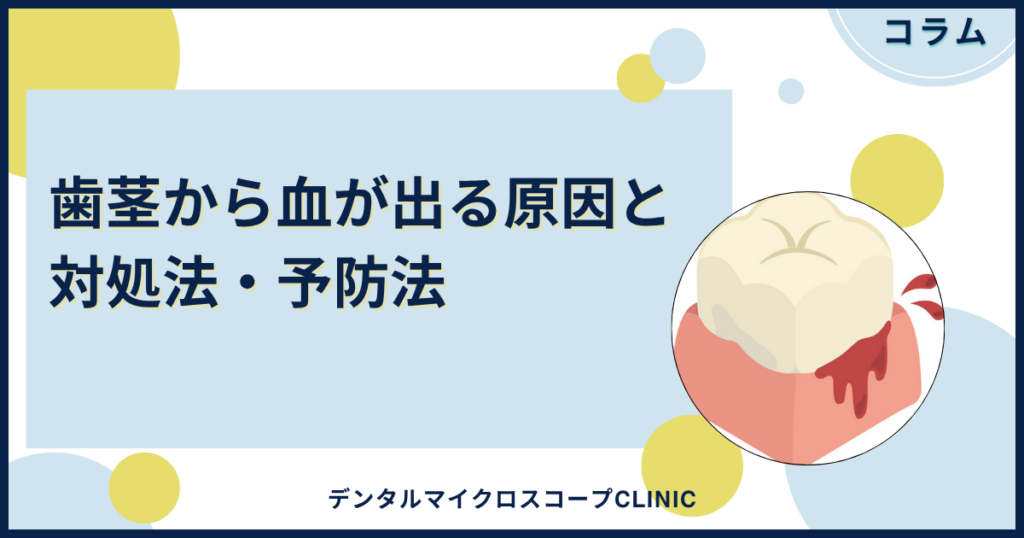
歯茎から血が出る原因と対処法・予防法
歯茎から血が出ることは、多くの方が経験される身近な症状ですが、その背景には様々な原因が隠れています。軽度な歯肉炎から重篤な全身疾患まで、出血の原因は実に多岐にわ...
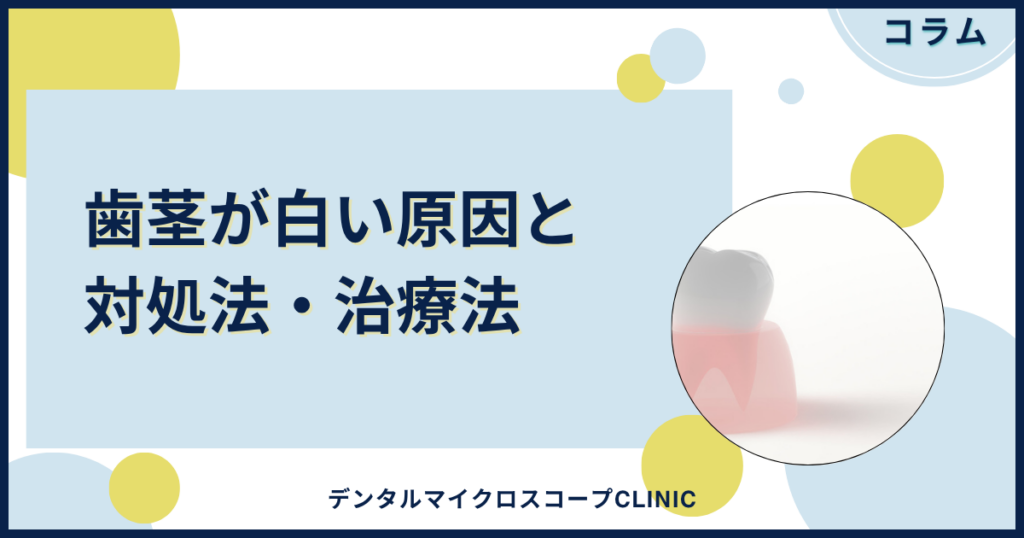
歯茎が白い原因と対処法・治療法
歯茎の健康は全身の健康状態を映し出す鏡とも言われています。普段はピンク色をしている歯茎が白く変化すると、何かしらの異常が起きているサインかもしれません。歯茎が白...


