噛んだ時の鋭い痛みや、治らない歯ぐきの腫れ。その不調は、もしかしたら歯ぐきの中で歯の根が割れる「歯根破折」が原因かもしれません。
歯根歯折は放置すれば周囲の骨が溶けるリスクもありますが、早期に発見できれば歯を残せる可能性も十分にあります。この記事では、歯根破折の原因や診断、治療法、予防法までを徹底解説していきます。手遅れになる前に、正しい知識で大切な歯を守りましょう。
この記事の監修歯科医師

医療法人あかり会歯科
脇田奈々子
大阪大学歯学部卒業後、同大学予防歯科学教室にて医員として勤務。
現在は大阪市内の歯科医院で、予防歯科からインプラント、矯正治療まで幅広く対応している。治療の先の心のケアにもつながる“医療としての美容歯科”として、ボツリヌス治療、ヒアルロン酸注入、リップアートメイクにも注力している。
「口元の健康と美を通じて、最後まで美味しく食べ、自信を持って笑える人生」をサポートすることを理念としている。
歯根破折の4つの原因

ここでは歯根破折が起こる主な原因と、見逃してはいけない症状を解説します。
- 神経のない歯への過度な負担
- 歯ぎしり・食いしばりによる継続的なダメージ
- 転倒や事故など外傷による強い衝撃
- 虫歯や不適合な被せ物による歯の弱体化
神経のない歯への過度な負担
歯根破折の一般的な原因は、神経を抜いた歯(失活歯)への過度な負担です。神経は、歯へ血液や栄養を供給する大切な役割を担っています。
<神経のない歯の危険性>
- 栄養が得られず弾力性がなくなり、もろくなる
- 硬い食べ物を噛むと割れやすい
- 神経の治療で歯の内部(象牙質)が削られ、構造的に弱くなる
さらに、治療後に歯を補強する「コア」という土台も、破折の原因になることがあります。特に金属製のコアは硬すぎるため、噛むことで歯根に強い力が加わると、歯の内側から割れるリスクが高まります。
歯ぎしり・食いしばりによる継続的なダメージ
就寝中の歯ぎしりや、日中の無意識の食いしばりも、歯根破折の原因となり得ます。
歯ぎしりや食いしばりでは、体重以上の強い力が毎日かかり、歯に見えないヒビが入って破折に進むことがあります。神経を失った歯は特にもろく、破折リスクが高まります。またこのような習慣があると歯だけでなく顎関節にもダメージを及ぼす可能性があります。
歯ぎしりを指摘されたことがある方や、食いしばりの自覚がある方は注意が必要です。
転倒や事故など外傷による強い衝撃
スポーツ中の衝突や日常生活での転倒、交通事故などで顔を強くぶつけた際に、歯根破折が起こることがあります。特に前歯は外からの衝撃を受けやすく、注意が必要です。
外傷で少し欠けただけに見えても、歯根が割れていたりヒビが入っていることがあります。数日から数か月後に歯の変色や歯ぐきの腫れで破折が判明することもあります。転倒などで顔面に強い衝撃を受けた後は、慎重に症状のチェックをするとともに、念のため歯科医院でレントゲン撮影など詳しい検査を受けましょう。
虫歯や不適合な被せ物による歯の弱体化
大きな虫歯や、不適合な被せ物も、歯を弱らせる原因となります。
虫歯が進むと歯が弱くなり、見えないところまで広がって突然折れることがあります。また、被せ物と歯の隙間や段差から細菌が侵入すると内部で虫歯が再発し、歯折の原因になることもあります。
保険適用の金属クラウンが使えなくなる原因の約19%が、歯根破折であり、被せ物周囲の歯周ポケットが深い場合、破折のリスクが高まることも報告されています(※1)定期的な歯科検診で、虫歯と合わせて被せ物の状態を確認することが大切です。
歯根破折の主な症状|放置するリスクとは

歯根破折は初期段階ではっきりした症状が出にくく、見逃されやすいのが特徴です。以下のようなサインに気づいたら、歯根破折の可能性が考えられます。ご自身の症状と照らし合わせてチェックしてみてください。
| 主な症状 | 現れるサイン |
| 噛んだ時の痛み・違和感 | ・歯が浮いた感じ、食べ物が挟まるような違和感がある・進行すると、噛んだ瞬間に鋭い痛みが起こる |
| 歯ぐきの腫れ | ・歯の根元周辺の歯ぐきが赤く腫れたり、ブヨブヨする |
| 歯ぐきのできもの | ・ニキビのような「おでき」ができ、膿が出ることもある |
| 歯の揺れ | ・被せ物や差し歯がグラグラする、よく外れる |
こうした症状を放置すると、激しい痛みや歯ぐきの炎症の原因となったり、周囲の健康な骨が溶ける歯槽骨吸収が起きたりします。
ご自身で判断するのは難しい場合もあるため、気になることがあれば放置せず、できるだけ早く歯医者さんに相談しましょう。
歯根破折の診断
歯根破折の診断では、まずレントゲン撮影を行うのが一般的です。しかし、これだけでは確定診断が難しい場合も少なくありません。レントゲンは二次元の平面的な画像なので、ヒビの入っている方向によっては、破折線が写らず、見逃されてしまうことがあるためです。
そこで、より正確な診断のために「歯科用CT検査」が有効です。歯科用CTは、歯やその周りの骨を三次元的に、あらゆる角度から観察できるため、診断の精度が向上します。
歯根破折の治療法
ここでは、以下の歯根破折の治療法を詳しく見ていきましょう。
歯を残す治療法①:破折片の接着・再植術
歯を残すための選択肢として、割れてしまった歯の破片を、特殊な接着剤で元に戻す「接着治療」があります。この治療法には、主に2つのアプローチ方法があります。
| 項目 | 方法 | 特徴 |
| 直接接着修復 | 見えない部分は医師の経験と勘で判断 | 拡大視野により患部を直接確認できる |
| 歯への影響 | 歯を抜かずに、口腔内で直接ヒビに接着剤を流し込む | 比較的浅い、小さなヒビの場合に適応される |
| 意図的再植術 | 一度歯を抜き、口腔外で歯折部分を洗浄補修後、元の位置に戻して再植する | 破折の状態を直接見ながら処置できるため、より確実な修復が期待できる |
これらの方法は、破折の状態が比較的単純で細菌感染が大きくない場合に有効ですが、歯が粉々になっていたり、歯根の状態が悪いと適応できません。
歯冠部でのヒビや少しの破折くらいなら、補綴処置(クラウン)を行います。
歯を残す治療法②:矯正的挺出(エクストルージョン)
歯ぐきよりも深い位置で折れてしまった場合、そのままでは被せ物が作れません。そのようなケースで歯を残すための有効な治療法が「矯正的挺出(きょうせいてきていしゅつ)」です。「エクストルージョン」とも呼ばれます。
<治療の流れ>
- 1.破折した歯根の神経処置・感染コントロールを行う
- 2.引き上げたい歯の歯根に装置(フック)をつけて、矯正用のゴムをかけ徐々に歯肉と歯を引っ張り上げる
- 3.十分な位置まで引っ張り上げた後、歯肉の形態修正と被せ物を作成する
特に見た目が気になる前歯などでは、大きなメリットがあります。治療期間は数週間〜数か月かかりますが、抜歯しか選択肢がなかった歯でも残せる点もメリットです。
一方で、エクストルージョンは破折の位置が浅い場合のみ適応できます。また、歯冠歯根比(上に出ている部分と骨に植わっている部分の割合)が悪くなるため、歯の寿命としては短くなり、歯周病が進んでいる場合はできません。
なお、自由診療にはなりますが、審美性を求める場合は歯周外科手術も併用となることが多いです。
抜歯が必要となるケースと判断基準
残念ながら歯の状態によっては、抜歯が最善の選択となる場合があります。無理に残すことで、かえって口腔内全体の健康を損なうリスクがあるためです。歯医者さんは以下のような基準を総合的に見て、抜歯の必要性を判断します。
| 判断基準 | 具体的な状態 |
| 歯の折れ方 | ・歯が縦に真っ二つに割れている・歯が複数の破片に粉砕されている・修復が不可能なほど複雑に割れている |
| 感染の広がり | ・破折部からの細菌感染により、歯の周りの骨が広範囲に溶けてしまっている |
| 残っている歯の量 | ・過去の治療や虫歯で歯が大きく削られており、修復しても強度を保てない |
特に、神経を取る根管治療を繰り返した歯は、歯冠の構造がもろくなりがちです。根管治療後の歯根破折治療は、歯周組織の健康状態や、折れ方などで大きく予後が変わるため、抜歯して次の治療へ進むことが適切な選択となることがあります。
抜歯後の3つの治療選択肢
歯を抜いた後は、失った歯の機能と見た目を補うための治療が必要です。主な選択肢として「インプラント」「ブリッジ」「入れ歯」の3つがあります。
| 治療法 | 特徴 | メリット | デメリット |
| インプラント | 顎の骨に人工歯根を埋め込む治療 | ・天然歯のように自然に 噛める ・隣の健康な歯を削る必 要がない・見た目が美しい | ・外科手術が必要 ・治療期間が比較的長い ・基本的に自費診療 |
| ブリッジ | 両隣の歯を土台にして、橋を架けるように人工歯を固定する治療 | ・固定式で違和感が少な い ・比較的短い期間で治療 が終わる ・保険が適用される場合 がある | ・土台にするために健康な歯を削る必要がある ・土台の歯に負担がかかる |
| 入れ歯 | 周りの歯にバネなどをかけて固定する、取り外し式の人工歯 | ・健康な歯をほとんど削 らない ・比較的安価で治療期間 が短い ・外科手術が不要 | ・違和感が出やすいこと がある ・毎日のお手入れが必要 ・バネをかける歯に負担がかかる |
それぞれにメリットとデメリットがあるため、よく理解することが大切です。どの治療法がご自身に合っているか、歯医者さんと相談して決めましょう。
歯根破折治療後の予防法
歯根破折の治療後の歯は、人工物で補強されているため元の強度には戻りません。再発や他の歯への負担を防ぐため、以下の予防法を実践しましょう。
| 予防法 | 具体的な内容 | 目的 |
| マウスピースの装着 | 就寝中にナイトガードを装着 | 歯ぎしりや食いしばりによる過剰な力を緩和させ、補強した部分の破損を防ぐ |
| 咬合(こうごう)管理 | ・定期的な噛み合わせチェックと高さ調整 ・咬筋ボツリヌストキシン注入 | 特定の歯に負担が集中しないようにする |
| 定期的な検診 | 3〜6か月ごとにプロの診察を受ける | 被せ物の劣化や新たな問題を早期発見する |
治療で補強した歯や他の歯を守るためには、被せ物や噛み合わせの状態を継続的に管理することが、再発予防のカギとなります。
まとめ
歯ぐきの中で起こる歯根破折は、自分では気づきにくいものです。特に神経のない歯や歯ぎしり・食いしばりの癖がある方は注意が必要です。「噛んだ時の痛み」や「歯ぐきの腫れ」といった小さな違和感は、歯根破折のサインかもしれません。
放置すると顎の骨が溶け、抜歯しか選べなくなるだけでなく、将来のインプラントなどの治療も難しくなります。
しかし、早期に見つければ歯を残せる可能性は十分にあります。気になる症状がある時は自己判断せずに、まずは歯医者さんに相談してください。
参考文献
根管治療の関連コラム
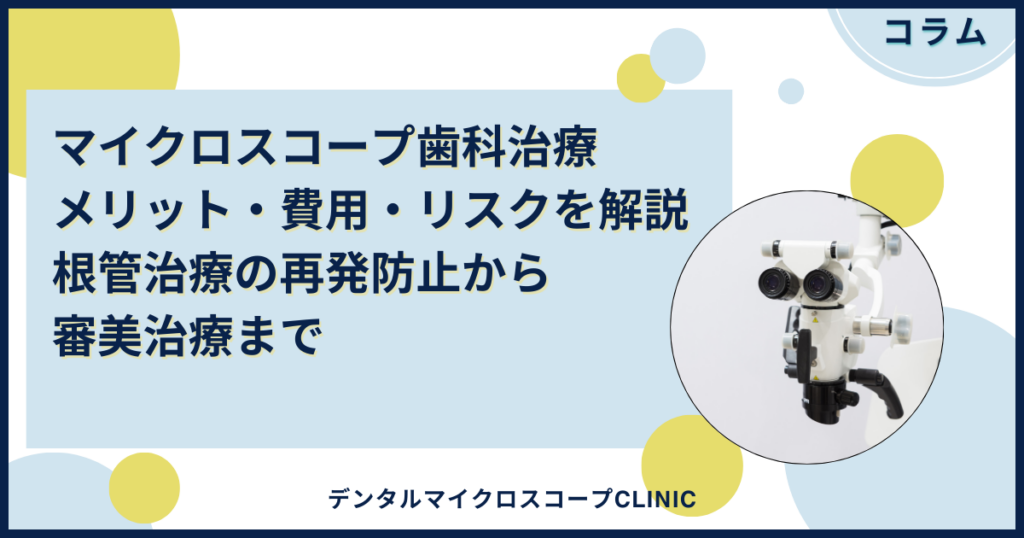
マイクロスコープ歯科治療のメリット・費用・リスクを解説|根管治療の再発防止から審美治療まで
あなたは今、「何度も治療しているのに再発してしまう」「この歯はもう諦めるしかないのか」という深い悩みや、「せっかく自費で治療するなら、一番長持ちする方法を選びた...
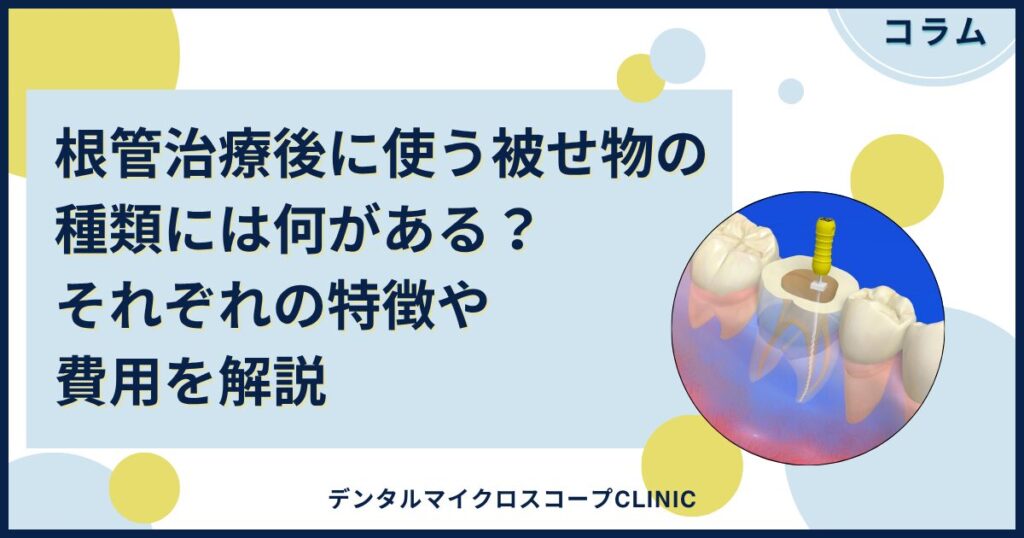
【医師監修】根管治療後に使う被せ物の種類には何がある?それぞれの特徴や費用を解説
根管治療をした後は、歯や神経を守るために被せ物をします。被せ物にはいくつか種類があり、特徴や保険適用となるのか、費用などが異なります。この記事では、保険・自費合...
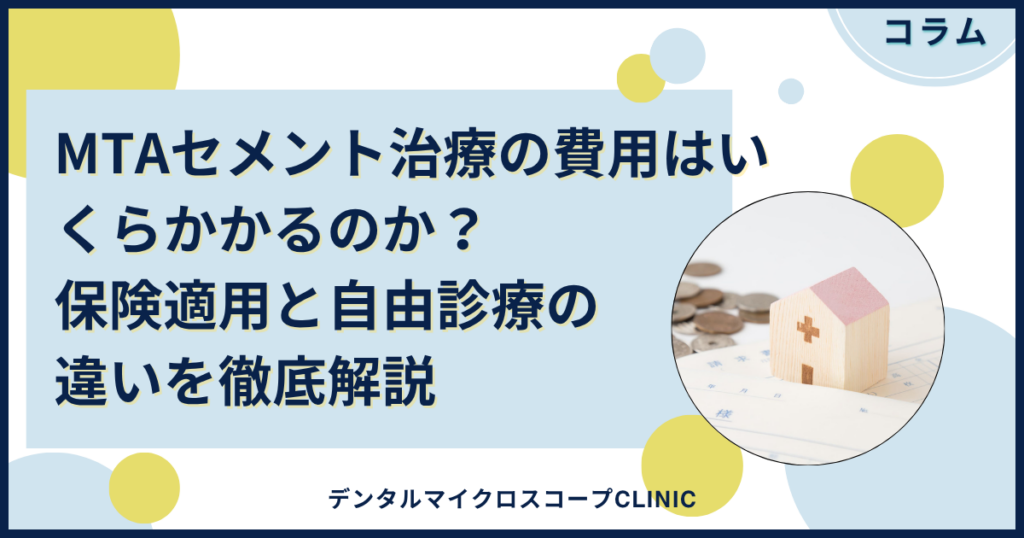
【医師監修】MTAセメント治療の費用はいくらかかるのか?保険適用と自由診療の違いを徹底解説
歯科医療の進歩により、従来なら抜歯しか選択肢がなかった歯も「MTAセメント治療」という方法で救える可能性が大きく広がっています。しかし、「MTAセメント治療はど...
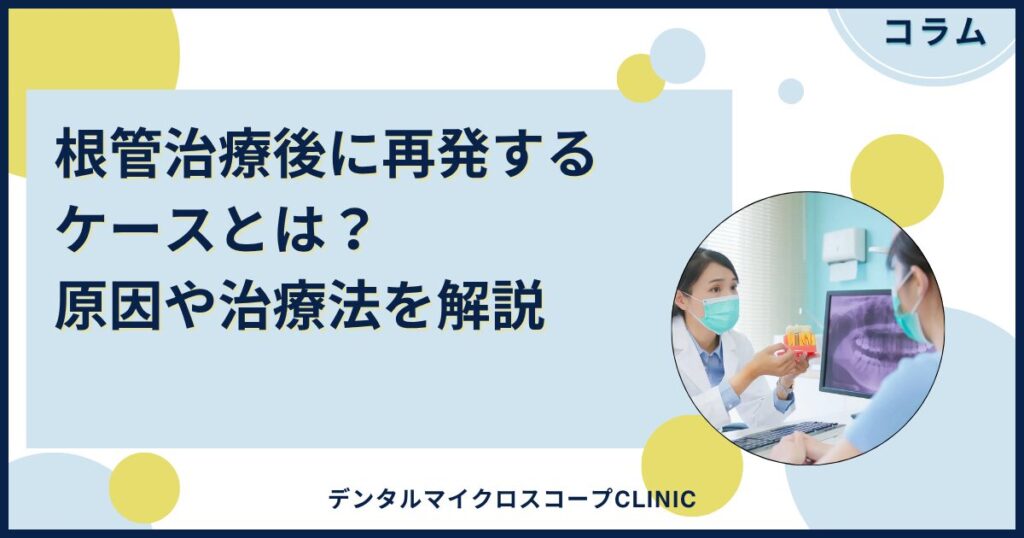
【医師監修】根管治療後に再発するケースとは?原因や治療法を解説
一度治療を終えたはずの歯が、また痛みだして、「治療がうまくいかなかったの?」と、不安な気持ちになっていませんか。歯の根の神経を取り除く根管治療は、歯を残すための...
根管治療でおすすめの歯科医院
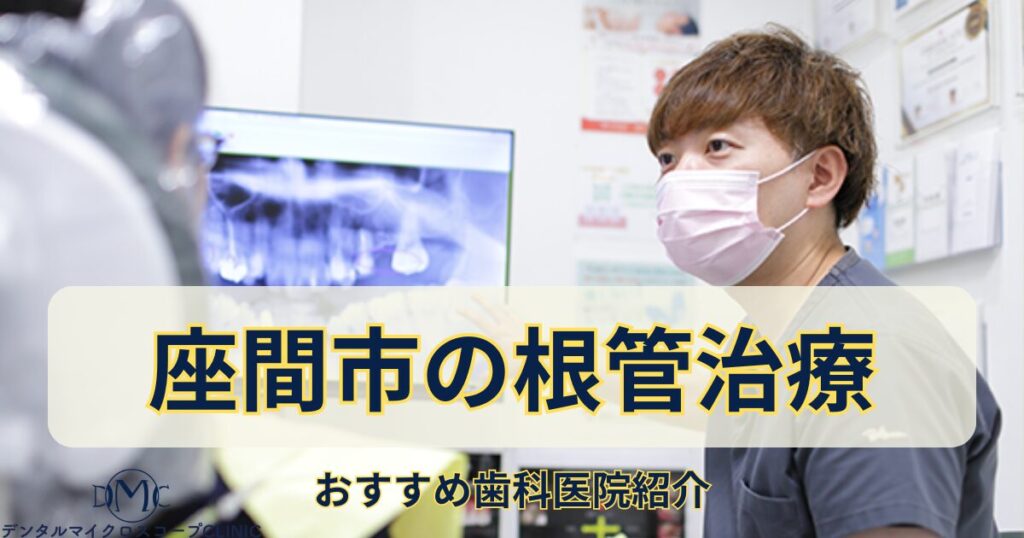
【座間市・精密根管治療】再発を防ぎ歯を残すマイクロスコープ|相武台ゆうデンタルクリニック
「治療したのに歯の痛みが引かない」「歯の神経を抜く治療が必要と言われた」神奈川県座間市で根管治療を受けるなら、無駄に歯を削らない・神経をなるべく抜かない精密治療...

【再発を防ぐ】盛岡市の根管治療|歯を残すなら日本顕微鏡歯科学会・認定指導医在籍のたかデンタルクリニックへ
「他の歯科医院で抜歯しかないと言われた」「痛みが治らない……もしかして治療に失敗した?」岩手県盛岡市で、ご自身の歯をできる限り残したい方、根管治療を繰り返してい...

横浜市港北区・綱島でおすすめするマイクロスコープ精密歯科治療は高田歯科クリニック
横浜市港北区・綱島エリアでマイクロスコープを用いた精密な歯科治療をご希望の方へ。東急東横線「綱島駅」から徒歩3分の高田歯科クリニックは、医学的根拠(エビデンス)...
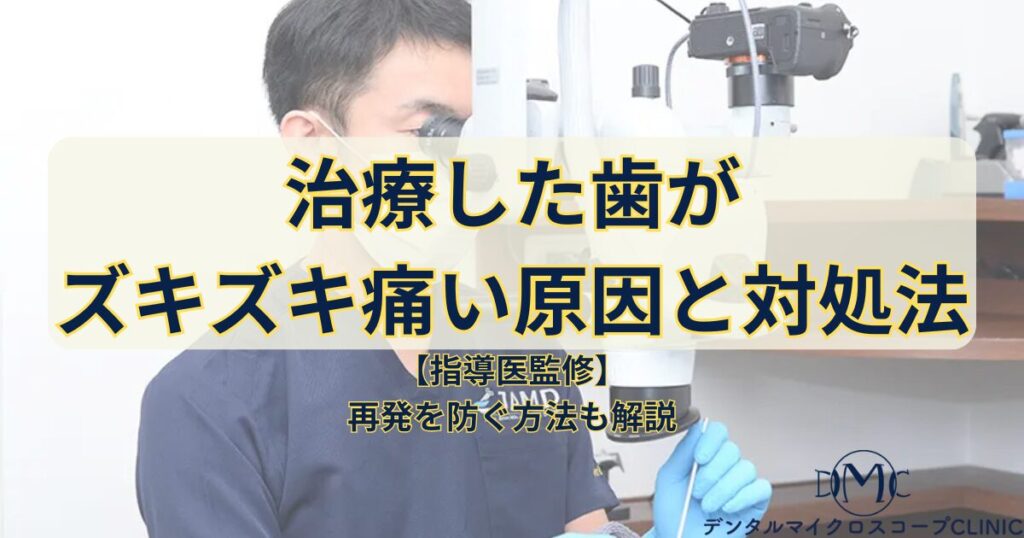
【指導医監修】治療した歯がズキズキ痛い原因と対処法|再発を防ぐマイクロスコープ
「ズキズキと脈打つような歯の痛みをなんとかしたい」「以前治療した歯が痛い……もしかして失敗した?」当記事では、治療した歯が痛くなる原因、【治療後すぐ】【しばらく...
