根管治療中に歯に詰める白い「仮蓋」は、治療の成否を分ける「鍵」です。仮蓋の役割が適切に果たされないと、消毒した歯は細菌に再び汚染され、これまでの治療が振り出しに戻る可能性があります。
最悪の場合、大切な歯を失うことにもなりかねません。
この記事では、仮蓋の役割から、万が一取れてしまった際の対処法、治療期間を安心して過ごすための注意点まで解説します。ただの詰め物と侮らないために、正しい知識をつけましょう。
この記事の監修歯科医師

医療法人あかり会歯科
脇田奈々子
大阪大学歯学部卒業後、同大学予防歯科学教室にて医員として勤務。
現在は大阪市内の歯科医院で、予防歯科からインプラント、矯正治療まで幅広く対応している。治療の先の心のケアにもつながる“医療としての美容歯科”として、ボツリヌス治療、ヒアルロン酸注入、リップアートメイクにも注力している。
「口元の健康と美を通じて、最後まで美味しく食べ、自信を持って笑える人生」をサポートすることを理念としている。
根管治療の仮蓋が担う3つの役割

根管治療中に歯に詰める仮蓋は、治療中の歯を一時的に保護するために使用される詰め物の一種です。次回の治療でスムーズに外せるよう、あえて接着力の強すぎない材料で作られています。
仮蓋の主な役割は以下の3つです。
- ①細菌感染の予防と無菌状態の維持
- ②薬剤効果の維持
- ③治療中の歯の破折防止
①細菌感染の予防と無菌状態の維持
根管治療は、歯の内部にある「根管」という細い管から、虫歯菌に汚染された神経や血管を取り除き、洗浄と消毒をします。そのため、根管治療では、いかに根管内を「無菌状態」に保てるかが重要です。
たとえ丁寧に歯磨きをしていても、口腔内には常に多くの細菌が存在しています。治療のために歯に開けた穴は、細菌にとって絶好の侵入口です。
虫歯や歯の根の先の感染症を含む口腔疾患は、細菌だけでなく真菌やウイルスなど多様な微生物が関与する口腔マイクロバイオームの乱れによって起こります。近年の研究では、この微生物バランスの乱れが心血管疾患や妊娠への悪影響、呼吸器疾患など全身疾患にも関係することが報告されています。(※1)
根管治療は複数回にわたることが多く、次回の治療までの間、穴を仮蓋で完全に封鎖する必要があります。仮蓋がないと、唾液や食べかすに含まれる細菌が、消毒したはずの根管内に侵入し、再び感染します。
痛みの再発や、再治療を防ぐためにも仮蓋は重要です。
②薬剤効果の維持
仮蓋には、根管内に詰めた薬剤の効果を引き出し、維持する役割があります。
根管治療では、根管の内部を消毒したり、炎症を鎮めたりするための薬剤を入れます。薬剤が効果を発揮するには、一定期間、根管内にしっかりと留まることが必要です。
仮蓋は、この薬剤が唾液に触れて流れ出したり、効果が薄まったりするのを防ぎます。そのため仮蓋の密閉性が低いと、薬剤が漏れ出し、期待された薬剤効果が得られません。
結果として、根管内の消毒が不完全になったり、痛みが長引いたりして治療期間が延びる原因となります。
③治療中の歯の破折防止
治療中の歯は、健康な歯に比べて脆く、割れやすい状態です。仮蓋には、この弱った歯が食事などの力で壊れるのを防ぐ「補強材」の役割もあります。
脆くなる主な理由は以下のとおりです。
- 虫歯部分を削り、歯の中心に穴を開ける
- 神経・血管を除去し、栄養や水分供給を失う
- 健康な歯より耐久性が低下し、枯れ木のようにもろくなる
この状態で食事時に強い力が加わると、ひび割れや破折の危険性が高まります。東京の歯科医院を対象とした調査では、垂直歯根破折が抜歯理由の約3割を占め、多くの場合で抜歯が避けられないと報告されています。(※2)
仮蓋が取れた・欠けたときの4つの正しい応急処置

万が一仮蓋が取れたり欠けたりした場合の応急処置のポイントは以下の4つです。
- ①速やかにかかりつけ歯科医院へ連絡する
- ②自分で戻さない・市販接着剤は使用しない
- ③痛みがなくても放置しない
- ④噛むのを避け反対側の歯で食事をする
①速やかにかかりつけ歯科医院へ連絡
仮蓋が取れたり、大きく欠けたりしたことに気づいた際は、速やかにかかりつけの歯科医院へ連絡をしましょう。たとえ痛みがなくても、自己判断で次の予約日まで放置するのは危険です。
お電話の際は、以下の情報を落ち着いて、できるだけ正確にお伝えください。
| 歯科医院へ伝えること | 状況の具体例 |
| 仮蓋が取れた状況 | ・昨日の夕食中、硬いものを噛んだら全部取れた ・今朝の歯磨きで、一部分がポロっと欠けた感じがする |
| 現在の歯の症状 | ・痛みはないが、水がしみる感覚がある ・何もしなくてもズキズキと痛む |
| 取れた仮蓋の状態 | ・粉々になってしまった ・大きな塊のまま取れて、手元に保管している |
上記の内容は、歯科医師が状況を把握し、的確な指示を出すための重要な判断材料です。
歯科医師は、患者さんから聞いた情報を元に、根管内の汚染や歯の破折リスクを考慮し、すぐに来院すべきかの指示を出します。
診療時間外であっても、まずは歯科医院への電話が大切です。留守番電話に状況を伝えるメッセージを残すなど、できるだけ早く連絡を取りましょう。
②自分で戻さない・市販接着剤は使用しない
取れてしまった仮蓋をご自身で歯に戻そうとする行為は、行わないでください。また、「アロンアルファ」に代表される市販の瞬間接着剤の使用は極めて危険です。これらの行為は、良かれと思って行った結果、治療を複雑にし、歯を失う原因にもなりかねません。
仮蓋を自分で戻すと、以下のようなリスクがあります。
| 予測されるリスク | 理由 |
| 細菌を根管内に押し込む | 仮蓋や指に付着した細菌が根管奥まで入り、再感染の恐れがある |
| 弱った歯を傷つける | 無理な装着で治療中の歯に亀裂や欠けが生じる可能性がある |
| 有害物質によるダメージ | 市販接着剤の化学物質が歯や歯茎を傷め、除去も困難になる |
ご自身の歯を守る最善策は、自己判断せず歯科医師に相談することです。
③痛みがなくても放置しない
根管治療では神経を除去しているため、仮蓋が取れても痛みを感じないことがあります。しかし、「痛くないから大丈夫」という自己判断は危険です。
仮蓋がない歯は無防備な状態で、放置すると次のような事態を招く恐れがあります。
| 予測される事態 | 理由 |
| 唾液による再感染 | 口腔内の細菌が唾液を介して根管に侵入し、内部で繁殖する |
| 治療の長期化・成功率低下 | 再感染で洗浄・消毒をやり直す必要があり、期間延長と成功率低下を招く |
| 抜歯リスクの上昇 | 感染が根の先端や骨に広がり、根尖性歯周炎へ進行する |
研究では、臼歯の根管再治療後、歯質残存率が29.5%未満の歯は、それ以上の歯に比べて抜歯率が約3倍高いと報告されています。(※3)仮蓋が取れた場合は、痛みがなくてもすぐに歯科を受診することが重要です。
④噛むのを避け反対側の歯で食事をする
歯科医院を受診するまでの間、日常生活で注意すべきことは食事です。治療中の歯は脆く、汚染リスクも高いため、反対側で食事を取りましょう。主な理由は以下のとおりです。
| 起こり得る事態 | 理由 |
| 歯の破折 | 噛む力で割れる恐れがあり、歯根まで縦に割れる「歯根破折」になると抜歯がほぼ必須 |
| 根管内の汚染 | 食べかすが穴に入り細菌が繁殖し、感染悪化の原因になる |
歯科医院で適切な処置を受けるまでは、治療中の歯とは反対側で食事をしましょう。
仮蓋をしている期間の2つの注意点

根管治療中に仮蓋が入っても、最終的な被せ物が入るまでの過ごし方が治療の成否を左右します。この期間は歯が脆く、細菌感染のリスクも高いため、日常生活での注意が必要です。
特に意識すべき点として、「①硬い食品・粘着性食品を避ける」「②治療中の歯は優しく磨きフロスは控える」を解説します。
①硬い食品・粘着性食品を避ける
仮蓋に強い力が加わったり、くっついたりする食べ物は避けましょう。仮蓋が破損したり、外れたりする直接的な原因になります。
治療中に避けるべき食べ物を以下の表にまとめています。
| 食品の種類 | 食べ物の例 | 理由 |
| 硬い食品 | せんべい、ナッツ類、氷、骨付き肉、フランスパン、りんごの丸かじり | 仮蓋の割れや「歯根破折」が起こりやすくなる |
| 粘着性の高い食品 | ガム、キャラメル、ヌガー、お餅、グミ、ソフトキャンディ | 仮蓋に強く付着し、噛んだり口を開けたりした際に蓋を剝がしてしまう |
治療中は、おかゆ・うどん・スープ・豆腐・ヨーグルトなど、あまり噛まなくても良い柔らかい食品がおすすめです。もし穴に食べ物が入ってしまっても、爪楊枝などで無理に取らず、軽くうがいをする程度に留めてください。
②治療中の歯は優しく磨きフロスは控える
治療中の歯は刺激に敏感なため、普段通りにゴシゴシ磨くのは避け、工夫して磨く必要があります。仮蓋をしている期間も、口腔内を清潔に保つことは必須です。
下記のポイントを意識することで、口臭や歯肉炎の予防につながります。
- 歯ブラシは、毛先が硬いものではなく「やわらかめ」を選ぶ
- 力を入れすぎず、歯ブラシを優しく当てて小刻みに動かす
- 鏡で確認しながら、仮蓋と歯の間の境目を意識して磨く
仮蓋をしている歯にフロスや歯間ブラシを通すと、引っかかって蓋が取れるリスクがあるため基本的には、治療中の歯への使用は控えましょう。
補助的に殺菌成分の入った洗口液を使う方法もありますが、補助的なものであり、歯ブラシによる清掃の代わりにはなりません。
仮蓋をしている時期にみられる症状とその対策
仮蓋をしている期間中によくみられる症状として、「薬の味や匂い」「仮蓋の変色や歯茎の痛み・腫れ」を解説します。
薬の味や匂い
仮蓋中に薬の味や匂いを感じるのは珍しくなく、多くは一時的です。原因と対処法、受診が必要なケースを以下にまとめます。
| 内容 | 詳細 |
| 主な原因 | ・根管の消毒・消炎薬が唾液でわずかに溶け出すため ・仮蓋は密閉性はあるが完全防水ではない |
| 対処法 | ・一時的でかすかな味なら問題なし ・気になる場合は水で数回うがいをすると和らぐ |
| 受診が必要な症状 | ・常に薬が漏れている感じがする ・急に味が濃くなった、腐ったような強い匂い ・味や匂いに加え、痛みや歯茎の腫れが出る |
上記に当てはまる場合は、仮蓋の隙間や根管内トラブルの可能性があるため、すぐに歯科医院へ相談してください。
仮蓋の変色や歯茎の痛み・腫れ
仮蓋の変色や歯茎の痛み・腫れの症状は、受診が必要なサインです。以下のような症状があれば注意してください。
- 仮蓋の変色:黒や濃い茶色になってきた
- 歯茎の痛み・腫れ:赤く腫れる、押すと痛い、白いできものがある
- 噛んだときの痛み・違和感:噛むと痛む、歯が浮いた感じがする
これらの原因を正確に突き止めるには精密な検査が必要です。通常のレントゲンでは見えにくい微細な亀裂や複雑な根管形状も、CTのような高解像度技術なら詳細に観察できます。(※4)少しでも違和感があれば早めに歯科医院へ相談しましょう。
まとめ
仮蓋は、治療中の歯を細菌から守り、薬剤の効果を保ち、歯が割れるのを防ぐ大切な存在です。一見、簡易的な詰め物に見えますが、治療の成功を大きく左右します。
万が一、取れたり欠けたりした場合でも、ご自身で戻そうとせず、まずは速やかにかかりつけの歯科医院へ連絡しましょう。「痛くないから大丈夫」という自己判断が、治療をやり直しにする危険な落とし穴です。
治療中のデリケートな歯を守ることは、ご自身の歯の未来を守ることにつながります。気になることがあれば、一人で悩まず、まずは歯科医師に相談しましょう。
参考文献
根管治療の関連コラム
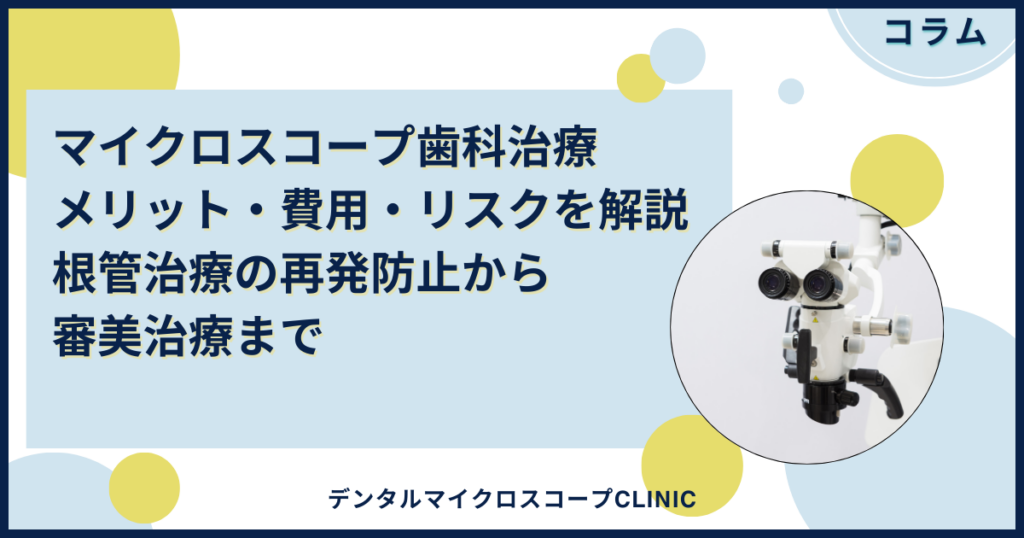
マイクロスコープ歯科治療のメリット・費用・リスクを解説|根管治療の再発防止から審美治療まで
あなたは今、「何度も治療しているのに再発してしまう」「この歯はもう諦めるしかないのか」という深い悩みや、「せっかく自費で治療するなら、一番長持ちする方法を選びた...
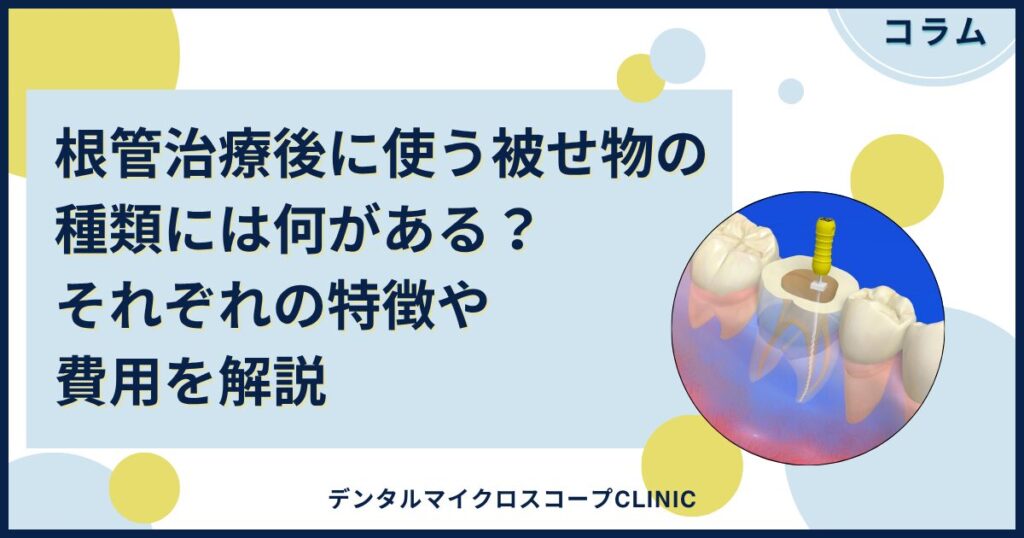
【医師監修】根管治療後に使う被せ物の種類には何がある?それぞれの特徴や費用を解説
根管治療をした後は、歯や神経を守るために被せ物をします。被せ物にはいくつか種類があり、特徴や保険適用となるのか、費用などが異なります。この記事では、保険・自費合...
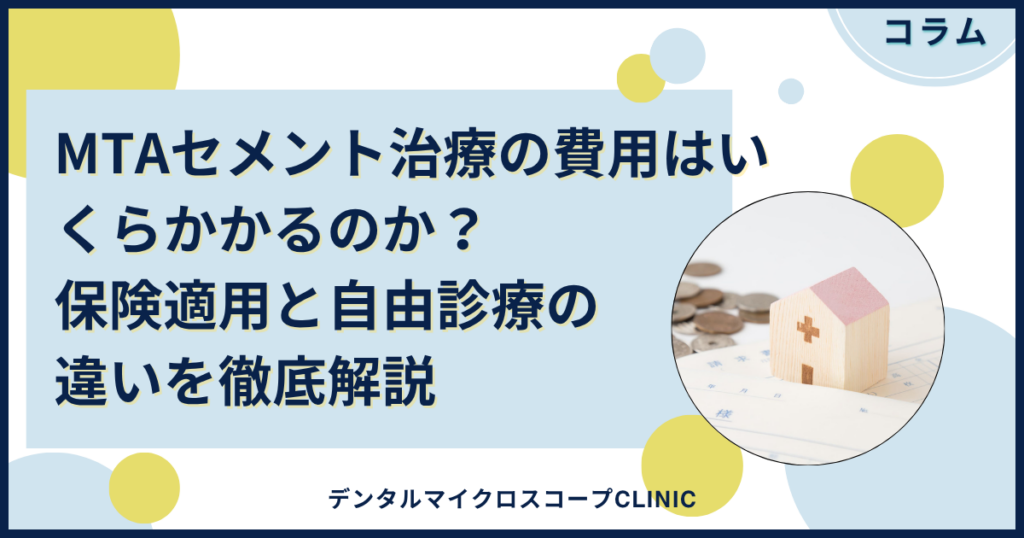
【医師監修】MTAセメント治療の費用はいくらかかるのか?保険適用と自由診療の違いを徹底解説
歯科医療の進歩により、従来なら抜歯しか選択肢がなかった歯も「MTAセメント治療」という方法で救える可能性が大きく広がっています。しかし、「MTAセメント治療はど...
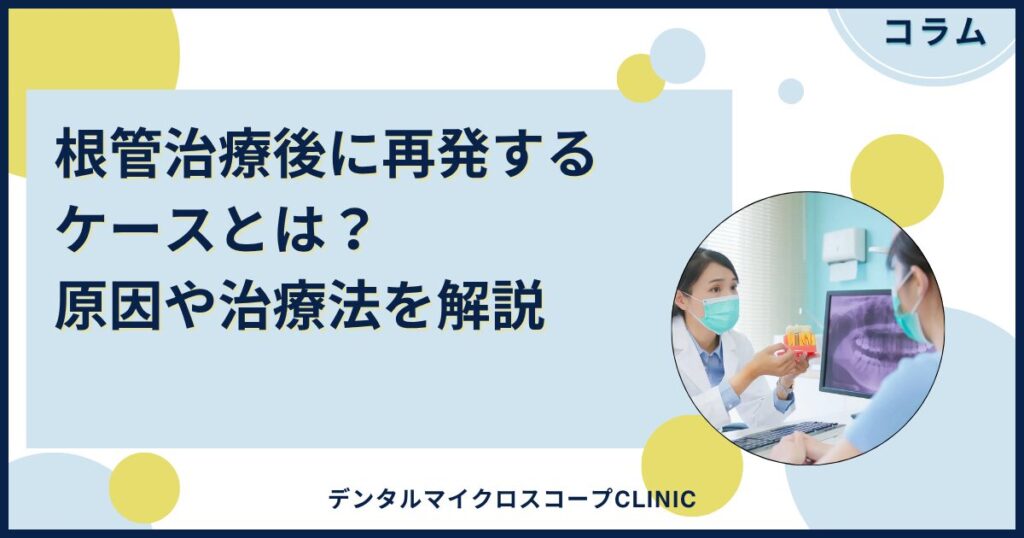
【医師監修】根管治療後に再発するケースとは?原因や治療法を解説
一度治療を終えたはずの歯が、また痛みだして、「治療がうまくいかなかったの?」と、不安な気持ちになっていませんか。歯の根の神経を取り除く根管治療は、歯を残すための...
根管治療でおすすめの歯科医院
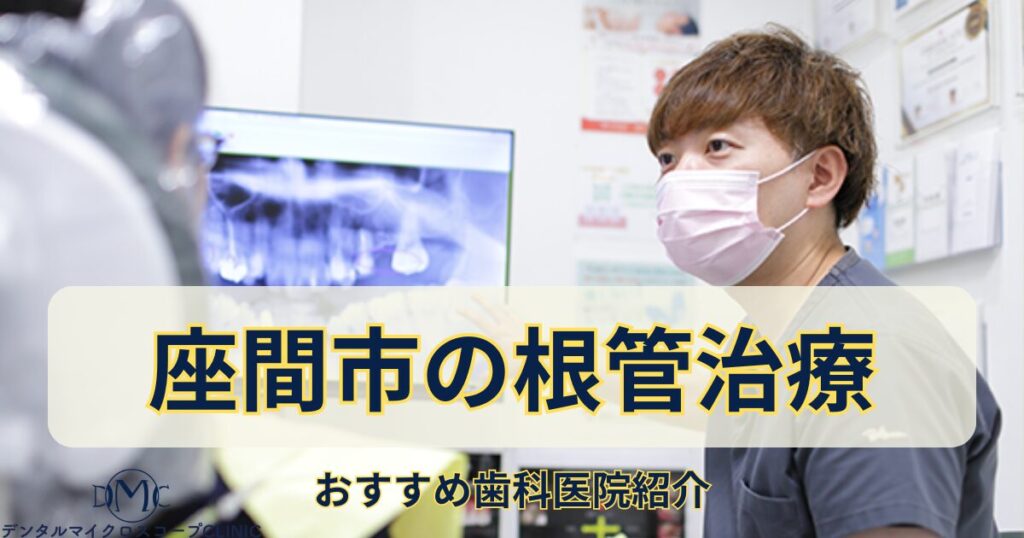
【座間市・精密根管治療】再発を防ぎ歯を残すマイクロスコープ|相武台ゆうデンタルクリニック
「治療したのに歯の痛みが引かない」「歯の神経を抜く治療が必要と言われた」神奈川県座間市で根管治療を受けるなら、無駄に歯を削らない・神経をなるべく抜かない精密治療...

【再発を防ぐ】盛岡市の根管治療|歯を残すなら日本顕微鏡歯科学会・認定指導医在籍のたかデンタルクリニックへ
「他の歯科医院で抜歯しかないと言われた」「痛みが治らない……もしかして治療に失敗した?」岩手県盛岡市で、ご自身の歯をできる限り残したい方、根管治療を繰り返してい...

横浜市港北区・綱島でおすすめするマイクロスコープ精密歯科治療は高田歯科クリニック
横浜市港北区・綱島エリアでマイクロスコープを用いた精密な歯科治療をご希望の方へ。東急東横線「綱島駅」から徒歩3分の高田歯科クリニックは、医学的根拠(エビデンス)...
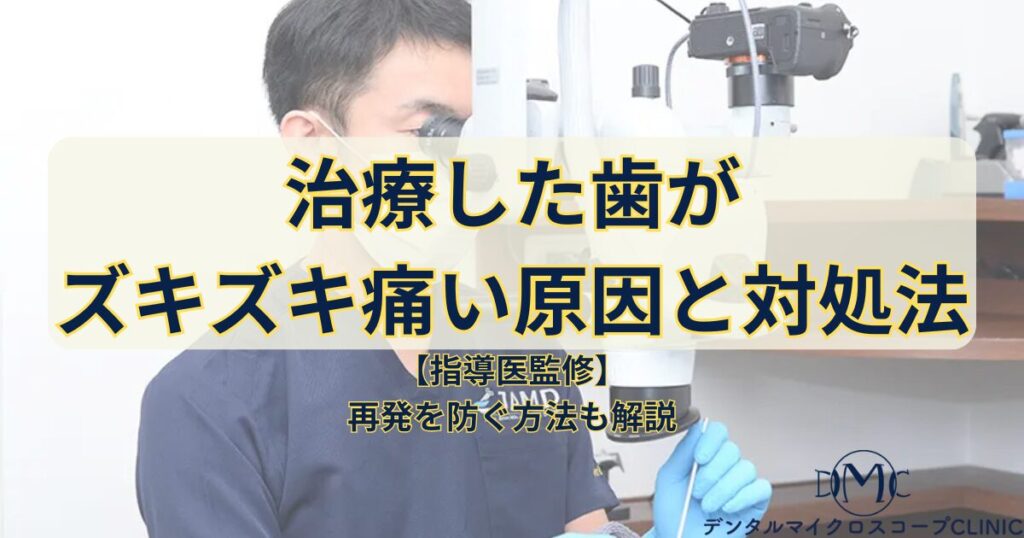
【指導医監修】治療した歯がズキズキ痛い原因と対処法|再発を防ぐマイクロスコープ
「ズキズキと脈打つような歯の痛みをなんとかしたい」「以前治療した歯が痛い……もしかして失敗した?」当記事では、治療した歯が痛くなる原因、【治療後すぐ】【しばらく...
