「痛みがないから大丈夫」、そう思って、歯の変色や歯茎にできたおできを放置していませんか?実はそれ、痛みを感じないまま歯の神経が死んでしまう危険なサインかもしれません。症状がないからと放置していると、歯の内部では深刻な問題が静かに進行していきます。
最悪の場合、歯が根元から折れて抜歯に至るだけでなく、細菌が血管を通って全身に広がり、心臓病などの深刻な疾患を招くリスクもあります。
この記事では、神経が死んだ歯を放置するリスクをはじめ、死んだ歯のサインや原因、大切な歯を残すための治療法まで解説します。手遅れになる前に、ご自身の歯を守るための正しい知識を身につけましょう。
この記事の監修歯科医師

医療法人あかり会歯科
脇田奈々子
大阪大学歯学部卒業後、同大学予防歯科学教室にて医員として勤務。
現在は大阪市内の歯科医院で、予防歯科からインプラント、矯正治療まで幅広く対応している。治療の先の心のケアにもつながる“医療としての美容歯科”として、ボツリヌス治療、ヒアルロン酸注入、リップアートメイクにも注力している。
「口元の健康と美を通じて、最後まで美味しく食べ、自信を持って笑える人生」をサポートすることを理念としている。
神経が死んだ歯を放置する5つの深刻なリスク

神経が死んだ歯の放置によって起こりうる、5つの深刻なリスクは以下のとおりです。
- ①歯の根の先に膿がたまる根尖病巣ができる
- ②突然の激しい痛みや顔の腫れを引き起こす
- ③歯が脆くなり根元から折れる歯根破折
- ④細菌が全身に広がり心臓病などの全身疾患を招く
- ⑤放置により抜歯しか選択肢がなくなる
①歯の根の先に膿がたまる根尖病巣ができる
神経が死んだ歯の根の先には、膿がたまる「根尖病巣(こんせんびょうそう)」ができることがあります。根尖病巣は、歯の内部で増えた細菌が、根の先から顎の骨に侵入し、体の免疫反応によって膿の袋が形成されます。
根尖病巣には、以下の特徴があります。
- 普段は自覚症状がない
- レントゲンで歯の根の先に黒い影が見える
- 体力が落ちたときにうずいたり腫れたりすることがある
- 放置すると顎の骨が溶けていく
進行すると膿の袋が大きくなり、治療が難しくなったり、歯を残せなくなる可能性もあります。
②突然の激しい痛みや顔の腫れを引き起こす
根尖病巣は、激しい痛みや顔の腫れを引き起こすことがあります。これは、静かだった炎症が急に悪化する「急性化」によるものです。
急性化は、以下のようなタイミングで起こりやすくなります。
- 仕事や育児の疲れ、睡眠不足
- 風邪などの体調不良
- 強いストレス
- 生活習慣の乱れ
症状が出ると、ズキズキと脈打つような激しい痛みや、軽く触れただけでも我慢できないほどの鋭い痛みが現れます。膿の圧力が高まり、歯茎や頬まで腫れが広がって口が開けづらくなることもあります。
ここまで進行すると、日常生活に支障をきたし、治療も大がかりになるため、症状が出る前の早期発見・治療が重要です。
③歯が脆くなり根元から折れる歯根破折
神経が死んだ歯は、見た目に問題がなくても、脆く折れやすくなります。これを「歯根破折(しこんはせつ)」と呼び、多くの場合で抜歯が避けられません。
脆くなる主な原因は以下のとおりです。
| 原因 | 詳細 |
| 栄養供給の停止 | 神経が死ぬと血流が途絶え、水分や栄養が届かなくなり、歯が乾燥してもろくなる |
| 歯質の喪失 | 神経が死ぬ原因の多くは虫歯による損傷であり、歯の構造自体がすでに弱っている |
| 治療の影響 | 根管治療で歯を削ることで壁が薄くなり、咬む力や外圧に耐えにくくなる |
こうして弱くなった歯は、硬い物を噛んだときや歯ぎしり・食いしばりなどの力で、ある日突然、根元から割れることがあります。特に縦に割れた場合は、細菌が歯の中に侵入しやすく、保存が困難になるため、ほとんどのケースで抜歯が必要です。
④細菌が全身に広がり心臓病などの全身疾患を招く
歯の根の病気は、口の中だけでなく、全身の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。以下は、関係が指摘されている代表的な疾患です。
| 疾患名 | 内容 |
| 感染性心内膜炎 | 心臓の弁や内膜に細菌が感染し、重篤な心臓病を引き起こす |
| 糖尿病の悪化 | 炎症がインスリンの働きを妨げ、血糖コントロールが難しくなる |
| 敗血症 | 血液中で細菌が増殖し、全身に強い炎症反応を引き起こす命に関わる状態 |
| 慢性片頭痛との関連 | 歯や歯周の炎症が、全身の慢性炎症を介して頭痛を引き起こす可能性がある(※1) |
口の中のトラブルは放置せず、全身の健康のためにも早めの治療が重要です。
⑤放置により抜歯しか選択肢がなくなる
神経が死んだ歯を放置し続けると、最終的に「抜歯」しか選べなくなることがあります。以下は、抜歯に至る主なケースです。
- 根尖病巣の拡大:病巣が大きくなり、骨の破壊が進んで回復が難しくなる
- 歯根破折:歯の根が割れ、細菌の侵入を防げなくなる
- 歯質の喪失:虫歯や破折により、被せ物を支える健康な歯質がほとんど残っていない
ただし、神経が死んだ直後や病巣が小さいうちであれば、根管治療などで歯を残せる可能性があります。歯を失うと咬み合わせが乱れ、他の歯への負担や食事の不便につながることもあります。
抜歯後にも治療法はありますが、天然の歯に勝るものはありません。歯を守るには、早期の治療が大切です。
神経が死んだ歯が発する4つのサイン

神経が死んだ歯が発するサインは以下の4つです。
- ①痛みはないのに歯が黒や灰色に変色する
- ②歯茎にできる白いおでき(フィステル)
- ③特定の歯の周囲から発生する不快な口臭
- ④かたい物を噛んだときに違和感や軽い痛みがある
①痛みはないのに歯が黒や灰色に変色する
神経が死んだ歯は、痛みがなくても徐々に色が変わります。これは、歯の中にある神経や血管が損傷し、血液中の色素(ヘモグロビン)が分解されて鉄分などが沈着するためです。鉄分などの色素が象牙質に入り込み、内側から黒っぽく、または灰色に変色して見えます。
歯の変色のチェックポイントは以下のとおりです。
- 色の変化:周りの歯と比べて白さがなく、灰色、茶褐色、黒っぽい色をしている
- 変色の範囲:特定の歯1本だけ、もしくは隣り合う数本の歯だけ色が違う
- 透明感の喪失:健康な歯のようなツヤや透明感がなく、マットな見た目をしている
- 時間による経過:時間の経過とともに、色が濃くなっているように感じる
このように、痛みがないからといって色の変化を放置してはいけません。歯からの重要なサインとして受け止め、歯科医による診断を受けることが大切です。
②歯茎にできる白いおでき(フィステル)
歯茎にできる白いおできは、「フィステル(瘻孔:ろうこう)」と呼ばれ、歯の根にたまった膿が出るための出口です。痛みを伴わないことも多く、気づかずに放置されることもあります。
フィステルは、以下のような過程で生じます。
- 1,歯の内部で細菌が増殖する
- 2.根の先で炎症と膿ができる
- 3.膿の出口を求めて排出路ができる
- 4.歯茎の表面におできとして現れる
フィステルは、体が膿を外に出そうとする自然な反応で、一時的に痛みが引くこともあります。しかし、これは治ったわけではありません。
歯の内部の感染を放置すると、再び炎症が起きたり、顎の骨がさらに溶けて歯を失ったりするリスクも高まります。根本的な治療には、感染源の除去が必要です。
③特定の歯の周囲から発生する不快な口臭
歯磨きや舌のケアをしているのに、特定の歯の周辺から強いにおいがする場合は、神経が死んだ歯が原因かもしれません。
神経が死ぬと、歯の内部で組織が腐敗し、酸素を嫌う細菌(嫌気性菌)が繁殖します。嫌気性菌がタンパク質を分解する際に、強い硫黄臭や腐敗臭に似たガスが発生します。
口全体からではなく、特定の歯の周辺からにおいがする傾向があります。歯磨きやマウスウォッシュをしても、根本原因が歯の内部にあるため、においはなかなか消えません。
フィステルから膿が出ている場合、その膿自体も強いにおいの原因になることがあります。こうしたにおいは、歯の内部で深刻なトラブルが進行しているサインであり、早めの受診が重要です。
④かたい物を噛んだときに違和感や軽い痛みがある
神経が死んだ歯でも、かたい物を噛むと違和感や痛みを感じることがあります。痛みの原因は歯そのものではなく、歯を支える歯根膜が刺激を受けているためです。
歯根膜の神経は圧力を感知するため、根の先に膿がたまると、その刺激で以下のような症状が引き起こされます。
- 歯が浮いているように感じる
- 噛むと鈍い痛みがある
- 特定の歯だけ噛み心地が違う
これらの違和感は、歯の周囲組織からの異常信号であり、放置せず早めに歯科を受診することが大切です。
最近では、特定の波長の光を用いて神経の感覚回復を促すレーザー鍼治療が、歯科領域の神経障害に対する治療選択肢の一つとして注目されています。こうした研究が進められていることからも、噛んだときの違和感は体からの重要なサインであり、見過ごさず、早めに相談することが重要です。(※2)
神経が死ぬ主な3つの原因

歯の神経は、ご自身が気づかないうちに静かにダメージを受け、機能を失ってしまうことがあります。神経が死ぬ主な3つの原因は以下のとおりです。
- ①重度の虫歯による神経の壊死
- ②歯にできた亀裂やヒビからの細菌感染
- ③事故や打撲などによる外傷
①重度の虫歯による神経の壊死
神経が死ぬ一般的な原因は、治療せずに放置された虫歯の進行です。虫歯は感染症であり、以下のような段階を経て、最終的に神経を壊死させます。
- 1.エナメル質の虫歯:歯の表面が溶け始める(痛みはほとんどない)
- 2.象牙質の虫歯:内側まで進行し、冷たいものや甘いものでしみる
- 3.歯髄炎:神経に細菌が達し、ズキズキと強い痛みが出る
- 4.神経の壊死:歯髄が破壊され、血流が途絶えて機能を失う
神経が壊死すると、激しい痛みが突然なくなるため、「治った」と勘違いされがちです。しかし実際には、細菌が歯の内部で繁殖し続けている危険な状態です。
痛みの有無だけで判断せず、早期の検査と治療を受けることが、歯を守るために欠かせません。
②歯にできた亀裂やヒビからの細菌感染
虫歯が見当たらなくても、歯にできた亀裂やヒビからの細菌感染によって、歯の神経が死んでしまうことがあります。歯ぎしりや食いしばり、硬いものを噛む習慣があると、目に見えないほどの亀裂が生じることがあります。
亀裂から細菌が侵入し、知らないうちに神経(歯髄)に感染が広がります。痛みが出にくく、気づいた時には歯が変色したり、歯茎が腫れていたりするケースも珍しくありません。
以下のような習慣がある方は、歯に負担がかかっている可能性があります。
| チェック項目 | 内容の例 |
| 歯ぎしり・食いしばり | ・寝ている間に歯ぎしりをしていると言われたことがある ・日中も無意識に噛みしめている |
| 硬い食べ物の習慣 | 氷・ナッツ・硬いせんべいなどをよく食べる |
| 噛んだ時の鋭い痛み | 特定の歯で硬いものを噛むとピリッと痛むことがある |
思い当たる習慣がある方は、知らずに歯にダメージを与えている可能性があります。違和感がある場合は早めに歯科医院を受診し、ヒビや亀裂の有無をチェックしてもらうことが大切です。
③事故や打撲などによる外傷
転倒や衝突、スポーツ中のケガなどで顔や口元を強く打つと、「外傷」として、歯の神経が死んでしまうことがあります。見た目に損傷がなくても、衝撃で歯の根の血管が切れ、血流が止まることで神経が徐々に壊死することがあります。
外傷による神経の壊死はすぐには現れず、数か月~数年後に歯の変色などで気づくケースも多く見られます。また、歯の位置がずれた場合は矯正治療が必要になり、神経の有無が治療方針への影響も考えられます。
過去に歯を強くぶつけた経験がある方は、現在痛みや違和感がなくても、一度歯科で検査を受けておくと安心です。
神経が死んだ歯の治療法と期間の目安

ここでは、神経が死んだ歯に対して行われる治療法と、その期間の目安を紹介します。治療内容の正しい理解によって、安心して治療に臨むことができます。
歯を残すための精密根管治療
精密根管治療は、感染した神経や血管を取り除き、再感染を防ぎながら歯を残すための治療です。基本的な流れは以下のとおりです。
- 1.感染部分の除去
- 2.根管の探索と清掃・消毒
- 3.根管内の薬剤充填
- 4.土台と被せ物の装着
根管治療は、歯の内部にある神経の通り道(根管)を処置する「歯の基礎工事」です。まず、虫歯を削って感染した組織を取り除き、根管の入り口を丁寧に探し出します。
次に、ファイルと呼ばれる専用の器具で根管内を清掃し、消毒薬で繰り返し洗浄して無菌状態に近づけます。この工程が治療成功のカギになります。
根管がきれいになったら、ゴムのような薬剤を使って密閉し、細菌の再侵入を防ぎます。最後に、歯に土台(コア)を作り、被せ物(クラウン)を装着して機能と見た目を回復させます。
根管治療にかかる通院回数・治療期間の目安
根管治療は、歯の根の中に潜む細菌を丁寧に除去・消毒するために複数回の通院が必要な治療です。1回の治療で無理に終わらせてしまうと、消毒が不十分となり、再発のリスクが高まります。
以下の表に、通院回数と治療期間の目安をまとめています。
| 内容 | 目安 |
| 通院回数 | 3〜5回程度 |
| 治療期間(根管治療のみ) | 約2週間〜1か月半程度 |
| 治療期間(被せ物完成まで) | 約1〜2か月半程度 |
根の先の病巣が大きい場合や、根管が細い・曲がっているなど構造が複雑な場合は、さらに時間がかかることもあります。歯をしっかり保存するためにも、治療途中でやめず、最後まで通院を続けることが大切です。
また、将来的に矯正治療を検討している方は、事前の根管治療が有効とされています。ある系統的レビューでは、適切な根管治療を終えた歯は、矯正中の歯根吸収リスクが低いと報告されています。そのため、矯正前に病巣を治しておくことで、より安全で安定した治療につながります。(※3)
長期的な視点で歯の健康を守るためにも、計画的に治療を進めることが重要です。
根管治療の費用目安
根管治療の費用は、保険診療か自由診療かによって大きく異なります。保険診療の場合、自己負担は3割で、前歯では3,000〜4,000円程度、小臼歯では4,000〜6,000円程度、大臼歯では6,000〜10,000円程度が目安です。歯の種類や治療回数によって金額に差はありますが、比較的負担は少なく済みます。
一方、自由診療ではマイクロスコープやCTを使った精密な治療を受けられるほか、一度の処置にしっかり時間をかけるため、通院回数が少なく済むこともあります。その分費用は高額になり、1本あたり数万円から十数万円程度が一般的です。料金は、使用する材料や治療方法によっても金額は変動します。
抜歯後の治療法
歯を失ったあとは、そのまま放置せずに、噛む機能や見た目を回復させるための治療が必要です。以下に、主な抜歯後の治療法をまとめました。
| 治療法 | 特徴 | メリット | デメリット | 費用相場 |
| インプラント | 顎の骨にチタン製の人工歯根を埋め込む | ・周囲の歯を削らない ・しっかり噛める ・骨が痩せるのを防げる可能性 | ・外科手術が必要 ・治療期間が長い ・保険適用外で費用が高い | 1歯あたり30〜50万円(基本的に自由診療) |
| 歯への影響 | 両隣の歯を削って人工歯を橋のように固定 | ・固定式で違和感が少ない ・治療期間が短め ・保険診療も選べる | ・両隣の歯を大きく削る ・土台の歯に負担がかかる ・清掃しにくい | 保険診療:1歯あたり10,000円~30,000円程度自由診療:1歯あたり5,000〜200,000円程度 |
| 入れ歯 | バネなどで固定する取り外し式の人工歯 | ・歯をほとんど削らない ・外科処置不要 ・保険で安価に作れる | ・異物感が出やすい ・噛む力が落ちる ・審美性に劣ることがある | 保険診療:5,000〜20,000円程度自由診療:100,000〜500,000円程度 |
ここで紹介する費用はあくまでも目安で、歯の状態や治療法によって異なります。
それぞれの治療法にはメリットとデメリットがあり、すべての人に共通する正解はありません。ライフスタイルや健康状態、費用、見た目の希望などを踏まえて、歯科医師と相談しながら選択することが大切です。
まとめ
歯に痛みがないからといって、必ずしも安全とは限りません。歯の変色や歯茎にできたおできなどのささいな変化は、歯の内部で問題が静かに進行している証拠です。
放置すれば、ある日突然の激痛に襲われたり、歯を失ったりするだけでなく、全身の健康にまで影響を及ぼすリスクがあります。しかし、早い段階で適切な根管治療を受ければ、大切な歯を残せる可能性はあります。
この記事で紹介したサインに1つでも心当たりがあれば、決して自己判断で放置せず、まずは歯科医師に相談してください。手遅れになる前に、ご自身の歯を守るための一歩を踏み出しましょう。
参考文献
1.Mohammed MMA, Almayeef D, Abbas D, Ali M, Haissam M, Mabrook R, Nizar R, Eldoahji T, Al-Rawi NH.The Association Between Periodontal Disease and Chronic Migraine: A Systematic Review.Int Dent J,2023,73,4,p.481-488.
2.Manente R, Pedroso GL, Moura APGE, Borsatto MC, Corona SAM.Laser acupuncture in the treatment of neuropathies in dentistry: a systematic review.Lasers Med Sci,2023,38,1,p.92.
3.Zhao D, Xue K, Meng J, Hu M, Bi F, Tan X.Orthodontically induced external apical root resorption considerations of root-filled teeth vs vital pulp teeth: a systematic review and meta-analysis.BMC Oral Health,2023,23,1,p.241.
根管治療の関連コラム
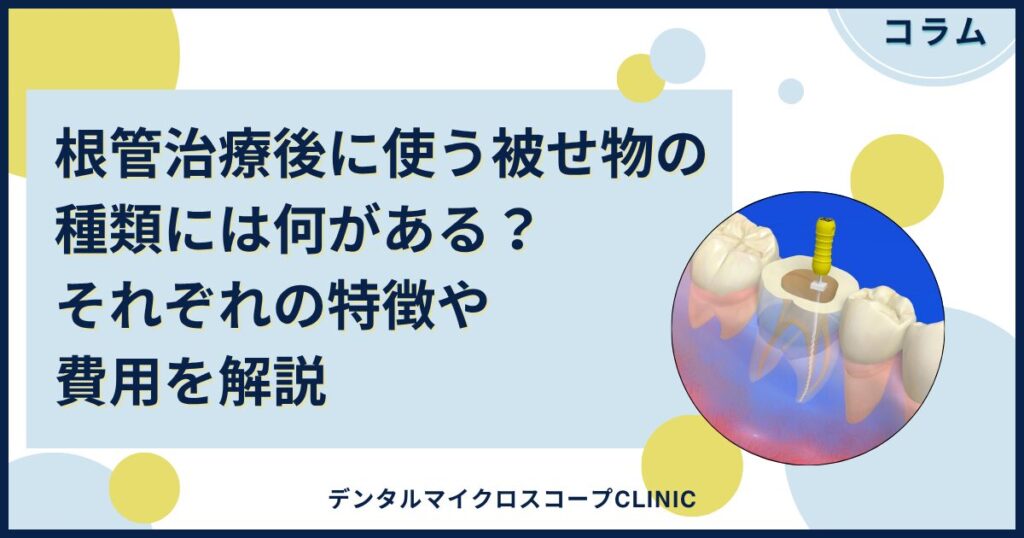
【医師監修】根管治療後に使う被せ物の種類には何がある?それぞれの特徴や費用を解説
根管治療をした後は、歯や神経を守るために被せ物をします。被せ物にはいくつか種類があり、特徴や保険適用となるのか、費用などが異なります。この記事では、保険・自費合...
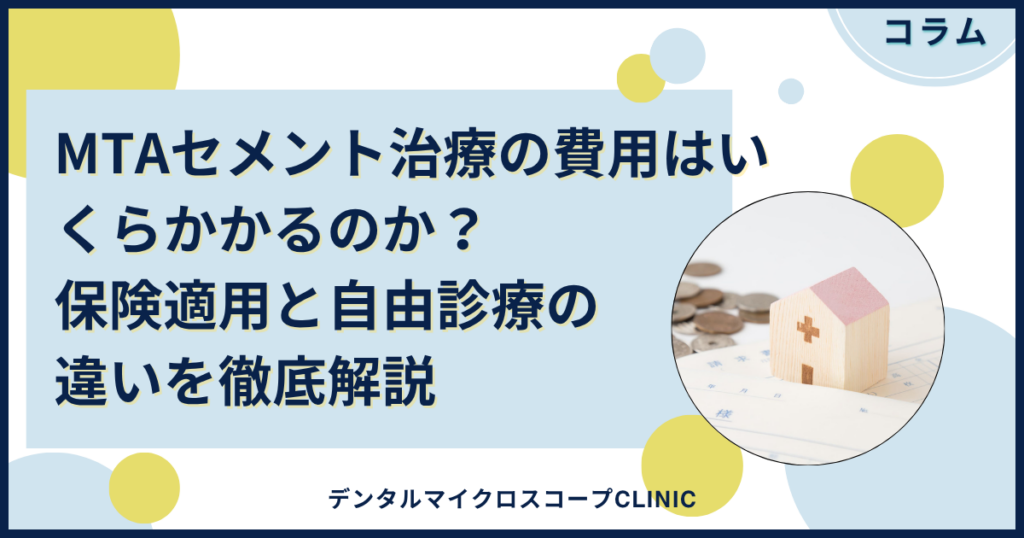
【医師監修】MTAセメント治療の費用はいくらかかるのか?保険適用と自由診療の違いを徹底解説
歯科医療の進歩により、従来なら抜歯しか選択肢がなかった歯も「MTAセメント治療」という方法で救える可能性が大きく広がっています。しかし、「MTAセメント治療はど...
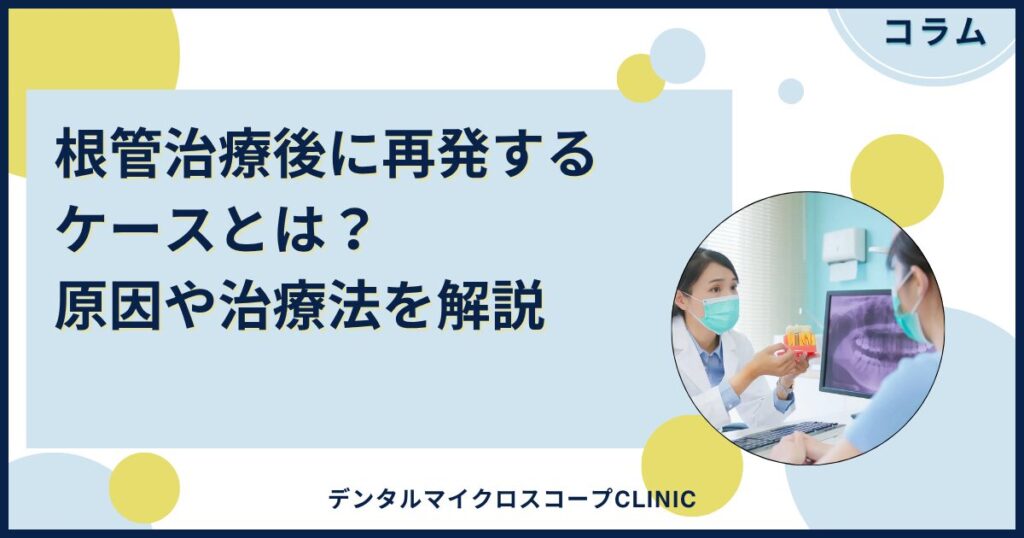
【医師監修】根管治療後に再発するケースとは?原因や治療法を解説
一度治療を終えたはずの歯が、また痛みだして、「治療がうまくいかなかったの?」と、不安な気持ちになっていませんか。歯の根の神経を取り除く根管治療は、歯を残すための...
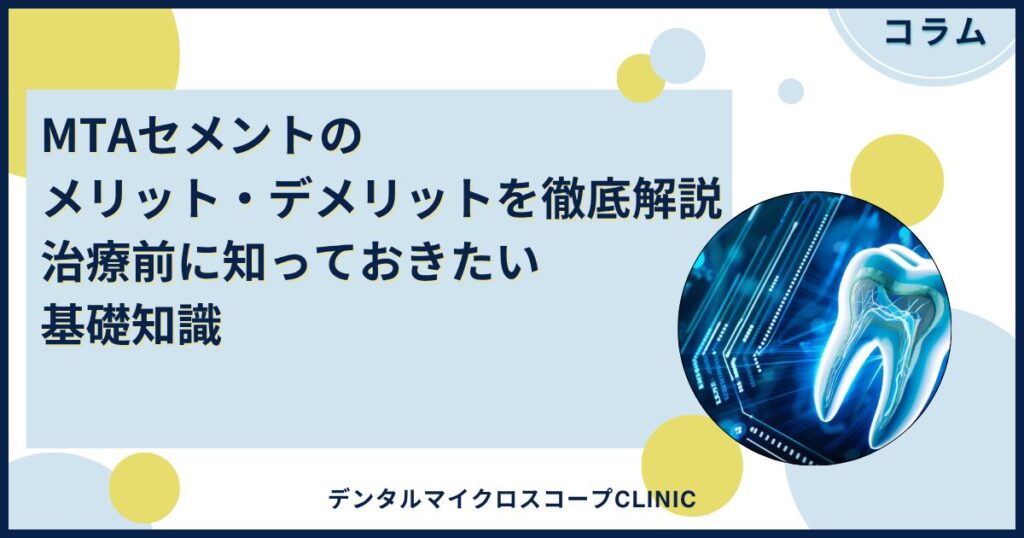
【医師監修】MTAセメントのメリット・デメリットを徹底解説|治療前に知っておきたい基礎知識
「この歯はもう抜くしかないかもしれません」歯科医師からそう告げられ、大切な歯を諦めかけていませんか。しかし、深い虫歯でも神経を残し、歯の寿命を延ばせる可能性を秘...
根管治療でおすすめの歯科医院
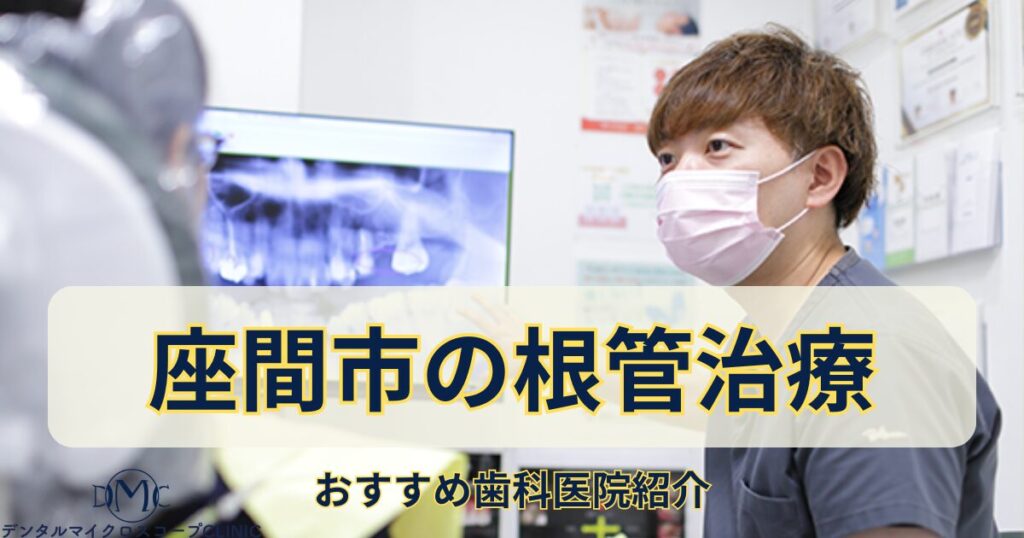
【座間市・精密根管治療】再発を防ぎ歯を残すマイクロスコープ|相武台ゆうデンタルクリニック
「治療したのに歯の痛みが引かない」「歯の神経を抜く治療が必要と言われた」神奈川県座間市で根管治療を受けるなら、無駄に歯を削らない・神経をなるべく抜かない精密治療...

【再発を防ぐ】盛岡市の根管治療|歯を残すなら日本顕微鏡歯科学会・認定指導医在籍のたかデンタルクリニックへ
「他の歯科医院で抜歯しかないと言われた」「痛みが治らない……もしかして治療に失敗した?」岩手県盛岡市で、ご自身の歯をできる限り残したい方、根管治療を繰り返してい...

横浜市港北区・綱島でおすすめするマイクロスコープ精密歯科治療は高田歯科クリニック
横浜市港北区・綱島エリアでマイクロスコープを用いた精密な歯科治療をご希望の方へ。東急東横線「綱島駅」から徒歩3分の高田歯科クリニックは、医学的根拠(エビデンス)...
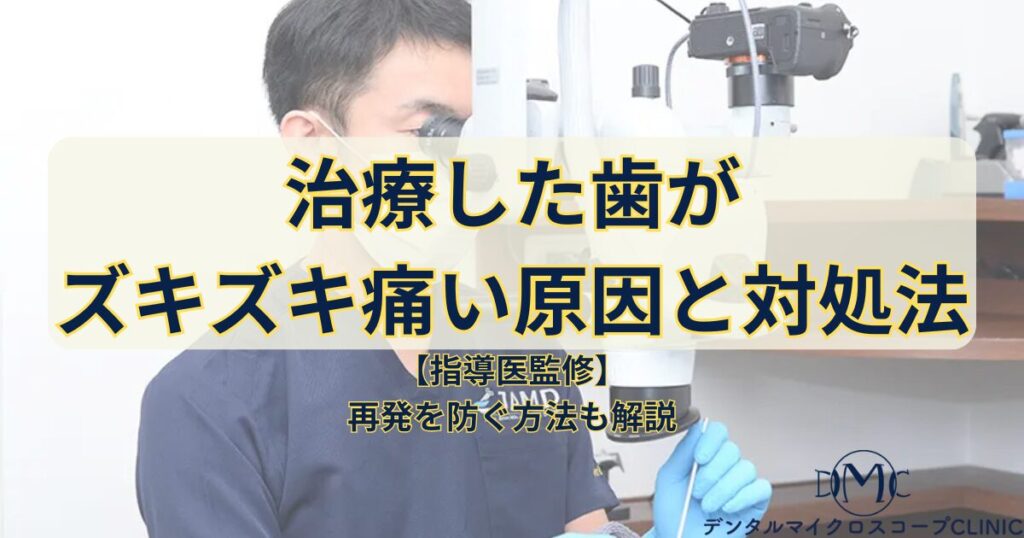
【指導医監修】治療した歯がズキズキ痛い原因と対処法|再発を防ぐマイクロスコープ
「ズキズキと脈打つような歯の痛みをなんとかしたい」「以前治療した歯が痛い……もしかして失敗した?」当記事では、治療した歯が痛くなる原因、【治療後すぐ】【しばらく...
