「しっかり治療したはずなのに、なぜ?」神経を抜いた歯が数年経ってから痛み出すと、何か大変なことが起きているのではと不安になりますよね。実は、治療後の歯が痛むのは決して珍しいことではなく、目に見えない歯の内部でトラブルが起きていることを知らせる重要なサインなのです。
多くの場合、原因は一つではありません。歯の根の先に膿がたまっていたり、治療した部分に細菌が再感染していたり、あるいは歯そのものにヒビが入っていたり…。これらの問題は、数年という時間をかけてゆっくりと進行し、ある日突然、痛みとして現れます。
この記事では、なぜ神経を抜いた歯が痛むのか、考えられる複数の原因を詳しく解説します。
この記事の監修歯科医師

谷川歯科医院
谷川 淳一 副院長
歯科医師。日本口腔インプラント学会専修医。小児歯科治療や小児矯正、インプラント治療を得意とし、他の歯科医師への指導も行う。
患者様一人ひとりと真摯に向き合って治療方針を決めていくことを信条としている。
神経を抜いた歯が数年後に痛いときに考えられる原因

一度治療を終えた歯が、数年も経ってから痛み出すと、「しっかり治したはずなのに、なぜ今ごろ?」と、大きな不安を感じることでしょう。
実は、神経を抜く治療(根管治療)をした歯が、後になって痛むことは決して珍しくありません。治療直後は問題がなくても、お口の中で時間をかけてゆっくりと変化が起きているためです。
主な原因として、以下の4つが考えられます。
- 歯の根の先に膿がたまる
- 治療した部分に細菌が再び感染する
- 歯そのものにヒビが入る、または割れる
- 被せ物の下で虫歯が再発する
これらは、それぞれ異なるメカニズムで、数年という時間差を置いて痛みを引き起こします。これから、各原因について詳しく解説します。
根の先に膿がたまっている(根尖性歯周炎)
神経を抜いた歯が数年後に痛む場合、最も頻度の高い原因が「根尖性歯周炎(こんせんせいししゅうえん)」です。
これは、歯の根の先端(根尖)の周りにある顎の骨が、細菌感染によって炎症を起こし、膿の袋(根尖病巣)ができてしまう病気です。
歯の根の中は、非常に複雑な形をしています。根管治療では、この内部を丁寧に清掃・消毒しますが、肉眼では見えないほど細かな部分に細菌が残ってしまうことがあります。
体の抵抗力が十分な間は、これらの細菌の活動は抑えられています。しかし、細菌は時間をかけてゆっくりと増殖し、根の先端から外側の顎の骨へと感染を広げていきます。
これが治療から数年という長い時間が経過してから、急に痛み出す代表的なパターンです。
治療後の再感染(根管治療の不完全な処置)
一度はきれいになったはずの歯の根の中に、唾液に含まれる細菌が再び侵入して感染を起こすことも、痛みの原因となります。
最初の治療がうまくいっていても、数年の経過とともに再感染のリスクは高まります。
再感染が起こる原因には、いくつかの代表的な経路があります。
ひとつは、治療後に装着した被せ物やその土台(コア)と歯との間にできるわずかな隙間です。時間の経過とともに劣化や変形が起こると、歯との間にごく小さなすき間が生じ、そこから細菌が内部に侵入して根管内が再び感染してしまうことがあります。
もうひとつは、治療の際に見落とされた根管の存在です。特に奥歯では、根の数が多かったり、先端が複雑に枝分かれしていたりするため、非常に細い根管や予想外の位置にある側枝・副根管にまで器具や薬剤が届かないことがあります。こうした場所に残っていた細菌が、数年後に痛みや腫れの原因となることもあるのです。
再感染はゆっくりと進行するため、自覚症状がないまま時間が経ち、ある日突然強い痛みや腫れとして現れるケースも少なくありません。
歯根破折や歯にヒビが入っている場合
神経を抜いた歯は、健康な歯と比べて強度が低下し、もろくなる傾向があります。神経と一緒に血液を供給する血管も失われるため、歯に栄養が行き渡らなくなり、組織が脆くなってしまうためです。
このような歯に、日常的に強い力が加わることで、目には見えない歯の根の部分にヒビが入ったり、割れてしまったりします。これを「歯根破折(しこんはせつ)」と呼びます。
【歯根破折の原因となる力】
- 食事中に氷やナッツなど硬いものを噛んだときの強い衝撃
- 就寝中の歯ぎしりや、日中の食いしばりの癖
- 硬い金属の土台(メタルコア)による、歯根への力の集中
神経がなくても、歯の周りには「歯根膜」という、噛んだときの感触を脳に伝える敏感な組織があります。歯根にヒビが入ると、噛むたびにその部分が刺激されたり、ヒビの隙間から細菌が侵入して歯茎に炎症を起こしたりするため、痛みを感じます。
「噛むと響くように痛い」「特定の場所の歯茎だけが繰り返し腫れる」といった症状は、歯根破折のサインかもしれません。
被せ物の下で虫歯が再発している
「神経を抜いた歯は、もう虫歯にならない」と思われがちですが、それは大きな誤解です。
神経がなくても、歯そのものは残っているため、虫歯になる可能性は十分にあります。特に注意が必要なのが、被せ物とご自身の歯との境目です。
歯と被せ物の境目は、汚れがたまりやすく、細菌が繁殖しやすい場所です。そこから侵入した細菌が、被せ物の下で虫歯を静かに進行させてしまうことがあります。
神経を取った歯は痛みを感じにくいため、虫歯がかなり大きく進行するまで自覚症状が出ないことが多く、発見が遅れがちです。やがて虫歯が歯の根の近くまで達し、周囲の組織に炎症が広がったり、歯がもろくなってヒビが入ったりすると、初めて痛みや腫れを感じるようになります。
このように、見えない場所で虫歯が進行している場合もあるため、神経を抜いた歯であっても定期的なチェックが大切です。
神経を抜いた歯の痛みが気になる方は下記記事もあわせてご覧ください
神経を抜いた歯が数年後に痛いときの対処法

神経を抜いた歯の痛みは、放置しても自然に治ることはまずありません。むしろ、その痛みの裏には、歯の内部や根の周りで何らかのトラブルが起きているという重要なサインが隠されています。
大切な歯を将来も長く使い続けるためには、痛みの原因を正確に突き止め、できるだけ早く適切な対処を始めることが何よりも重要です。
放置せずに歯科医院を早めに受診する
神経を抜いた歯に痛みや違和感を覚えたら、ご自身の判断で様子を見ることはせず、できるだけ早く歯科医院を受診してください。「そのうち治るだろう」と放置してしまうと、状況が悪化してしまう可能性が非常に高いです。
歯の根の中に潜んでいる細菌を放置すると、以下のようなリスクが高まります。
- 感染が拡大する
- 症状が悪化する
- 治療が困難になる
市販の痛み止めを飲めば、一時的に痛みは和らぐかもしれません。しかし、これはあくまで対症療法であり、根本的な解決にはなりません。原因である細菌がなくなるわけではないため、薬の効果が切れれば再び痛みがぶり返します。
レントゲン・CT検査で状態を確認
歯科医院では、まず痛みの原因を正確に突き止めるため、詳しい検査を行います。特に、目では見えない歯の内部や、その周りの骨の状態を把握するために、画像検査は欠かせません。
レントゲン検査(デンタルX線写真)は、歯の根の先に膿の袋(根尖病巣)ができていないか、被せ物や土台の状態に異常がないかを確認するための基本的な検査です。ただし、レントゲンは二次元の平面画像であるため、歯の根の複雑な構造や、重なった部分に隠れた小さなヒビなどを正確に捉えるのが難しいことがあります。
そうした場合に有効なのが、歯科用CT検査です。CTでは歯や顎の骨を三次元の立体画像で確認できるため、レントゲンでは把握しきれない細かな情報を得ることができます。たとえば、根管の本数や分岐の有無、レントゲンでは見つけにくい歯の根のヒビ(歯根破折)、膿の袋の正確な大きさや顎の骨内での広がり、さらに上顎洞炎など歯以外の病気との鑑別にも役立ちます。
このような精密な画像診断を通じて、痛みの本当の原因を特定し、一人ひとりの状態に応じた最適な治療計画を立てることが可能になります。
再根経治療・外科処置・抜歯の選択肢
精密検査で原因が特定された後、歯の状態や患者さんのご希望に合わせて治療法を決定します。主な選択肢には、歯を残すための再根管治療や外科処置、抜歯などがあります。
- 再根管治療
一度入れた被せ物や土台を外し、根管内を再度きれいに洗浄・消毒して薬を詰める治療法 - 外科処置
麻酔をした後に歯茎を切開し、歯の根の先端と、そこにできた膿の袋を直接取り除く手術 - 抜歯
麻酔をした後に歯を抜く処置
根管治療後の痛みについては下記記事でも詳しく解説しています。
神経を抜いた歯が数年後に痛くならないためにできる予防策

神経を抜いた歯が数年後に痛くならないためには、以下の予防策が大事です。
- 定期検診とレントゲンによる経過観察
- 噛み合わせや日常のストレス管理
- 適切なケアと被せ物の管理
定期検診とレントゲンによる経過観察
神経を抜いた歯のトラブルを防ぐうえで最も大切なのは、歯科医院での定期的なチェックです。というのも、神経のない歯では痛みを感じにくく、根の先に膿がたまっていたり、周囲の骨が溶けていたりしても自覚できないことが多いためです。
定期検診では、歯や歯茎の状態を目で見るだけでなく、レントゲン撮影によって歯の内部や骨の変化を確認します。症状がなくても、レントゲン上に「黒い影」として異常が見つかることは少なくありません。問題が早期に見つかれば、対応も比較的容易で、歯を残せる可能性も高まります。
検診の頻度は状態によりますが、一般的には半年に一度が目安です。リスクが高い場合には、3か月ごとの受診が勧められることもあります。
定期検診では、レントゲンで根の状態や骨の変化を確認し、歯茎の腫れや膿の出口がないか、被せ物や噛み合わせに異常がないかなど、総合的にチェックが行われます。
噛み合わせや日常のストレス管理
神経を抜いた歯は、血流も失っているため栄養が届かず、もろくなります。この状態で強い力が加わり続けると、歯の根が割れる「歯根破折」を起こすことがあり、抜歯が必要になるケースも少なくありません。
特に注意が必要なのが、就寝中の歯ぎしりや日中の食いしばりです。知らないうちに大きな力が歯にかかり、ダメージが蓄積されていきます。顎のだるさや家族に歯ぎしり音を指摘された経験があれば、それは歯からの警告サインかもしれません。
歯科医院では、ナイトガードというマウスピースを作ることで、こうした力の負担を和らげ、歯根破折のリスクを軽減することができます。自覚がある方は、早めの相談がおすすめです。
適切なケアと被せ物の管理
「神経を抜いた歯はもう虫歯にならない」と思われがちですが、それは大きな誤解です。神経がなくても、歯の表面(エナメル質や象牙質)は残っており、虫歯になるリスクは十分にあります。
特に注意したいのが、被せ物と歯の境目から始まる「二次カリエス」です。どんなに精密に作られた被せ物でも、長年使ううちにわずかな隙間ができ、そこから細菌が侵入して、内部で虫歯が進行してしまうことがあります。神経がないため、痛みを感じにくく、気づいたときには深刻な状態になっていることも珍しくありません。
こうしたトラブルを防ぐには、歯磨きだけでなく、デンタルフロスや歯間ブラシを使った丁寧なケアが不可欠です。また、被せ物にぐらつきを感じたり、食べ物が挟まりやすくなったと感じたら、それは劣化のサインかもしれません。小さな変化を見逃さず、早めに歯科で確認することが、再治療を避ける大切なポイントです。
まとめ
今回は、神経を抜いた歯が数年後に痛む原因と、その対処法や予防策についてご紹介しました。 治療を終えたはずの歯が痛むと、「また治療が必要なのだろうか」と、とても不安になりますよね。
その痛みや違和感は、歯が発している見逃してはならない重要なサインです。 神経のない歯は問題が静かに進行しやすく、放置すると歯を失うことにも繋がりかねません。
痛みを感じたら、決して自己判断せずに、まずはかかりつけの歯科医院に相談しましょう。
精密な検査で原因を突き止め、適切な治療を受けることが、ご自身の歯を守るための第一歩です。 そして治療後も、定期的な検診と日々の丁寧なケアを続けることで、大切な歯を将来にわたって長く守っていくことができるでしょう。
根管治療の関連コラム
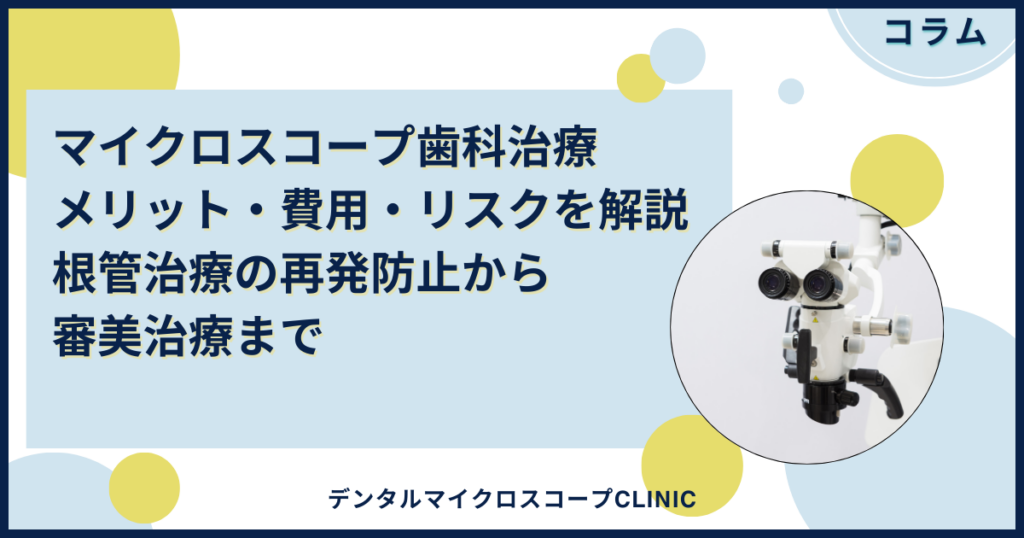
マイクロスコープ歯科治療のメリット・費用・リスクを解説|根管治療の再発防止から審美治療まで
あなたは今、「何度も治療しているのに再発してしまう」「この歯はもう諦めるしかないのか」という深い悩みや、「せっかく自費で治療するなら、一番長持ちする方法を選びた...
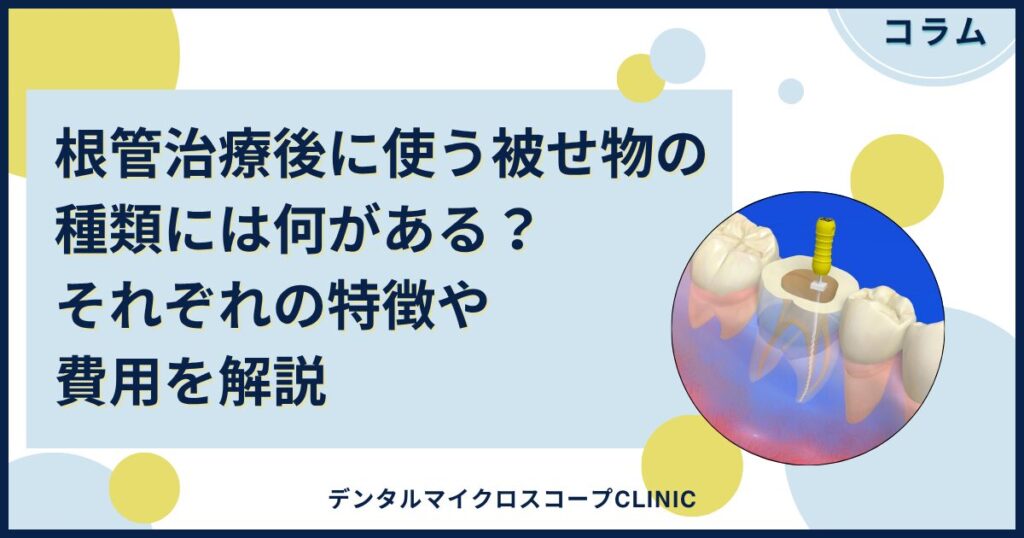
【医師監修】根管治療後に使う被せ物の種類には何がある?それぞれの特徴や費用を解説
根管治療をした後は、歯や神経を守るために被せ物をします。被せ物にはいくつか種類があり、特徴や保険適用となるのか、費用などが異なります。この記事では、保険・自費合...
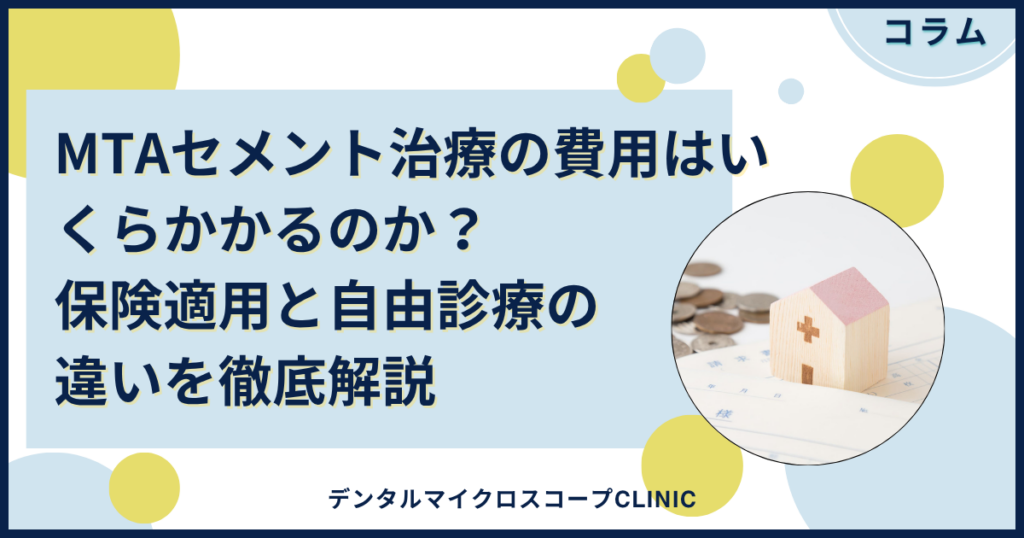
【医師監修】MTAセメント治療の費用はいくらかかるのか?保険適用と自由診療の違いを徹底解説
歯科医療の進歩により、従来なら抜歯しか選択肢がなかった歯も「MTAセメント治療」という方法で救える可能性が大きく広がっています。しかし、「MTAセメント治療はど...
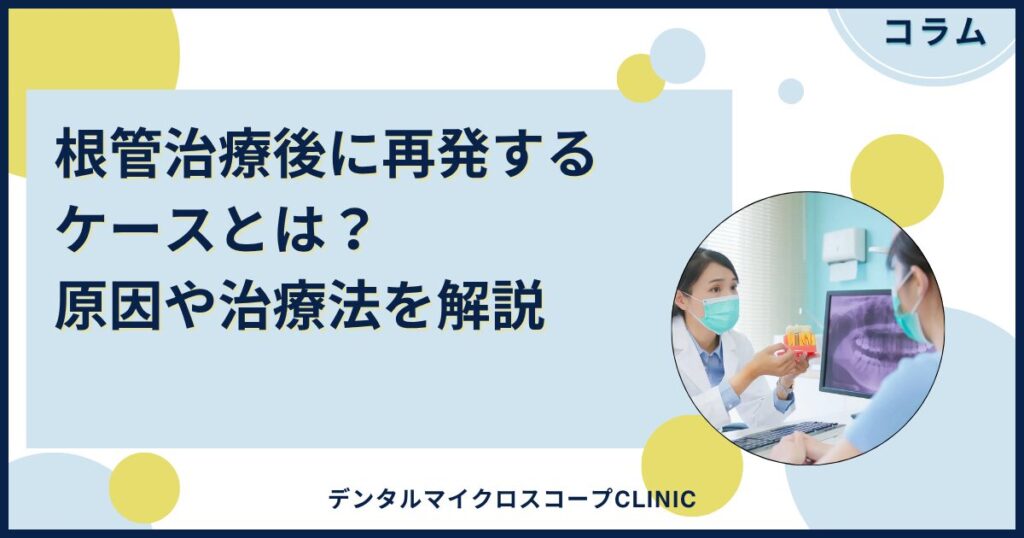
【医師監修】根管治療後に再発するケースとは?原因や治療法を解説
一度治療を終えたはずの歯が、また痛みだして、「治療がうまくいかなかったの?」と、不安な気持ちになっていませんか。歯の根の神経を取り除く根管治療は、歯を残すための...
根管治療でおすすめの歯科医院
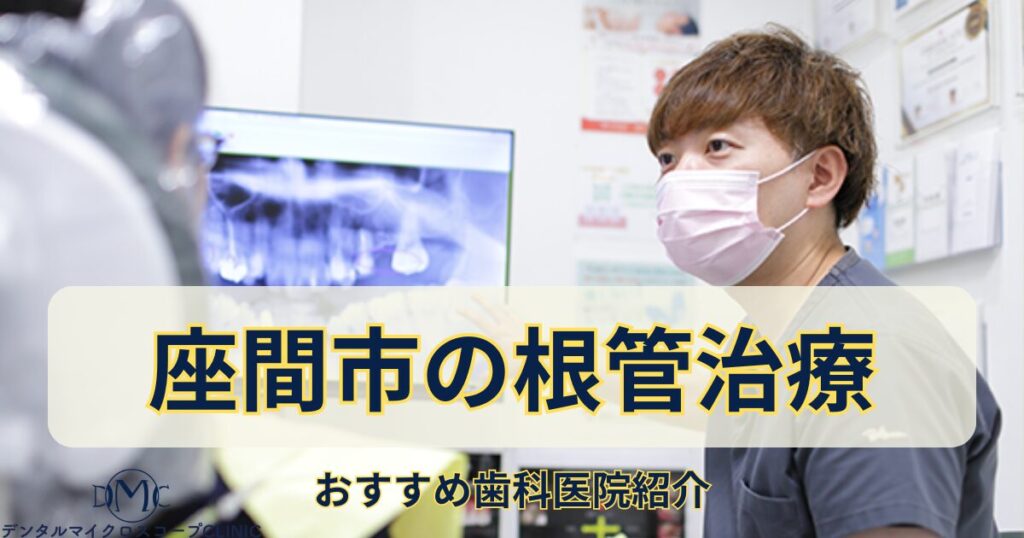
【座間市・精密根管治療】再発を防ぎ歯を残すマイクロスコープ|相武台ゆうデンタルクリニック
「治療したのに歯の痛みが引かない」「歯の神経を抜く治療が必要と言われた」神奈川県座間市で根管治療を受けるなら、無駄に歯を削らない・神経をなるべく抜かない精密治療...

【再発を防ぐ】盛岡市の根管治療|歯を残すなら日本顕微鏡歯科学会・認定指導医在籍のたかデンタルクリニックへ
「他の歯科医院で抜歯しかないと言われた」「痛みが治らない……もしかして治療に失敗した?」岩手県盛岡市で、ご自身の歯をできる限り残したい方、根管治療を繰り返してい...

横浜市港北区・綱島でおすすめするマイクロスコープ精密歯科治療は高田歯科クリニック
横浜市港北区・綱島エリアでマイクロスコープを用いた精密な歯科治療をご希望の方へ。東急東横線「綱島駅」から徒歩3分の高田歯科クリニックは、医学的根拠(エビデンス)...
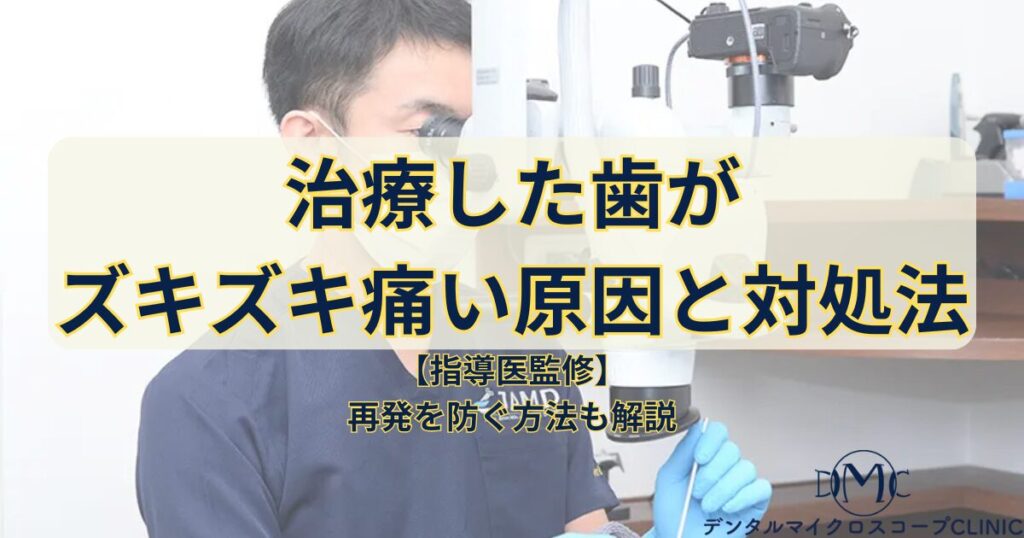
【指導医監修】治療した歯がズキズキ痛い原因と対処法|再発を防ぐマイクロスコープ
「ズキズキと脈打つような歯の痛みをなんとかしたい」「以前治療した歯が痛い……もしかして失敗した?」当記事では、治療した歯が痛くなる原因、【治療後すぐ】【しばらく...
