一度治療を終えたはずの歯が、また痛みだして、「治療がうまくいかなかったの?」と、不安な気持ちになっていませんか。歯の根の神経を取り除く根管治療は、歯を残すための精密な処置ですが、再発してしまうケースがあります。
再発の根本的な原因は、歯の根の中に潜む目に見えない「細菌」です。
この記事では、根管治療が再発してしまう3つの主な原因から、再発時の治療法の選択肢、そして将来の再発リスクを下げるための予防法まで解説します。大切な歯を失う前に、まずは再発のメカニズムを正しく理解することから始めましょう。
この記事の監修歯科医師

医療法人あかり会歯科
脇田奈々子
大阪大学歯学部卒業後、同大学予防歯科学教室にて医員として勤務。
現在は大阪市内の歯科医院で、予防歯科からインプラント、矯正治療まで幅広く対応している。治療の先の心のケアにもつながる“医療としての美容歯科”として、ボツリヌス治療、ヒアルロン酸注入、リップアートメイクにも注力している。
「口元の健康と美を通じて、最後まで美味しく食べ、自信を持って笑える人生」をサポートすることを理念としている。
目次
根管治療が再発する3つの原因

再発の根本的な原因は、歯の根の中(根管)に潜む「細菌」です。ここでは、なぜ根管治療が再発してしまうのか、その主な原因として、以下の3つを解説します。
①根管内の細菌の取り残し・再侵入
②複雑な根管の見逃しや清掃・充填の不備
③治療後の歯のひび割れや歯根破折
①根管内の細菌の取り残し・再侵入
根管治療が再発する主な原因は、細菌が残ること、または治療後に侵入することです。
根管は人によって形が異なり、複雑に枝分かれや湾曲をしているため、器具が届かず細菌が残ることがあります。治療後の詰め物や被せ物に微細な隙間が生じ、唾液とともに細菌が侵入して再感染を起こす場合もあります。
根管の形態や感染の程度、使用する材料や封鎖性の高さが、治療の成功に大きく影響します。リスクを最小限に抑えるには、精密な診断と高い封鎖性を持つ材料を選ぶことが重要です。
②複雑な根管の見逃しや清掃・充填の不備
根管は非常に複雑で、特に奥歯には細い側枝や副根管が存在します。これらを見逃したり処置が不十分だったりすると再発の原因になります。
主な要因は以下のとおりです。
- 根管の見逃し:細い根管を発見できず感染源が残る
- 清掃・洗浄不足:細菌や汚染組織が残り炎症を起こす
- 充填の不備:薬剤が先端まで詰まらず隙間で細菌繁殖
こうした技術的課題は治療の成功率に直結します。肉眼には限界があるため、歯科用CTによる三次元的な根管形態の把握や、マイクロスコープによる精密治療が、見逃しや不備を防ぐ鍵になります。
③治療後の歯のひび割れや歯根破折が原因
根管治療を行った歯は、神経や血管を取り除いているため、歯に栄養が行き届かなくなります。その結果、健康な歯に比べて脆くなる傾向です。
脆くなった歯に過度な力が加わることで、歯にひびが入ったり、割れたり(歯根破折)することがあります。ひび割れや破折が起こる主な原因は以下のとおりです。
- 硬い食べ物を噛んだ時の強い衝撃
- 歯ぎしりや食いしばりによる継続的な負担
- 転倒など、顔や口をぶつけた際の外傷
歯の表面や、特に歯茎の中に埋まっている歯根にひびが入ると、亀裂から細菌が根管の内部へ侵入する新たな感染経路になってしまいます。
歯根破折は、根管治療後に起こりうる合併症の一つです。一度破折が起きてしまうと、残念ながら抜歯に至るケースも少なくありません。治療後の歯を長持ちさせるためには、強い力がかからないように注意することが大切です。
根管治療再発の症状

根管治療の再発を疑うべき症状には、いくつか特徴的なサインがあります。もし、以下のような症状に心当たりがあれば、早めに歯科医院に相談しましょう。
- 痛みがある噛んだ時にだけ痛む、響く感じがする
- 何もしなくてもズキズキと脈打つように痛む、以前治療した歯の周りの歯茎を押すと痛い
- 歯茎が腫れている治療した歯の根元あたりが、ぷくっと丸く腫れている
- 膿(うみ)が出ている歯茎にニキビのような白いできもの(フィステル)ができる
- 歯が浮いたような感じがする
- 口の中に嫌な味がしたり、口臭が気になったりする
これらの症状は、根管の中で細菌が増殖し、再び炎症を起こしているサインです。症状が軽いうちに治療を始めることが、大切な歯を守るために重要です。
再根管治療が必要になるケースで放置した場合のリスク
再根管治療が必要なのにそのまま放置すると、感染は時間の経過とともに拡大するリスクがあります。
最初は軽い違和感や噛んだときの痛みで済む場合もありますが、次第に歯ぐきの腫れや強い痛みを引き起こし、膿が溜まって顔が腫れるケースも少なくありません。
さらに進行すると、感染が顎の骨全体に広がり、骨の破壊や膿瘍(のうよう)の形成につながります。まれに全身に菌が回ることで、発熱や倦怠感など全身症状を伴う危険もあります。
この段階まで悪化すると、歯を残す治療は難しくなり、最終的には抜歯以外の選択肢がなくなってしまうこともあります。根管治療後に再び違和感や痛みを感じたら、できるだけ早めに歯科を受診することが大切です。
根管治療再発時の治療法
根管治療が再発した場合でも、ご自身の歯を残すための治療の選択肢はあります。ここでは、歯の状態に合わせて検討される代表的な3つの治療法と、それぞれの費用の目安を詳しく解説します。
再根管治療|歯を残すための第一選択肢
再根管治療は、再び根管治療を行う方法です。根管治療の再発が起きた場合に、ご自身の歯を保存するために、まず検討される基本的な治療法です。
再根管治療の流れは以下のとおりです。
1. 被せ物・土台の除去:クラウンやコアを慎重に外す
2. 古い充填剤の除去:専用器具や薬剤で除去
3. 根管内の清掃・消毒:細菌や感染組織を徹底的に除去
4. 薬剤の再充填:隙間なく封鎖して再感染を防止
5. 土台・被せ物の再装着:形態と機能の回復のために、土台に被せ物を取り付ける
なお、再根管治療は初回治療より複雑で難易度が高く、成功には年齢や根尖性歯周炎の有無、根管形態などが影響します。ある研究では、完全治癒が50%、部分治癒が30%、改善なしが20%と報告されています。(※1)
これに比べて初回の根管治療では、保険診療では50〜60%程度にとどまりますが、自由診療でマイクロスコープなど高度な診療器具を用いた場合には90%前後に達するとされています。
歯根端切除術|外科的アプローチで感染源を除去
歯根端切除術は、再根管治療を行っても症状が改善しない場合や、構造的に再根管治療が難しい場合に行う外科的な治療法です。歯茎の「外側」から直接、根の先端と病巣を除去します。歯根端切除術が検討されるケースは下記の場合です。
- 再根管治療を繰り返しても、根の先の病巣(膿の袋)が治らない場合
- 根管内に太く長い土台が入っており、除去する際に歯が割れるリスクが高い場合
- 根管が石灰化などで塞がってしまい、器具が根の先まで届かない場合
治療の流れは以下のとおりです。
- 歯茎を切開し、骨を一部削る
- 根の先端と病巣をまとめて切除
- 根の断面を特殊なセメントで封鎖(逆根管充填)
- 歯茎を縫合して閉じる
複雑な根管形態など、通常の再根管治療では対応できない症例に有効です。奥歯などでは適応が限られますが、ほかにも一度歯を抜いて外で処置して戻す「意図的再植術」という方法があります。
抜歯とその後の治療法
抜歯は、再根管治療や歯根端切除術などを行っても歯を残すことが困難な場合に検討されます。
抜歯が避けられないケースは以下のとおりです。
- 歯の根が縦に割れている(歯根破折)
- 虫歯が歯茎の下の深くまで進行し、被せ物が作れない
- 歯を支える周りの骨が、歯周病や感染によって大きく失われている
抜歯後は、失われた歯の機能や見た目を補うために、以下の3つの方法を検討します。
| 治療法 | 概要 | メリット | デメリット |
| ブリッジ | 見え両隣の健康な歯を削り、橋渡しするように連結した被せ物を装着する | ・比較的治療期間が短い ・固定式で違和感が少ない | ・健康な歯を削る必要がある ・支えとなる歯に負担がかかる ・清掃がしにくくなる |
| 部分入れ歯 | 金属のバネなどを隣の歯に引っかけて固定する取り外し式の歯を入れる | ・健康な歯をほとんど削らない ・比較的費用が安い(保険適用) | ・違和感や異物感が出やすい ・バネが見えることがある ・噛む力が弱い |
| インプラント | 顎の骨に人工の歯根を埋め込み、その上に人工の歯を装着する | ・自分の歯のように噛める ・周りの歯に負担をかけない ・見た目が自然で美しい | ・外科手術が必要 ・治療期間が長い ・自由診療で費用が高額 |
まれなケースですが、抜歯後も痛みが続くことがあります。これは歯の炎症による痛みではなく、神経そのものが過敏になってしまう神経障害性の痛みの可能性があります。
抜歯はあくまで最終手段であり、慎重な判断が求められます。
治療法ごとの費用と成功率の目安
保険診療と自由診療(自費)では、使用できる材料や機器、かけられる時間が異なるため、費用と成功率に差が出ることがあります。
| 治療法 | 保険診療の費用目安 | 自由診療の費用目安 |
| 再根管治療 | 5,000~15,000円程度(被せ物代は別途) | 80,000~200,000円程度(被せ物代は別途) |
| 歯根端切除術 | 10,000~30,000円程度 | 100,000~250,000円程度 |
| 抜歯 | 1,000~5,000円程度 | - |
| ブリッジ | 15,000~30,000円程度 | 300,000~500,000円程度 |
| インプラント | (保険適用外) | 400,000~600,000円程度 |
費用は歯の種類(前歯・奥歯)や本数、使用材料により大きく変動します。上記はあくまで一般的な目安です。
治療の成功率は、歯の状態や感染の程度、患者さんの全身状態など多くの要因に影響されるため一概にはいえません。
自由診療では、マイクロスコープ(歯科用顕微鏡)や歯科用CTを用いることで、より正確な診断と処置が可能です。
ご自身の歯の状態と、将来的なリスクやご希望を考慮し、歯医者さんとよく相談して治療法を選択しましょう。
再発リスクを下げる予防法3つ

治療した歯を将来にわたって守り、再発のリスクを最小限に抑えるためには、治療後の「予防とメンテナンス」が何よりも重要です。
ここでは、ご自身の歯を長く健康に保つための具体的な方法として、以下の3つを解説します。
①適合精度の高い被せ物(クラウン)の装着
②丁寧なセルフケアと定期検診
③精密治療(マイクロスコープ・CT・ラバーダム)の活用
①適合精度の高い被せ物(クラウン)の装着
被せ物(クラウン)は、根管治療後に細菌の再侵入を防ぎます。適合精度が低いと、歯と被せ物の間にミクロの隙間が生じ、唾液中の細菌(1mlあたり数億個)が侵入し、再感染の原因になります。
適合精度が重要な理由は以下のとおりです。
- 隙間から唾液と細菌が侵入し、根管内で繁殖する
- 再発や二次的な虫歯の直接的原因となる
根管治療の成功には内部の清掃だけでなく、被せ物をきっちり合わせて、すき間なく封鎖することが大切です。
②丁寧なセルフケアと定期検診
治療後の歯を長く守るには、日々のセルフケアと定期的な歯科メンテナンスが大切です。治療した歯だけでなく、お口全体の健康を支えます。
セルフケアのポイントは以下のとおりです。
- 丁寧なブラッシング:毛先の柔らかい歯ブラシで歯と歯茎の境目、特に被せ物の縁を一本ずつ磨く
- 歯間清掃の徹底:デンタルフロスや歯間ブラシを毎日使用する
歯と歯茎の境目、特に被せ物の縁の部分は汚れ(プラーク)が溜まりやすい場所です。歯ブラシだけでは歯間の汚れを約60%しか取り除けないという報告もあります。(※2)そのため、デンタルフロスや歯間ブラシの併用が重要です。
定期検診で行われる主なチェック項目は以下のとおりです。
- レントゲン撮影:根の先に再び病巣や骨の状態を定期的に画像で確認する
- 被せ物・土台の状態チェック:被せ物にひび割れや摩耗、適合不良、土台の緩みなどを確認する
- 噛み合わせの確認と調整:特定の歯への負担がかかっていないかをチェックして調整する
- 専門的なクリーニング(PMTC):セルフケアで落とせない歯石や汚れを、専用の機器で除去する
根管治療の再発は自覚症状なく進むこともあるため、「治療して終わり」ではなく、そこからが健康維持のスタートです。
③精密治療(マイクロスコープ・CT・ラバーダム)の活用
根管治療の成功率、つまり再発リスクの低減は、治療の「精度」に大きく左右されます。精度を高める先進機器と防湿法には、次のようなものがあります。
- マイクロスコープ:術野を20倍以上に拡大し、根管内を直接確認できる細い管
- 歯科用CT:歯や骨を立体画像で把握し、治療前に根管形態や病巣の範囲を正確に診断できる
- ラバーダム:治療する歯を隔離し、唾液中の細菌侵入を物理的に防ぐゴム製のシート
マイクロスコープは、直視できるため清掃・消毒を行いやすいです。歯科用CTは三次元画像で根管や病巣を正確に確認でき、治療計画の精度を高めます。ラバーダムは治療中の歯をゴムシートで隔離し、唾液中の細菌侵入を防ぎます。
これらを組み合わせることで、科学的根拠にもとづく精密治療が可能となり、長期的な歯の保存につながります。
保険診療と自由診療の違いと選び方
根管治療には、健康保険が適用される「保険診療」と、全額自己負担の「自由診療(自費診療)」があります。再発リスクを下げ、ご自身の歯を長く守るためには、それぞれの違いを正しく理解し、ご自身で治療法を選択することが大切です。
以下の表に保険診療と自由診療の違いをまとめています。
| 項目 | 保険診療 | 自由診療(自費診療) |
| 費用 | 比較的安価 | 高額になる傾向 |
| 治療時間 | 1回の治療時間に制約がある | 十分な時間をかけて丁寧な治療が可能 |
| 使用機材 | 使用に制限があり、CTやマイクロスコープは一般的ではない | 精密治療のための歯科用CTやマイクロスコープを標準的に使用 |
| ラバーダム | 使用されないことが多い | 細菌感染防止のため、原則として使用 |
| 使用材料 | 使える薬剤や被せ物の種類に制限がある | 精度や生体親和性に優れた材料を自由に選択できる |
どちらの治療を選ぶかは、患者さんご自身の価値観やライフプランによります。「まずは費用を抑えたい」場合は、保険診療が適切です。
「将来的な再発リスクを低くして、自分の歯を一本でも多く残したい」場合は、自由診療も検討してみるといいでしょう。
大切なのは、目先の費用だけで判断せず、「将来的な再治療にかかる費用や時間」「歯を失うリスク」などの長期的な視点を持つことです。歯医者さんから十分な説明を受け、それぞれの利点と欠点を理解したうえで、納得できる治療法を選んでください。
まとめ
治療を終えた歯が再び痛んだり腫れたりすると、不安に感じると思います。再発の主な原因は、歯の根の中に潜む「細菌」ですが、再根管治療や歯根端切除術など、大切な歯を残すための治療法があります。
何よりも重要なのは、治療した歯を長持ちさせるための「予防」です。以下の予防法を試すことで、再発リスクを大きく下げる可能性があります。
- 細菌の侵入を防ぐ精密な被せ物を入れる
- 日々の丁寧なセルフケアを行う
- 歯科医院での定期的なメンテナンスを続ける
もし少しでも違和感や気になる症状があれば、決して我慢せず、まずはかかりつけの歯医者さんに相談してください。
参考文献
- Shan Sainudeen, Priya Rani, Divya Batra, Bhargavi D Vedula, Vidya A Vaybase, Suresh Mitthra, Mohammed Mustafa. Factors Influencing the Success of Endodontic Retreatment: Insights from a Retrospective Study. Journal of Pharmacy and Bioallied Sciences, 2024, 16, Suppl 3, p.S2391-S2393.
- Kiger RD, Nylund K, Feller RP. A comparison of proximal plaque removal using floss and interdental brushes. J Clin Periodontol, 1991, 18, 9, 681-684.
根管治療の関連コラム
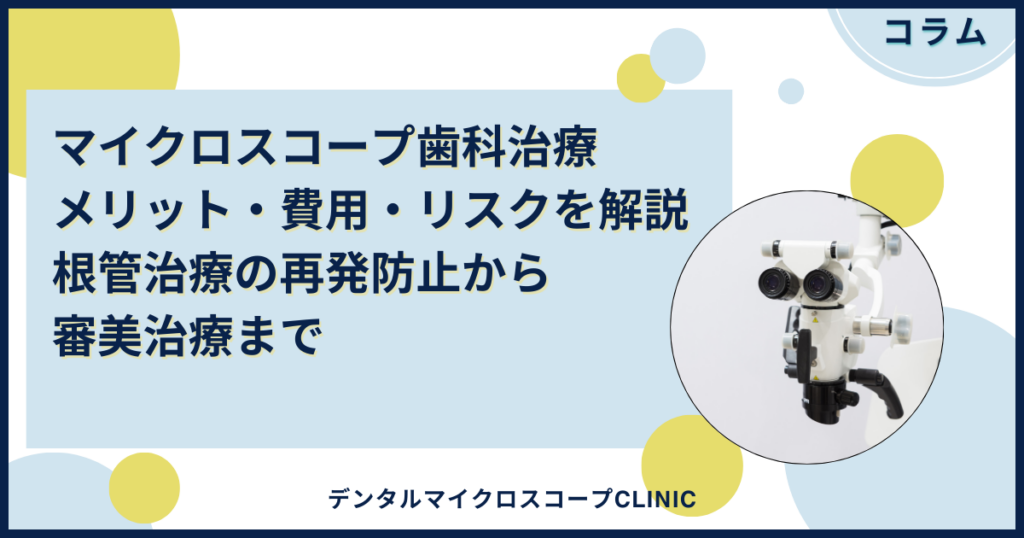
マイクロスコープ歯科治療のメリット・費用・リスクを解説|根管治療の再発防止から審美治療まで
あなたは今、「何度も治療しているのに再発してしまう」「この歯はもう諦めるしかないのか」という深い悩みや、「せっかく自費で治療するなら、一番長持ちする方法を選びた...
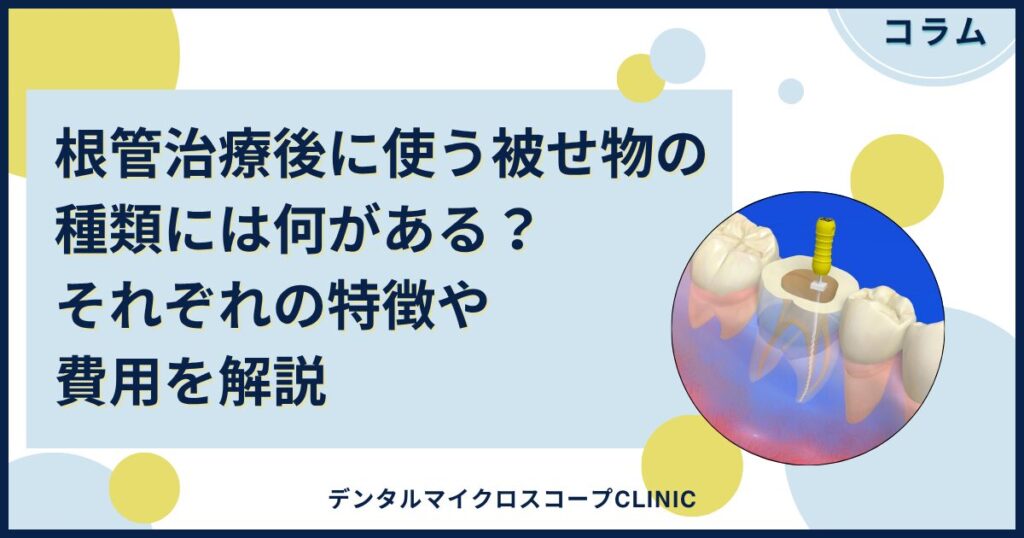
【医師監修】根管治療後に使う被せ物の種類には何がある?それぞれの特徴や費用を解説
根管治療をした後は、歯や神経を守るために被せ物をします。被せ物にはいくつか種類があり、特徴や保険適用となるのか、費用などが異なります。この記事では、保険・自費合...
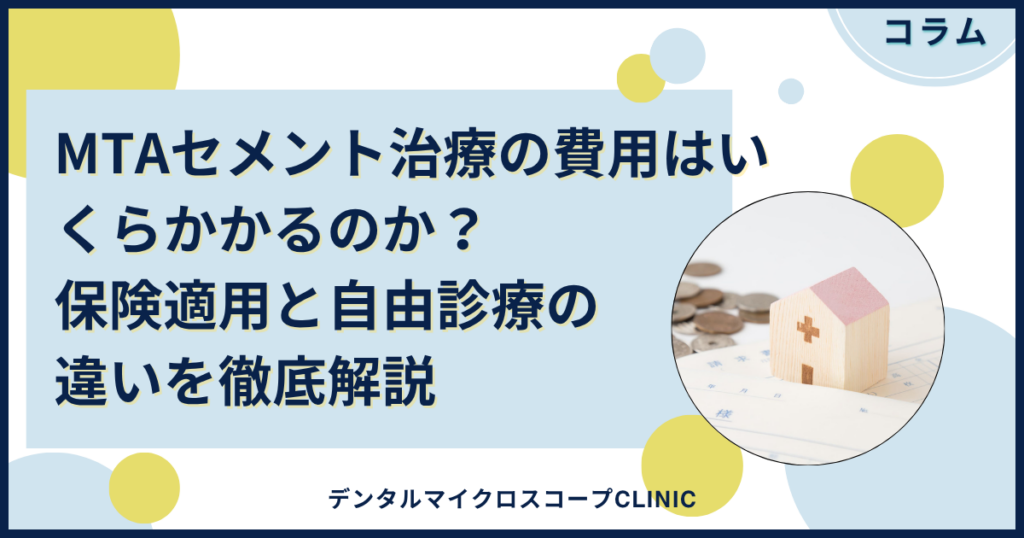
【医師監修】MTAセメント治療の費用はいくらかかるのか?保険適用と自由診療の違いを徹底解説
歯科医療の進歩により、従来なら抜歯しか選択肢がなかった歯も「MTAセメント治療」という方法で救える可能性が大きく広がっています。しかし、「MTAセメント治療はど...
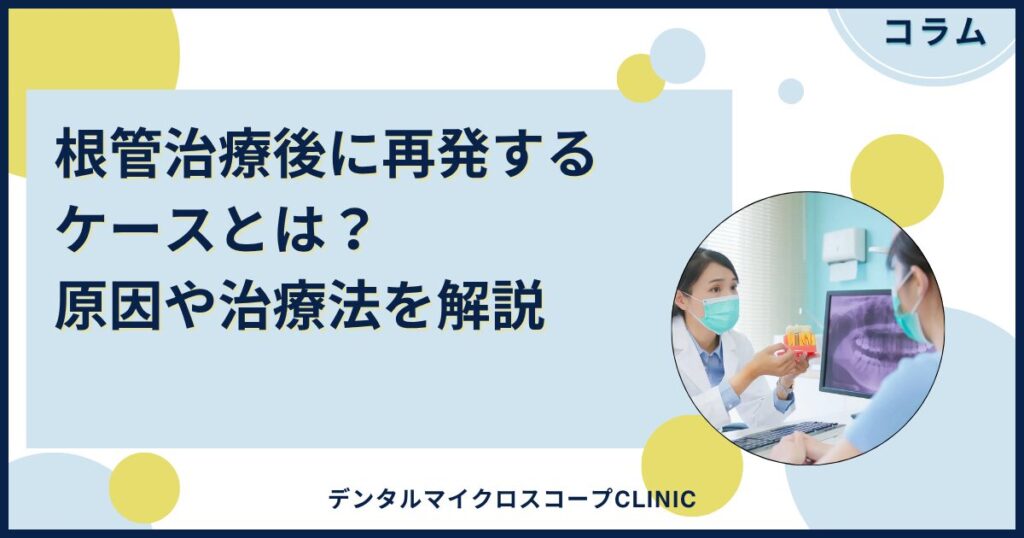
【医師監修】根管治療後に再発するケースとは?原因や治療法を解説
一度治療を終えたはずの歯が、また痛みだして、「治療がうまくいかなかったの?」と、不安な気持ちになっていませんか。歯の根の神経を取り除く根管治療は、歯を残すための...
根管治療でおすすめの歯科医院
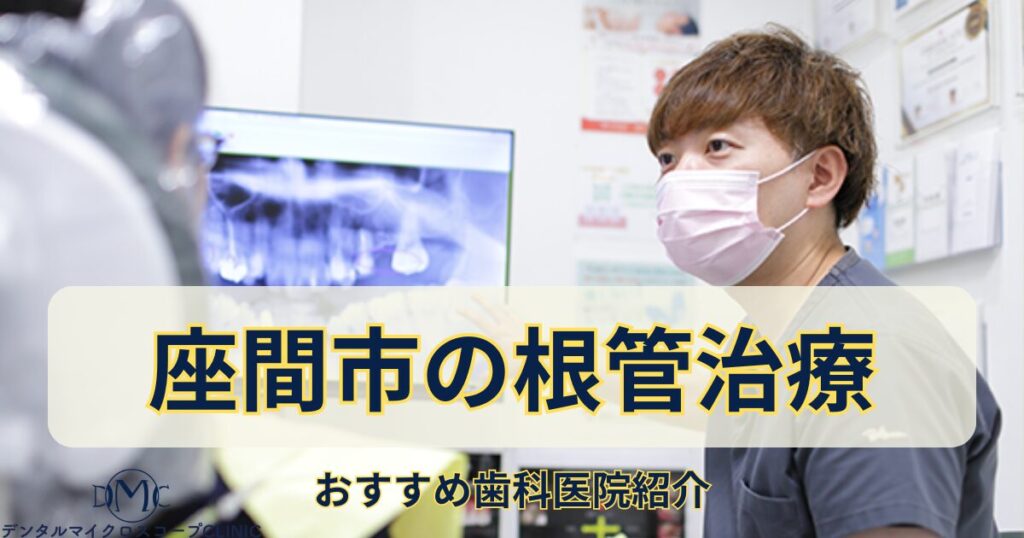
【座間市・精密根管治療】再発を防ぎ歯を残すマイクロスコープ|相武台ゆうデンタルクリニック
「治療したのに歯の痛みが引かない」「歯の神経を抜く治療が必要と言われた」神奈川県座間市で根管治療を受けるなら、無駄に歯を削らない・神経をなるべく抜かない精密治療...

【再発を防ぐ】盛岡市の根管治療|歯を残すなら日本顕微鏡歯科学会・認定指導医在籍のたかデンタルクリニックへ
「他の歯科医院で抜歯しかないと言われた」「痛みが治らない……もしかして治療に失敗した?」岩手県盛岡市で、ご自身の歯をできる限り残したい方、根管治療を繰り返してい...

横浜市港北区・綱島でおすすめするマイクロスコープ精密歯科治療は高田歯科クリニック
横浜市港北区・綱島エリアでマイクロスコープを用いた精密な歯科治療をご希望の方へ。東急東横線「綱島駅」から徒歩3分の高田歯科クリニックは、医学的根拠(エビデンス)...
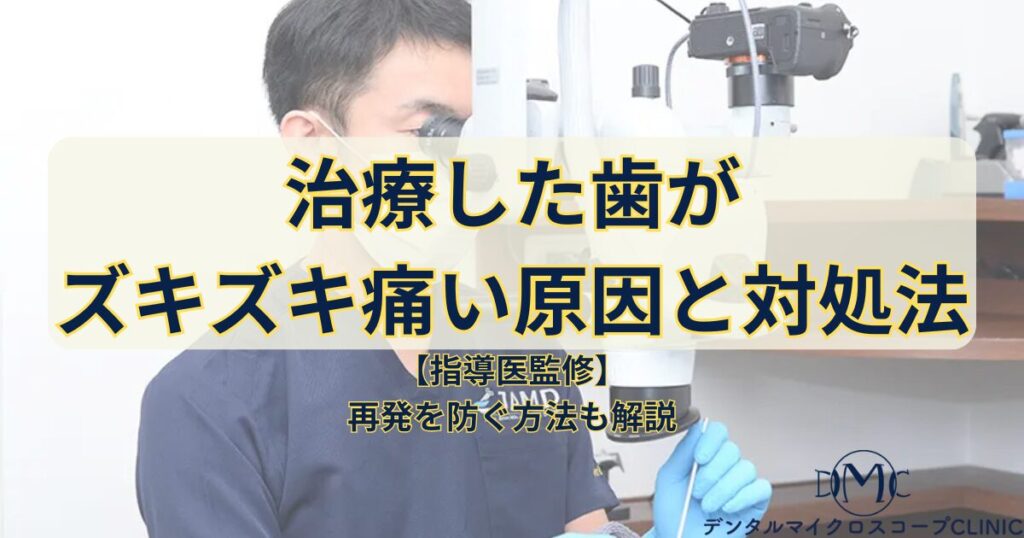
【指導医監修】治療した歯がズキズキ痛い原因と対処法|再発を防ぐマイクロスコープ
「ズキズキと脈打つような歯の痛みをなんとかしたい」「以前治療した歯が痛い……もしかして失敗した?」当記事では、治療した歯が痛くなる原因、【治療後すぐ】【しばらく...
